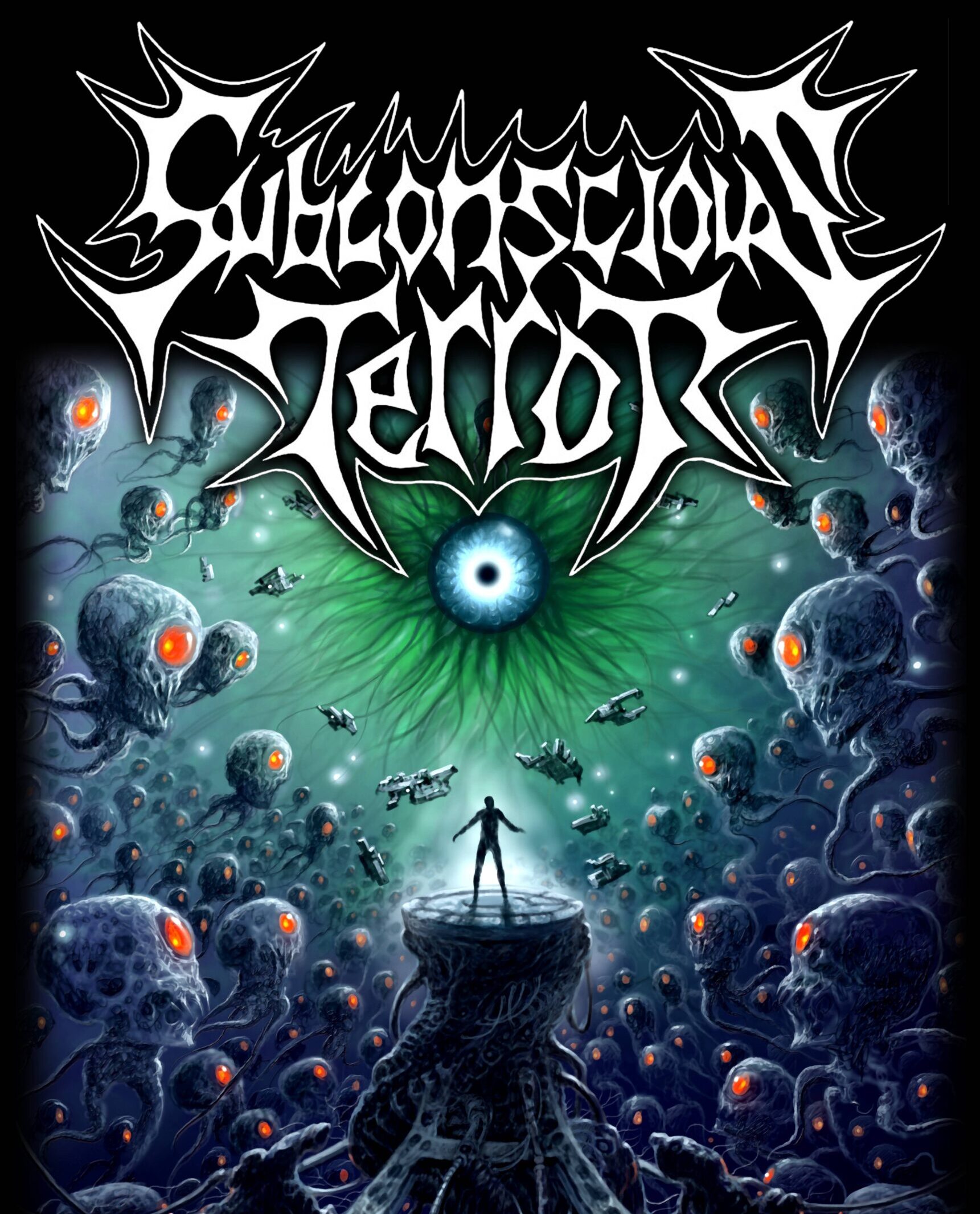作品リリースのペース分析と理解
今回は作品のリリースペースについてです
例として下記5バンド(スラッシュ&デスメタル大御所)の活動年数とリリース作品数で割り出してみます(ライブ作品やコンピは除く)
バンド名 年数(約)作品数
Metallica 45年 11
Megadeth 43年 17
Slayer 38年 12
Cannibal 38年 15
Deicide 39年 13
上記5バンドを平均で割ると「約3年に1枚のペース」でリリースされていることが分かりました
(総活動年数÷リリース作品数=206年÷68枚=約3年)
この「約3年に1枚」のペースでのリリースですが、長寿エクストリームメタルバンドの理想的基準の指標にもなりそうです
ではこれを我々Subconscious Terrorに当てはめてみます(デモリリース2作品やライブDVD等は除く)
我々の場合、結成から数えると32年(2026年現在)になりますが休止期間がありますので実質活動年数で計算してみます
第一期(1994-1998年)
第二期(2019-2025年)~現在
計10年÷4枚=2.5年
これまでリリースのペースを計算したことはありませんでしたが結果としては「2.5年に1枚のペース」であることが分かりました
パッと見なら上記大御所バンドのリリースのペースより少し早いイメージに感じます
ですが、よくよく考えてみると大御所バンドはリリースした後に数年レベルでワールドツアーを行っている事を想定するとむしろ彼らの方が早いペースと言えそうです
と言うのが、我々の様な超小規模バンドだと海外ツアーをしていると言っても範囲も知れてますしショーの数も彼らとは雲泥の差です、なのでむしろ我々の「2.5年に1枚のペース」は早いとは言えないかもしれません
「リリースのペースが早い」というのはバンドの能力においてかなり重要だと思います、特に我々の様な非有名/小規模バンドであれば尚更です。矢継ぎ早に「毎年」出せる位の能力すら必要だと思います
第一に「バンドがアクティブであること」を示せる
第二に「沢山作曲できる能力があること」を示せる
第三に「ファンやプロモーターへの活動訴求」
1つずつ見て行きましょう
第一の(外交的に)「バンドが動いている事を示す」ですが、例えば我々の海外ツアーにおけるプロモーターさんからの招聘はSNS上(Instagram等)でバンドが積極的に活動中であることを拝見下さり、お話を頂く事が多いです。実際、海外からのファーストコンタクトはInstagramからのDMが一番多いです。チョコマカと色んな国に行ってコツコツ活動しているバンドなんだ=「ガチ」でやっている意気込みが伝わります
第二の「沢山作曲できる能力がある」ですが「質を下げず」に「短期間で多数の作曲ができる能力があるかどうか」です。これはコンポーザーにとって「感性の次に重要なセンス」だと思います
もう少しかみ砕くと「なかなか曲を創れない」(アイデア枯渇)、「曲を創るのが遅い」というのはそこがバンドの上限範囲にもなりかねず、テンポの良いリリースが出来ないと「昔取った杵柄」(過去作品のみに依存)の様な形になってしまう懸念もありそこからの前進は厳しくなるかもしれません。やはり挑戦し続ける事です
確かに有名大御所バンドであれば間が空くことは先述の背景からあるかもですが、非有名&小規模バンドで「リリースが遅い、リリースが少ない」というのはただでさえ非有名なのに輪を掛けて致命的に「存在を忘れられる可能性」が潜んでしまうとも考えられます
そういう意味でもリリースのペースについては更に上げて行く必要性はありそうですし、創作能力の有無が試されるところでもありますね
我々、昨年(2025年)の「Devoid of Seraphim」リリースに続き、今年(2026年)もアルバムリリースの予定を立てています
上述の「沢山作曲が出来る能力が有るかどうか」の挑戦でもありますし非常に楽しみです
これからあと何枚リリースできるかな
バンド活動は事実を足跡にしていく
表題の「バンド活動は事実を足跡にして行く」についてですが、言葉を借りるならば「検証可能な事実や具体的な成果で判断される領域」で音楽活動を行う事で「活動方針のあいまいさや迷いを減らす指標になる」という内容です
つまり言葉や評価で判断せず、「事実」や「成果」に基づくバンド活動をすることであいまいさや迷いを減らすです
例えばX(旧Twitter)であればXをやっている中だけの世界。その中だけの会話ですから何も影響を受ける必要は無いと思います。実際、日常生活において身近な知り合いでTwitterをやっている人には出会ったことがないですしね
なので各SNSはそれをやっている人たちだけの憩いの場であり活動方針においての影響は不要です
このようにあくまで「活動や実績の事実で判断する領域」で方向性を定めることで各SNS上での真偽不明な話やそれらに影響を受けたりなどの取捨選択を含め活動に対する迷いは減ると思います
例えばですが「ツアー時」においてどの国で、そのエリアで自分達の音楽が受け入れられるかなどの事実を分析することです
マーチの販売量だったり、現地国SNSでの活況度(取り上げられ方)だったり、DMやコメントでの「又来て!」の数だったり、はたまたインタビューの申し込み数が増えたり
そもそも母数が大衆音楽とは異次元で少ないので「相思相愛なエリアで相思相愛な共感を共有する」です。デスメタルを聞かない人の前でデスメタルをやるのは相互にシンドイですからね
あとはもちろんショップでの販売数(ランキング)も「事実としての成果」なので判断材料として重要です
事実を判断して行かないと、先述の特定SNSだけの中で「これは良い、これは悪い」という評価や判断に洗脳や影響されるのだけは避けないとバンド活動自体に迷いが生じる可能性も考えられます
しかもSNSはアルゴリズム的に「トゲがある表現者が目立つ」様なので偏った思考表現をする人たちも多いと思います
いわゆる「有名だから聴く」、「有名だからその曲はスゴイ」と崇められるもその例ですね
例/去年2025年にBLOOD INCANTATIONが1曲20分にも渡る曲をリリースした際、「右に倣えで崇拝」している人がいましたよね、これが正にそう。「皆んなが凄いと言うから凄いと言っておこう」、そして悦に浸るの様な人が恐らくいると推測します。逆にそうは思わないという人はわざわざSNSに挙げないとも推測されますので「この曲は凄い」だけが独り歩きします。個人的にはBlood Incantationは好きなバンドの1つですがこの曲を絶賛するまでは感じなかったです
我々、SNSが苦手と常々書いていますがこのブログ以外ではそう言った感情を排除し「ライブ告知」「リリース告知」「マーチ告知」のみを淡々と発信し続けているつもりです
できるだけ感情を排除
トゲを出したり感情表現すると結局は「ミイラ取りがミイラになる」ような気がしていて
音楽は自由にやりたいので偏った意見等での判断や影響を受けたくないからです
だからこそ「事実に基づいた活動」をすることが「迷わずに進める足跡」ではないかと
もしマネージャーが存在するならばSNSや告知は全任し、我々は音楽創作とライブだけに没頭したいのが本音です。ただ小規模バンドである我々はそういう訳にも行かないのでブレずに淡々と告知に活用していく感じになります
SNSは応援が我々にとって最大の鼓舞です
ではバンド側の音楽創作以外で「事実や成果を得る為のプロセスとしてどのような具体的行動をすれば良いのかですが例えばライブ毎の改善
お客さんの前で演奏披露させて頂く訳ですからその1回のライブには沢山の情報量が埋蔵しています
なので「ライブをした→終わり」では無いです、ましてやライブはショーエンターテインメントです
部屋でヘッドホンで聴くのとは違い「視覚+聴覚」のライブショーです
我々の場合だとライブ後はメンバー各自が「こうしたい、ああしたい、ここを改善したいetc」をどんどん箇条書きで共有しています。それらを分析判断し次回ライブから即実行しています
とにかくやってみることです、効果が無いならまた改善と言う具合にずっと続きます
なのでショーの内容は去年と今年だけでも全然違うと思います



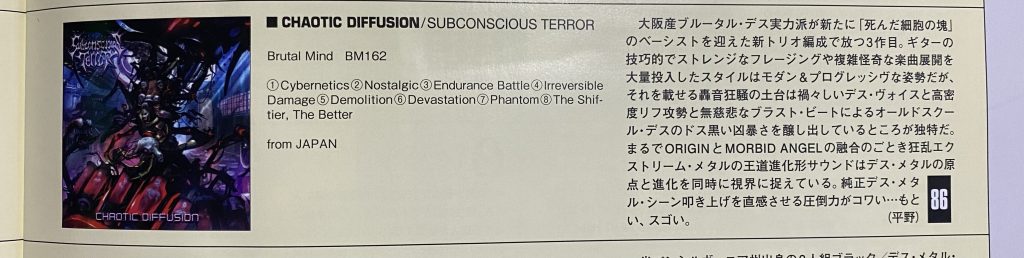
↑これは言葉での評価範囲ではありますが雑誌にて言葉のキャッチボールの無い一方通行な事実として捉えています。インタビューもそうですね
単純なほどに難解
時代と共に「音階」はある程度出尽くしたとも言われています
今回は「音階」=「ギターリフ」として話をしてみます
1オクターブの中に存在する全ての音の数は12音です
つまり12音の中での組み合わせで音階が成立しています
特に何十年もメタル系を聴いてきていると単純なギターリフは今や「既視感/既聴感」がある様な気がします(時代が進む程に)
だからと言って「音を足していく事」(スケールスウィープしたり速弾きしたり)で本当に良いのかという気持ちもありますし、それすら飽和しています
例えが良いかどうか分かりませんが「ギター初心者の方でもコピーし易いようなデスメタル曲を創る」というのはとても難しいと今は感じています
それほど「音を減らす」というのは難しいとも言えますが、ただそれこそガチのデスメタルリフの神髄であるとも思いますし更に「感性」を働かせてその突破口に挑戦です
バンド練習とは
国内のメンバー募集で「都内で週1回集まってスタジオ練習可能な方」等を見掛けます
それが不思議というかそれだとメンバーがなかなか見つからないでしょう
条件が楽器スキルよりも「週一で集まれるかどうか」という
つまり「スタジオ練習に来れるかどうか」になっています
楽器スキルは個々/個人のものです
下記Youtubeリンクの10:20辺りからを是非ご覧ください
上記は元Angra、元Megadethの世界的技巧ギタリストの”Kiko” Loureiroさんの動画です
彼の来日コンサート編のVlog動画なのですが日本公演前日にメンバーで1回リハスタを行う内容です
メンバーが各自遠方住まい
なのでこの動画では現地の日本集合の日本のスタジオで1度リハをしての本番公演です
これが普通というか例えば先述の「毎週スタジオ」に入って何をするのかがむしろ分からないです
まさかスタジオで「ちゃんと弾けるかどうか、ちゃんと叩けるかどうか」の確認は流石に論外です
何が言いたいかというと「メンバー集合」=「自身のプレイがMAX状態に仕上がった状態」で集まるということ
彼らと同じく我々も事前の十分な相互確認と普段からのクリック音源練習で各自準備に余念が無いです
なのでメンバーが揃った演奏はあくまで「実音」の確認なのです
曲作りでのスタジオ練習ならまだしも毎週スタジオに入って何をするんだという不思議感があります
言葉を選ばずにいうならば、プロ意識をもったプレイヤーはスタジオで「ちゃんと演奏できるかどうかの確認」なんて流石にプレイヤープライドも許さないと思いますし、ファンの前でそんな恥ずかしい演奏は個人的にも許せない気持ちになるでしょう。普段から自分にプレッシャーを与えながら練習し続けることになります
キコさんの動画と同じく、我々もメンバー全員が遠方住まいです
我々の場合の海外ツアー時は国内空港最寄りスタジオで3時間リハーサルからの出国が多いですね
国内ショーの場合はライブ会場最寄りのスタジオで3時間、確認リハーサルに入ってからライブ会場に向かうのが基本です
これらは「プロ意識」の問題だと思います
日々練習です
黙々と創るコンポーザー
現代機器のお陰でDTMでデモを創って保存できることで音楽制作のスピードが一気に上がりました
90年代はラジカセにギターリフを保存しておき、曲構成を組んだ後は一発録りでイントロから最後まで(しかもクリックも無し)弾き切ってそれを元にメンバー全員が曲を覚えるという。
当時はそれが普通でしたが今となってはスゴイ大変な事をしていたのだなと感じます
曲創りは楽しいとともにどこかで歯止めを利かせる必要があります
つまりアレンジをし始めるといつまで経ってもその曲が完成することが出来ませんよね
コンポーザーのセンス有無はそこも重要だと思います
もしも定期的にリリースしたいなら期限を決めるなりしてどこかで止めないと永遠にリリースできませんよね
これも音楽センスだと思います
つまりダラダラとしている性格だったり、逆に竹を割った様な性格だったりなバランス感覚
当方の場合はイントロから最後まで構成を練った後は最大でもRev10(展開やリフ変更の修正回数)以降は触らないようにしています、よっぽどのことが無い限り
なので非公開DEMOファイルにはレビジョンを付けているのですがDemo_00(修正回数0回)から始まりDEMO_10(修正回数10回)までがMAXです
上手く創れた曲はDemo_03くらいで完成することもあります
ちなみに毎日10回以上を2週間位は時間を置きながら聴き直します(例/昼・夕方・夜・夜中など)
ですからDemo構成が出来た時点でも既に何百回と聴いている状態になります
そこから本番のレコーディング、バンド練習、そして実践でのライブ演奏という流れになりますからリリースされる時点で既に1000回単位の範囲で聴き込んでいると思います
そして表題、「黙々と創る」のお話です
承認欲求に捉われたり、何かに期待したりなヨコシマな気持ちが入るとやはりヨコシマな曲が出来る可能性があると思います
このシーンはどちらかというと大衆音楽とは反対方向なアンダーグラウンド音楽シーンですから「創りたいものを創る」が正解だと我々は思います
常々言っている「バンド活動ができる生活環境を整えて自由に好きに創作やライブを演る」です
もちろん沢山の人に届けられればこの上なく嬉しいことですが、あくまでも創作は純粋なままで黙々と創るです。これは自分にも念を押して言い聞かせている部分もありますが、最も重要な事は「ピュアで居続ける事が永く続けられるコツ」でもあると思います
バンドマンの「羨ましい」と「嫉妬」の関係
結論としては「行動力/実行力センス有無」の感情の違いだと思っています
①羨ましい・・・肯定感情(憧れ/自分もそうなりたい)
②嫉妬・・・否定感情(相手を妬む)
よくあるのが同ジャンルや同年代で活動中の他バンドの規模感が増した際に、①か②の感情に枝分かれし易い傾向があるではないかと考えています。ほとんどが①だとは思いますが
我々の場合も①ながら加えて規模感が増していくバンドとはどんどん交流したい気持ちが強くなります
なぜならそのバンドの活動が上手く行ってるということですから彼らにアプローチできれば吸収学習できる可能性が高まります
②の感情パターンは少数だとは思いますが、その時点でバンド活動自体もそこが上限でしょうし、つまりは行動力の無さが現況の結果を生んでいる訳ですから何か原因があるはずです。その原因を徹底追及し自己解決(またはバンド内解決)できない限り難しいと思います
「羨ましい」と「嫉妬」における感情の差異は「行動力と実現力(のセンス)有無」の裏返しでもあると考えています
例えばですが「どうしてもCannibal Corpseと全米ツアーを廻りたい」としましょう
結論としては「廻りたければ廻れば良い」しか選択肢はないです
なぜそれをしないのか
全ては何かしらの理由を付けて言い訳をしている可能性が高いです
これだけSNSが普及している今、幾らでも彼らやエージェントにアプローチは出来るはずです
もちろん前提として単なる浅はかな熱意だけではダメで、そこに辿り着くまでにどんな準備が出来ていて、どこまでしらみつぶしに情報入手が出来ていて、その為の十分なアプローチ資料だったり活動資金が準備が出来ているかなどはそもそもな話です
こういったあ範囲は努力とすらいえない最初期の準備になります
精力的にバンド活動を行っているバンドはその熱意が「異次元」です
そう言った異次元で実行力と情熱の有るバンドはジャンル不問でリスペクトしています
永遠に続く機材更新のお話
ライブの際、手持ちのIphoneをギターアンプの近くに置いて動画を撮っています。
そして後日にギターの音質を聴いては改善すべく機材更新してきています。
(バンドアンサンブルはもちろんなのでこの部分は今回省きますがですがそれらは各自の仕事)
もはやこのブログではギター機材更新記事を何度書いたか覚えていない位な定番になりつつある今回の内容となります
前提をおさらいですが弦楽器隊はライブ会場でキャビネットスピーカーとコンセント差込口のみをお借りしています
今回はギター音が「ドライ音過ぎることに気づいた」問題です
背景としては周波数被り(ドラムとベースとボーカル声質)を出来るだけ避ける為、ギター音質は基本カリカリした音です(低音を出さず、中高音域を出しまくる)
これはこれで輪郭が敏感過ぎる位に曲が分かり易いので好んでいます
実際、メンバー全員の音の分離はかなりハッキリしていると思います
ですがギター音があまりに「ドライ音過ぎる」ということに気づきまして
そこで今後導入していくのがBossのRV-6です
リバーブ系機材ですがこのエフェクターにはRoom機能というのが付いています
このルーム機能だけを使います
ライブ時に「空間感」が出せるのでギターリフの立体感が出るのと速い刻みなどでも粒がボヤけないというメリットを感じています
ですので内音を小さくしたい我々にとってはギター音に立体感がでることで音量が小さくても前に出やすいメリットです。
音量については前回も書きましたが「外音」(お客さん側の会場スピーカ)の音量バランスが全てです
内音はとにかく音が廻らない様に小さい音で音の分離重視で演奏パフォーマンスを挙げて行きたいです(以前に書いた通り、ステージ内はドラムの生音とボーカルの返し音がメインで聴こえてくる位がベター)
ただこのエフェクターはギターバッキング時に使うのでツマミ的には12時を超えることは無く「薄く掛ける」感じになります
我々は特にシングルギターのバンドなので音に厚みが出せると考えています
早速次回のライブから使ってみて本採用かどうかです
お次の機材は高価(10万円~)なのでまだ購入を躊躇していますが2チャンネル仕様のステレオパワーアンプです
下記2選択肢です(但し共に市場流通が少ない)
①Marshall 9200(ラック式)
メタリカを始め多数のエクストリームメタルバンドが使用だそう
②GT1000FX(ラック式)
メガデスを始めこちらも多数のエクストリームバンドが使用だそう
Matrix Amplification
2チャンネルあるパワーアンプですのでプリアンプからスプリッター(分岐機器)を使う事で2つのキャビネットスピーカーから同時に音を鳴らせます
例えばキャビネットAからは低音重視の音厚サウンド、もう1つのキャビネットBからは中高音重視で輪郭をクリアにするというようにです。更に分岐先からイコライザーを用意すればプリアンプ側が1つでも2種類の音を同時に出せるのでライブ時に音の厚みや輪郭が前に出せると算段しています
ただ既にライブ用ギターアンプヘッドだけでも5台も所有していますので躊躇しています
今年度中の「欲しいものリスト」に挙げておきたいと思います
機材改善は終わりが無いですね…
和風は戦略なのか、それとも幼少時からの親しみから生まれた創作なのか、それとも?
・ビジュアルがいかにも日本風メタル(和服、兜、神社、お寺、etc)
・音階使いがいかにも日本風メタル
これらの音楽はもしかしたら日本人の洋楽メタルファンの中にはアレルギーがある人もいるかもですが、日本のアニメ産業を始め、和服や神社などのビジュアルは海外の人にとっては日の丸ニッポンと分かり易く、特にフェスなどでは国代表的なポジションでその風貌から、イベント主宰からもお客さんからもウケが良いと思います
これは決して否定するわけでは無いですし、むしろナイスアイデアだと思います
自分達の音楽を届けるための1つの手法です
届けたくても届けられる力が弱いなら工夫が必要です
かといって我々が明日から着物を着たり、兜を被ってライブをする訳はないのですが、ただ音階については思う事はあります
幼いころから聴いて来た馴染みある音階、いわゆる日本音階(平調子)です
我々の様な音楽性だと使うのは意外と難しくややもすると、コッテリした和風メタルになりがち
でも、これも海外の人にとって実は新鮮だったりします
ギターリフも音の使い方1つでガラッと変わります
我々のこれまでの創作曲は基本、音階が「明るい」デスメタルミュージックだと思っています
というのが音楽で楽しくなりたいを追求してきているので、聴けば聴くほど落ち込むようなニュアンスの曲は創っていないつもりです。
逆に聴けば聴くほどハイテンションになる曲を創っているといえば分かり易いでしょうか
人によって感受性は違うのであくまで当方の思考ですが
もちろんダークネスに走ればいくらでもダークネスに出来ますし、日本音階を使えばいくらでもジャパメタ風にも
海外ツアーが増え多数の方々と関わる様になってくると「From Japan」を魅せることも重要ではないかと思い始める自分もいます
和服を着たり兜は被れないけれど和風な音階に関してはちょっと興味ありますね
精神制御
現在は次作アルバム創作が佳境なタイミングです
それもあってか、ここ最近は唸りを上げ頭がおかしくなりそうで気が狂いそうな瞬間があります
これまではそういうことはなかったので初体験です
俯瞰すると勝手に自分自身にプレッシャーを与えているのかもしれません
その背景としては、もしかしたらですが海外ツアーも増えて来たことでここ数年で一気に沢山の方と交流させて頂く様になりましたので「次回お会い出来る際にはMAX値で頑張った新作を届けたい」という気持ちが承認欲求的に先走ってしまっているのかもしれません
ただ、この気持ちは同時に空回りと勘違いを発生させる可能性も感じ始めているので一旦冷静になる期間を設けた方がよさそうです
現況の創作曲を一旦眠らせ、期間を置いてからまた聴いてみてどう思うか(ダメなら全削除)を確認したいと思います
これまで創作に困ったことは無かったのでこのような心情になったことに複雑な部分もありますが、初めて創作の難しさを実感しはじめているのかもしれません
恐らく創作者が通る「通過儀礼」なのでしょう
その扉をこじ開けてみせますし、それによりまた新しいものが産まれるのだと考えています
きっかけとバンド演奏の初体験
17歳(高校生)の時にメタリカのMasterアルバムを聴いてぶっ飛び、衝撃過ぎて次の日にはギターを買いに行ったエピソードは以前にこのブログ内で書いたことがあります。
当時は世の中にこんな音楽が存在して良いのかと言うくらいに衝撃でした
80年代当時は歌謡曲が全盛期でしたし周りにも洋楽ましてやメタル系を聴く人は殆どいない環境でしたし洋楽と言えばマイケルジャクソンくらいの知識でした
ギター購入後はすぐにBatteryやMaster ofをコピーし始め、それこそ寝ても覚めてもギターを弾いている毎日
その後、バンド形態で演奏してみたい衝動に駆られるのですが、当時は高校生
メンバー募集という発想も無く
どうしたかというと同じクラスの友人がボーカル、吹奏楽部で打楽器をしていた同級生がドラム
この3人で初めてバンド形態で合わせてみたのを今でも覚えています
当時は皆んなが「やりたい曲を持ち寄ってやってみよう」でした
・ドラマーはXの紅
・私はBatteryとMaster
・ボーカルはZiggyのGloriaとI’m getting blue
何でもありです
しかも音楽スタジオを借りての練習という知識もなかったので高校の土日に潜り込んで吹奏楽部の教室でコッソリやっていました。教員に見つかって何度か怒られましたが今となっては時効ということで良い思い出です
その後は大学入学し即、軽音に入る訳ですがとにかく音楽三昧でした
大学卒業後も就職せずにそのままサブコンシャステラーで活動していましたからね
大学の軽音時代は5バンド位を掛け持ちしながらあらゆるジャンルのコピバンをして軽音の定期コンサートでライブ経験を積んでいました
大学2、3、4年生時は連続で学際の大トリ(Sepultura、Slayer、Metallicaのコピバン、その時は既にギター&ボーカル)でも出演させて頂き自信が付いてきて徐々に一からオリジナル曲を創りバンドを組みたいと感じ始め音楽雑誌BURN!誌上でメンバー募集をし大学3年生の時にサブコンシャステラーを立ち上げました
二十歳ソコソコでしたので数十万円もするジャクソンギター(ランディV)やPEAVEY5150アンプヘッドやメサブギーのキャビネット、更にはツアー用の機材車までの購入で高額負担でした。機材一式は揃えるのが大変でしたがやり始めたら止まらない性格だったので
振り返ると当時メンバー皆んな学生の身分でしたし、よくツアー機材一式を揃えられたなと思います。今となっては懐かしい思い出です
当方が作曲するとは言え当時の相棒デスオ(ドラム)の力はかなり大きかったです。なにせ当時は「ブラストビートとは何ぞや」の時代でしたからね。彼が居ないと成立していなかったです。
当時は国内でブラストビートを叩くドラマーは数える程だったと思いますし彼のドラマーとしての評判はとにかく凄かったです。だから結成2年でレーベル契約CDリリースまで行ったのだと思います
フロントマンにとっては「こんなにも合わせやすいドラマーは居ない」というくらい希少なプレイヤーで彼とは未だ交流はありますが現在はメタルはやってないです。サブコンシャスシャステラーが上手く行く事を望んでくれているのでそれを肝に頑張っています。あと、リードギターだったキノッピはRolandに就職と聞いていましたので過去メンバーは皆んなやっぱり「音楽漬け」が揃っていますね
各自が各自なりの人生を歩んでいることを総合すると、もしも末永くデスメタルをやりたいならば(流石にデスメタルで飯を食うは無いので)それがやれる生活環境を作れる事がデスメタルプレイヤーを続けられる最も重要な事だと思います
ツアー日程のやりくり
今年2026年分のツアー日程に関する大枠について
去年からプロモーターさんとやりとりしていますがちょっと大げさに言うならば楽しいですが大変です
我々は超小規模バンドなのでツアーエージェント契約所属している訳でも無く各国の、はたまた更に各地域(各都市)のプロモーターさんと個別にやりとりをさせて頂くケースであったり1つのプロモーターさんが該当国の全行程をツアー手配くださるケースがあったりします
もし前者の各地域毎(各都市)に個別やりとりが必要な場合は多くの過程があります
分かり易く、例えば1つの国で3都市のツアーを廻るとしましょう
その際は3都市の各プロモーターさんと連続でショーが出来る様にやり取りの中で連結して行くという「荒業」です
その上で仮に大筋の日程が決まったとして、各プロモーターさんが会場を押さえて下さるのですが万が一その際、2会場が抑えられたとしても残る1会場が空いてない等で無ければ最初からやり直すケースも
そこに被さってメンバー各自の都合もあるので綱渡りの様な全てが「紙一重」なスケジュール組みになります(なので我々は事前にNG日も伝えています)
順調に会場と日程を押さえられたとして更に共演バンド探し(依頼)もあります。我々は残念ながらワンマンやヘッドライナーを務められるレベルではありませんのでサポート頂くかサポートをさせて頂くかになります
これらのハードルを全てクリアしてようやく「フライヤー告知」されますので上記の様な様々なプロセスの背景には沢山の人が動いて下さった上で成立しています
2026年も複数の海外ツアー予定がありますが足を向けて寝れない程に多くの方々のご協力の元で成立していることを常に肝に銘じ感謝の気持ちで一杯です、本当にありがとうございます
※バンド側で出来る事は入念な準備、精一杯の告知、精一杯のショーパフォーマンスで全方向(お客さん、プロモーター、会場、現地の方々)に満足いただけるように頑張るのみです。ツアーが成り立つこと自体、感謝の気持ちで一杯です。
※海外ツアー時、「パフォーマンス」+「お客さんからの受けが良ければ」、周辺国のプロモーターさんからもお声掛け頂けたりもします。そこからはどんどん輪が広がりますのでこれから海外ツアーを目指すバンドはどこまでも準備万端を心がけて下さいませ
なぜ創作が楽しいのか
楽曲創作が何故好きなのかを考えてみました
これは人それぞれ全然違うかもしれませんね
当方の場合は大きく2つあります
①0から1を作り出す事が好きな性格である(何もない所からの創造)
②自分が聴きたいと思うエクストリームメタルを作りたい
①については毎作品、創作中は知恵熱?が出そうになるくらい考え込むのですがそれを苦しいとは思わないです。だから好きなのだと思います。特にエクストリームメタルの中でもデスメタルミュージックは沢山の音階を使います。パズルの様な、それでいてフックの効いた音階、自分で聴いてアドレナリンが出る様な音階の想像の集合体です。かなり集中した状態、完全に自分の世界にのめり込んでいる状況下&静寂下で創作しています。これを苦しいというのかどうか分かりませんが言語化するならば深い深いトンネルの入り口に入り、そこからずっと先にある遠い出口から差し込んでいる光に向かって少しずつ進んでいく感じでしょうか。以前は7分前後の曲も多かったですが近年は4分前後で締めくくる曲が多いのでその部分に関しては少し出口が近くなった気もします。とにかく何もない所から作り出す「潜水」の様なことをするのが好きなのかもです
②の「自分が聴きたいと思う曲を創る」ですがこれは他人からの依頼で曲提供をするでもない限り、創作者はほぼ全員そうでしょう。ライブバンドなら実際のショーでプレイする訳ですし自分達が誰よりも一番好きな曲であるはずです。「0から1になる段階」から育てて創ってきている訳ですから音階や曲構成を含めリリース段階では既に何百回と聴くことになりますし創作後の思い入れは相当なものがあります
ちなみに創作完成後は更に相当量の各曲の練習が必要になってきます。
何故かと言いますとレコーディング時は「これでもか」という位に弾き倒す事になるとは言え、あくまでレコーディングは「上手く弾けた瞬間の録音内容」ですからライブ演奏でそれを安定化(ミスを減らす)させる必要があります。
更に当方の場合はギター&ボーカルなので手と声の分離がしっかり出来るようになるまで(もつれない様になるまで)
結果、レコーディング後も相当量の練習が必要
あとは我々の創作曲はそもそも曲のスピードも速いので全体で合わせて行くのに目と耳と手と脳内全ての感覚を集中させるトレーニングです
特に新曲を初めてライブ演奏する際は身体に染み込ませるまでの十分な準備と細心の注意を払っています
意思
以前から書き続けている「バンド活動=奇跡の連続」
メンバーの「上船、下船」と言う例を挙げて過去記事で書いてきましたね
(乗船=加入、下船=離脱。これはバンド活動において自然)
理由(下船)についてもその殆どが音楽性の相違等では無く経済的に続かないということも書きました
バンド活動は楽器が巧いとか、創作が出来るとか、デザインが出来るとかは当然の上で、更に金持ちの道楽くらいの生活環境の上で活動を考えられる位での集合体でないと幅広い範囲での活動継続が難しく、そうでない場合は地元ローカルでたまに演るのが精一杯になりがちだと推測しています。
ましてや海外ツアーも視野に活動したいバンドともなると四畳半のアルバイトで夢を語っている場合では無いです。厳しい現実ですが非有名なバンドに海外ツアー資金のサポートはしてもらえないです
それらを実現して行きたい、叶えて行きたいならば、
極論を言いますと「練習する暇があるなら自由に活動出来る環境と資金準備に費やす」です
楽器スキルも創作能力もセンスですが、練習量についても言わずもがなの前提ですからね
そもそもセンスある人が物凄い練習量で活動しているのですから、センスが無いならその何倍もトレーニングを積むことが必要だと思いますし、センスが無くてかつ練習時間すら取れない場合は難しいでしょう
我々は90年代に続き現在もありがたくも活動黄金期に入っています
そのタイミングで「あるある」なのが気の緩みからかバンマスはついつい「分業」を考えがちです
サポートメンバー在籍時は、お手間を取らせてしまう訳にも行かないのでプロセスは省き、全ての準備とアレンジをした上で「結果のみ」をお伝えしていました(例/RECなら全パート収録したデモ音源と各担当分のタブ譜の準備、ライブなら事前の都合確認とライブ日の連絡等)
バンマスは普段プロモーターとの交渉、創作、日程調整、デザイン、Rec調整、機材、レーベル交渉、アートワークやMV制作段取りなど短/中/長期計画を含めて準備が年中継続しています。
これが国内にとどまらず、海外ツアーや世界的有名バンドサポートでの出演ライブともなると一年以上前からプロモーターからの連絡を含めたショー開催までのデザイン打ち合わせをするケースも多いです
これらをバンバン即断しながら進めてきましたが気の知れたパーマネントメンバーになると”ゆるみ”というかこれまで上記を含む全ての責任と判断を追い過ぎてきたプレッシャーや反動からか自分を少し解放したくなり「決断を相談する」ケースも生まれがちです
つまり、これまで瞬時に自分で決めていたことを全員で過程を共有しながら決めて行くとなると先ずは時間差が生まれます
各自の思考時間もありますから当然ですし相互リスペクトしているので、むしろその際に気を使ってしまう部分もあります
万が一その際に意見が合わないとか違和感があるとその調整に掛かる思考や時間が原因で「活動スピード感」が崩れるリスクもあるかもしれません
なので以前と同様にバンマスが瞬時に決断し「過程を排除した結論のみを伝える」ということも実はありなのかもしれません
この辺りはバンド毎に様々なパターンがあると思います
「意思決定」の仕方については、各バンドへのインタビュー記事とかがあれば拝読してみたいです
拘らない
デスメタルをプレイする人って音楽に対する範囲が広い気がしています(私的感想)
当方であれば邦楽/洋楽ポップスからEDMやビジュアル系、洋楽/国産国産を問わずロック、ハードロック、ヘビーメタル、スラッシュメタル、そしてデスメタル。更にはグラインドコアやデスコアやスラミングデスメタルまで。あとちょっと特殊かもしれませんが大学生時代はギタースクールに通っていましてその際の先生がジャズフュージョン系。ですのでいわゆる普段から拘らずに何でも聞く感じです
純粋に音楽が好きな中で特にエクストリームメタルが好きだといえば分かり易いでしょうか
SNS等の外交的には「デスメタルをやっています」と伝える方が理解が早いのでそう書きますが普段は何でも聴きたいです
ライブをさせて頂く際、近いジャンルの方達と共演をさせて頂くことが多いですが、デスコアバンドの方達との交流は何故か少ないです、当バンドが面識が無さ過ぎるのもありますがデスメタルとデスコアの混合ショーは世界的にも殆ど組まれていない気もしています、勘違いかもしれませんが
デスコアとは、デスメタルとハードコアの融合的な言葉が由来だと勝手に想像していますが同じエクストリームメタルジャンルでありながらも我々にとっては最も交流が少ないジャンル
デスコアというジャンルは、自身が音楽をプレイすることから離れていた空白期間(2000年~2020年)に生まれたジャンルの様ですので単純に触れてこなかった事がやはり最大理由かもしれませんが、ライブのフライヤーを見てもデスメタルとデスコアが混合されているショーってあまりイメージがないです
そもそも当方も現況、デスコアジャンルの知識自体が薄いですが、今後可能性があるならば交流もさせて頂きたいジャンルの1つではあります。
ライブでの相性と言う面ではまだ想像がつきませんが同じエクストリームメタルの範疇ですし、恐らくデスコアが好きな方はデスメタルも好きな可能性もありますので興味津々ですし、交流があればデスコア好きな方達のルーツであったり、どんなバンドやどんな音楽が好きなのかも伺ってみたいです
ロゴやシンボルマークの今後ついて
まず初めに以下は当バンドのロゴ変遷です
①1994年1stデモテープ時のロゴ↓

②1995年2ndデモテープ時のロゴ↓
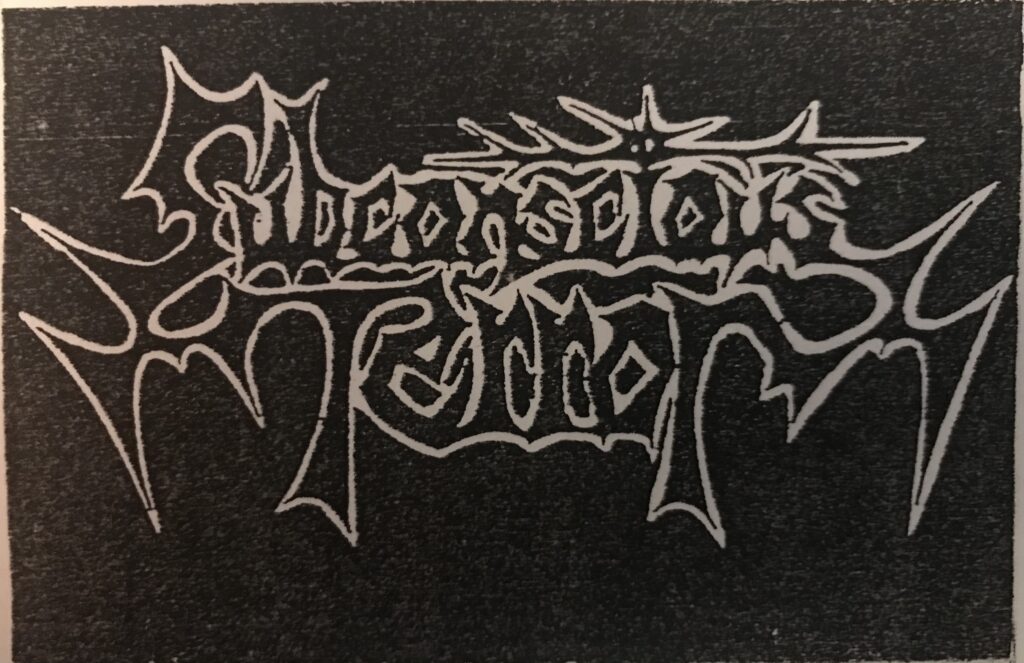
③現在(2020年以降)のロゴ↓

今回のテーマは「ロゴの将来」についてです
先に結論を書くと将来的には「分かり易く可読性のあるもの」に回帰していく予測をしています
バンドロゴやシンボルマークは「信頼」を作る記号だと思っています
近年はどう読むのか分からないロゴが一世風靡していますよね
あくまで個人的ではありますが、どう読むか分からないロゴは好まないです
我々の初期時代に遡ると90年代当時はネットも無かったですしレコードショップにデモやCDが置かれてもロゴが読めないと始まらない(気づいて貰えない)ことや、フライヤーも一目で音楽性まで分からないとどんなイベントかも分かり難いことなどを感じていたからかもしれませんが
例えば気になったバンドがあってもバンド名が読めないところからのスタートはハードルが高い感覚もあります
なので「可読性」があってその音楽性も分かるロゴが好きです、あくまで私的感想ですが
最近だとライブ告知フライヤー上で読めないロゴの下にローマ字でバンド名が書いてあることがありますが、そもそもローマ字を入れないと分からないというのは(くどいですが私的感想です)仮にその音楽に興味が湧いたとしても読めない時点で辿り着かずにそこでギブアップしてしまいます
ロゴと言うのは会社のマークと同じで「信頼」、「信用」だと思っています
我々も正にそうですがバンド名が可読できるロゴで、音楽性もその形状での表現ができれば音楽を聴く前からイメージも掴みやすいと思います
デスメタルバンドのロゴの将来予測(10年後や20年後)
近年の「読めないロゴ」が飽和した今、やっぱり分かり易い可読性ロゴ(+音楽性表現形状)へ回帰していくのではと勝手に予測しています

理解した上でやると楽しいです
ベイエリアスラッシュのパイオニアEXODUSのGary Holtさんのインタビュー記事
→ https://amass.jp/186946
EXODUSといえばメタリカのカークハメットが居たバンドですね。エクソダスは学生時代からよく聞いていました
そんなGary Holtさんのインタビュー内容ですがバンドマンの現実を赤裸々に書いておられます
例えばバンドマーチのオンラインストア。自身で運営し自宅で梱包して自身で発送対応
我々は正にそうですが彼らクラス(EXODUS)のプレイヤーであってもです
記事の中で気になったのが「出演料だけでツアー経費を賄えたら大成功」という表現です
恐らくプロモーターが公演を買うパターン(出演料のみ)の事だと思われますので経費は出演料の中で自分達で賄っていくツアーなのでしょう
分かり易い例を挙げて考えてみます
・EXODUSがヨーロッパツアー1週間
・仮に出演料トータルパッケージで200万円として
経費自腹(出演料から差し引く)とのことですのでメンバー5人だと仮に飛行機代往復40万円x5人=200万円
これだといきなり航空費で出演料を使い切ってしまいますね
なので上記条件(200万円の出演料)だと彼らはそのツアー案件は先ず受けないでしょう
そうなると話がそこで終わってしまうので出演料を変更し300万円だとしましょう
それでも上記の航空費を差し引くと残りが100万円です
そこから仮に
・ホテル代9泊xツインx2部屋=30万
・食事代10万円
ならば残りが60万円です。(実際はレンタカーで寝泊まりしながらホテル代を浮かしたり、食事はカップラーメンで簡単に済ませることも想像できます)
そしてEXODUSはメンバー5人ですので
出演料300万-航空費200万-食住40万なら60万円が利益ですがメンバー5人で割ると出演料は1人あたり12万円です
7公演で12万円ですので1公演あたりに割ると12万円÷7日間ツアー=僅か約1.7万円の日当
1週間ツアーをして日当1.7万円という現実…
Garyさんの言う「出演料だけでツアー経費を賄えたら大成功」というのはこういうことでしょう
それが大成功というならば経費負けして赤字で帰ってくることもありうるということです
だから「旅する服の販売員」みたいなものだと
確かに、上記を経費想定するならば「マーチで収入を得て行く」しか無いですよね
ちなみにツアー上でのマーチですが「どうやって持っていくか問題」があります
例えばツアーTシャツ
メンバーのスーツケースに入れて持って行く範囲だと数に限りがあるので売上の上限が決まってしまいます。かといってスーツケースを増やしたりコンテナの様なもので運ぶとなると運送コストで売り上げがすぐに飛んでしまいます。
なのでデスメタル系の来日バンドでもよくある「ちょっとしかマーチ持ってきてない」パターン
これはメンバーのスーツケースに入る分だけしか持ってきてないことが往々に
特に格安航空券だと預け荷物の重量制約もありCDやシャツを少量しか持ってこれないケース
これを解決する方法としては、ツアー先の現地国でシャツを作って販売するというパターンもありますがこれは一気に薄利になります
なぜかというと、マーチ売上からシャツ制作原価と販売手数料等(例10%)や発送費が引かれるからです
仮に「販価5000円シャツ」ー「原価1500円」ー「手数料500円」=純利3000円だとしてもメンバー5人で割ると1人当たりの利益は600円/枚です。
EXODUS規模のヨーロッパツアーであればキャパ200人クラス(中央値)が埋まるクラブツアーになるとは思いますがそれでも1公演で最低でも30枚はシャツが売れないと先述の日当金額すら厳しいと思います
もしこれが専属PAも帯同の場合はもっとシンドイでしょう(更に追加で航空費、ホテル、食事、給与が掛かる)
当バンドは現行3人のみで動いていますがこれは国内外を廻って行くために経費面を含め早々に上記の事に気づいたからです。
我々の場合は
①メンバー人数ミニマム
②機材の最軽量ミニマム化(荷物費)
③格安航空券活用で移動経費ミニマム
④会場環境要因でパフォーマンスが落ちるのが嫌なので自分達の音を自己完結できるように備えておく(イヤモニやクリックなど)
普段からこれらの整備に勤しみつつ活動範囲を拡げられるよう心がけています
EXODUS規模でも大変なのですから我々の様な超小規模バンドは必然的に工夫が必要になってきます
その様な事を想像するとそれをやってのけている大所帯バンドにはリスペクトしかないですし本当に凄いことだと思います。
いやらしい話になりますが、つまるところバンド活動は経済的余裕が無いと難しいです。つまり余剰で音楽活動できる生活環境でないと難しいです
「練習する暇があるならお金を稼げ」
「幅広い音楽活動をしたいなら先ずはお金を稼げ」
とはよく言ったもので
夢を壊すようで恐縮ですが、無理をしたところで途中で続かないか結果的にローカルでの活動範囲が精一杯になると思われます。
10代、20代で音楽活動一筋なプレイヤーは、上記現実を先に知っておくことで将来幅広い音楽活動をするためには何をすれば良いのかに早く気づけるのでむしろ上手くやれると思います
ガチなら迷っている時間はない
ガチでバンド活動をやりたい人は「迷っている暇はない」です
迷っていると一瞬で老けて高年齢にまで辿り着いてしまいます
後で後悔するみたいなショボいメンタルになるならば「前のめり」でやれば良いと思います
我々は90年代の結成バンド。古いメンバーも高齢化してきています
ですが今更ながら「今やらずして、いつやるんだ」という気概が益々強くなってきています
なので本気で音楽をやりたい10代、20代の方は「めいいっぱい」やることをお勧めします
もちろん若いというのは「勢い」というアドバンテージもありますが、マイナスも沢山あります
どういことかというと「海外でも活動したい」とか「あの機材が欲しい」とか、「カッコいいMVが創りたい」とか、「世界的エンジニア氏にミックスして欲しい」とか、、、そういうことを考えた時
そもそも活動費用(原資)が無ければ何も出来ないからです
そういうこともあって20代で思うように行かず諦める人や、思い悩んで鬱病になる人も多い様な気がします
もしも、、10代、20代だけでバンドを組んで上記の様な活動をしたいならば「誰かがお金持ち」か、「富裕層2世」か、「起業して同年代よりも桁が違う経済力を持っている」かになると思います
過酷な話ですが原資が無いとどうにもならないので
極端な話、例えば貴方がヨーロッパ巨大メタルフェス出演枠が貰えたとしても、そもそも往復航空チケットが買えなければ出演は叶わないです。バンド単位ならば行くだけでも100万円位は必要でしょう
いつも言い続けていますが「金持ちの道楽レベルの心持ちでやれないと心が歪んで行く」です
どうしたらよいかですが
10代、20代の方で、本当に本気で音楽活動したい、自身の人生を音楽活動に捧げたいくらいに真剣で強い意思があるならば経済力のある年上の年齢の人とバンドを組む、もしくは誘うです
その他には、既に有名なバンドに入ってそこで自分を発揮して行くかです
どれにも属せないならばYoutubeやInstagram等で個人でバズってからその余波でやるかどうか
そのくらい音楽活動を続けることは難しいですし、たどり着けない道が沢山あります
我々も2020年から再活していますがこの5年、一歩一歩な亀足ペースですし、いわゆる「超小規模バンドなまま」です
それを考えると未だ10代、20代だから若いと思っても高齢化するまで一瞬です
あくまでですが、もしもガチならば中途半端な考えでは厳しいのと「中途半端なら中途半端にしかならない」です
特にエクストリームメタルという興行を含む音楽活動への茨の道を選んだ人には是非伝えたい内容かもしれません
ここまで色々と書いてきた内容を総合するとバンドには「経済力+頭脳プレイにも長けたメンバーが居る事」は必須だと思います
【追記】もう一つバンド活動における重要事項としては外国語です。方向性次第とは言えせっかく海外のバンドやプロモーターと知り合えても意思の疎通が出来ないとそれっきりな関係になる可能性もあります。言語が出来る人であれば表面上だけでなく深く懐に入ることが出来ますし更に次のステップに繋がる関係構築や情報取得も出来る上にどんどん人脈も広げていけます。なので、もしもバンドメンバーを探している段階であれば探す際に「プレイヤー兼外国語話者」であることもオススメかもしれません。あとはお金で解決できるなら別ですが、そうでないならばアートワークを含めデジタルデザインが出来る人もバンド内に必要です
※色々と要求が厳しいかもですが「これが現実」だと思って取り組めるならばガチでやれると思います
盲目的に好きになれるまでがバンド活動の最終地点なのかも
メガデスは10代からずっと好きで聴いてきています、学生時代はコピバンも沢山しました
そのメガデスが2026年にラストアルバムリリース&ラストツアーを宣言されています
新曲もすぐに聴かせて頂きました
楽曲については、新鮮さというよりも大佐がギターを弾いて歌っているだけで満足というか
もはやそれがメガデスの代名詞
「創作目線」で聴くとこれまでの焼き直しやHoly Wars時代の様なキレキレ複雑リフな創作では無いと感じますが当方にとってもはや「盲目的に好き」という次元なのかもしれません
我々は「作品毎に進化を遂げる為には何が出来るか」という様な勝手なプレッシャーというか焼き直しでは無い新しいものを創ろうとする部分があります
それはもしかしたら我々はまだまだ音楽的挑戦への欲求が残っており、これは盲目的に応援くださる方達を欲していることの裏返しなのかもしれません
とはいえ、同一人物が創作する限りその範囲は「自然に身を任せた創作行動」でも良いのかもしれませんね
そう考えるとなんというか「無理して背伸びするような必要は無い」というか、わざわざ奇をてらったことをやってやろうなんて思う必要も無いのかもしれません
現代においてはギターの音階にしてもドラムパターンにしても「既に出尽くしている」とも言われていますので音楽創作はある種のパズルの様な音の組み合わせとも
これが幸いなのかどうかは分かりませんがサブコンシャステラーは結成が古いこともあり既に「サブコン節」があるので伝統芸というか、続けながらも新しい取り組みもやって行きたいと思います
メガデスの新曲を聴いて改めてそう思ったのと結局それがバンドの個性に繋がっているのだと思います
大改革計画
「ライブ」=「ショー」
ライブは演奏やビジュアルだけでなくパフォーマンスやその魅せ方も全て込みでのショーです
近年は有難くも多くの国でのツアーをさせて頂いています
その経験を通じ、ショーを「”眼”で聴いていただきたい」という想いが強くなりました
我々はこれまでその部分に関して大いに不足していたと感じました
来年以降少しづつですが「ライブのあり方」を変えて行こうと思います
慣れや試行改善も必要ですので一気に全部変えるのは難しい為、一歩一歩ではありますがそのプロセスは見守って下されば幸いです
詳細はここでは書かない方が良いと思いますので来年2026からのライブ会場でその変化の過程をお楽しみに
興行ビザ/値上がりしてきている
我々日本人バンドが海外でツアーを行う際の興行ビザ取得費用が値上がりしてきています
来年(2026年)のツアー段取りをしているのですが某国でライブする興行ビザ取得費用は1人約75,000円
当バンドは3人編成なので75,000円x3人=225,000円
プロモーターさんと交渉の末、興行ビザの取得費用は自己負担
我々の様な超小規模バンドでかつ非有名なバンドはそうなります
ですので該当現地国でライブをするのに先ずは自己負担225,000円掛かる所からのスタート
有名バンドにならない限りバンド活動のコストは掛かり続けます
これまで、このブログ内で何度書いてきたか分かりませんが「音楽活動ができる経済環境を整備できる人」が「音楽センス」そのものです
環境整備できなければ音楽を届けに行く事すらできませんからね
現在、幸いにもメンバー全員がその環境があるので活動ができています
普段の練習や創作、自己研鑽、ライブでのショーパフォーマンス等は当然というか、そもそも音楽活動をする上での前提ですので
来年のツアーも非常に楽しみです
【追記】上記とは違うエリアではありますがつい先日、当バンドのヨーロッパエリア担当マネージャー窓口が出来ました。本当に感謝ですし将来招聘チャンスを掴めれば行きたいです
激速スウィープ奏法をしながら兼ボーカルが出来る人
表題ですがそれをライブでやっているバンドってなかなか見つけられないです
参考にしたいと思うのですがなかなか。しいて言えばNecrophagistのギターボーカル氏
我々は現在、次作創作中ですがその中に「激速リズムスピードに激速スウィープを乗せながらメインボーカルを取る曲」があります
実際、歌いながらそのフレーズを弾くというのはメチャクチャ難しいです。
そもそも「弾く事自体難しいのにメインボーカルを乗せる」という
でも、その曲はイメージ的にそうしたいのでやるのですが
どんなトレーニングを積めば良いのだろうと考えながら遂行しています
でも経験上、いつの間にか出来ています
出来るようになるまで「考えながら練習する」といった感じです
我々は新作毎に技術的な挑戦をする曲も創っています
自身のスキルアップにも繋がりますし幅も広がると思っています
なにより「自分で創った曲なのに弾けないは無い」のでその分、練習量がかなり増えることもありそれは良いことだと思いトレーニングしています
来年以降になりますがご期待くださいませ
扇風機ヘドバン
我々の音楽の世界では昔から続く伝統パフォーマンスの1つである「扇風機ヘドバン」
英語では「Windmill Headbanging」と言われています
これ実際には難しいです
体幹が重要で楽器を弾きながらやるのであれば相当な練習が必要です
肩から下は体全体が動かない様に固定できないと演奏が崩れます
「弾きながら扇風機ヘドバンが出来る」プレイヤーで「最も美しい」と思ったのが元Cattle Decapitationで現CRYPTOPSYのパーマネントメンバーであるOlivier Pinard(オリビエ・ピナール)さん
(ただし彼の場合は直毛ではなく髪の毛の中間より下の方は束感あるパーマが掛かってらっしゃいますが、それも有用ということですね)
ちなみに扇風機ヘドバンについて「チョットやってみよう」ですぐ出来るものではないです
やってみると分かりますが首を回そうが単に髪の毛がバラバラになるだけで扇風機の様には回らないです
どうしたらよいのかですが
ワックスで髪の毛の束(1cm~3cm)を作る事で解決しやすいです
そうすることで束感とその重量感も相まって首を回せばグルグルと髪も回り易くなるでしょう
イメージとしては洗髪後にドライヤーで半乾きのような状態に近いかもしれません
気になる人はツアー時の機材セットの中にワックスを忍ばせておくと良いでしょう
その他の注意事項としましては、イヤモニはリケーブルして1.6mにしておいた方が良いです。標準の長さだとヘドバンの勢いで万が一、受信機からスポッとジャック抜けの可能性も否めないのと実際にこれまで共演頂いた世界的デスメタルバンドの方達が「これから受信機を付けようとするタイミング」では耳から膝くらいまでの長さのイヤモニケーブルがぶら下がっていましたので正にです↓
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/209630
IEMシステムの再構築
我々は現況、全員がイヤモニでクリック(リズムトラック)を軌道にしてライブをしています
ですが会場環境依存でモニタの返し音量バランスであったり、アンプの音量で音が廻ったり、ステージ上の音の分離が難しかったりで「行き当たりばったりでパフォーマンスが落ちる可能性」を究極まで無くしたい想いがあります。
せっかく足を運んでくださったお客様に最高のパフォーマンスを届けたいです
近年、世界的に有名なツアーバンドとの共演が増えてきました
我々はその都度、彼らから機材環境について根ほり葉ほりヒントを頂いています
そして表題です。
現況のリズムクリックトラックだけ聴いて演奏している事に関し改訂を行います
どういうことかというと距離の離れたアンプから鳴る音を聴き取りながら演奏するよりも、アンプから鳴っている音をイヤホンから直接聴いた方がアンプからの距離も気にせずダイレクトに演奏することができますよね
結果、イヤモニからは「リズムクリックトラック」と「自分の弾いている音」を混在させて聴きつつ演奏したいところに辿り着きました
どうやるのだろうと
先日の世界的バンドのツアー帯同中にそれを学びました
どうりでステージ内の音量が控えめなんだと。
なんならステージ内はドラムの生音が鳴っている位の印象でした
これで完全に腑に落ちました。
ステージ内で爆音だと何をやってるか分からなくなりがちで音の分離もおかしくなりがち
お客様側で聴こえてくる音はあくまでアンプやドラムに近づけて設置しているマイクで拾った音を外のスピーカーに繋いで鳴らしている訳ですから、自分の音を聴き取りたいが為にステージ内を爆音にする必要は無いという結論です
アンプからイヤホン(イヤモニ)で聴けば良い訳です
これまでに共演等をさせて頂いて来た世界的有名バンドはどのバンドも殆どがこのやり方(リズムクリック+自分の奏でる音でライブを行う)であることが判明しました
「なるほど」しかないです
更に大きな利点がありました
それは「リハーサル時間の大幅短縮」です
このIEMシステムが構築されている時点で「全てが自己完結」していますので、リハーサルの際は「音が鳴るかと聞こえるかの接続チェックだけ」です
先日のCryptopsyツアー時、「リハーサル」も三日間みっちり学びの場として過ごさせて頂きました。
彼らにとってのリハーサルは「ほぼ接続時間のみ」です
つまりラインチェック、要は「機器がちゃんと繋がっているか」のチェックです
なのでリハーサル時間内での実際の演奏は「曲の出だしから30秒ほど」プレイしただけでリハーサル終了でした。(但し外音は専属PA氏が持ち込みで来ていたので、我々の様な専属PAが居ない場合はライブハウスPA氏の外音調整時間が必要なので曲を演奏する必要がありますが)
これぞラインチェック(リハーサル)です
正にガチプロのやり方だと感嘆しながら帰国してきました
メリットしかない素晴らしい手法だと思いました
実際に構築する方法ですが、我々はDIY系ですので高級機材は使えない前提になりますが以下へ。
現況の我々のMTRからは「自分達で聴くリズムクリック」と「PAに返すオープニングのSE」の2つがあります
具体的にはMTRからミキサー(を準備)に繋ぎ、そこからギターアンプ(DI)側とベースアンプ側(DI)に接続すれば、クリックも聴きつつ自分のアンプから鳴る音もダイレクトにイヤモニで聴こえるようなるシステムです
ミキサー例はこちら↓
BEHRINGER ( ベリンガー ) X AIR XR18 リモートコントロール・デジタルミキサー 送料無料 | サウンドハウス
しかもこれならリズムクリックと実際に弾くギター(ベース)の音量調整も個別にできますから自由度もありますね
なんでこんなシンプルなことに気づかなかったんだろうとも思いますが今後はこの手法をフル活用しライブパフォーマンスが毎回最高になれるよう目指してやっていきます
「I NEED!」に感謝と感激(CRYPTOPSY)
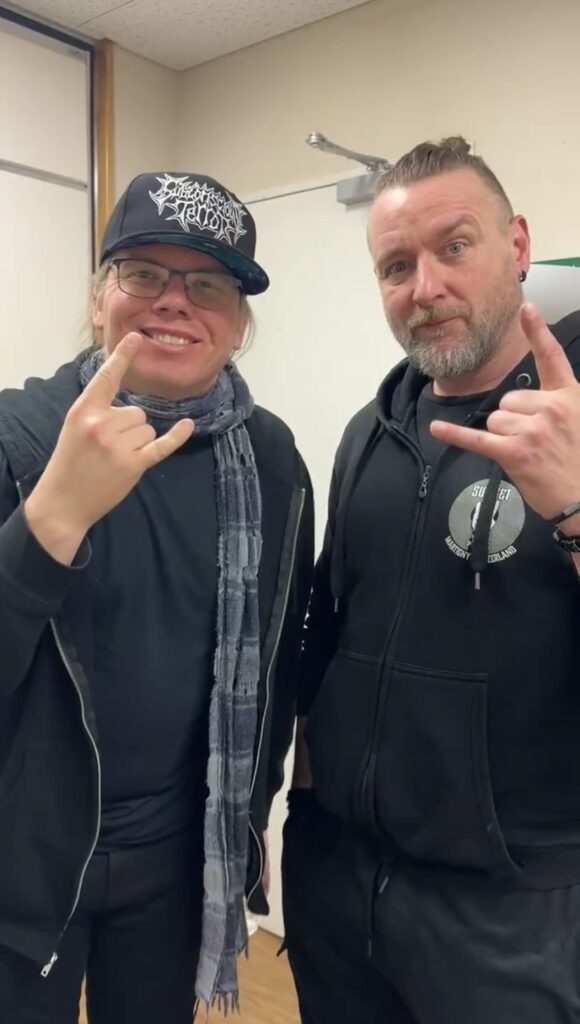
CRYPTOPSYとの中国ツアー3DAYS出演について
ご存じ通りかもしれませんが日中関係の影響で我々は中国へ渡るも出演は出来ませんでした。
本来であれば二年ぶりのCryptopsyとの再共演でした(前回は2023年の東京ショーで共演)
今回の内容は彼らとの滞在期間中の出来事の1コマです
CRYPTOPSYメンバーとは都合5日間一緒に過ごさせて頂きました
滞在中、当バンドロゴキャップを手に持っているタイミングでCRYPTOPSYボーカルのMatt氏が「I NEED!」と当方にお声掛け下さいました
我々メンバーは長髪なので普段は髪を括ってサブコンシャステラーのロゴキャップを被っていることも多いです
驚きと共に嬉しい思いでMatt氏へプレゼントさせて頂きました
とても気に入って下さり、その後もずっと被ってくださっていて大変嬉しい限りです
更に次の日にはドラムのフロモーニエ氏からも「俺にも!」ということでプレゼントさせて頂きました
Cryptopsyについては当方は彼らのデモ時代(当時テープトレードで回って来た)から聴いてきています
■1992年結成Cryptopsy(カナダ)
■1994年結成Subconscious Terror(日本)
活動規模は全く違えども年代的には同じくスラッシュメタルとデスメタルのクロスオーバー時代を過ごした世代です
今回、ホテルも隣の部屋でしたし一緒にご飯を食べたり共に移動したり
全てが記憶に残る思い出となりました。
我々も彼らもあの当時(90年初期)、デスメタルが産声を上げた時代を実体験してきたほぼ同世代です
帰国日。
彼らは韓国へ、我々は日本へというタイミングの空港での別れ際、
「今回、君たちは悲しい出来事になったけど次回絶対また一緒に演ろう!」という会話でフェアウェル帰国してきました
Cryptopsyに感謝です

さっさとブーストすべきなのか否か
世の中の多数のバンドがプロモーション費用としてフォロワー数と再生数を購入している話を聞きました
確かに一理あります
①「たとえ世界で一番スゴイ曲なるもの」を創っても世に届けられなければ誰にも聞かれない
②「有名だから」「再生回数が多いから」「フォロワー数が多いから」で「このバンドはスゴイ」と信じ込む社会
つまり我々の様な超小規模バンドが馬鹿正直にコツコツやっていると「いつまで経っても」の流れです
なので「サッサとやった方が良いよ」の助言
我々は超小規模バンドです
例えば音楽メインSNSであるInstagramを挙げるならフォロワー数で4000未満です。
ブーストしてサクサク1万人以上や10万人以上のフォロワー数を買う事もできる様ですががやっていません
地道です
これって難しいところで例えば10万人フォロワーをさっさと買えば大規模フェスに出演出来たりの可能性が上がります。あとは「このバンドはスゴイんだという妄信」により「曲も素晴らしいと妄信」されるので効果は抜群でしょうね
つまりバンドにとってはサッサと購入すれば「フォロワー数が多い」=「このバンドはスゴイの妄信」=「ライブチャンスも増える」の図式
心理的には「単なる見せかけ」ですからそんな事までしてやるのかという葛藤がありますよね
Youtubeも同様再生回数が1000回単位~100万単位で普通に売っています
もはや内容と再生回数は意味をなしていないです
単なるプロモーション費用になっています
我々はこれからも意欲的に海外ツアーを含め色んな国を廻りたいです
音楽を通じた国際交流をしたいからです
ですがそれを潤滑に進めるためには買わないといけないのかもしれないという葛藤との闘いがありますね
結論的には「やめておきます」ですが幅広い活動におけるハードルはやはりあります
こういった競争については「なんだかなー」ではありますがそういう人たちがいる限り、その人たちよりも我々はチャンスが少ないかもしれないのが現実とは言え諦めずにこれまで同様にその壁をぶち壊して行く所存です
数十年後のデスメタルバンド形態予測
我々は全パートが人間による演奏でのライブバンドですが近年は1人でデスメタルやブラックメタルをされているプレイヤーが以前よりも増している?という話を聞きまして
確かに1人だとライブ日程の都合、経費、好きな時にやれる、メンバーを探す必要も無いという
ビジュアルに関しても例えば我々の様な長髪に拘ってやりたいとしても自分1人だけが長髪であればOKですのでそのハードルも無いですね
ライブ視点でいうと、現在は未だ先入観もあって「ライブ=フロントマンが複数いて後ろでドラマーがいる」という視覚的要素重要度の比重が高い(音楽性の視覚表現)かと推測しますが(もしかしたら既にそうでは無いのかもしれませんが)将来、例えば数十年後にはこういったワンマンスタイルでのエクストリームメタルが自然に息づいている可能性もありそうです
現実としてこれからの5年でデスメタル創世記時代の人達が年齢的にも大量引退時代に突入します
第二、第三世代(2000年)のバンドも数十年後には引退世代になります
そうなってくると2030年、2040年頃にはデスメタルバンド自体がかなり少数になっている可能性も考えられます
エクストリームメタル黎明期の出で立ちについて
エクストリームメタル創世記(80年後半~90年中期)における出で立ち(ビジュアル)の大部分は以下でした
・スラッシュメタル→ジーパンにバンドシャツ
・デスメタル→黒服にド長髪
何故かと言うと、当時はインターネットも無かったですし「写真で見るビジュアル」と「CDのジャケット」でその音楽性を判断するしかなかったから
つまり見た目で「これは激しい音楽」であろうと予想判断するしか無かったからです
我々も黒服に長髪でのビジュアルが自然な流れでしたし現在もそうしています。
当バンドは結成当初からそのビジュアルなので「正装として自然」というか今もシックリきます
数十年後のデスメタルシーンがどうなっているかですが
以前にもここで書きましたが、もちろんAI音楽も席巻しているでしょうしその頃には音楽自体が人間とAIの共生状態だと思いますので以前から言われている「ライブ」とは「人間の演奏を浴びることの出来る体験」という付加価値はありそうです。
ただ、その頃にはそれをプレイする人間自体の数が激減している可能性もあります。特に我々の様なデスメタル音楽だと尚更
つまり全楽器のパートを生バンドでやれたとしても集客や興行成立するのが更に難しくなり、結果としてバンド活動を諦める人や、そもそも目指さないであったり、音楽制作まではやれどもライブ迄はやらないという人。もしもそれでも演る人は1人パフォーマンス形態のデスメタル。勝手な私的推測ですが
1人バンドでのライブ演奏だと下記3ケースが挙げられます
①自身はギターボーカルでドラムは音源を流すベースレス形態(ベースも音源を流すも有り)
②自身はベースボーカルでドラムは音源を流すギターレス形態(ギターも音源を流すも有り)
③ドラムボーカルでギターとベースは音源で流す形態
イマドキはこれでライブを演るのも機材的には簡単ですからね
例えばRolandから出ている型式SPD-SX機材。自身の楽器以外はこれ1つ持参しコンセントに繋げばOKです(正確にはPAに返すのにDIを持っていけば)
ワンマン形態でライブをするときは演奏曲毎にこの機材のパッド部をポチっと踏めばドラム音源がライブ会場のスピーカーから鳴らせて、もう一つのチャンネルからはカウントを入れたクリックトラックを鳴らしイヤホンで聞きながらドラム音源に合わせて演奏することも出来ます(ドラム音源とクリック音源独立方式)
こういうケースは数十年後、もしかしたら日常光景になっている可能性も感じています
なので創作出来る人がAI楽曲と対抗しながらライブシーンの中心になって行くかもしれませんね
レコーディング忘備録
「例の時期が来た」と言いますか来年(2026年)レコーディングをしたく、その下準備に入っています
新譜創りと言えども、ただ曲を創れば良いというだけでは無く「下準備」も相当重要になります。
大雑把ですが楽曲の創作をしたとして我々の場合は先ず以下の流れで進行します
①ラフデモ創作(把握用の粗音源)
↓
②譜面を作ってメンバー内で相互確認
↓
③プリプロ創作(本番レコーディングに向けたほぼ完成状態)
↓
④本番のレコーディング
④の「本番のレコーディング」に関し我々のスタイルだと下記マテリアルを1つづつ録音して行きます
①ドラム
②ギターバッキングA
③ギターバッキングB
④ギターソロA
⑤ギターソロB
⑥ベース
⑦ボーカル
⑧コーラス
⑨SE
事前にこれらのマテリアルを「いつ、どこで(スタジオ)、どの様にレコーディングするのか」を決めて下地を作っておきます
レコーディング前にはドラマーも下準備が多いです。レコーディングの際、フロントマンはリズムクリックトラックを聴きながら録音していきますので事前に全曲分のリズムクリックトラックを作りますので「暫くPCと睨めっこする期間」があります。
前作(現最新作)「Devoid of seraphim」のレコーディングは大阪のスタジオと当オフィスREC部屋で録りました(次作はどこで録るか現在検討中です)
そしてアートワーク(事前に依頼後、実際の開始日から完成までの納期想定3か月)やミックスマスタリングエンジニア(事前に依頼後、開始日から完成までの想定期間1週間)についても先にスケジュール手配進行をしておきます。特にアートワークはレコーディングの半年以上前からある程度想定しながら動いています。
ミックスマスタリングに関しては事前にエンジニア氏のスケジュール確認と共に依頼情報をまとめておきます
我々のやり方だと以下です
■Rec/48khz/24Bit
■ボーカル、ギター、ベース、コーラスの各トラック数&Dry wavの準備
■ドラムは録音したドラム音のデータ化(Midi)とリファレンス用のドラム2MIX wavの準備
■DDPマスター(=CDプレス工場用データ)、PQシート(CDプレス工場への指示書の様なもの)納品依頼
ISRC(識別コード)については自分で取得していますので曲毎のTIMEが決まった時点で申請手続きしています。あと加えて著作権登録もそうですね、当方は著作権協会の会員継続していますので引き続き自分で申請しています。この時期はとにかく鉄人生活のようなタイミングになります。
話が少し戻りますが特にギターのレコーディングはひたすら弾き倒す期間
どういうことかと言いますと当バンドは三人編成のシングルギターバンド。
ですがCDはステレオ音源(左右)ですので複数本を重ねてギター録音します
①先ずはギター1本目を録音
↓
②その後も弾き倒しながら2本目も録音
録ったあとは①と②を同時に鳴らして間違いやおかしい所が無いか全体確認をしますがその際に「なんとなく思ってたのと違う」というような違和感があった際はやり直すのでそこで沼にハマる時が往々にしてあります(ほぼ毎回)
ボーカルに関しては防音室に1人で籠ってひたすらですね。ボーカルのミックス関しては知識が無いのでエンジニアさんに基本的には一任ですが「録音した生声」に少しSlap Back Echoを掛けて頂く感じで依頼しています
全ての録音が終わったら、いよいよミックスマスタリング行程に移るのですがエンジニアさんに気持ち良く対応頂ける様なやりとりをしつつ、現在は有難くもレーベル契約しているのでレーベル側とも話を進めながらやっています
あくまで我々の場合はですがレコーディング時期は予めの下地と共に一気に同時進行します
他にもレーベルのデザインチームとのMV制作、マーチデザイン、生産管理担当とのフィジカル納期スケジュール、リリースアナウンス時期、デジタルリリース時期、果ては実際にCDショップさんに並ぶまでの想定をしながらスケジュール打ち合わせしていきますので正に千手観音のような動きになります。
ちなみにミックスマスタリングが終わったとしても実際に店舗に並ぶまでとなると最速でもそこから半年は掛かるだろうと見ています。DIYなら別かもしれませんがレーベルからのリリースだと半年ならむしろだいぶ早い方だと思います。
特に規模が大きいレーベルの場合、多数のバンドを抱えていますから予算も含めてリリーススケジュールについてもベルトコンベアの如く「バンドの並び」もありますし、そもそも工場プレスの順番も”並び”があります
上記のやり方はもちろんバンドによっては1づつを終えてから次のステップを考えて行くパターンもあるのでしょうが我々は「録り終えたら早くリリースしたい気持ちが強い」のでこのような動きをしています
この一連の流れに関してはようやく慣れて来たところです。
「例の楽しい期間がやって来る」という感じですやっています。
余談ですが、興味深いのが「ラフデモ」を作った時点の曲印象から「仕上がった最終音源」で聴いた感じがガラッと雰囲気の変わる曲もあります。なので当初の想定から楽曲順を変えることもあります。
あと聞いた話ではギターレコーディングに関しては右1本、左1本に加え更に中央1本で計3本録音したりすることも多いそうで(音が良い)、中には4本録音も多いそうです。我々の様なシングルギターバンドだと相当根気が入ります
DEATH(BAND)の出現当時
Deathが日本にマニアの間で伝わって来た1990年初期を思い出してみます
当時の個人的な最初の感想は「メガデスのデスラッシュ版」という思い出があります
そして聞けば聞くほどに「ドラムが凄い、ベースが凄い」、「ギターリフがキャッチ―で聴きやすい」でした
正にスラッシュメタル黄金時代における、皆が模索していたデスメタルとのクロスーバー期です
その後、「Indivisual thought patterns」(1993年)がリリースされると彼らは一つのポジションが確立されたというかインテレクチュアル・テクニカル・デスメタルの走りになった印象です
1995年の初来日時にライブを観に行き故チャック氏にデモテープをお渡しできましたね、そう言えば。
歌いながらテクニカルギターを弾く彼のライブスキルにはとにかくビックリしましたし、最前で観れたので(集客面ではまだ来日は早すぎたのか…)マーシャルアンプからの直音でショーを浴びれたのを覚えています。
その後、この流れはNecrophagistの様なデスメタル方向に全振りした激速テクニカルデスメタルバンドが出現
そして2010年以降の現代はグチャグチャなくらいにテクニカルバンドで溢れています
ただ思うのが我々もそうですがDeathが今も続いていたとしてもやはりその新曲もDeathだと思います
つまり楽曲の方向性はNecrophagistの様にはなってないと思います
コンポーザーは何か大きな契機(例/商業向けに変化)でも無い限り、音楽性が変わる事は無いと思います
我々現在、次作の創作をしていますがこれまでの方向性から大きく変わるような事は考えたことがありません。更にブルータルな楽曲にはなるかもしれませんがやはり気持ち良いスラッシュビートやブラストビートに感化されているバンドなので疾走感を主軸に仕上げて行きたいと考えています
タイムテーブルマウントの世界
我々は出演順番を気にしないバンドですが(気にするほどの規模でも無いですし)、世の中ではそれをバンドの「格付け」として見る人も

上記の様な有名バンドが揃う場合は出る順番を決める主催者(プロモーター/エージェント)はシンドイでしょうね、心中察します…
それは何故かですが「気にするバンド」も多いからです
まるで会社の係長、課長、部長の様な感覚で出る順番を捉えるバンドも存在します(と言いますか多い)
我々ほど超小規模バンドであればどの出順でも気にすらなりませんが中規模以上の知名度あるバンドは気にするバンドも多いです
主催者は恐らくSNSフォロワー数、ストリーミング再生回数、レーベル規模、結成年(先輩/後輩)などから総合して苦肉の策で出順を決めているかもしれませんが出順を決める際は板挟みでしょうね…
余談ですが以前に「どちらがトリで出るかで揉めていた」ライブがありました。我々はOAだったので無関係ですが、その日は非常に気まずい雰囲気でした…
音楽で世界を廻ることが出来れば
先日、南米からファンジン掲載の件で連絡を頂きました
感謝と共に突然そのようなコンタクトを頂けることにビックリします
現地国での紙媒体リリースだそうです
来年の発刊号内容なので詳細は伏せますが毎度思うのがどうやって我々の様な超小規模バンドにまで辿り着いて下さるのだろうと
その後、主宰の方とのやり取りを通じて事前に完成版の紙面内容の画像を送ってくださいました
スペイン語なので翻訳機能での和訳理解になりますがこのようなサポートには感謝しかないです
チャンスを作って将来現地で「生の音」を届けに行きたいですね
国内においては残念ながらそういった紹介やインタビュー系のお話はほぼ無いので我々の音楽性は海外向けなのかもしれませんがそれでも国内で我々をサポート下さる方々への感謝の気持ちは発信し続けていきたいです
国内メディアに対しての能動的なアピールは出来ていませんので(≒していないとも)自業自得ではありますが…
バンマスはSNSのPRが苦手なのでバンドメンバー内に「国内向けPR係」が居ると良いかもです
そして今回の表題について
「音楽で世界を廻る」というのはバンドメンバー全員が海外に出ていける生活環境と意気込みが整わないと出来ないです
誰か一人でも欠けると難しいです
現在はそれが叶いそうなメンバーが揃った状態なのでしっかり中長期目標を立てながら遂行して行きます
知識なのか感性なのか、そのバランスなのか
とにかくバンドを知らないです、他のバンド知識が薄いです
お客さんやメタル系友人との会話に出てくるバンド名に殆どついて行けない程に…
いわゆるメタリカ、メガデス、スレイヤー、セイダス、ディーサイド、カーカス、カニバル、クリプトプシー、サフォケイション、ナパームデス、デス辺りが自分のこのジャンルで聴いて来た範囲
近年は学習の為にSNS上に流れてくる「来日フライヤー」で知らなかったバンドを知る機会や聴く機会を増やしているといった具合です(90年代前後はジャケ買いかファンジンが頼りでしたからね)
でも、エクストリームメタルへの情熱は人一倍強いです
創作について想う事があります
①知識が凄い人が、その知識を以て創る曲
②知識が薄く、感性に頼って創る曲
当バンドは現況②に偏り過ぎています
②はバンド「節」(全てサブコンらしい)が出るとは思いますが、その範囲を拡げていく事ってどうなのでしょうね。何かそこで発見があるならばと思い極力他のエクストリームメタル等も聴こうとはしますが結果的には特に影響を受けることはない気がしています。むしろこれまで他ジャンルを聴いて来た幅の方が多いです。
「音楽は10代に影響を受けたものを歳をとっても・・」とはよく言いますがどうやら当てはまっているようです
特に学生時代だった80年後半~90年代は音楽混沌時代
あらゆるジャンルの創世記~成熟へ向かう時代でしたので余りにも衝撃が強すぎて今もそれがずっと残っているのかもしれません
そこから数十年を経た訳ですが近年のバンドは機材発達だけでなくプレイヤーがとにかく巧いです
何かヒントになればと能動的に近年のデスメタルやスラッシュメタルも聴いて行こうと思います
セッティングは日頃の習慣
公演の際、1曲でも多くリハーサルをしたいので日頃のセッティングの速さを重要視しています
先日SNS上で、リハが押して開場から終演が1時間押した様な内容が流れてきました
機材トラブルや交通事情、天災、不可抗力ならいざ知らず、単純にモタモタとリハーサルが遅いのはバンドの責任
公演では内部的なタイムテーブルがありリハーサル時間も決められています
それを守れないバンドはアマチュアです
事前にリハーサル時間が分かっている訳ですからそのリハーサル時間内で演れるようにセッティング準備しておくか、それが無理なら事前にプロモーターに対してリハーサルに掛かる時間を事前交渉しておけば済む話だと思います
当バンドのフロントマンは基本的に「5分以内で音出しまで完了する」でやっています
ドラムは各パーツの位置や高さ、更にトリガーやクリック用MTRやイヤモニのセッティングもあるのでもう少し掛かりますがそれでも10分
もちろんリハーサル時間は多く頂けることに越したことは無いですが、セッティングが早ければ早い程に1曲でも多く確認できますからメリットしかないです
ミニマムが20分でのリハ完結(ステージに機材を持ち込む所から→リハ→撤収まで)
①5分後→フロントマンのセッティング完了
↓
②10分後→ドラムのセッティング完了
↓
③残り10分で先ず3分台の曲の演奏し各自&PA確認
↓
④次の曲も3分台の曲を演奏し各自&PA双方で「最終チェック」
↓
⑤残り時間は機材を抱きかかえたまま楽屋へ戻る(撤収)
この辺りのセッティングについてはリハスタを含め我々の基本になっています(あと、セッティング中の”無駄音&無駄吠え”を出さない事については書かなくても分かると思いますが念のため)
ちなみにバスドラムへのロゴカバー掛けはセッティングが早く終わったフロントマンの作業です
そして公演が終われば「ステージの上」では片づけずにそのまま機材を抱きかかえて全部楽屋へ
ステージの上でモタモタとシールドを巻いたりは次に出演するバンドの時間を取るだけですからね
抱きかかえた機材を楽屋へ持っていくのが終わった人から順に他のメンバーの残りの荷物を手伝います
時間を守るという事だけでなく次のバンドが少しでも早くにセッティング開始できるようにです
これらって我々にとっては当然の動きなのですが上記の様なそれが出来ないバンドもいるのでしょう
いわゆる自己中心で「自分達さえ良ければ良い」の思考
我々は超小規模バンドですしとにかく共演バンドや主催に迷惑を掛けないを徹底しています
とはいえ、どんなバンドも最初は小規模から始まる訳ですからこれらはバンド自体がその意識(タイムルール)が無く、考え方がアマチュアのままでいるのだと思います。厳しい言い方をすると単なる我儘
大御所気取りの勘違いバンドは厳しいです
以前から何度も書いてきていますが「練習」とは演奏だけで無く「普段からのセッティング最速を目指す練習」も含めての準備です
(余談①)海外ツアー時の経験話ですがタイムテーブルの「リハーサル時間」と「本番時間」が徹底されていて(遅れたら)「ブチっとミキサーの電源を落とします」と事前に出演契約内容に書いてあるものもありました。むしろそれが普通というか。今回のSNSの内容がもしも機材トラブルや交通事情や不可抗力等の理由では無く「単にダラダラとリハーサルをしている」ならば、むしろ主催側の管理不足とバンド側の準備のノロさがお客さんと会場へ迷惑を掛けている可能性があります。リハの途中であろうが電源を落とすくらいの事前予告を徹底した企画のコントロールが出来ていないのでしょう。現場を見ていない限りは推測でしか無いですが、双方がアマチュアなのかもしれません
(余談②)「ステージの上で片づけるな」(全部そのまま抱きかかえて持って行く)については海外ツアーで学びました。逆に海外でモタモタ片付ける人は居ないです。大規模公演の際は複数人のスタッフさんが待機していて、演奏終了後はすぐにスタッフさんが当方のアンプからシールドを抜いて全部そのまま機材を抱きかかえて楽屋へ持って行ってくださりました。そののまま入れ替わる様に次のバンドがステージに入ってきました。この手際の良さには大変感心しましたね。他の公演の例では「リハ時も本番時もステージの上で片付けてはならない」(機材ごと抱きかかえて楽屋で整理して下さい)と出演契約内容に書いてあり、ライブ当日もバンド毎にその場で重ねてアナウンスがありました。素晴らしい興行コントロールですよね
すぐに洗脳され過ぎるのと世直し大名が多い日本
敗戦後の軍隊教育の名残りで幼いころから「体育座り」や「前に習え」を始め皆んなが同じ動きをするような教育をされてきています。つまり学校の先生から「前に習え」の号令が掛かれば全員それをやらないとマズイという。制服もそうですね(当方は自由を求めて私服の学校に行きましたが)
あとは「1日3食」というのも100年近く前に提唱されたそうですからね。今や「全国民が1日3食が良いのだ」と洗脳されている事象だと思います(当時と現代の食を考えると完全にカロリーオーバーなのかもしれませんね)
これらの「右に倣え方式」(それが正しいと思いこませる)は社会性と言う意味では「電車の並び整列」とか「飲食店での並び整列」等のメリットも多いです
ただそれらが影響背景にあるのか、我々日本人は少しでも曲がったことをする人を見るや否や「許せない!」という気持ちが強い人も多く、例えば自分と意見が違うとSNS等で相手をトコトン叩き切らないと気が済まない事象も往々に
ですので良い面も多数あると思いますが反面、敵対化しやすいイメージがあります
つまり「他人を気にし過ぎる人が多い」、「他人に構って行かないと気が済まない人が多い」です
自分の人生時間を使ってまでそれをするのですから根深いのだと思います
「他人は他人」という理解無く「自分はちゃんとしているからお前も同じことをしろ!」という世直し大名
例えば22:00閉店の飲食店があったとして「21:58分に締めたら口コミにボコボコに悪評を流す人」もいます。実際問題、閉店2分前で料理をオーダーして食べ切るはできないでしょう。それが「ラストオーダー閉店30分前」とデカデカと書かれていても「営業時間は22:00だろ!」と騒ぐわけです。
なんというか…
音楽の話にしましょう
西と東で完全にシーン規模が違います
もちろん人口の差は否めませんが仮に上述の敵対化や世直し大名も背景にありそうですが「全ては人望」によるところの方が大きいと思います
なにせ超小規模シーンですからね
・誰々が企画するなら「行こう」
・誰々が企画するなら「やめておこう」
もはや、どんなバンドが出演するのか以上に上記影響が大きくなってきている可能性
加えて残念ながら西で影響力のあるバンドは皆無です(我々の様なシーンでは)
その二重苦を積み重ねてきた歴史の結果なのかもしれません
過去に某地方都市でかつ、駅からも遠い場所にある会場でライブをさせて頂きました。当日はビックリするほど沢山の人達が来場くださいました。我々の様な超小規模バンドでは実現できないことなんですよね。何故だったかですが「企画者の人望」により人が集まっていました
この例をヒントにするならば「人望ある企画者と規模力のあるバンドが掛け算でタッグを組み」シーンを盛り上げていくは重要な要素かもしれません
では規模力が無いバンドはどうすれば良いのかですが(残念ながらそれは我々もそうなのですが)
我々の現況の動きは招聘くださる国や受け入れて下さる国でライブをし続け「自力」を付けて行きながら国内でのライブ機会のチャンスを見つけて行く活動をしています
もちろん母国ですから国内で沢山ライブしたいですしね
ただ国内は良曲/駄作が無関係で知名度ありきで集客が決まります
「有名だから行く」
「非有名だから行かない」
という流れ
厄介なのが知名度が無かったバンドが「後に有名になった」としてよくあるケースとして
「あの当時に俺は観ていた!やっぱり間違ってなかった!」とか「あの時から俺は知っていたんだぞ!」とか、「あのバンドはデカくなると思ってた」とか「あの時に企画したのは俺だ!」等で「ほれみろ」的なマウントを取る人がいます。それもまた余計と言うか、わざわざ言わなきゃ気が済まないのが表題の「世直し大名」マウントです。応援するサポーターの絶対数が増えた事は嬉しいと思う気持ち、いわゆる「推し活」で良いのではないのでしょうか
ただ近年バンドの「有名」という認知され方は大手レーベルと契約したり、海外でバズったりで「有名になった」が現代のシーン。そしてそれを皆が鵜呑みにして「あのバンドはスゴイ!」と更に神輿を担ぐ流れ
これって本来はおかしな話なんですよね。例えば億万長者のバンドならば簡単です。先ず再生回数を100万回ブーストして世界大規模フェスの出演枠を買って1万人の前でライブしてそれを実績にし、大手レーベルにお金払って契約すれば、あとは駄作だろうがなんだろうが「有名だ!凄いバンドだ!」で崇められるという。だから名前すら聞いたことが無いバンドが突然大規模フェスに出てくるのです
それくらい知名度で全てを判断される現代音楽シーン
それがデスメタルまで小さなシーンにもなると本当に厳しいと思います。だからバンド活動が出来る環境整備がバンドマンにとって最も重要なのですが
そもそもデスメタルは興味が無ければ「全く聴かない」(人が大部分)ので、その上で更に知名度すら無いとなると難しいです
仮にデスメタルに興味が湧いて聴いてみるところまで辿り着いたとしてもライブにまで足を運ぶのは相当遠い道のりだと思います、我々の様なよっぽどのマニアでもないと
結論的には「有名だから観に行く」と言うところまでバンド規模が上がらないと難しいでしょう
ちなみに海外のライブハウスは食事をしにきたりお酒を飲みに来たりの中でバンドがステージ演奏する所もあってちょうど先日行ってきた韓国のライブハウスさんが正にそうでした。オープンから一般のお客さんが飲食をされていて19:00になったら夜な夜な終わるまでステージ演奏が続くという。お店としてもレストラン兼ですから経営面でも屋台骨があってのライブハウス経営です。箱バン以外が来てくれることはお店の新陳代謝としても歓迎してくださいますから出演するバンドも願ったり叶ったりです。しかもそういった場では意図せずにその場に居た方達も我々のライブをご覧くださいますので知名度という話をするならば倍々ゲームで新規のお客さんと知り合うことが出来ます。そういった通常営業時は箱バンのレストランでデスメタルライブが出来る様な所から地道にスタートして母数を得ていくのもありかもですね
今回の内容は色々脱線しながら思いつきで書いてみたところも多いので後日に思考がまた変わる事もあるかもしれませんが諸々の解決の芽が出た時に西側の再興の可能性もあるかもしれません
我々も西日本バンドなのでシーンに対して負い目は感じます
コネ無し奮闘の世界
我々は特に徒党を組むでも無くコネクションがある訳でも無く単体活動しています
なぜなら自由に活動したいからです
ただ反面難しい面もあります
例えばですが海外フェス系イベント
その殆どがレーベルで枠を持っていたりエージェント枠があったりで我々の様な単体で活動しているバンドは可能性的には非常に難しいです。お金で解決する方法(出演枠を買う)はあるのでしょうが、それはしないので
なのでチャンスを得たその1回のライブで全てを掌握して行く必要があります
掌握というと言葉が厳しいですが、お客さん、企画者、会場スタッフ、全方面で再度招聘頂ける様なパフォーマンスを出す勝負をしていくことになります
もちろんパフォーマンスだけではなくその際の関係性構築であったり様々な準備や配慮が必要です
今回、なぜこの様な内容にしたかというと
後ろ盾や出演枠を持っている人と繋がっていないと、そこから先の活動幅の拡がりが難いと感じる事もあるからです
外部から見ると近年多数の海外ツアーをしているように見えるかもですが、ほぼ奇跡的な運です
その運を活かして次につなげて行っているだけです
ですが能動的に動きたいと思った時に、既にコネ枠が決まっていればどうにもなりません
奇跡的な運の数珠繋ぎでライブ活動をしていますがやはりハードルはありますね
解決するには、残念ではありますがもはや曲が良かろうが駄作だろうが一切関係なく、単に有名になるしかないのかもしれませんね(有名だから招聘されるケース)
なのでDIYツアー(プロモーターサポート無し)をしているバンドも多数あるのだと思います。DIYツアーバンド(自分達でブッキングして勝手に行って勝手に帰ってくる強いバンド)は特にリスペクトです
速弾き練習について
我々にとっては「テクニカルギター」と言う言葉は烏滸がましいレベルなので、今回はそれを踏まえてのお話です
短距離競争で速く走る為には「速く走る練習」は必要でしょう
歩く速度で練習し続けても足は速くならないでしょう
つまるところ、先に指の動きだけサッと覚えたらあとは「速弾き=最初から全速力練習」です
練習し始めでは「速すぎてついて行けない」がありますがそれを繰り返していくと、どこで躓くのかが分かってくるのでその部分の”瞬発力”を得る練習の繰り返しです
その際に最も有効なのが「アンプに繋いで音を出して練習する」事です
部屋でもどこでもやはりアンプで鳴らして「ニュアンスまで耳で感じ取りながら練習する」のが習得が早いです
以下は自分のやり方です
例えばBPM270のスウィープフレーズを練習するとしましょう
最初に指の動きをササっと覚えた後はひたすら原曲に合わせて弾き倒します
付いて行けなくても徐々に「脳からの指令と実際の指の動きの「時差」(タイミング差)、更に言うならばモタリが減ってくると思います
つまり速弾きは「瞬発力の習得」が全てだと思います
なんとなくでも弾けている感を得たならば次にメトロノームを準備しあえてメトロノーム設定をBPM170位から始めれば、もはやじっくりと味わいながら弾ける感覚があると思います
そこからはBPMを3段階位(例/20ずつ、30ずつ)で増やして行けば原曲スピードでいつの間にか弾けるように
「練習時からアンプ音を出す」ことで全体的なバランス(右手のミュート具合、ピックの場所、左手指の動かし方)が取れるので効率がかなり高く、身体全体の省エネ的動作も短期間で習得できると思います。特にピックと弦の距離感習得は「瞬発力」においては重要でしょうね
実際、自身の創作曲は最初は全然スピードについて行けてないです
それは手癖で曲を創らないからですが
曲の大部分のリフが頭でイメージする音を当てて曲を作ってきているので、創作の途中で物理的に無理な指の動きが出て来た場合は音の調整をしながら楽曲を仕上げることになります。ライブで演る曲しか創らないのでそうなりますね
以上ですが今回の内容、当方はテクニカルギタリストを名乗れるレベルでは無いのであくまで自身のやり方ですが興味があればトライしてみて下さい
「観ては凹む→その部分を練習するの繰り返し」と葛藤
前提として我々はライブ時に撮影下さる方を歓迎しています
後日に写真や動画をDMで送って下さったりインスタのストーリーにUPして下さったりYoutubeにUPして下さったり本当に感謝しています
そして毎回、観ては心が折れそうになるくらいに演奏の下手さに凹むの繰り返しです
サブコンシャステラーは他のメンバー(ドラマー、ベーシスト)の力で成り立っています
個人的に、更には自己承認欲求的に、パフォーマンススキルに毎回納得が行かないです
確かにテクニカルデスメタル系のライブ盤って殆どリリースされないかDTMでの修正が入っているケースが多いですが我々は「そのまんま」なので弾き損じを含め毎回動画を観ては顔が真っ赤になるほどです
ライブでのテクニカルな演奏はどこまで練習しても本番では難しいです、いっそのこと自身を音楽プレイヤーとしての改造人間ロボットにしてほしい位に
「観ては凹み、なんでこんなにも下手なんだろう」を繰り返しながら、またブラッシュアップを続けるという塩梅です
ギターを弾きながらボーカルを取るというのは肉体的分離の永遠の課題
右手で卓球、左手でテニスを同時にプレイするみたいな感覚があります
2パートを同時にプレイしているバンドマンは本当に見習うしかないです、難しいです
↑戒め用にリンクを貼ります
「観たくない(忘れたい)」vs「ちゃんとブラッシュアップしないと」の葛藤が続く日々
でもやっぱり正面から向き合う事が上達へのヒントだと戒めながらトレーニングし続けています
初歩的ミス反省/忘備録(海外ツアー/電圧仕様)
今年はツアー毎に持参するアンプヘッドを変えてライブしていました
そして韓国ツアー時、持参したパワーアンプを全損させてしまいました
初歩的なミスでした
将来的な事(長期ツアー等の構想)を考えて軽量装備で行きたくて「超小型(大出力)パワーアンプ」を持参したのですが100Vの日本仕様でした
韓国は220Vですから変圧器が必要です
現地到着後の音出しでコンセントプラグだけ変えて変圧器を挟まずにそのまま挿してしまいました
僅か数秒後には白煙が上がり慌ててOFFするも後の祭り
全損しました
このツアーに向けてかなり念入りにこのパワーアンプで音作りをしていたので非常に残念でしたが、ツアー自体は会場のアンプ機材をお借りすることが出来て本当に助かりました
これを教訓に帰国後に再度同じものを注文
次回の海外ツアーでもう一度リベンジしたいと思います。
忘備録として以下へ電圧をメモしておきます(行かれる際は自己責任にて詳細は調べて下さい)
◆日本と同じ系統→日本100V(50-60Hz)、台湾110V(60Hz)
◆韓国・中国→220V(50Hz、60Hz)
◆他のアジア→国によってバラバラで220-240V(50-60Hz)
◆ヨーロッパ→230V(50Hz)
◆アメリカ→120V(60Hz)
帰国後に対策方法を考えたのですが毎回変圧器を変えるのは面倒ですし、1つの変圧器で世界中を網羅する変圧器を探しました

辿り着いたのが変圧器工房さんで作られている「型式TGK2410-300」(ネットで12,000円位)
出力電圧100Vの日本仕様電気製品を220V~240Vの海外で使えるようにする変圧ダウン機器です
今回は在庫があり即納でしたが手作りだそうなので納期は要確認です
購入したばかりなので次回の海外ツアーから使用してみます
以下へ100V仕様を海外使用する際の接続順をまとめてみます
①パワーアンプ
↓
②変圧器「型式TGK2410-300」(変圧器工房製)
↓
③(その国の)変換プラグ
↓
④(その国の)コンセント差込口へ
ちなみに全損したこのパワーアンプは国内のライブで何度か使用したことがありましたが海外では初めてでした、完全にうっかりミスです
以前に海外で共演させて頂いたSinisterのギタリストWalterさんが正にこのパワーアンプを使用されていて「そう言えば、自身も同じのを持ってたな」と思い出し「もう一度使ってみよう」となりました(彼はその際にちゃんと変圧器を使っていたということ)

以上が電圧仕様に関する教訓忘備録です
イヤモニ忘備録
パフォーマンスに対する環境依存を極力減らすために導入したイヤモニシステム(以前記事に詳細)ですが今回はその忘備録的なお話です
①イヤホンから聞こえてくるリズムクリックの音
②自分が奏でる楽器(アンプやモニター等)から聴こえてくる音
③他パート楽器の音
ライブの際は上記①②③について自分の耳に聴こえてくる「音量優先順位」を深く考慮する必要があります(個人ごとの内音)

つまり「自分の耳に聴こえてくる音」に対して、実際どれくらいの音量バランス(音量優先順位)で演奏をするかについてです
以下へ纏めました
【弦楽器隊】
①リズムクリック(”最も大”で”最も明確”に聞こえる必要あり)
↓
②自分が奏でるギター/自分が奏でるベースの音(中/生演奏の精度を維持する)
↓
③ドラムのモニター返し(小/リズム感の確認)
【ドラマー】
①リズムクリック(”最も大”で”最も明確”に聞こえる必要あり)
↓
②キック(中/自分のバスドラムの音/タイムの安定とグルーブ感)
↓
③スネア(中/自分のスネア打面の音/拍の意識)
↓
④他パート(小/タイミング確認用で必要に応じて)
我々は上記で進めています
他のバンドのやり方も確認できればよいですが現場なのでなかなか難しいですね
薄ディレイ+軽コンプ
大部分のデスメタル大御所バンドって何故あんなにライブでギターサウンド音質が良いのだろうと
音作りに悩んでいてこれまでやってこなかった事に気づきました
お恥ずかしながらこれまで何十年も気づかなかったことです
それは「ディストーション」+「軽コンプレッサー」に「薄ディレイ」を掛けるということです
つまりバッキング時から「薄ディレイ掛けっ放し」です
「音抜け」に影響しない程度にバッキング時から「薄ディレイ」を掛けるです
調べてみるとCannibal CorpseのRob BarrrettやEric Rutan、NileのKarl Sanders、Deicideの故Ralph Santolla、CryptopsyのChiristian Donaldson等々、多数のデスメタル大御所バンドはライブでバッキング時にも薄ディレイを掛けていることが分かりました
いやー、これまでずっと「直」の歪み音だけで勝負してきました
なぜ気づかなかったんだろうとも思いますし確かに奥行きも出るのと脳内レベルで感じ取れる弾き損じも滑らかだと思いますし誤魔化すという訳では無く全体のバランス的にもその滑らかさによりメリットが多そうです
そんなこんなで、またエフェクターボードを組み直しながらパラメータを振っています
(接続順)
ギター
↓
コンプレッサー(ON)
↓
フェイザー(ギターソロ時のみ使用)
↓
ディストーション(ON)
↓
薄ディレイ(ON)※掛けっ放し
↓
パワーアンプ
↓
キャビネット
更にブースターやギターソロ用で別途ディレイやリバーブを入れるというのもあるのかもしれません
長年に渡って馬鹿正直に歪みエフェクターだけで勝負してきた中で、ようやく近年はコンプを挟みだしましたがバッキング時からの薄ディレイは過去一度もやってこなかったです
ふと思いました
なぜギターサウンドに対して「やたら拘るのかの理由」ですが、
ライブ時に「自分にとって弾いていて気持ち良いギターサウンドであるかどうか」が大きな要因にあります
完全自己満足な機材揃えであっても弾いていて心地良く無いと、その日のパフォーマンスにまで影響が出るような気がします、少なくとも現況の自分はそうです
例えばですが国内ライブハウスに多数置いてあるジャズコーラスアンプ(←大好きなアンプです)にアンプ直(エフェクター未使用)でデスメタルを演奏するとしたらクリーントーン過ぎて気持ち悪くないですか?心理的にもプレイが変になる感じしません?
結果、何個もエフェクターを購入したりアンプを変えたりしながら「あーでもない、こーでもない」が半永久的に続いています
ちなみに近年のレコーディング時ですが
歪ませ過ぎる事で「弾き損じが分かり難くなる」のが嫌でクリーントーン録音(Reprogrammingアルバム)したこともあります。その時はこれが正解だと思って気づかなかったですが最近はやっぱり感情を乗せる意味でも薄ディストーションを掛けてレコーディングしています(リアンプ)
変かもしれませんが良い意味でズレたい(自然な人間味)ですね
ライブをしたいなら
SNS上で非有名バンドのライブ集客の悲惨さが浮き彫りされる表現投稿がよく目に付きます
原因は「非有名だから」、「非人気だから」です
元も子もない無いですがそれでライブをやって集客が出来る訳が無いのです
以前にも書いた通り現代においては「ライブをやれば集客が増えるでは無く、有名になったその暁にその知名度を活用してライブをする」です
昔の様な路上ライブスタート的な「階段を上がる成功夢物語」では無い気がします
だから大部分のライブバンドはヘッドライナー(有名バンド)のサポートに付いてプロモーションライブを行っている訳です
なので「現代における精力的なライブ活動」はある意味で下記の二者択一かもしれません
①SNSで有名になってからその暁にライブをする
②ヘッドライナーツアーに参加してプロモーションライブ活動を行う
我々は①が非常に苦手なので②に重きを置いています
この②ですが我々の様な超小規模バンドにとっては、ヘッドライナークラスの有名バンドがどのようなやり方でライブを行っているかを間近で学べますので都度発見も多くこの上ない学習の場になります。集客が見込まれるショーに出演させて頂きつつその上で更に彼らの手法も学べるという経験と実績だけではなく「大きな学び」というプラスしかないと思います
なので②に重きを置くならば「ヘッドライナーツアー参加に辿り着くため」の時間もしっかり費やした方が良いと思います
例えば有名レーベル契約に辿り着きたいなら数十社くらいはサブミッションしてみれば良いし、
例えば有名フェスをターゲットにするなら世界中で行われている何百ものフェスの主催にサブミッションしてみれば良いし、
例えば有名アートワークに拘りたいなら世界中のアートワークアーティストに依頼を掛けてみれば良いし、
例えばMVに凝るならYoutube MV映像を研究し意中のプロデューサーに依頼してみれば良いし、
例えば理想的な有名バンドがあるならバンマスにコンタクトを取ってサポートアクトに付かせて頂けないかを交渉してみれば良いし
これらの前提には日頃からしっかりしたEPK作りもそうですよね
このように準備については幾らでも思い浮かびますし日頃から幾らでもやりようはあると思います
あとは「それをやりたいかどうか」、「やるならばやり切れる程の情熱があるかどうか」だと思います
年中機材変更で落ち着かない
年中ギター関連の機材変更をしている記事を書いていますがまた購入しました
今回はEVH5150OverDriveエフェクターです

90年代の活動時はPeavey5150ヘッドにメサブギーのキャビネットを機材車に積んで毎回持ち込みでライブをしていました
その5150のペダルエフェクター版です
近年、国内外問わず様々な場所でライブをするようになり「出来るだけ万能なディストーションエフェクター」が欲しいと思うようになりついつい色々手を出してしまいます
このペダルエフェクターは低音がしっかり出てジューシーな音です
これまでのエフェクターですが歪ませ過ぎるとジジジジっとデジタル音っぽくなり、かと言って低音弦をミュートで刻むと風圧の様な低音がでるエフェクターだと今度は輪郭がモコモコして分かり難いという。自己満足とは言え年中ハマっています
もちろん外音(お客さん側で聴こえる音)の良さを追求するのですが、ある程度はPA設定や箱の作り影響もありますからね
バンドアンサンブル時に「自分の耳が気こちよく聞こえているかどうか」もかなり重要です
その理由はそこが微妙だとライブ時のパフォーマンスに影響する気がしているからです
「なんか気持ち悪いな」「なんか物足りないな」と思いながらやることを避けたいです
まだ試行錯誤中ですが、なんとなく高音が足りない感じがしてチューブスクリーマーだったりヘッド側のハイで調整したり、とっかえひっかえを繰り返しています
日々迷い過ぎることもあり近年参考にしているのはCannibal Corpseの2024,2025、もしくはDeicideの2024,2025のライブハウスでのギターサウンドをYoutubeで聴き耳を立てながら確認しています
出来るだけ彼らが小さい箱でやっているときか、もしくは録画者がギターアンプの傍で録音されていて出来るだけギターの直音が聴こえ易い映像を探し回っては確認しています
録画状態もあるかもしれませんがバンドによってはバランスがグチャグチャとかギターの輪郭が潰れていて何をやっているか分からない映像も多数あるなかで彼らの動画はどれを見ても聴きとりやすいです
そう言った背景からサウンド作りの参考にもさせて頂いています
夢を語る人への回答
皮肉な表題ですが結論としては夢を語れる程の「度胸と準備と覚悟は出来ていますか?」という事になります
デスメタルバンドの大御所、オランダのSinisterが先日、12月のヨーロッパツアー概要をSNS上で示唆

Sinisterとは以前に共演をさせて頂いて以降、親交を深めさせて頂いています
もう半年以上前の話になりますがSINISTERのバンマス氏とチャットで会話中
「12月にヨーロッパツアーやるけど一緒に廻る?」という光栄なお話を頂きました
正にこの添付フライヤーの件です
しかしながらタイミング的に我々は既にCryptopsyツアーへの参加が決まっており重複日程によりお断りせざるを得なかったです
このフライヤーのSinisterヨーロッパツアー日程を文字でまとめると以下です
◆Death March Tour 2025
12月4日 イタリア・エルバ(Erba)/Centrale Rock
12月5日 イタリア・ローマ(Rome)/Defrag
12月6日 イタリア・ボローニャ(Bologna)/Alchemica
12月7日 スロベニア・リュブリャナ(Ljubljana)/Menza pri Koritu
12月8日 オーストリア・ウィーン(Vienna)/Viper Room
12月9日 ポーランド・クラクフ(Krakow)/Klub Zaścianek
12月10日 ポーランド・ワルシャワ(Warsaw)/Voodoo
12月11日 チェコ・プラハ(Prague)/Modra Vopice
12月12日 ドイツ・オーバーハウゼン(Oberhausen)/Helvete
12月13日 オランダ・アイントホーフェン(Eindhoven)/EMM
12月18日 スペイン・カステリョン(Castellón)/Sala Terra
12月19日 スペイン・ムルシア(Murcia)/Sala Spectrum
12月20日 スペイン・セビリア(Sevilla)/Sala Supra
12月21日 ポルトガル・リスボン(Lisboa)/RCA Club
踏まえ、表題の話に繋がって行きます
概要は2.5週間に渡るヨーロッパ9カ国14公演です
もしもこのツアーに参加する場合、日本からの往復も考えると3週間は必要です
バンドとしては以下の必要条件が挙げられます
①12月(師走時期)に3週間、家を空けられる事
②メンバー1人当たり50万円(往復航空費+α)はポンと出せる事
国を跨ぎながら移動を繰り返し、毎日演奏をし続けられる気力と体力が有ることや、そもそもバンド活動をするにあたっての前提(演奏力や創作曲やビジュアル含む)は既存条件として省略した話です
その上で①と②を卒なくクリアできる人(またはバンド)であることが必須条件です
日本を離れ現地イタリア到着後、Sinisterと合流をして以降はありがたくも国跨ぎや会場間移動をSinister号(寝台ライナー・ツアーバス)で一緒に連れて行って下さる話だったので、ある程度身はお任せできると思いますが足手まといや迷惑は掛けられないですから気も張った3週間になるでしょう。その上で演奏やパフォーマンスもシビアになります(会場環境依存しないセッティング追求が普段から出来ていて都度そのパフォーマンスを出せるかです)
でも、これらってバンド活動をするにあたり情熱と覚悟のあるプレイヤーならば普段の生活環境整備の時点から準備して行けることですよね
その準備すらやっていないのに「音楽活動が上手く行かない等の不満」をSNS等でわざわざ漏らす人はこれらを淡々とやってのける人達がわんさか居る中で情熱や行動レベルや音楽に向かう姿勢に大きな差があるのだと思います
そして音楽活動において「その為の準備」は人一倍に能動的であるべきだと思いますし、その上であとは度胸/覚悟と人一倍の情熱
ヨーロッパツアー、近いうちに実現したいですね
2020年代から再活約6年経過しての「シーンに対する感想」
1991年にギターを手に取りメタリカ、スレイヤー、セパルトゥラ等のコピバンからスタートし
↓
1994年7月Subconscious Terror結成
1994年10月1stデモリリース
1995年5月2ndデモリリース
1995年12月Eclipse Records契約
1996年5月1stフルアルバムCDリリース
↓
1998年活動休止
↓
その後、四半世紀ワープして2019年秋に再始動宣言
↓
2020年春に新譜リリースとライブ活動再開
この流れでやってきていますが
1990年代初期中期はファンジン誌や文通やカセットデモのトレードを主体としたヒソヒソ感のある「知る人ぞ知る」情報共有時代
それが2020年代ともなると「デスメタル」という単語自体の認知度が大衆用語くらいにまで知れ渡っています
今思うと1990年代は勢いが凄かったです、知る人ぞ知るというのがむしろ熱狂を生んでいたのかもしれませんし、特に我々の様なエクストリームミュージックジャンルにおいては何をやっても「創るもの全てが新しい感覚」な印象がありました
当時は紙媒体の情報共有だったのでライブに来られたお客さんへは次のライブチラシをお渡しするかMCでの告知になるので歯抜けがあると(次のライブ参戦を休むと)更にその次のライブ日程が分かり難くなることもあり「通し」で来られる方が多かったです
当時のデメリットをしいていうならば某全国誌は「洋楽No1主義」で「国産バンドをコテンパンに全否定」で完全に洋楽と邦楽のメタルに頭ごなしで優劣を付けていたことでしょうか
ですのでファンジン誌(国産バンドサポート)と全国誌(洋楽至上主義)では全く内容が違いましたね
そんな背景を経過した現代は「紙媒体からネット主体」へ
日本ではX(旧Twitter)での国内ライブ告知が多いと思います
矢継ぎ早に流れてくるライブ告知情報は「情報の渦」と化していて、すぐに埋もれていきますので我々の様な超小規模バンド(影響力の無いバンド)は「いつまでたっても拡がらない」という悪循環も
紙媒体のアングラファンジンであれば優劣無く活動すればするほどに掲載される回数も多かったですのでバンドも更に精力的に頑張るモチベーションにも
それが現代のSNS上でのバンド情報については、そのアルゴリズムにより活動告知よりも「解散や脱退や逝去」などのネガティブ内容ばかりが目立って流れてくるのでバンドはただただ疲弊して行っている様な印象を受けます
ひたすら続く解散や脱退のタイムラインに疲弊感
その根源にはアングラはどこまでやっても「経済的疲弊しかない」事も1つに挙げられると思います
つまりバンド活動はやればやるほどの経済的疲弊で結果的に生活が歪んで心も歪んで行くプレイヤーが出てきて脱退の際は外交上「音楽性の違いによる」というパターン
実際、経済的な疲弊があるバンドマンはどこかのバンドに加入しても遅かれ早かれ続かないと思います。短期で加入しては辞めるを繰り返すケース
我々は活動を永く続ける為にその部分に関しちょっと俯瞰している部分があります
バンドマンは最終的には「生活環境を整えられている人」しか「継続したバンドメンバー」には選ばれないです
デスメタルで収益を上げるというのは困難ですからね
仕事を休んで自分達で経費を捻出してライブをするバンドが世の中の99%
無理をしないのが前提なのに無理をするから建前上は「方向性の違い」で欠員が起きたりして歪んで行くことがあるのだと推測します
極論を言うとアングラ音楽をやるならメンバーが資産家か会社社長か不労所得で経済的余裕のある人がベターです
子供ではないのでまさか「デスメタルで家が建つ」とは誰も思わないでしょう
生活まで賭けられてしまうと遅かれ早かれその温度差でメンバー間に歪みが生まれると思います
末永く続けられる人は「環境作りをやれたプレイヤー」
そろそろSNSから離れたいと思う程にこの業界の経済的疲弊内容がタイムラインに流れてくるのが目に付くのでちょっと残念というか「何を夢見てるんだろう、まさか家が建つとでも?」という感じも
夢を見たいなら例えば自宅で1人で邦楽ポップのボカロ曲をDTMで作曲し続け毎日1曲デジタルリリースし「当たり」が出るまで少なくとも1000曲位はリリースし続ける覚悟でやってみると良いと思います。1年365日ですから1000曲リリースするなら3年も掛からないですし短期間で自分の音楽センス有無を確かめるのには十分ではないでしょうか。今なら自宅にPCがあれば1人で出来ますしリリースも僅かな経費(ストリーミング登録料)でできますし手軽ですよね
アングラ系音楽活動の話に戻ります
言葉を選ばずに表現するならば「富裕層の遊びレベル」からバンド活動を始めないと続けられないのを俯瞰出来ずに夢を見ている人が多い様な気もします
もちろん我々も富裕層では無いので末永く続けられる選択肢とバランスを取りながら活動していますが
今から音楽的影響を受けることはあるのか
80年代や90年代初期である学生時代に音楽に影響を受け「自分でもバンドをやりたい」と思って1994年にオリジナルバンドSubconscious Terrorを始めました
そこから約30年経過した現在、音楽に何か影響を受けることがあるのかを述べたいと思います
結論的には”ほぼ”無いですね
学生時代当時の80s,90s初期のMetallica、Slayer、Megadeth、Sepultura、Sadus、Deicide、Carcass、Napalm Death等の楽曲に刺激されました
その源流については結成30年を超えた現在でも同様な感覚です
2000年以降のエクストリーム系音楽については完全に素人で、2019年秋の再始動時はデスコアやメタルコアやスラミングデスという呼び名ジャンルすら知らなかったぐらいですし当時のままヘビーメタル、スラッシュメタル、デスラッシュ、デスメタル、グラインドコアの呼び名で止まっています
なので近年は友人やバンド仲間に教えて頂きながら試聴してみて気に行ったら聴かせて頂いたリスペクトの意でフィジカルを揃えるといった感じです
我々の創作曲はどうあがいても俗にいうオールドスクールなのでしょうね。同一人物が創り続ける限り。これがもしもボカロ曲を創るとなれば同一人物でも全く違う曲調になるとは思いますが
周りを見渡してみると、当時から活動しているバンド群もやはり当時のままの創作の流れであることが多いです
MetallicaやCarcassはガラッと変わりましたがいわゆるアングラデスメタルバンドは30年が経過した今でも当時の流れを組んでいて機材の向上で音質が上がる事はあれどもその殆どが曲調の路線変更をしたという感じでは無いと思います
一時期クリプトプシーがデスコア寄りになり思いっきり叩かれていたそうですが現在はまた元の路線に戻りつつ
我々は何かに流されて路線変更をするという事は無いですね
そういう創作楽曲が好きだからです
時代に合わせてそれが求められるから音楽性を変えるとかは無いです
デモや1st時代から聴いて下さっている方からすると2025年の最新作も「そのまんま」だと思います
良い意味で言うならばオリジナリティを崩していないです
逆に思うのが2000年代以降のバンドはどうしているんだろうとも思います
後続バンドにとっては、どうしても「過去の焼き直し」(オリジナリティ欠如)の様な感覚で捉えられてしまいがちな部分を上手くやって行く必要がありますよね
1990年のデスメタル創世記を経た2000年頃以降はオリジナリティ追求から「超絶テクニカルデスメタル」が出現したのでしょう。ただそれも2020年代の今ではオリジナリティと言う面ではおおよそ出尽くしているかもしれません
そういった背景込みで現在、他の音楽的な影響を受けるというのはほぼ無いです
カッコよく言うならばあくまで「普段の生活環境の中で感情を音にしていく」ですね
外国語言語への恥ずかしさはなぜ生まれるのか
日本は日本語だけが公用語です
ちょっと冒険して海外に出てみると2,3か国語が公用語だったりもします
日本人が頑張って外国語で話している姿はカッコいいですしその熱意に対して応援したくなります
海外の人達も意を組んで理解し喜んで下さる人が多数です
ですが一方で、日本人は日本人が外国語を話すと発音がどうとか文法がどうとか揚げ足を取ったり「その表現は間違っている」などと指摘する世界的にも稀であろう特殊文化が根付いています
学生時代、英語がネイティヴっぽい発音で話すのが恥ずかしいとかありませんでしたか?
恥ずかしいと思わせる空気がある時点でかなり歪んだ文化だと思います
確かに「右に倣え」「体育座り」の様な軍隊用語で幼少時から育ってきているので周囲の人と同じことをする、みんなと同じことをしなければならない的な教育なので、そこで蓄積された敗戦後の謙虚洗脳や卑下文化も相まってなのかもしれませんが
でもこういった背景は英語学習へのマイナス要素にもなっているような気がします
今は小学生から英語の授業がありますよね
大学まで行けば10年以上に渡り英語を学ぶことになります
それでも「全然話せない」というイメージがあるのは「恥ずかしい」という長年の内面的な原因により活用してこなかった事があるかもしれません
音楽業界も似ている感じがします。本当に狭い所で揚げ足取りや叩き合いや指摘のし合い等、正に英語発音の揚げ足取りと似ていますね
「ここは日本だから」で片づける視野の狭さなのかどうか、頑張っている人を下げなきゃ気が済まない流れは文化の醸成に対しては成長を阻害するマイナス要因かもしれません
バンド練習スタジオ(日本と海外)
日本のリハーサルスタジオ(バンド練習スタジオ)は防音壁な上にドラムセットからミキサー、ギターアンプからベースアンプ等なんでも揃っていて、更に時間貸しがあるという世界でも稀に見る最高のサービスがあります
海外の場合は殆どが月極めの空間貸し(空っぽ)で部屋の料金を払ってドアの鍵を貰い機材は全て自前で用意し、その月極め期間中は機材を置きっぱなしで好きな時間にバンド練習するパターン
なので海外で「ちょっとスタジオ練習したいなー」なんて思っても空っぽの部屋を月極めレンタルすることになるので現実的には難しいですね
大規模バンドならまだしも我々の様な超小規模バンドだとリハスタの為にドラムセットやスタックアンプを飛行機に積んで持っていく訳にも行きませんので
海外ツアー時に現地のスタジオでリハ練をするのはよっぽどの機会が無い限り難しいでしょう
もうすぐ韓国ツアーなのですが、現地でスタジオ練習をしてみたいと思って色々探してみましたがやはりドラムセットやアンプ機材が常設されている様な日本式のスタジオは無かったです。いわゆるダンススタジオの様な空っぽ部屋のスタジオでした(たまたま知り合いがいて今回は現地でスタジオリハ予定も入れる事ができましたが)
でも確かに合点が行くんですよね
例えばカニバルコープスやクリプトプシー等の大御所デスメタルバンドはメンバーの誰かがスタジオ経営者やミックスマスタリングエンジニアであるケースが非常に多いです。自前のスタジオですから自分達の機材を置きっぱなしに出来ますしバンド練習もし放題ですよね
聞いた話ではそういった自前の練習場の無いバンドは工業地帯の倉庫を借りて自分達の練習場にしたり自宅のガレージや地下室に機材セットを自前で用意したりだそうですね
大都市であるロンドンやNY、ロサンゼルスの様な一部地域には機材常設のリハーサルスタジオも稀にあるようですが、普段使い出来る様な料金体系では無いでしょうね。もはやガチの兼レコーディングスタジオ
なので特に海外の名の知れたバンドは何かしら自分達のリハ部屋を持っているようです。そうじゃないと全体練習が困難になりますしね
そういう意味では日本のバンド練習環境は本当に恵まれていると思います
ギターを背負って駅前徒歩5分で気軽にスタジオリハーサルができるという
海外の人からすると感動レベルだと思います
SNSでの村八分
海外某バンドを皆で寄ってたかってSNS上で村八分にしているのがタイムラインに流れてきました
様々な事情や背景は分かりませんがネットリンチは見ていて気持ちの良いものでは無いです
我々に無関係な話とは言えども近しいエクストリームミュージックシーンという枠組みの中です
音楽は創作品ですが皆で一斉に人物(バンドという集合体)を袋叩きするのがタイムラインに流れてくるのは怖いです
そして叩いている方達もデジタルタトゥーとして残っていきます
今後も他人を叩いていく人達であるという認識付けも
こういうのを見るとSNSはやっぱりやらないがベター、もしくは関わらない方が良いのかもしれません
ただ情報を届ける為の告知はしたいので感情や私情を排除した(単なる)情報告知のみで引き続きSNSは活用していくことにはなるのですが
我々の活動は結成当初から今現在に至るまで内輪感が無く自由にやらせて頂いている独自路線。それが良いか悪いかは別として気楽ではありますね
「クリック音」&「自分の奏でる音」両方イヤモニで聴く
我々には縁がありませんが例えば東京ドームでライブするバンドってどうしてるのだろうとふと
ギターアンプのボリュームを全開MAXにした所でステージを大きく使うなら聴こえにくいエリアもありそうです
足元のモニター(フロアモニター)に音を返すにしても離れたら聞こえずらくなります
ひょっとしたら、イヤモニで「クリック音」と「自分の奏でる楽器音」(例/ギター)の両方をイヤホンで聴きながら演奏しているプレイヤーもいそうです
我々が普段活動している様な「背中からモロにドラムの生音が聞こえてきてそれに合わせて演奏する」小規模ステージ感覚ではないかもしれません
それって「出来るのかな?」とふと思いまして(→クリック+自演奏楽器を両方イヤホンで聞く)
「環境依存による演奏不安を無くす」ことへの一環で考えてみました
結論的には可能ですね
以下はあくまで当方が考えてみたDIYパターンです(大規模バンドがどうやってるかは分かりません)
ギターアンプのラインアウトに簡易ミキサーを繋ぐ(リンクは例)
↓【高音質】【おすすめ】アナログミキサー CLASSIC PRO MX-EZ4 ライブ お祭り 学園祭 運動会 定番 送料無料 | サウンドハウス
↓
その簡易ミキサーの1ch側にドラマーの送信機から送られてくるクリック音を受けている受信機を繋ぐ
↓
上記簡易ミキサーの2ch側にギター用の送信機を繋ぎ、別途もう一台用意した受信器を身体装着しイヤホンで聞く
そうすることで簡易ミキサー側のボリュームツマミ操作によりイヤホンに聴こえてくる「クリック音」と「自分が奏でる楽器音」を個別に音量バランスも取れますし、どこにいても両方の音がステレオで聞こえてきますよね
そうなってくると、もはやキャビネットから鳴らす音は演出用というか鳴らしても鳴らさなくても自分の演奏には依存しない範囲でプレイが出来るので、つまりは中音(ステージ内の音)依存せずライブ演奏ができる想定です
音回りがする系の小箱ライブハウスではむしろこの手法はアリかもです、中音が静かになるのでクリアサウンドが得られそうですしトライしてみたいです
前座という呼称並びにサポートアクト
■オープニングアクト=前座(落語や演芸舞台で主役が出る前に場を温める為の伝統的な言葉)
■サポートアクト=メインアクトの構成の一部分
ChatGptに尋ねるとこのような説明でしたが国内ではゴッチャ理解も多勢だと思います
先日のOASIS来日公演情報で「前座なんかいらん!」「サポートなんかいらん!}というSNSコメントで溢れているのは出演バンドに対して可哀想過ぎます
なぜそんなことをサポートバンドに向かって目に付く様にわざわざ言うのだろう
そういう事象があると今後サポートアクトに抜擢されたとしても、叩かれるかもしれないから怖いし遠慮しておこうという、せっかくのプロモーションの機会なのにサポートアクト=ネガティブな印象が根付いてしまう事も
そもそも招聘側が該当サポートアクト出演をメインアクトであるOASIS側と相互承認した上で契約している訳でそれを批判するという事はOASISを批判しているということにも
優しい文化でありたいですね
「敵と味方」に分けて相手を叩き切らなきゃ気が済まない日本文化
これは皮肉にも「日本が安全な国」であることととも関連していると思います
つまり、銃がフリーな国だったりサツジンを安く雇うのが容易な国であればそんなに簡単に「いがみあう」、「敵対する」ことはできないからです
過去に約10年海外に在住していましたが、どうにかしてお互いが揉めずに済むかを探り合うというのが命を守る第一でした
相手を批判することは命にまで関わるので
長年にわたる敗戦国の自虐文化
日本人同士を嫉妬で責め合うギスギス感
自国民族を応援しないギスギス感
「OASISのサポートに選ばれた日本人グループなんてメチャクチャ凄いじゃん!」
「祝!!大快挙!」
「日本人として誇りに思う!」
こういう風にならないのが不思議です
長年の洗脳教育で醸成された自虐文化がそうさせるのか
競技スポーツでもあるんですよね
他の日本人選手が活躍すると嫉妬してアラを探しSNSで叩くという
もちろん島国育ちで外の世界に出たことの無い人が多勢であることは分かるのですが器が狭く、視野も狭いまま大人になりそのまま次の世代(親が子へ)へ引き継ぎその伝統を洗脳していくというのが常態化しているのだとは思いますが
やる気を削ぎ合い、傷をなめ合うことを楽しむ日本人
勤勉で素晴らしい芸術が溢れる日本文化なのに本当にもったいないです
だから結果的に一部のバンドはそこを俯瞰して国内との距離感を保ちながら海外をメインに活動していくバンドが居るのかもしれません
余談ですが来日バンドのサポートアクトバンドって「嬉しがるのも最初だけ」で以降は上記背景からプレッシャーを感じるバンドも居ると思われます
我々は幸いにも超小規模なバンドなので知名度が無い分、そういった話題にすらならないので助かっていますが知名度のあるバンドはそういった事象をも乗り越えなければならないというキツイ部分(精神的ハードルや鈍感さ)もありそうですね
SNS投稿を考える
我々の様な超小規模バンドとしては先日、インスタグラムで初めて1投稿「1000いいね」超えしました

つまり1000人以上の方がGoodボタンを押してくださったという
SNSのGoodボタンは単なる「自己承認欲求を満たす為」という考えもありますが、やはり影響がありました。この投稿はライブ前のプロモーションを兼ねたアー写です
実際、ライブ当日券がどんと増えましたし、フォロワー数がこの投稿後の数日間で400名位増加しました
ということはやはりバンドにとっては大きなプロモーション告知になっています
なぜこの投稿がそうなったのか
ライブ直前の告知であったことと新しいアー写であったとしても、まだ他にも要素がありそうです
分析してみたところ、恐らくですが背景が神社で日本の古風なオールドデスメタルとの一致もその要素の1つとしてありそうです
結果的にこの投稿で初めて我々を知ったという方からのフォローが激増しましたしマーチオーダーも増えました
現社会においては「いかに認知されるか」が大きなポイントになっています
以前にもここで書きましたが「世界で一番凄い曲なるものを創っても認知されない限り駄作で終わる可能性も」です
冷酷ですが音楽とはそういう部分もあると思います
他にも中国版TwitterのRedで14万インプレッションが付いたことがありました、確かGoodボタンは600だったと思います。それは上記とは全然異なる流れでした
なぜか当方が「中国の国民的歌手にそっくり」だということでリツイートされまくり拡散
お笑い要素を兼ねたコメントも溢れたのですが、それでも「認知される」という部分ではライブ前日の告知において大きなプロモーションとなり実際に公演は大盛況でした
エージェントからも物凄い喜ばれましたし長所しかなかったです
公演は2日だけだし、まさかそんなに売れないだろう前提で持って行った物販CD200枚ですが2日目の途中で全部売切れました
それほどSNSの影響力というのは大きいことをまざまざと見せつけられました
ただ注意すべきは、逆に考えると「諸刃の剣」でもある訳ですので、これも以前にここで書いた通りですが我々の様な超小規模バンドにとってSNSへの投稿内容は私情や感情を極力避け、淡々と無難な告知内容を続けることが末永く活動をしていける選択肢の1つかもしれません
演奏の出来と実際の相違
演者はその日のライブ演奏の好不調で「その日のライブがどうだったか」と自分なりに解釈評価しながら「凹んだり」「上手く行った!」と感じていると思います
ですが実際には「ライブ演奏の出来」と「お客さん側の盛り上がり」は一致しないことも多々あるというお話です
結論的にはバンド演奏の出来不出来ウンヌン以上に「その場の空気を支配できれば盛り上がる」、「支配できなければ盛り上がらない」なのかもしれません
演者は当日の自分のプレイの出来具合で落ち込んだり、喜んだりしがちです
ですが、お客さん側からすると「衝動」や「迫力」、「一体感」が全て
ライブは体感なのでお客さんも演者も双方がアドレナリンが出るような迫力ライブが出来れば「最高!」という空気が生まれます
バンドとしてはこれを作り出せるルーティンを見つけ出しそれを習慣化できれば理想ですよね
以前のライブで、個人的には演奏がボロボロと感じ後日も凹み続けていたライブがあったのですが、ライブそのものはメチャクチャ盛り上がり評価もうなぎ上りという経験をしたことがあります
これが正にそうなんだと思います
個人的には演奏がボロボロだと感じても、その時は幸運ながら「空気を支配」していたのでしょう
ただ、これを意図的に作り出すというのは様々な角度からの分析、ルーティン、習慣etcを探る必要があります
どうしたら良いのでしょうか?
我々はまだその段階のバンドでは無いのかもしれません、対策が見つからずにいます
ただ逆パターンもあります。「今日は演奏上手く行ったぞ!」と思ったライブで反応で得られなかったケース
これは「空気を支配する一体感を創れなかった」からだと今のところ考えています
バンド全体の「動き」と「間」なのかもしれません
この課題解決を難問に感じるレベルなのでライブバンドとしてはまだまだヒヨッコなのだと思いますが今後真剣に取り組んで行く必要性を感じます
デスメタル・ボーカルのマイク
マイクの種類は知見が無いです、人づてや自身でトライしてみて気に入ったものを使っています
これまでの使用経歴は90年代がShure57で、2020年の再活後はShure58でした
ですがライブ経験値が上がるにつれ物足りなくなってきてどうしようかと。
そして現在は「これしかない!」というマイクに辿り着きました
これも定番中の定番ではあるのですが「Shure Beta58」です(Shure58の上位モデル)

最安値はサウンドハウスさんで24000円切るくらいでしたので10万円以上するマイクも多い中ではかなりのお値打ちだと思います
このマイクに変えた経緯としては先日のシンガポールショーの際にPAさんから超オススメされまして
実際にお借りしてライブしましたところこれまで持参してきたマイクよりもかなり良かったです
「なにが良かったのか」は感覚的なのですが精神的な安心感のある出音でしたし
特にBETA58はマイクは仕様的に他よりも感度が高いので音量も上がりますしそう感じたのでしょう
知見の無い、当方の使用マイク紹介ではありますがで「デスメタル向き」だと思いましたので参考まで
信用を見定めることと自己防衛を常に想定
天災や健康問題以外でもライブ出演/開催が飛ぶ様な内容を少なからず見聞きします
我々は決まったライブをキャンセルしたことが無いです
あるとすれば交通事故骨折などが発生してそもそも楽器が奏でられなくなったとか災害等で物理的に移動がままならない事でも起きない限り無いでしょう
決めたなら出演するだけで以外の選択肢は無いです
言うは易しと思う方も居られるかもしれませんが、それしか言いようがないです
なので「決めるまで」のプロセスに全力を注いでいます、もちろん招聘側からの決断要求(Yes or No)は準備の為に急ぎたいので即断決定する必要があります
我々は基本「即答」(遅くとも48時間以内の返信マスト)でやっています
ただ特に海外でかつ、初めてコンタクト頂いた場合はどうするかですが
簡単に例えるならば「エージェント版の四季報を細かく確認するような感じ」でその会社や個人についてSNSやHPや過去のイベント履歴を細かくリサーチしています。それでも分からない場合は過去の出演者を辿ります
過去に招聘をお断りせざる得ないと判断したイベントが複数ありました
詳細は留めておきますが、やり取りの中で結果的に相互が上手く行かないのではという匂いを感じたりがあります、臭覚というか
初回は特に雑談は重要だと思います。人物像や開催方向性を把握して行く事ができますので
なのでいわゆる騙された的なイベントには”ほぼ”出演したことは無いです。危機一髪回避はありますがそれは事前にやんわりとお断りさせて頂いています(せざるを得ないと判断したので)
”ほぼ”と書いていますが予め決まっていた演奏フィーが一切無かった(ゼロ円)ことがありました。その一度だけですね
逆パターンも見聞きします
「バンドが来ない、ブッチした」というケース
これは最悪手です、まずバンドの信用度が無くなります
招聘側からも呼ばれなくなるし、チケットを取っていたファンも離れる可能性大
これを防ぐにはやっぱり普段からのやりとりは重要だと思います
例え開催当日に初めて会う事になる場合でもチャット等で雑談ができるまでの信頼関係が築けるかは重要だと思います
仮に雑談できるまでの関係性では無くとも連絡が密に取れて会話のキャッチボールが円滑であるかどうかはキーポイントです
ちなみに返信が遅いケースは怪しんだ方が良いと思います
やる気がある人は反応が早いですし「前のめりになる」くらいまで反応が早い人は経験上、例外はあるかもですが信用度は確率的に高い感じがします
ただし最も重要な事は「詳細条件を全て相互が事前に承認できた上で決めること」です
曖昧はNGです、恐らく何か起きるでしょう
日本人はお金の話になると曖昧にしがちですが、その曖昧さは相手に隙を与えることになるので不利にしかならないです。なので先にハッキリと境界線を提示くださるプロモーターはありがたいです
つまりバンドとしてはキッチリと冷静に最初から条件提示くださるエージェントは信用度が高いです
できること、できないことをハッキリ最初に分かるので迷いも少ないです
それであってもあらゆる角度からの最悪パターンをも想定してからツアーに出ています
バンマスはメンバーを守る責任がありますので
分かり易い例だと「空港送迎が有る事前条件で到着後、誰も迎えが無い」
これも万一を想定しておいてその国の配車アプリを使えるようにしています
あとは「手配頂いているはずのホテルが行ったら予約されてなかった」
これも周辺のホテルをすぐ見つけられるようにしておくのと自力で会場に行く手段も準備しいます
つまり「まな板の鯉」にせず、最悪は出演の機会だけを頂いて「勝手に行って勝手に帰ることもできる」までをも想定しています
こんなことを書くと、まるで誰も信用して無い様に見えるかもですが自己防衛の一環です
過去に10年海外で生活していたことがあるのですがその中で「何が起こるか分からない未来は何事においても自分でなんとかしていかないと」という習慣がついてしまっています
言えることは
①相互のやり取りが密であったかどうか
②反応(返信)が早かったかどうか(ホッタラカシにされている感があればその匂いを嗅ぎ取る能力必要)
③事前に条件がクリアに整備されていたかどうか
だと思います
肌の色
タイトルですが本当に勇気のいる内容になります
メタルはハクジン労働者階級から発生した音楽という歴史が多々語られておりデスメタルバンドでいうと初めてそれを覆したSuffocationがなぜ認められて来たかが分かると思います
我々オウショク人種。そのオウショク人種でデスメタルバンドとして世界を席巻するようなバンドが歴史上出現したことが無いと思います
Suffocationの様に将来いつか打ち破るバンドが出現して欲しいです
ひょっとしたらと注目しているのは中国のデスメタルバンドです
後追いながらもエクストリームメタルバンドが出現しています
演る人達は必然的に世代も若い人になりますし最新鋭機材からのスタートが出来ますし演奏技術に関してもSNSや動画からのレシピで上達スピードも半端なく、更にはデスメタルミュージックの歴史を探る吸収スピードも物凄い速さで習得されています。更にはMV制作やマーチ関連制作も中国は強いです(安く作れる上に品質も抜群に上がっていますので大手も含め主要な生産依頼先になっています。その方面ではベトナムやインドネシアも)
余談になりますが下記我々のビジュアライザーMVは中国のデジタルデザイナー氏に制作頂きました
メールでMV制作依頼をしたのですがマテリアルは①アートワークと②歌詞だけです。データ送付後、次の日に「出来たよー」と連絡が来て特に修正するような必要も無い完成品でしたので、そのままデータを頂き完納です。やりとり僅か3回(依頼→マテリアル送付→納品)も凄いですが、依頼して僅か数日で完了というのも凄いですよね。こういう感じなので誰も勝てないでしょう。その位、何をやるのも早くて安くて制作スキルも凄いです
話がだいぶ逸れてきましたので戻します
将来、オウショク人種でDeicideやCannibal Corpseクラスでメインストリームに出現する可能性
ちなみに英語(英詞)に関してはもはやジャパニーズイングリッシュも受け入れられている時代(外国人も日本人の英語発音に慣れて来た)なので気にしなくてよいと思いますし、むしろその方が日本人アピール的に良い影響をもたらすことすら出てきていると思います、アイデンティティというか。ライブ上でも一生懸命その国の言語で挨拶をしようとする姿勢の方が歓迎されやすい感じがあります。例えるならデーブスペクターさんの日本語は上手すぎてバンドライブでは外タレ感が無くなるという皮肉な可能性も
現況国内でのデスメタル系ライブシーンは海外有名バンド来日ですら100人も入らない範囲が常態化しているのは、やっぱり世界のメインストリームに立てるくらいの日本人デスメタルバンドが存在しないからかもしれません。その位の立場のデスメタルバンドが出てこない限り国内デスメタルシーン活性化にはハードルがあると感じます
国内筆頭だとDefiled、Kruelty、兀突骨、Invictusでしょうか。幅広い視野を持って精力的に活動されていると思います
もちろん我々もコツコツ頑張りますし他責にはしませんが、彼らがもう一段階ガツンと殻を破って国内メインストリームでシーンを引っ張って行く様なことが起きれば後続もどんどん出てきて国内プロモーターにとっても集客力を含めて興行成立し易くなると思います。それほど期待しています
我々日本人デスメタルバンドが多勢のサポート(ファン)を得るには海外からの逆輸入でないと認めてもらえないのではという長年のメタル文化というか、そんな風には思いたくないのですが、それでもその様なニュアンスは少なからずあると思います
我々を応援下さるコアファンは少数精鋭で長年ずっと応援してくださっています。彼ら(彼女ら)の支えにより我々は活動が出来ているのですが全体のパイと言う面で考えると本当にマニアな世界ですし、如何ともし難い状況かもしれません
サブコンシャステラーはコロナ直前に再活だったのでいきなり出鼻をくじかれましたが、コロナ後からは国内のみならず海外、先ずはアジアのマップを塗って行こうとここ数年そのような活動にも重きを置いています。実際どの国に行っても熱烈に迎えて下さりバンド冥利に尽きるだけでなくファンの母数が一気に変化しました
日本人でメインストリームに立つ様なデスメタルバンドの出現があれば国内ライブシーンの再興はあるでしょう
エクスペンシブ・ホビー
敢えてカタカナ書きに留めておきますが海外にツアーへ行くと、海外のバンドや海外プロモーターとの雑談内で頻繁に出てくる、ある意味では皮肉的なワードです
近年有難くも海外プロモーターからお声がけ頂くことが増え各地のオーディエンスに届けたいという強い想いの元でショーを行っています
そしてツアー先である該当国へ到着後はウェルカムディナーと言いますか関係者から食事のお誘いを頂いたり、ショーの後の食事も同様、更には気を使って隙間時間にその国の観光や特色紹介に連れて行って下さったりもあります。その際の雑談がとても勉強になっています
今回のタイトルはその際に頻繁に出てくるワードです
以前から「音楽活動は金持ちの道楽レベルな思考からスタートしないと難しい、そもそも貴方の事を誰も知らないのだから」と何度も書いてきましたがタイトルは正に同義といっても良いでしょう
4畳半アパートでアルバイトをしながら将来のロックスターを夢見るなんて言うのはテレビドキュメンタリーの世界です
アメリカツアーであろうとヨーロッパツアーであろうと航空チケットすら買うお金が無ければツアーの実現できないでしょう
ですので世の中の99%のツアーバンドはライブ活動に対する強い意志の元で経費や都合を捻出しながら敢行しています
地元でのライブや国内ツアーならまだしも、果敢に海外まで出て行って能動的ツアー活動しているバンドはそれだけでもの凄い事だと改めて認識しています
デスメタルの場合、ロックスターになるようなジャンルでは無いのでツアー活動をやるかやらないかはバンドメンバー全員の「強い意思と音楽への並々ならぬ熱意」が全て
ご存じの通り、決して動員が何千人もあるようなビジネスショーというよりもこの業界は100人単位(少ないときはそれ以下)のショーです(収益化を目指すことは困難な道&トントン以上なら成功部類)
勿論、一般のオーディエンスの方からすると音楽の好みは人それぞれですので「あのバンドは好き、あのバンドはイマイチ」など各自の好みがあって自然だと思いますが演者側の視点で考えると海外に行ってまでツアー活動しているバンドに対しては、もはやそのバンドの音楽の好みを超えた尊敬の念の方が強いです
我々も演者側なので想像ができるんですよね、その活動に辿り着くまでの物凄い努力や交渉能力、たゆまない準備や生活環境整備。そして何より音楽活動に対する次元を超えた人一倍のパッション
共演者やプロモーターからもツアーの度にあらゆる角度での苦労話やその置かれた環境を含め学ばせて頂いています、毎回感服しきりです
何より先行者(先輩)の知見と経験から学ばせて頂く事は重みも違います
我々は超小規模バンドで亀足テンポのヒヨッコ
先行者へのリスペクトと共に彼らからも吸収学習させて頂きながらコツコツ活動して行こうと思います
文化の違いで済ますのかどうか
12月にCRYPTOPSYツアー中国公演の全日程3デイズに共演出演させて頂きます
収容内訳は
①DAY1/大都市(例/東京クラス)で800人収容
②DAY2/同会場(大都市)の2日連続開催なので同じく800人収容
③DAY3/地方都市(例/福岡クラス)で400人収容
そしてチケットは間違いないく「完売」する見込みだそうです
正に驚愕レベルではあるのですが果たして人口の差や文化の差で「日本は諦めてしまっても良いものでしょうか?」というお題です
まず第一に
日本の場合は「個人がそのバンドを見たいかどうか」が全てで、個人の行動(観に行く/行かない)によるところが大きいかもしれません
一方で中国の場合はイベント=社交・祭りの場としても気軽に集まる文化
友達を誘って皆で音楽を聴きに行ってお酒を飲んだり喋ったり物販を見に行ったりのイベントの様な
例えるなら若者が友達同士でゲームセンターに行くような「遊び場」感覚とも言えるかもしれません
2025年2月にSinister中国公演で共演出演させて頂いた際に感じたのは、もちろん生粋のメタルファンも多数ですがイベントを「お祭り的に遊びに来ている」感覚も強いです
ただこれを参考にして国内で解決するのは根深いと思います
日本は敗戦後の自虐文化が80年以上に渡り根付いています
同じ日本人同士で足を引っ張るネタを探すかマイナス方向を面白がっては報道やSNSで叩く文化
ですので何事も閉鎖的ですし尖ろうものなら揚げ足をとってでも降ろすというか
中国の場合は「そんなことをしようものなら」…(省略)ですからね
とはいえ著名海外デスメタルバンドですら国内では観客100人が精一杯という流れは厳しいですね
「何が変われば日本のシーンが変わるのか」をまず現状把握してみたいと思います
①宣伝媒体が限られ過ぎてその多くはバンド個人発信レベルでしか情報が届いていない(知られない)
②アルゴリズムを含めフィードに運よく乗らないと情報が届かない(知られない)
③地方からわざわざ行くまでの話題性やお祭り感が出せていない(知られない)
つまり「情報が届いていない、知られない」が大きな1つの要因だと思います
確かにデスメタルは地下シーンではありますが「知られない限り」は母数の増加は難しいでしょう
なぜなら中国の様な「イベントに敏感でお祭りに行く感覚」ではないのですからね
難しい問題です、戦後の大手メディアが80年掛けて作り上げて来た揚げ足取りと足の引っ張り合い報道
そしてそれをコソコソと楽しむ日本の習性文化が完全に醸成されてしまっていますからね
バンド系SNSを見ていてもそうです
脱退、解散、スキャンダル、逝去の発信ばかりが目立ちタイムラインに流れてきます
本来、ライブ告知やリリースなどで目立つ事が本望というかそれが「知られる」ですからね
真逆であるこの状況を覆して行くというのは、これからまた80年掛かるのかどうか、日本人の民族的な精神自体が変わる事も必要でしょう
更には同じエクストリームメタル界隈でも叩き合うというか、「業界を盛り上げるためのイメージ作り」とは掛け離れたいざこざ?の様な事も多いですしね。これも例えるならどうでも良い他人事の不倫スキャンダル等を必死で叩くのと同じと言いますか、個人的には全く興味が無いです笑
日本人同士なのに、助け合うではなく蹴落とし合う文化はそう簡単に変わる事は無いでしょう
とはいいましても現実的?に何が出来るのかを考えてみたいと思います
先ずはSonyやAvexなど極端に大規模なレーベルから契約リリースするです。否応なしに「知られる」が達成されるでしょう。極端ですが極端でないと風穴は開かないと思います
以前から幾度も書いてきていますが「たとえ世界で一番凄いデスメタル曲を創っても知られない限り誰も知らない」です
あとはメディアがこれまでにしてきた偏向報道(というか制作側の思想と思惑)ですがみんな信じて来たわけで、その情報洗脳により幼少時から大人になってきてるので大手メディアの情報操作次第で人間の人格まで形成されてしまっています
次は難しいですが垣根を取り払うです
細分化し過ぎているメタルジャンル
ブルデスは好きだけどメロデスはチョット..
.スラッシュメタルは好きだけどデスメタルはチョット…
好みまでも細かく拘りが強過ぎていることも日本文化の特徴
例えばですが個人的には「エクストリームメタルフェス」ならスラッシュ、グラインドコア、デスメタル、ヘビーメタル、デスコア、スラミングデス、ミクスチャー、ノイズetcのあらゆるメタル系が「ごっちゃ煮」であるからこそ「フェス」だという感じがします
ですが実際は長年に渡り近似値バンドでイベントが固まる印象(それが悪いわけでは無いですし親和性があるファンも集まりやすい)がありますので「広がり」と言う面ではハードルを越えられずにいるかもですし、それがかえって更に拘りと細分化へまっしぐらな蟻地獄モードになる可能性もあります
ただこれも難しいハードルで小さい塊(地下バンド個体)が長年に渡り分散化してきているので、それを混ぜればすぐに収容規模があがる(シーンが盛り上がる)かというと、そうでは無いと思います
大きな塊のごっちゃ混ぜの大成功を経験し「それが面白い」という流れで「流行る」まで行かないとなかなかでしょうね。ただ現状は拘り精神が強すぎて(興味無いバンドは観ない傾向)挑戦するのがなかなか難しいのかもしれません
あと最大の問題はシーンが小さ過ぎて各自が自分の身の事で精一杯なので他のバンドを応援するとか後続を引き上げるなどの余裕が無い可能性も
ちなみに我々も情報発信していますがバンドから「いいね」を押されることはほぼ無いです
ほぼコアな地下シーンのファンの方のみからです
バンド同志で相互に押し合っているところは普段から身内感あるバンド同志の儀礼的「相互いいね」
特に我々の場合、普段音楽関連の方達と関わることが無い生活をしているのでバンド徒党的な部分は皆無です。共演等で知り合いのバンドやリスペクトしているバンドは居れども普段接触機会はほぼ無いです
生きている間に中国の様なお祭り感なライブシーンが国内で起きることがあれば見てみたいですね
時代の変化とSNS
僅か数十年前はテープトレード、手紙(文通)のやり取り、個人ファンジン誌で情報を得ることが主要だったアングラ音楽
その後にCDやビデオテープが全盛を迎え、更にはインターネットも出てくるわけですが、今やストリーミングの登場で「音楽は無料でも聴ける」になってしまいました
幸か不幸か我々の様なデスメタルジャンルになると好きなバンドTシャツを着たり、物理マーチであるCD/レコードを入手したいと思う傾向がかろうじて残っている感じです。
そんなインターネット社会でバンドとして何が出来るかを考えてみます
一旦話を逸らせますがスポンサーの少ないマイナースポーツ競技業界では選手が各自でYoutubeチャンネル開設し自分の試合の配信ライブをし始めています。試合前に自分で三脚を立ててIphoneで流す感じですから手間も掛かりません
こういった選手個人が自分の試合を自力でライブ配信していくという「輪」が広がり今では皆んなやってるというくらいに瞬く間に広がっていきました。スポンサーが居ない選手は遠征経費を含めて自腹ですし、成績が悪ければ大会結果のメディアに名前が載ることも無いですしね
なので個人でどんどん発信して行っています。これが功を奏し「オススメ欄」を含め雨後のタケノコの様にどんどん出てくるので、ふとしたきっかけで業界自体に興味を持つ人が増える事でこれまで日の目に当たらず存在すら殆ど知られていなかった選手を知る事ができるきっかけとなりファンも増えています
特にライブ活動をするバンドであればSNS発信は告知プロモーションの為にやった方が良いでしょう
以下へ音楽系を対象としたSNSで重要度の高い(効果/影響大)と思われる順番に挙げてみます
(アジアのバンドが世界に向けて発信する基準)
①Instagram
②Youtube
③小紅書(Red)
④Bandsintown
⑤Facebookバンドページ
⑥X(旧Twitter)
⑦バンドオフィシャルHP
個人的に考えた順番ではありますが特にアジアのバンドにとってはほぼ合っているのではと思います
ひょっとしたら、ここでいう最下位のXが一番上ではないかと思う人もいらっしゃるかもしれませんが音楽系は世界人口で考えるとインスタグラムの独走だと思われます。日本は独自文化がありますのでXでの利用率が高いのでしょう。実際、Cannibal CorpseやDeicideがツイッターを頻繁に更新しているイメージは皆無ですよね。なので海外ミュージシャンは来日公演があるときだけ慌てて久しぶりにXを開いて告知更新をするみたいな。あくまで日本向けで告知利用する傾向だと思います
順番のトップ2は視覚と聴覚のSNSです、つまり↓
■インスタグラム→フライヤー告知やライブの写真
■Youtube→MVや新曲を聴けるようにして告知する
このような仕組みだと思います
なお③の小紅書(中国版X)は開設するなら今の内です。これからの数年でレッドオーシャンになるかもです。一年くらい前(2024年)に開設しましたがおススメにどんどん日本の著名ミュージシャン出てきています。つまり矢継ぎ早にこぞって開設し始めています。(例えば最近だとマーティフリードマンが開設)やはり人口が人口ですし市場規模も大きいこと、母数が大きいこともありますが追い打ちを掛けて「エクストリームメタルの波」が来始めていますからね。今後はそうこうしている内にかなりの数のデスメタルバンドの小紅書も乱立していくと思われます
そして④Bandsintown(チケットリンク付きライブ告知SNS)については我々は完全に後追いで最近開設したばかりです。このアプリ自体は既に10年以上前からレッドオーシャンと言いますか、もはや「バンドやってるなら皆活用していて当然でしょう」と言うと言い過ぎですがそれくらいメジャーな「音楽特化型のライブ告知アプリ」です。このアプリは海外ツアーをし始めてから知る機会となり、今更感はあれども開設しました。内容的にはてっきり海外ツアー向けかなと思いきや国内邦楽系の著名アーティストを含め、なんなら現在地付近の本日開催されるライブ情報(チケットも携帯から買える)まで出てきますので便利です。このアプリは完全に浦島太郎でしたし開設以降は色々チェックしますね
以上、昔のテープトレードやファンジン漁りの時代からいまやアプリ告知とストリーミングという時代の流れについてでした
ステータスマウント
今回は敢えて故意にチョットいやらしい風な表題を付けてみましたが
『あの〇〇大規模フェスに出た」、「あの超有名な〇〇と共演した」
このような感じの内容をSNS等で発信しているのをよく見掛ける意味について考えてみます
もちろん「そのフェスに出たから偉い」とか「その有名人と共演したから偉い」ということは全く無い訳ですが、表現の仕方によってはそういう風に聞こえる(見え隠れする)こともあります
そもそもバンド音楽自体の本質的表現とは全く関係ない部分ですが
それでも「あのフェスに出た=そのバンドは凄い」、「あの有名人と共演した=そのバンドは凄い」という、仮に本人は凄くなくてもその有名人と共演したこと(虎の威を借る狐)でバンド評価自体が上がるならばその影響は大きいのでしょうし逆にそんなことが影響するならばチョット馬鹿らしいですが、それだけやっていれば良いのではという冷めた現実も考えられます
本末転倒…
ただバンドにとっての長所もあります
その実績を表現することによる「バンドの信頼性」です
エージェントやヘッドライナー側がそのバンドの出演にOKを出している訳ですからそういう意味で認められたバンドという捉え方です
確かにそういった実績を書くことで曲を聞いたことすら無い”初見”の人にも一瞬で”凄いんだ”という信頼感イメージを与えることが出来るという要素も挙げられます
ただ、それを起点に実際に聴いて下さるのかどうかは別物ですし、名前は知ってるけど聞いたことは無いし、見に行ったことも無いは実は多いと思います、あくまでSNS表現等の知名度先行型バンド
もちろんその文面を見て「へぇー、凄いんだー」だけで終わる可能性もあるかもしれませんが、それでもその瞬間だけでもそのバンドを「知る」というきっかけが出来るのでつまりは認知の全体母数が多くなることによる「周知の可能性が拡がる」に繋がります
この件についての個人的な現況の思考は、ステータスを目的にするのは本末転倒ではあれども周知の為に実績面をツールとして活用するのは有効といった感じでしょうか
ただこういった華々しい実績を盾に「俺は偉いんだぞ」的な文面を見た時はちょっとヒキますね
あくまで「周知の為のツール」として使う表現をすることが有用でしょう
実績を盾に文面での言語表現をするバンドが多いのは「認識される可能性の母数の多さ」があるからでしょう
①「大規模フェス等の出演実績有り&再生回数が多い」=「そのバンドは凄いバンド」
②「大規模フェス等の出演実績無し&再生回数が少ない」=「ショボいバンド」
と言う大衆の認識/判断が多数です(なので俗に言う炎上商法すら流行してしまう訳ですが)
我々の様な超小規模バンドにとっては耳が痛くて厳しい話にはなりますが現実社会ではそのような評価と認識をされる傾向が大いにありそうです
経費面で考えると例えば海外ツアーならば著名バンドのオープニングアクトで廻った方が一度に沢山のお客さんの前で演奏できるのでDIYでホールブッキングして行くよりもパッケージツアーの方が経費効果は絶大かもしれません
最終結論としては「表現手法には気を使いながらも実績は上手く有用して行った方が良いのかな」といったところです
ライブに招聘されたら出来ることを全力
ライブに招聘されたら出来ることを全力で告知です
たとえ我々の様な超小規模&拡散力も無いバンドであってもです
主催の方は会場を借りたり準備したりフライヤーを作ったり一生懸命宣伝します
興行が赤字だと困るから必死なはずです
我々の様なヘッドライナーでは無い超小規模バンドであっても出演させて頂く限りは助力になればと必死で告知します
その興行が「上手く行かないと心が痛い」からです
ヘッドライナーでは無くとも申し訳ない気持ちになりますし、どのバンドもそれが自然だと思っていましたがバンドによってはイマイチ宣伝していないケースもちらほら
何の為にライブをやるんだろう的なこともありますし、主催者の立場や関わるスタッフの方達の事を思えば「宣伝告知しないは無い」です
実はちょっと心配なんですよね、間もなく遠征する某ライブ
厳しい言い方になりますがヘッドライナーがプロモ告知してないので「そもそもその日にそこでライブがあることすら誰も知らないのでは?」というくらいに静かです。現況の前売り券数もほぼ我々を目当てに来場くださる精鋭のお客さん
日程が迫って来た現在、主催者は焦り始めました…それはそうですよね
現在、メインアクトではない我々がマメに連絡を取り合い、プロモアイデアを出し合いながら必死で告知しているという
こういったアクションをしないバンドの行動心理は読めないです
以前にも某ライブで似た経験がありますが興行の結果自体はやはりイマイチでした(ですがそれでも公演を探し出して来場くださった激熱な精鋭ファンとの交流が出来たのは幸いでしたが)
ライブしに行くなら事前のプロモーション告知は必要でしょう
「日程、会場名、会場住所、出演者、チケット入手方法、当日券有無、開門時間」は最低限の告知情報です(できれば出演タイムテーブルも)
なぜやらないのかは思考が違うから分からないですが不思議です
ただ我々にとってはこういう事がきっかけでヘッドライナーよりもエージェントとの絆が強くなり信頼関係が深まるという
強固なバンド(メンバー)とは
近年、光栄にも多くの著名バンドと共演させて頂いていますが、世界的に有名なバンドであっても毎年のようにメンバーの誰かしらが下船(離脱)し新しいメンバーを迎えるという上船(加入)の状況が続いています。(今年2025だとDeicide、Cannibal Corpse、Cradle of filth、Pestilence、Sinister等)
個人的には「バンドメンバーは下船と上船が続くのが自然」とすら思っています
ファンからすると知る由もない事も多いとは思いますが、下船理由の99%は経済活動的に続かないからです(表面上、そうは言わないとは思いますが)
例えば2週間や1か月のツアーをするとしたら
先ず最初の段階、つまりツアーに参加する前段階で「普段の生活がそもそも基本的に自由の身である必要」があります、言い換えるならば長期間に渡り家を空けても「やっていけるかどうか」です
なので帰国後の経済生活も成立できることが前提です。それが出来ないパターンでツアー後に離脱するとか、レコーディング後に離脱するとかはもはや定番かもしれない位によく聞く話です。「ツアー中に仲違いした」とかその類は実は「経済的な話」(やればやるほどシンドイとかの金銭的にキツイ系)が糸口となり、もつれただけなのかもしれません
ご存じの通り「デスメタルで家が建つ訳では無い」ので
となると著名バンドであってもツアーで家を空け、その後に僅かばかりのギャラを持って帰ってくることができたとしてもツアー後の生活はどうするんだとなります
なので、ツアー活動が無い日常生活期間においては例えばですが下記で賄える様な人じゃないと難しいと思います
①自営業
②会社社長(自由が利く)
③ツアーの為に有休が取れる会社に勤務
④富裕層(不労生活可能)
これらは「バンド活動をするために幼少期や青年期からかなり頑張ってきた人」「もしくは生れながらに運の良い人」(例/富裕層子息、親の会社を引き継げる等)じゃないと上記を満たしながら好きなバンド活動を自由に行うというのは難しいかもしれません
それでいて長髪だったり、機材を揃える経済力だったり、そもそも楽器スキルだったり、創作スキルだったり、更に現代ではSNSの使い方が巧いかどうかだったりも
これら全てをクリアしている人は少ないと思います
だから下船と上船が続く訳です、たとえ世界的に有名なデスメタルバンドであってもです
逆に、上記に当てはまるメンバーが集まれば「強固なバンド」になると思います
サブコンは今そこに到達しようとしていますので一体感というかワクワク感がありますね
※追記的な話になりますが表面上でよく聞く「音楽性の不一致」とか「性格不一致」とかの下船の話はむしろ羨ましいというか、その類の次元で上船下船になることは(我々は)無いです。何故かと言うと前提が「活動方向性への一致」が全ての前提になりますのでその意思を持った人が集まる事になります。ですので上記の様な音楽性ウンヌンの様な部分がそもそも課題にならないです。なのでメンバーを探す必要がある際はどんな音楽ジャンルの人でも気にすらしないですし、あくまで活動意思とおかれた環境です
Defeated Sanityの新譜に聴き惚れ
上記はDefeated Sanityのドラムプレイスルー動画です
なんと言いますか、現行の我々には創れない曲です
彼らの場合、ドラムのリズムからリフ(音階)を創るのでしょう
リフ(音階)からこのリズムパターンへの着想は先ず無理であろうと推測します
いやはや、彼らの独自の道への歩みは凄過ぎますしリスペクトバンドです
良い意味で(大称賛の意味で)プレイヤー向けのバンドと言いますかガチの音楽マニア集団
ギターが曲を創るバンドは「そのギタリストは相当ドラムが叩けた方が良い」「もしくはドラムリズムに相当理解が深い方が良い」とはよく言ったものでアイデアは多彩になります
我々も次作以降に「先にドラマー作ったリズムにギターリフを載せる」というのはやってみたいですね
唯一ですが我々の3rdアルバム「Chaotic Diffusion」内の曲名「Irreversible Damage」はドラムリズムから創りました。この曲は個人的にはかなり特殊な曲で、ドラムリズムをイントロから最後までザックリと創り「それを聴きながらギターを弾いたらこうなった」という曲でギターリフの創作については確か30分も掛からなかったと思います。ドラムリズムに合わせて一気に一筆書きの様な感じで弾き切ったので一瞬で創ることが出来たという曲です
気づく人は気づくかもですが「リフに乗せたドラム」と「ドラムに乗せたリフ」は性質が違います
なのでこの曲は我々にとってはかなり異質曲となります
ギターリフから創った曲やドラムリズムから創った曲など織り交ぜられればバラエティ豊かになりますし新しい発想もありそうで面白いかもですね
ちなみに経験上、ギターリフの創作は「練れば練るほど」おかしくなります(悪くなる方向に行きがち)
我々の場合はインスピレーションでパッと行き切った創作曲の方がアルバムのオープニングや前半収録曲になることが殆どです
↓Defeated Sanityとの共演時(2024.08)写真

音の抜けは棲み分け
バンドで音を出す際は自分が好きな音を出せば良いでは無いと思います
あくまでバンド全体でどのように聴こえていて各パートの音がしっかり抜けているか
例えばですが1人でギター練習している際に「自分の好きなギターサウンド」があったとしても
そのままバンド形態に持ち込んでそのサウンドで上手く行く事は殆ど無いと思います
あるとすれば既にバンド全体での音が固まっていて(音の分離が完了状態)そのセッティングで練習する事が習慣化しているプレイヤーだと思います
よく言われるのが「帯域」
前提としては我々の場合はブラスト多めの低音ボイスバンドのケースです
先ずは帯域の近いベースとボーカルが被らない様にです
そしてギターもベース帯域と被らない様に、アンプやエフェクターのツマミの低音域は「ほぼカット」しベース&ボーカルに被らない様に
なのでギターは「耳が痛くならない範囲で中高音域を上げまくる」にしています
例えるならギターはシンバル帯域とギリ被らない位のイメージでしょうか
以前にギターの音圧が欲しいみたいな事を書きましたがやはり全体音質で考えると低域はドラムとベースとボーカルに任せる方が良いという判断結果です
我々の場合はこうすることで「全楽器の音抜け良い」(各楽器の輪郭がクリア)という現時点での結論に至りました
全楽器の中で音色を変えやすいのはギターサウンドが一番融通が利きますしね
あとは、他の楽器でしいて言うならばスネアをカンカン鳴らすような高音にすると低音帯域と被り難くなるので特にライブではスネアの音がかなり聴こえ易くなる傾向です。音楽性にもよりますがデスメタルのツアードラムプレイヤーにはお勧めかもしれませんね(例/小口径スネア、打面&裏面ヘッド高め、金属シェル、薄いヘッドetc)
実際、バンドアンサンブルの為のギターサウンドでギターを1人で練習していると中高域が高くてキンキンしている様な気がして低音弦ミュートで刻む際も「ズンズンした感じがあまり無いなー」(例/パンテラサウンドの様な)とは思うのですが慣れてくると大丈夫(気にならない)になりました
あくまでバンド全体としての音質(帯域分離)が全てだと考えています
ライブで音抜けが悪いと聴く側(お客様)からは何をやっているか分からないのでそれだけは避けたい想いです
確かにその引き換えとして演奏ミスをするとすぐに分かるので(誤魔化しが利かない)シビアな演奏にはなりますが、でもそれはバンドが上達していく為の本望(誤魔化さない)でもあります
もちろん人間ですからミスをしない事はないですし、あくまで致命的にならない様な小さいミスであればむしろ人間味があってそれはそれでアリだとプラス方向に考えています
ギタープレイヤーが他バンドのライブを観る際、ギターを弾かない人よりも「聞き耳を立てる」というか音色やスキルに耳が敏感だと思われます
なので「ついついチェックしがち」というか「耳に入ってきやすい音」部分ではあるかもしれません
もしもこれが音圧重視で輪郭が無く、何をやっているか分からないサウンドだとなんというか、興味が減るわけでは無いですがもう少し曲の輪郭を理解しながら聴きたいなと思う事があります(ノイズ系や狙ってそうしているバンドは別ですが)
個人的にはギターをあまり歪ませずに中高音域メインで「タッチが敏感でミスがすぐわかる音なのにそこを勝負しているプレイヤー」的なところを目指したいと思います
もしこのサウンドでほぼミス無しレベルのライブが出来たら双方(バンドもお客様も)気持ち良いでしょうね
上達を目指す為に出来るだけクリアな音作りと帯域分離でライブ修行していきたいと思います
人間は調子の良し悪しがつきものですが普段から自己動作を言語化できてそれを記憶と習慣化し俯瞰しながらその瞬間を調整しながら均衡を保てるプレイができれば高レベルなプレイの平均化(いわゆる”ゾーン”に入る事を日常化する)を目指せると思います
余談ですが昔、別業界(競技スポーツ)で長年プレイしてきた経験上の話です。「ゾーンに入る」と動作が無意識に近い状態でルーティン化し視界焦点すらボンヤリしたまま周囲の視界意識も消え脳が全てを支配した状態になり「無双化/無敵化」していきます。あくまで私見ですが楽器も行き着く先はそうなのかもしれません
音楽活動は正に心技体です
ギターボーカルによる作曲
我々はギターで曲を創っています
ただその楽曲群は「ボーカルギターが創っている」ことと、ツインギターでは無く「シングルギターのバンド」という背景です
偶に思う事があります
「弾きながら歌う(歌える様に)を想定」して創るのかどうかです
もしも自身がリードギタリストとしてのポジションであれば(歌わないので)もっと好き放題に複雑にギターを弾いていたかもしれませんし、そういう曲にしているかもしれません
もしもバンドにリードギタリストが居ればボーカルギターはバッキングギターに集中しシンプルな部分を弾けるのでどこまでも複雑怪奇な曲もできそうですよね
ただ、そうなってくると今度はそれを弾ける人を探すのが難しくなってくるのでこのバランスについては何とも言葉では難しいところもあります
そういう意味ではやはりストレートというかシンプルな方がライブバンドとしては良いのかもしれません
Necrophagist、Spawn of Possesion等の超絶テク系デスメタルバンドもリスペクトしています
ですが、やはり彼らも活動が続かない(続けにくい)結果になっています
メンバー全員が超人テクが必要な楽曲の場合、万一メンバー欠員した時点で代替メンバー探しが難航しますし、そこで活動がストップになりがちです
我々の場合はテクニカルなんて言葉は不要というくらい烏滸がましい範囲で楽曲作りをしていますのでこの部分に関しては懸念せずに済んでいますが
もし自身がリードギタリストポジションであったらそっち方面にも凝っていたかもしれませんね
迷子に再突入
ここ3年くらいはライブでのギターサウンドに関しては小さな変更はあれど固めてきていました
ですがまたウロウロと迷子になってきています
現況は逆ドンシャリといいますかイコライザー的には右肩上がりです
ツマミ的にはベースをカット、ミドルをマックス、ハイをマックスの手前です
こうすることでベース音やドラム音との帯域を避けられるのでギターサウンドが切り離されリフの輪郭がクリアでライブ演奏上でも何をやっているかがハッキリクッキリ分かり易いとしています
ですが近年のエクストリームメタルライブを公演会場やYoutubeなどで拝見していると、ライブでは音圧重視というか「音の迫力」をメインに音作りをしているのではないかという私見です
なのでズンズンとベース帯域をマックスにしたようなギターサウンドが多い様な気がしています
もちろんその分、リフの輪郭が塊になるというか埋もれるというか、予めその曲を知っていれば分かりますが、知らなければちょっと曲の輪郭が分かりにくいというか
そういう感じのバンドが多い?風潮?の様な気もしています
例えリフの輪郭が埋もれがちであっても低音帯域マックスでライブをすると音の渦的な迫力があります
ですので対バンライブの場合、その後に我々の出番になるとサウンドのクリアを追求し過ぎたが故なのか、ちょっと迫力が落ちるというか音圧負け?しているのではという
この塩梅が難しいところです
なので最近、その迫力部分を出す為に練習中に故意にEQで低音をマックスにしてみたり色々とやってはみるのですが迷子になりかけています
聴かせるバンドなのか、イカつい低音域の迫力で押すサウンドなのか
これがたとえテクニカルデスメタル系であっても輪郭よりも低音メインで音圧迫力によるライブ感重視で行くのか(一番下に参考動画リンク/どう捉えて良いのかは判断が難しいですが)
もちろん音抜けが良くて低音域の迫力もあれば良いのですが綱引きみたいな関係性も感じます
以前に書きましたがサスティンブロックを変えて以降、音抜けがかなり良くなってはいるので低音を増やしてライブしてみようと考えています、チューブスクリーマーでブライトな音質を上げつつですが
日々そうこうしていると何が何だか分からなくなりがちなのですが、機材のトッカエ・ヒッカエとツマミいじりは永遠に終わりが無さそうです
これらは究極の自己満足
ですが最終的にはバンドアンサンブルなので「バンド全体での音質に沿う形」になりますね
参考1)中音、つまりアンプからの音が直で(生で)聴こえている(No Mixサウンド)と思われるステージ前面からの動画
https://youtu.be/zX7xFx1mY1E?si=xq4NgtHqYyJTBrJd
参考2)こちらはギターの目の前からの動画(あまり歪ませてない感じのクリア系と言えそうですね)
https://youtu.be/CMQLVvqnBH8?si=P-wRvBnvUzVPc2GL
余談ですがSinister、Cryptopsy、Defeated Sanity、Massacre、Pestilence、Skeletal Remainsなど海外有名デスメタルバンドと共演させて頂いて思ったのがギターソロの際は「思い切った音量ブースト」や「ハッキリしたディレイ」(ショートディレイではなく)を利かせていました
曲のメリハリがつきますし「おおお!カッコいい!」と感じました
不器用な当方にとっては歌いながらスイッチを踏み変えるのは難しいのですがこちらも少しづつトライです
ライブ時の持ち物/忘備録
連続でライブの予定があります
そこで今回は、当バンドがライブ時に持っていくものを忘備録的に書き綴ってみます
①パスポート
②航空チケット予約確認書の控え
③着替え
④各パート楽器一式
⑤イヤモニ&送受信機一式
⑥MTR(クリックをイヤホンに流すための機器)
⑦ドラムトリガー(打撃の電子信号変換センサー)
⑧着替え
⑨マーチチラシ
⑩物販卓でマーチのチラシを立てるための衝立
⑪折り畳みハンガー(会場の壁にシャツのサンプルを掛ける為)
⑫フック付き吸着(物販会場の壁によってはサンプルシャツを引っ掛ける場所が無い事もあるので)
⑬オープニングSEを入れたUSB(CDRに焼いたものも念のため持っていく)
⑭ステージプロット(事前に送っていますが念のため紙媒体でも持っていく)
⑮バスドラムに貼るバンドロゴカバー
⑯ガムテープ(位置決めや固定用)
⑰物販CD/DVD/シャツ/ステッカーなど
⑱布製バックドロップとそのUSBデータ(ステージ背景に使用)
⑲セットリストのプリント(メンバー数+PA提出分)
思い付いただけでもざっとこのような感じです
我々はこれらを1人につき3つの荷物にまとめています
手荷物x1、飛行機預け荷物x2です
荷物数を追加すると経済負担(追加料金発生)になるので数と重量オーバーも気にしながら荷物を詰めています(ただ、航空会社によっては預け荷物が1つの場合もあるのでその場合は事前予約するとかなり安いです、当日清算だと倍以上に…)
あとはその国の会場最寄り空港に到着すれば、ありがたくもプロモーターさんによる空港送迎、食事、ホテル、バックラインなどを用意くださっている感じになります。本当に感謝です(ひょっとしたら空港到着した後も全て自己手配の様なライブもあるのかな?かもしれませんが今の所はその経験は無いです)
特にライブ前は本番への不安を残さない様にこれでもかと言うくらいオーバープラクティス気味に練習します
その他としましては当日に現地カメラマンが入るとか、ステージの広さや形でフォーメーション(並び)をどうするか等、事前に現地の方との打ち合わせや取り決めがあります
さらに細かい話になりますが物販に関して
国によってはキャッシュレス決済がメインです
なので該当国のキャッシュレスアプリをインストールしQR決済できるようにしておく必要があります
ちなみに中国は現金決済がほぼ無いのでWechat PayとAli PAYのQRを持って行かないと物販は全く売れませんのでお気をつけを
近々行く予定のあるシンガポールだとPay Nowアプリが主要です
なので各国向けに主要キャッシュレス決済QRコードを準備する必要があります
事前準備が沢山ありますが各国のやり方や文化に触れられる機会もあるので毎回勉強になります
どうしてギターが弾けるのか
あえてこの様な表題にしてみました
ギタープレイヤーは自分の曲であればほぼ無意識で弾いていますよね
もちろん当方も自分の曲を無意識レベル(脳内で音を奏でながら指先に指示している)で弾いています
では「なぜそうしているのか」、はたまた「なぜそれが出来ているのか」を紐解いて行きたいと思います
ネット上でも調べてみました
運動記憶(muscle memory)と身体知(body knowledge)が関係しているそうです
①運動記憶→”反復練習”で指が勝手に動く回路を作る
②空間認識の形成→フレット(指板)を”地図認識”して身体感覚で染み込ませてる
③耳と指のリンク→”耳で聞いた音”や頭の中で鳴った音がそのまま”指の動きに直結”し、これが進んで行くと考える前に音が出るようになる
だそうです
これに当てはめて考えてみたのですが自分がギターを弾く際は大部分が③でした
もしかしたらですが「曲を創る系ギタープレイヤー」は特に③の値が異常に高いのでは無いでしょうか?それが合ってるかどうかは分からないのと、それで良いのかどうかも分かりませんが自身はこの部分にかなり偏っています
「10代の野生の感?」だけでギターを始めたのが要因なのかどうかは分かりませんが「感覚で音を探しながら弾く」という”癖”?があります
例えば他者の曲をTAB譜(譜面)を見ながらコピーする様な場面では①の能力が強い方が良い様な気がしますが自分の場合は音を探しながらコピーする方が好きなのと覚えも早いです(極端な超絶スウィープ等を除いてですが)
結論的としては言語化するならば「音当てゲーム」の様な感覚でギターをプレイしている感じです
「その音が欲しい」→「その場所を押さえている自分がいる」
このような感覚と表現すれば分かり易いでしょうか
やはり③が強いのとそれが好きですね
耳に頼って音を出しているのでしょう
ただあくまで当方の場合ですので人によっては全然違うのかもしれません
逆に今後はどうしたら良いのか、何が良いのかを知りたいのと追及です
機会が有れば他のギタープレーヤーに①、②、③の強弱感覚を伺ってみたいです
これらを分析&紐解いて行けば作曲傾向や手法、音の使い方などに関して何か新しい発見があるかもしれません
とにかくギターが大好きなのですが全然上手くならないので上手くなりたいですし藁をも掴む思いでヒントを探し出して行きたいです
これからバンドやってみたい人、音楽を創ってみたい人
音楽に興味を持ち「音楽を創ってみたい」、「オリジナルバンドをやってみたい」という方達向けのお話です
昔と違い、今は1人からでも簡単に立ち上げられます
先ずは「PC+DTM」さえ用意できれば楽器すら出来なくても大丈夫です
ドラムもギターもPCでポチポチできますし、たとえ音痴でも歌はピッチ修正できますし、ボカロ(歌声合成ソフト)に歌わせることすらできます
もし将来的にバンドを組むならば自身が興味のある楽器をやってみると良いでしょう
その位、現代は音楽創作が手軽です
いきなり「将来俺は人生を賭けて音楽でやって行くぞ!」となる前に先ずは自分でやってみて創作センスの有無を確認してみたり、YoutubeにUPして受容角度を見てみるも良いですし、この楽器なら自分にもやれそうだとかの判断も出来ます
自創作をしてみて、結果的に思い描いた想像とは大きくかけ離れているかもしれませんし、意気込みと現実の相反で自信喪失する人もいるかもしれませんが、オリジナル楽曲創作の難しさであったり実際に楽器で奏でることの難しさやニュアンスも理解できるので次の方向性に繋がる可能性もあります
そういう意味では現在は手軽に創作チャレンジができますし、早々に自身のセンス有無を確認もできるという羨ましい時代でもあります
サブコンシャステラーの90年代はラジカセにギターリフを録音し続けながら、そこから構成を組んでいきメトロノームも無しでイントロから最後まで弾き切ったテープをダビングしてメンバーに配り各々が聴きまくってスタジオで全体(ドラム/ベース/ボーカル)を完成させていました。(1stアルバムCDの「Invisible」もメトロノーム無しのほぼ一発録音です)
それが今ではPC+DTMにギターを繋ぎ録音しながら自宅でデモを創れ、曲の構想段階では他パート(例/ドラム)もザックリと打ち込みで作れますし、その後のプリプロで各担当楽器メンバーが実際に奏でながら曲の最終形態を創れるので時間効率も良いです
更にはTAB譜(楽譜)もプログラムソフト(Guitar Pro)があるので創作時にPC上でポチポチ打っておいてPDF化しておけばメンバーに新曲を渡す際に各自がすぐに取り掛かれますしね
ひょっとしたらDTMの使い方が分からないという人も居るかもしれませんがそこを探求して潜れないならばそこまでの熱量であったということかもしれません。さもなくば最初からメンバーを探してのバンド形態でやって行くことになるでしょう
曲を創るって簡単ではないかもしれませんが熱量があればそれらは超えられると思います
コアファンの方達に感謝
このブログ欄についてはどちらかというと気づかれないテイと言いますかコッソリやっている感じで、内容自体もネット検索に引っかからない仕様にはしていますが今年に入ってからページビュー解析を見ると大体毎日300人位のアクセスがあります
なぜかというと音楽性とは違う範囲の話も多いのでそれが影響して当バンドの音楽性イメージへの興味が変わってしまう事を懸念しているからです
あまりにもバンド内情や取り組み方について正直に書き過ぎています
今後も素直な感覚でバンド活動の内容を書いていきたいですが我々の様な超小規模バンドにとってはこのページビュー数はちょっと怖いというか万が一にも増加を辿ると「繕った表面上の事」しか書けなくなる様な気もしています
当初この項目は日々レベルで5人~10人のページビューと言った超マニアックに「気づいた人だけがコッソリ拝見」下さる様な書き綴り感覚でした
とはいえ初期から拝見下さった方もいらっしゃるのでその方達への感謝の意味でも可能な範囲でバンド活動については赤裸々&正直に書き綴って行こうと思います
これまでの内容はもしかしたら賛否両論あるお話もあるかもしれませんがそこはご愛敬と参考程度に見て下されば幸いです
ありがとうございます
浮かれている場合では無い
つい先日、残念ながらお断りを入れたライブ招聘がありました
招聘者が必ずしも良い人かどうかは分かりません
海外案件ですがかつて散々な目にあったバンドばかりのイベントでした
具体的な名前は出せませんがそういうケースもあります
そのライブに出演したが最後、事前の約束事や諸々の条件が全て破綻するようなケース
ですのでバンドマンは海外からの招聘に浮かれている場合ではありません
やはりしっかり身元調査というかこれまでの過去のイベント状況であったり、過去に出演したことのある先輩や先人のバンドにアドバイスを伺ったりする方が得策でしょう
特にバンマスはメンバーを守る「責任義務」がありますから
ライブのお話は頂けども「なんでもかんでも飛びつく」は危険かもしれません
我々もそうですが「ライブをしたい」気持ちが強いバンドは要注意です
それを学費と思って敢行するのもあるかもしれませんが後味の悪い公演は事前に想定をしつつ避けたいところです
もちろんそれでもやりたければやれば良いと思います
ですが深呼吸して周りや先輩や先人にアドバイスを請うのも一考だと思います
バンドはストリーミングサービスに登録するか否か
表題ですが我々の様な超小規模バンドであれば登録しても登録しなくてもほぼ微塵も影響のない範囲なので「好きにしたらよい」、もしくは「自分たちのポリシーで好きにしたらよい」という感じになってしまうのかもしれませんがそれでも我々を見つけて下さりサポート下さる方に感謝しかありません
ただ影響力のあるバンドは現在、このサービスに登録するのか否かで判断に迫られている感じがします
先日、スポティファイは軍事AIに日本円換算で約1000億円の投資を発表し軍事ドローンや無人潜水艦などの製造開発をするそうです
普段、バンドメンバーが戦争反対を謳ったり、平和祈念を謡ったりしていたとしてもスポティファイは軍事投資会社でもある訳ですから登録料を払ってストリーミングしているということはむしろ戦争への協力活動をしているという「言動が矛盾」した捉え方も
そのことについてスラッシュメタルバンドDark Angelのインタビュー記事が掲載されていました
DARK ANGEL’s GENE HOGLAN Explains Why New Album Isn’t On Spotify: “I Can’t Be Comfortable With That Right Now” – Metal Injection
その中でドラムレジェンドのジーンホグラン氏は「スポティファイからは離脱し所属レーベル(※)からのデジタルダウンロードリリースをする」そうです
つまり軍事AI製造開発投資への違和感からこのストリーミングサービスから降りると
ちなみに彼らの(※)所属レーベルReversed Recordsですが、Dark Angel以外にもORIGINのドラマー氏のマネジメントやDeath To All(Deathのトリビュートバンド)など著名アーティストが所属しているロック&メタル系レーベル(カナダ)です
REVERSED RECORDS
今や携帯電話1つですぐに音楽を探せて&聴けるという、バンドの立場からは「一瞬で音楽を世界中に届けられるという利便性」との兼ね合い
特に影響力のあるバンドや有名な歌手は活動方針(フィジカル/デジタルリリース)だけではなく上記諸々を踏まえ音楽を届けるための選択を迫られる岐路かもしれませんね
フレットケアはこれ一択
指板潤滑剤や指板クリーニングにはスプレー缶タイプが多いですがこちらを使用しています


塗るタイプです
商品名はMUSIC NOMAD MN109
MUSIC NOMAD ( ミュージックノマド ) MN145 Premium String Care Kit | サウンドハウス
(↑リンクは補充液付きセットです)
国際線だとスプレー缶は制限が厳しいですし、やはりこの「塗るタイプ」が都合が良いです
例えるなら肩こりのアンメルツの全弦一気塗り版のような感じです
連日でライブがあったりすると手垢も付きやすいですし、公演後に急いで片づける際もサッと一拭きの手軽さもそうですし、弦疲労というか音の張り具合が悪くなる心的懸念も払しょくできます。公演内の曲間にも塗れますしお勧めですね。この潤滑剤は別名「神の油」とも
使う時はまず付属のクロスで軽く弦を拭いてから(埃等落としてから)塗ります
また商品説明でも「フィンガリングノイズを大幅軽減」とのこと
上塗りして行けばエリクサー弦みたいなコーティング感も更に増して指が滑らかで気持ち良いです
当方使用弦はエリクサー(コーティング弦)ですが更にこのMN109を上塗りしています
現状「エリクサー弦+Music Nomad MN109(指潤滑剤)」の組み合わせが全方向でNO.1です
ライブで集客する方法
結論は「ライブをしない、知名度と人気が出るまでは」です
元も子もないですが今はYoutubeやストリーミングサービスやインスタグラム等のSNSも沢山あるので現地に行かなくても地球上で音楽を届けることが出来ます
人気が出て招聘される位になってからライブをすればプロモーターも会場勤務スタッフもバンドも三方位で成立
そうでなければ自己の欲求でライブ活動をしておいて不満は言えないでしょう
集客がキツイから活動赤字というのは単に人気が無いからです
人気が無くてもライブをしたいなら自腹になることは自然ですよね
昨今のSNS上で度々流れてくる、こういった不満?の様な話は自腹になるのがキツイからでしょう
であれば見つめ直すしかないと思います
好きでやるなら自腹活動に不満を言わないことしか選択肢は無さそうです
「やりたいからやる」、それで良いのではないでしょうか
それが嫌なら事前準備です
例えばツアーをしたいならば一番上に書いたストリーミングサービス等でのプロモーショ以外に
①大手レーベルとの契約(影響力)
②プロモーターへのPR&契約(ツアーを組むチャンス)
③ビッグバンドとの繋がり構築(サポートアクトのチャンス)
この辺りは普段の日常生活の中で出来ることですし自宅に居ても出来ることです
作曲だって自宅の部屋でDTMで1人でも幾らでも作ってストリーミングにアップできる時代です
バンド形態ならメンバーの住まいが遠隔でも自宅レコーディングすらできます
それらをやるかやらないかだけだと思います
以前にも書いたことがありますが「本当に音楽が好き過ぎてぶっ飛んでいる人」はそもそもの視界が違いますし、このあたりの内容を「頑張る」と言う言葉ですらなく呼吸レベルでやっていますし「音楽生活環境を整える事が出来る」という末永く活動を続けるための「最も重要な音楽センス」を持っている、またはしっかりその部分も考えて行動しているです
再三ここで書いてきていますがたとえ「世界で最も凄い曲なるもの」を創っても世の中に届けられない時点で聴かれないでしょう。むしろ「世界で最も凄い曲なるもの」であっても反応は無いかもしれませんし、二日酔いでDTMの打ち込みで30分でパッと創った曲がCMやアニメ主題歌で使われ物凄いバズるかもしれません
音楽の良し悪しは難しいところもあります
個人で楽器演奏をしている人はここ30年横ばいだそうですがバンド形態の数は減っているそうです
なのでこれからの新人類の可能性としては最初は1人で立ち上げYoutube等で人気が出たらバンドを組み(各楽器プレイヤーを雇う)その後にライブをするという新しいパターンな人達が益々増えていくかもしれません
皮肉と言うか、影響力のある人が「この曲は良い」と言えば「右ならえ」というくらい大波及するSNS時代なので逆利用できる人はアリかもしれません
なので最近は「物凄い話題の楽曲だけど自分には響かなかった」というトピックも大量に出てきているのかもしれません
サウンド改善/ツアー持ち運びの便利さ/環境依存を減らす機材の選定
ブログ内で今年だけでも使用機材改善に関する内容を幾度か綴ってきていますが、また変更しました
ギターを鳴らしていると何かに気づいては弄ってしまう癖があります
いつも書いていますが機材は「とにかく頑丈で壊れにくい」(+代替が効く一品ものでは無い機材)が前提ですがペダルボードにセットする内容を改善変更

特徴としてはデンマークのTC Elecrtonics社のノイズゲート(Iron Curtain)を追加しています
オレンジ色のノイズゲート・エフェクターです、一万円を切る低価格帯も魅力的でした

ちなみにペダルボードの収納ですが「カメラ三脚保護バッグ」に行き着きました。超軽量でしっかりしていてかつ、ペダルボードを組んだ時の長さに対して豊富にサイズの種類が有るので重宝しています。
それをスーツケースの中に入れてツアーに持って行っています
ライブのステージセッティング時は「ギター本体」と「このカメラ三脚保護バッグ」(アンプ、ペダルボード、ワイヤレス、イヤモニ等このバッグ1つに全て収納)の2点になりますので楽ですね。肩掛けショルダー式にて両手が開くのでなにかと便利です。ちなみにアンプやペダルボード一式を収納しているこのカメラ三脚保護バッグですがアマゾンで2800円くらいでした
話を戻します
普段の生活環境がライブさながらの音量で鳴らせる事もありまして最近は練習時からライブ機材セットを繋いでライブハウスで鳴らす位のボリューム設定で音作りをしながらトレーニングをしています
小さい音量で一生懸命に音作りをしても実際のライブハウスでの設定音量にすると音質が変わる感じ(私感)がしたので普段の練習時から同じ音量でという具合です
そこで気になったのが音を鳴らさないタイミングでの「サーッ」というノイズ音
これを消したいと思いまして
とは言えども「サステイン(音伸び)が欲しい」時にノイズゲートの作用で「ビタッと音が切れてしまう」のは避けたいという、ちょっと我儘な要求も相まりそれを解決する為にこちらを購入してみました
想定通り効果抜群です(次回ライブの際に動画録画し実際の効果を確認してみます)
我々の創作曲に「ピッキングハーモニクスを鳴らしっ放しにする曲」(曲名/Endurance Battle)がありその箇所では音が切れて欲しくないけど鳴らしてない時のサーッというノイズ音は無くしたい
以前使用していたノイズゲートだと上記該当曲では鳴らしっぱなしにならず「ピッ」と音が切れてしまう事があり色々やってみましたが上手く調整ができずこのノイズゲートに辿り着きました
そういえば近年はPA直のアンプを使わないデジタル系プレイヤー(アンプシュミレーターから直接PAミキサーに音を送る)のライブが主流ですが我々はアンプ直使用のライブですね
古い思考なのかもしれませんが普段の練習の際に「あーでもない・こーでもない」とアナログ機器を色々と変えてみたり触ったりするのが好きです
余談ですがミックスマスタリングに関しては色々なエンジニア氏にお願いするのが好きです。自身はミックス知識が無いのでエンジニア毎に色々なやり方(サウンド作りや進め方)があったりするので都度吸収学習させて頂いています。いつか落ち着くとは思いますが現在は知識吸収期間です
練習習慣
再活後の現在はライブ用のレパートリーが11曲あります
ドラマーの場合は自宅に電子ドラムもしくは防音部屋が無いと全体的なトレーニングは難しいのでスタジオに行っての練習が主要になりますが、弦楽器の場合は自宅でも練習できます
現在は仕事場のデスクの横にライブ用のアンプにマーシャルキャビネットを繋いでギターをそばに置いています。いつでもすぐにギターを担いでアンプをONすればすぐに音が鳴る様に。以前はDTM(PC)にギターを繋いで音を出して練習していましたが最近はライブ用セッティングの状態でアンプから鳴らして練習しています。自宅のリビングもほぼ同様な状態にしています
幸いにして爆音を鳴らせる生活環境があるので、時折ライブ時さながらの大音量での練習もしています(その際に色々と気づいてライブ用の音作りを改善することもしばしば)
そして本題です
現況は僅か11曲のライブ用レパートリーではありますが全曲をプレイ1周するのに50分~1時間くらい掛かります
なので練習の1時間というのはあっという間です。1周だけだと物足りないので重点曲などを再度プレイして行きます
ちなみに「1か月弾かない期間があって、すぐにドラムに合わせていきなり弾く」としたら自作曲ではあってもピッキングミスを含め間違えます。特にテンポが激速な箇所は全然ダメです
楽器は身体で覚えているので”間が空いていしまう”と「音を探しながら弾くようなダメなプレイ」になってしまいます
90年代当時、過去曲をTAB譜面に残してこなかったので再活後は「TAB譜」に残して行く癖を付けましたが、しばらく弾いていないと「自作曲なのに必死で自分で耳コピする」ような事態にもなりえます
活動を休止したりライブを数年休んでいた様なバンドによくあるのが「実際の音源とリフが少し変わってたり」、「ギターソロが変わっていたり」しているケース
これはTAB譜面に残してこなかったことも要因で「たとえ自分たちの曲であっても」その後にアレンジ版になってしまう場合もあります
あとはメンバーが変わった場合もそうですね。分かり易いのが例えばYoutubeにもよく挙がるメガデスのトルネードのGソロ。歴代リードギタリストのニュアンスや音階自体も違う完コピでは無いバージョンがあったり
これが決まったコードを掻き鳴らす楽曲であれば問題無いと思いますが特にデスメタル音楽の場合はリフがメインですし、ソロもディミニッシュ等のスケール派生だけでなく手癖やクロマチックも多いのでやはりTAB譜面に残しておかないと再現するのに苦労する場合が考えられます
サブコンシャステラーの楽曲は全て当方が創ってはいますがそれでも練習期間が空くとすぐに弾ける訳ではありません、30年以上前に創った曲を今でも上手く弾けるようになりたくて必死で練習しています
そのくらい音楽の練習には終わりが無いですね。「習慣付け」はずっと続きます
現代のライブ予定
ライブ予定が決まるのが早いです
昔の様に?次月や数か月先のライブが決まるみたいな感じは無く、近年はどんどん早くなっています
これを書いている2025年8月現在、既に複数の来年分の出演が海外遠征含め決まっています
一年先の話が既に決まっているとかが普通になってきています
今年2月のSinisterツアー参加も1年以上前からの話でしたし、今年のツアーも一年くらい前から既にお話を頂いていた公演もあります
ふと思ったのですが
例えば入院レベルの病気をしたりとか、メンバーチェンジのタイミングと重なったとか、そういった未来の想定外アクシデントすら普段から想像しながら先に対策も考えておくのがバンマスの仕事なのかもしれません
バンドは生き物ですしその時にどうなってるかは分かりませんがそれでも完遂させるという
とにかく年々動きが早くなってきていて海外の有名フェスだと一年先の開催分のラインナップが既に発表されてチケットも既に販売開始されているケースも
とにかく目まぐるしいのですが我々もなんとかその時代の流れに追随しています
早く決まることは勿論メリットもありスケジュールが決まっていることで行動予定が立てやすいです
例えば空いた期間にレコーディングをしようとか、その期間を逆算して創作曲を仕上げておこうとか
今後も準備万端で臨んでいきたいですね
もはや存在自体が稀少なのと”志”の強さ
今回は「デスメタルバンドでありながら、かつ、ツアーバンドの存在」について
現実として本当に稀少ですよね
特に日本のデスメタルバンドだと国内のみならず海外も含めてワールドワイドに活動するバンドは数えられる程の希少範囲になると思います
しかも世界的に見ても99%のバンドがバンド収益で生活をしている訳では無く、普段は他に仕事をしているマニアなジャンルです
そこに加えてビジュアルが「長髪のバンド」ともなると更に稀少です(長髪での生活環境を持った人でないと難しいでしょう)
一般企業勤務だと就業規則等で長髪での出勤はなかなか難しいでしょうし、それに加えて平日問わずに移動をしながらライブツアーを行う訳です
もはや「バンドが成立していること自体が奇跡」の様な状況と言っても良いでしょう
我々、幸運にも活動できていますが辿り着くのは本当に難しいです
バンドマン目線の話になってしまいますが、メンバー間の音楽性や性格の相性とか楽器スキルとかそういうのはもはや低次元な話とまでは言いませんが、そういう視界でバンド活動はしていないです、少なくとも我々は
音楽で世界を通じ自由に活動を行いたいかどうかという「志」のみです
なので「経済的自立が出来ていてツアー活動の環境作りが出来るプレイヤー」であるかどうかが志が同じ同胞としての視界になります
実際問題、どんなに音楽が好きだとか、バンドで有名になりたいとか、バンドで売れたいとか思おうが環境が無い時点で音楽センスは無いです。極論を言うと1週間後にヨーロッパで5万人のフェス出演の話が来たとして、ただし「自腹航空費」と「平日移動含め都合を付ける」が出来ますか?という事です
「音楽にぶっ飛んでいる人」はそのチャンスを逃さないですし皆んな肝が据わっています
出来ないなら「下船」するしかないでしょう
本当に音楽活動にアツい人達は次元が全く違います。つまり見ている視界や世界が違いますので、「俺は誰よりも音楽がやりたい」という次元も全然異なる視界です。そういった熱意が1億倍レベルで高い人達との競争を思慮してそこに追随できないならば「下船」するしかありません
多くのメインストリーム系デスメタルバンドはその過程を経ながらメンバーチェンジ(上船/下船)などもありつつ、諸々の環境を搔い潜って這い上がり、やがて最終的にある程度強固な「精鋭メンバー」という構成になっていきます
来日バンドでも、その日はベースが来日できないからツインギターの片割れ側が代わりにベースを弾くとか、欠員を現地でサポートプレイヤーを見つけて敢行するとか、そういうのは本当に凄いと思いますし決して諦めない強い意志を持ったバンドです
あくまでバンド目線になってしまいますが、そういうストーリーを目にするとどこまでも意思や志の強いバンドなんだと思います
「やりくり」とその「志の強さ」に学びがありますし、そういったぶっ飛んだバンドはやはり創作曲も自信に満ち溢れていてそのバンドの「曲自体が強い」です
知名度が有るか無いかだけの構造
後にも先にも「知名度が無い限り何をやっても難しく」なってきています
一時代前はコツコツとライブハウスを廻ったりがありましたが、現代のネット社会では「知名度ありき」
なので「知名度が出たら」ようやくライブをする事(興行成立)が出来るという図式も
逆説的に考えると知名度が無いのにライブをするのは興行不成立なのであくまで自力プロモーション
良曲を創り→ネット上で流して→沢山の人に聴かれて→需要が出てライブ(興行)が成立する
我々の様な市場規模の小さい音楽業界ではかなりハードルが高いです
ですので自主企画だったり、小規模ライブハウスでのマニアの集い的な流れになります
ひょっとしたら今後はバンド結成後、「曲がバズるまでは一切ライブをせず」、バンド活動資金はMVなどでプロモーションし続ける(DECIBELマガジンや音楽ニュース系にどんどん広告を打ち、youtubeもプロモーション広告をし続ける様な)といった手法もありそうですね。MV上でのビジュアルも独特な出で立ちで非の打ちどころが無い所まで突き詰めて考えながら
我々は思考が古いのか、単にライブが好きなので超小規模なバンドながらもライブバンドとして活動していますがもしかしたら上述の様なやり方もあるのかもしれません
なのでSNS上で度々流れてくるような「チケットが売れない」とか「集客が厳しい」という内容は「人気が無い」、「知名度が無い」、「観に行く程では無い」それだけの事になるかと思います
大変非情ですが音楽活動の世界は厳しいと思いますし、だからこそ「音楽活動をガチでやりたいなら活動を続けられる生活環境の整備が全て」なのです
バンドの終活
メガデスが「ラストアルバムリリース」と「フェアウェルツアー」をオフィシャル発表
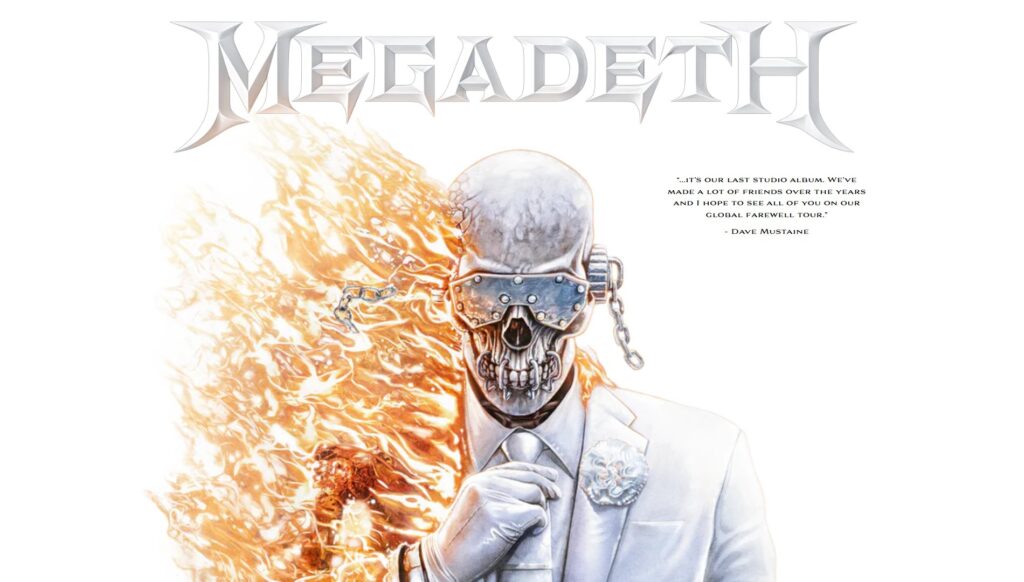
30年以上聴いてきていますがいよいよ1つの時代が終わるのかという感じです
先立ってのスレイヤーに続き今回のメガデスの発表(2025.08.14)
今後、近い将来メタリカもそうなる時期が来るのか
上述の彼らはエクストリームメタルがメインストリームに出た立役者達です
確かに前提としてサバスやベノム等、彼らにとっても更なる源流はあれどもこれだけ商業的にもメディア的にもエクストリームメタルが世界的に知れ渡ることになった彼らの貢献は計り知れないと思います
80年代後半から90年代にかけて成立したスラッシュメタル、デスメタル、グラインドコア、その後のテクニカルデスメタル、ブルータルデスメタル、更にその後2000年代のデスコアやスラミングデス等、これらのジャンルは元をただせば彼らからの影響下、歴史下から出て来たといっても過言では無いでしょう
メガデスと言えば1990年当時「インテレクチュアルスラッシュ」というワードと共に「ラストインピース」が世界中で大絶賛されました(このCDは150万枚以上売れたそうです)
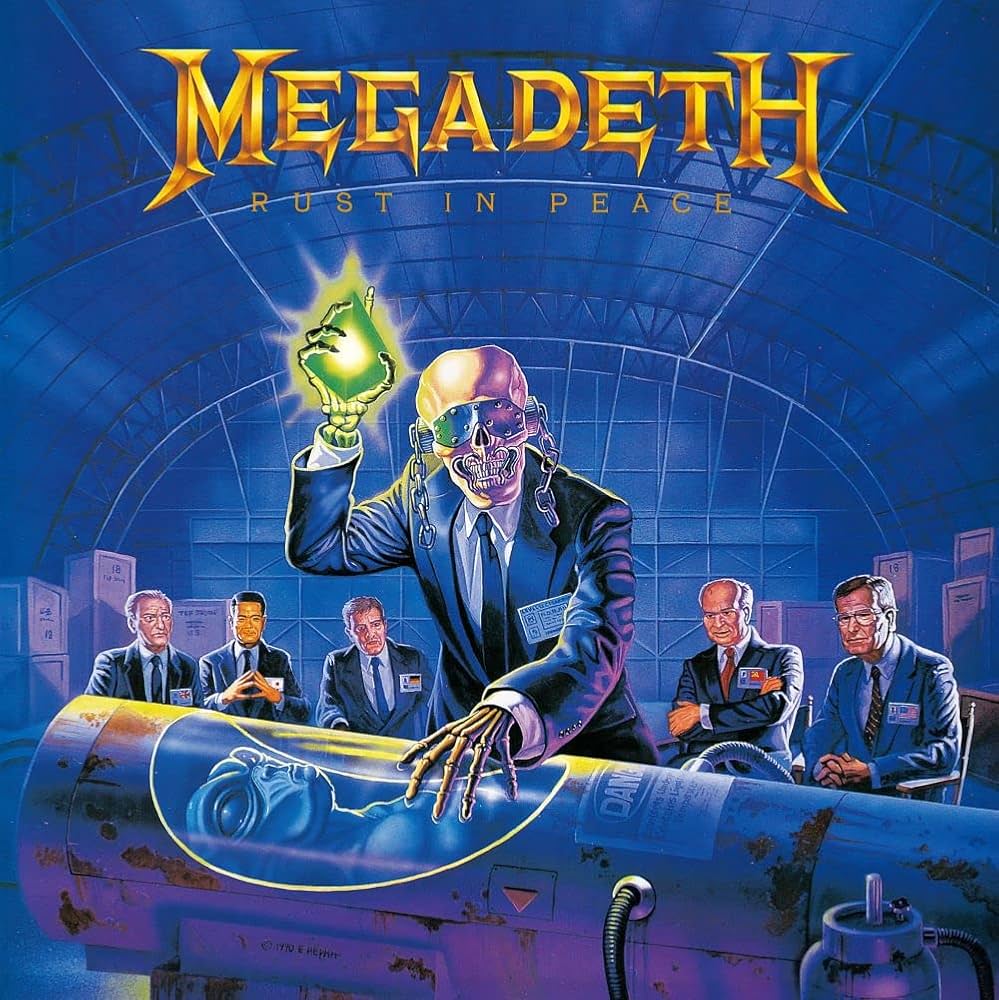
(↑エド・レプカ氏のアートワークとして世界的にも有名なデザインですね)
当方もリリース当時、琴線に触れまくり毎日のように聞いて沢山コピーをし学生時代だったので文化祭でメガデスコピバンも演っていました。今でもマスターピースアルバムの1つ。息遣いやピックアタックが分かるほどと言っても過言ではない程に細かく聞き込んで身体に染みついています。当時1990年代のメタルギタープレイヤーはこぞってコピーしたりコピバンをしていたのでは?
遡ると大阪厚生年金会館で1991年に初めて生メガデスを観に行っていますね、ラストインピースツアーの日本公演でマーティフリードマン在籍時のメガデス黄金期
思い返すとあのアルバムで「エクストリームメタルの作曲手法が全て出た」のだと思わせる程の完成度だと感じます。それほどバンマスのデイヴムステインはギター創作曲の天才の1人だと思います
メガデスにブラストビートはありませんがあのアルバムは音階メロディやリフ展開を含め繰り返してしまいますが「トータルでエクストリームメタルが完成されたタイミングの時代」だと思います
スラッシュメタルが好きなギタープレイヤーであればきっとそのギターリフの作り方や展開の秀逸さが分かるかもしれません
そんな彼らがラストアルバムとフェアウェルツアーの発表
メガデスはこれからバンドの終活に入るのだと受け取っていますが、みんながいつか来るその時期
我々も逆算しながら色々と考えてしまう事もありますが悔いの無い様に自由に活動して行きたいですね
我々今年はツアーが入っていますが来年はアルバムレコーディングを想定していて創作曲を温めています。(不器用なのでツアー中はバタバタしがち。腰を落ち着けて期間を組んでじっくり創りたいです)
プロバンド活動のステップ
バンドの海外ツアー活動におけるピラミッドは以下の様な感じです
①全て自費
↓
②航空費は自費、その他(宿泊、食事、現地移動費)はエージェント負担
↓
③航空費も宿泊費も食事も現地移動費もエージェント負担、ただしギャラは無し
↓
④航空費も宿泊費も食事も現地移動費もエージェント負担、かつ、ギャラも有り
ChatGPT調べでは「世界中のバンドの90%以上」が①もしくは②だそうです
ちなみに③まで行けると「いわゆる有名で凄いバンド」だと思います
④は世の中的にはフルタイム系バンドと捉えられていて世界的知名度のあるバンドの領域ですね
つまり「航空費負担の有無」がバンド規模としての1つの「境目」になっています
この境目は「知名度が有るか無いか」「集客力が有るか無いか」が大きな割合を占めます
我々は超小規模バンドですので基本が②で稀に有難くも③という感じです
なので海外に出て行ってギャラが頂けるなんてことはまず無いですし「空港送迎や宿泊ホテルや食事、現地内移動、バックライン、物販スペース提供」というのが基本になってきます
※バックライン(Backline)・・・会場での楽器用機材(ドラムセットやギターやベースのアンプキャビネット等)
招聘者(会社)にはいつもながら大変感謝しかないです
これがもしも数週間のヨーロッパツアーになってくるとツアーバス(寝台バス)の費用が加算され、更にバンド側で100万円前後を負担(レンタル寝台バス&運転手)するレベルになります
ですので物販でメチャクチャ頑張って出来るだけマイナスを補うという感じです
このブログでも度々書いてきていますが野心を持っていて、海外でもどんどんツアー活動を進めていくならば結成段階の時点で「バンドは金持ちの遊び」レベルを想定して潤沢な資金を貯めておく必要があります
なぜならば①→②→③→④のステップがあるからです
結果的にそこで篩に掛かり①と②が全体の90%以上を占めることになります
才能や技術やビジュアルなどは有って当たり前の前提
その上でもしも世界的な活動を行いたいならば辿り着くのに何年掛かるか分からない①→②→③のステップを踏む潤沢資金の用意が無いとスタート地点にすら立てないです
この環境作りも音楽センス
厳しい話になりますが極端に言うと「バンドマンを夢見て普段が4畳半アルバイトで繋ぎ、生活がカツカツ」だとしたらアメリカツアーは現実的ではないでしょう。そもそもビザ取得が高額なのでビザ取得にすら辿り着けないので。これらは曲が良いとか悪いとか、楽器が巧いとか以前の問題になります
具体的なバンド名を挙げることは出来ませんが世界的に名の通った有名デスメタルバンドでも③というバンドが多いのにビックリする位です。「物販の売り上げのみが彼らの収入」。これで世界ツアーをしているという。確かに、経費ゼロで世界中を廻れるので物販収入が最終利益になるのでマイナスは無いですからね。ツアーが終われば、ツアーの無い期間に日当仕事をしていたりもよく聞きます。
みんな本当に好き過ぎるんです、デスメタルが
真鍮サスティンブロック交換はオススメ
楽器店へギターメンテナンスに出すタイミングで今回、真鍮材質のサスティンブロックを付けて頂きました

工場出荷時のブロックは亜鉛合金やスチール材質ですが今回ブラス(真鍮32mm)材質に変更。
(超高級ギター、いわゆる上位モデルだと工場出荷時から真鍮やタングステン材質のブロックが付いている事も)
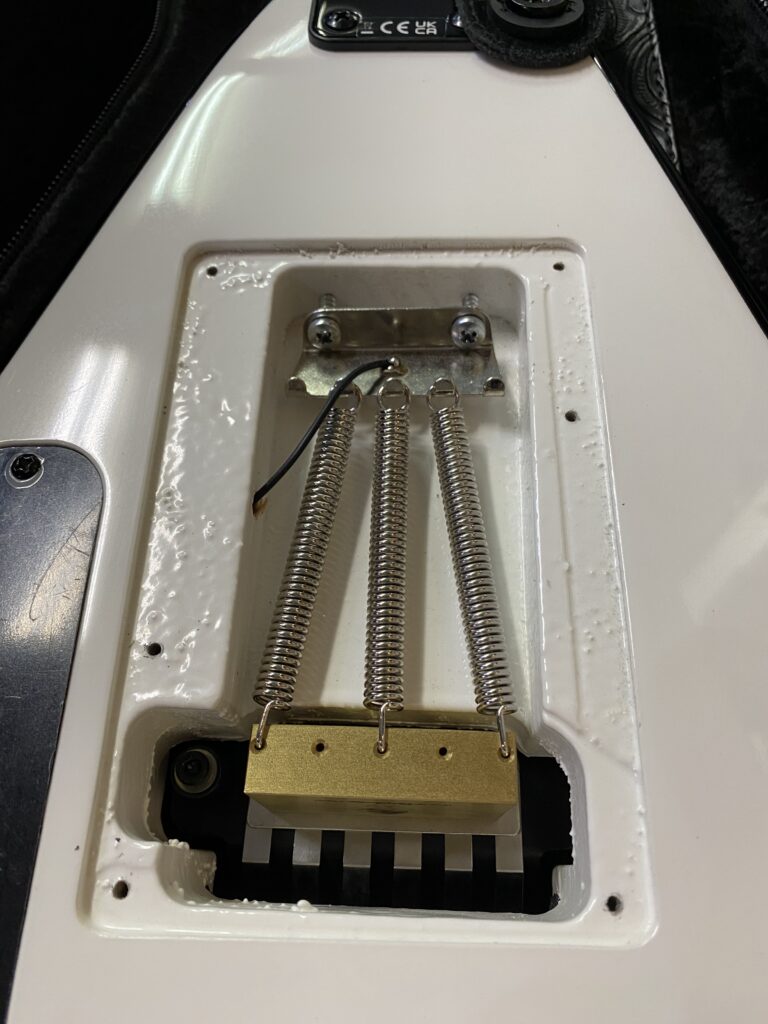
音が一気に変わりました
ミドルが前に出る感じで「音の鳴り」「音の輪郭」がかなり良いです
これだけ効果があるなら所有ギターは全てサスティンブロックをブラス(真鍮)材質に交換して行こうと思います
下手にエフェクターを色々と探すよりもサスティンブロック交換の方がそもそもの「本体の鳴り」が良くなるので効果抜群です
これからギターを始める、または購入する方は「自分の好きな色」や「自分の好きな形状」で筐体を選ぶことをお勧めします
あとから音が気になることがあっても電気ギターですから「ピックアップ交換」と「サスティンブロック」を交換すればどんなギターでも大丈夫かもしれません
自身が好きな形のギターは練習モチベーションアップにも繋がります
(現在使用中のピックアップはこちらBlack Winter↓)

当方のギターへの要求は前提として「とにかく壊れ難くて頑丈」ですがあとは上記2点の交換でOKかもです
この「真鍮サスティンブロック32mmフロイドローズ純正」はコロナ禍以前は3500円でしたがコロナ禍後の今回は6600円でしたので楽器関係も物価高騰していますね

※定期メンテナンスに出す際はクリーニング、弦高調整(ネック反り確認調整)、オクターブチューニング、弦交換
※使用弦はエリクサーの52で約1900円、セットアップ(作業)費用は6,050円(普段は自身で弦交換しますがメンテ依頼は年数回なので折角ですし新弦交換しています)

※使用ピックはジャズ3のXL(Ultex素材の1.38mm)に落ち着きました。XLタイプなのでノーマルよりも1回り大きいサイズです。太い弦を使用していることもあるのと我々の曲は速弾きで低音弦をひたすら刻む様なリフも多いので演奏中に指汗で滑ってきたり、位置がズレて来たりするのを防ぐのにこのピックに行き着きました

ステージパス/ゲストパス
◆ステージパス・・・ステージ裏やステージ上に立ち入ることが許可される無料パス。つまり出演者、設営/照明を行うスタッフ向け。一般来場者に発行されることは一切無い無料パス
◆ゲストパス・・・関係者招待の為のパス。チケットが無くても会場への入場が出来る無料パス
上記はchatGPTより抜粋
ちなみに我々は第三者へパスを出すことは無いです
そもそもアングラでゲスト系パスを出していたら箱代/経費すら厳しいシーンですし、むしろ購入をお願いする立場ですので、それでもパスを申請をするとしたら「責任を持つことが前提」
過去にカメラマンさんへ撮影仕事の依頼でパス申請をしたことがあります
公演時はカメラマンさん自身、汗びっしょりでシャッターチャンスに集中されていますし楽しめるどころでは無く、もの凄く忙しく駆けずり回られています。なので公演後に仮に我々がそのカメラマンさんに「今日の演奏どうでしたか?」と伺ったとしても「全く聴いてないです、撮影に必死だったので」がデフォルトでしょうし、公演後は「上手く撮れましたか?」という会話になります
もしも知り合いや友達を呼ぶならば、なおさらチケットの購入での入場をお願いしますし来場くださった暁には直接御礼/感謝を述べに行くのが我々のこれまでというかそれが自然だと思っています。
ちなみに元メンバーも普通にチケット購入して見に来てくださっています
結論的には「パスは出演者以外は出す意味が無い」、「そうしないとチケット購入者に不公平」と思っている派です
これがもしも大規模で有名なバンドならば「ローディーが居る」、「専属PAが居る」、「専属スタイリストが居る」、「舞台装飾スタッフが居る」等で必要に迫られることもあるのでしょうが我々の様な基本が100人前後のライブハウス規模ではなかなかの希少部類だと思います
ファンの方々がチケットを購入し足を運んで観に来て下さるのに「第三者にパスを出してタダで観れるようにする手筈」は我々にはあり得ないです
ファンに対してあまりにも失礼過ぎるというか、それならば「その公演はフリーライブ」にしないと公平では無い感じがします
あとは出演者側の立場としても第三者が楽屋を含めて自由に出入りされるのは怖いです。例えば盗難、盗撮など
更にはライブ当日、対バン同士(出演者同志)で顔を合わせ「本日は宜しくお願いします」的な挨拶をしその際にバンド名と顔を一致させて頂くので、関係者ではない第三者が幕内に存在するのは怖いというか背景紹介が無いと不安があります
もっと付け加えるならば本番中のステージ袖に主催者/スタッフ/出演者以外の「何者か分からない人」が居たら違和感があり気になると気が散ります
例えばですが万が一その人がハンザイシャで突然ナイフを出してきたらどうしようとか、変質者が紛れ込んで来たのではないかとか
今回の騒ぎはSNS上で矢継ぎ早に流れて来て知った内容ですし、部外者ではありますがむしろこういったことが表面化されたことで「ライブハウスの安全面」についても良い方向へ向かうことを願いたいですね
あくまでこれらは全て個人の感想ですが各種各様の興行が有ると思いますので「パスについては興行主の規則に従う」ことになります
(余談)以前に海外のバンドさんが本番直前、楽屋で「我々はこれから集中に入る」ので「すみませんが、我々だけの時間を過ごさせて下さい」という律儀なバンドさんもいらっしゃいました(共用楽屋だったので。これから出番のあるバンドが主演者ですから勿論速やかに楽屋から離室させて頂きました。直前に集中モードに入るのは重要な時間ですからね。当方も本番直前は脳内集中モードに入りたいので1人で居たいか、もしくはメンバーとだけ居たいです)
(追伸)この騒ぎはSNS上で見ている限り「敵味方化」している様相に感じますがそうでは無いんですよね。何故か「思考が違う」=「その人を全否定」という構図がシンドイですね。叩き切らないと気が済まないというか。双方が建設的に問題解決と納得をしていけば本来は倍々ゲームでシーン人口はもっと活性化しそうですが…
島国妄想と現実の距離感
島国日本
国内だけで使われる日本語という使用言語も相まってか、外の世界(外国)に妄想を抱きやすい傾向にあるのではというお話です
海外バンドのフェス出演等の動画を観て「世界は凄い」「規模が違う」なんなら「海外のバンドは国内のバンドよりも優れていて日本はショボい」と勘違いをされがちな可能性もありそうです
確かに、規模感でいうと日本のデスメタルバンドより集客数が桁違いなバンドも存在します
ですが基本的にはどの国もさほど変わらないと思います
あるとすれば人口規模の違いによる母数差であったり先進国/発展途上国といった文化の違いによる音楽性の差でしょうか
例えばテクニカルデスメタルバンドとして特に日本でも崇められていると思われる2バンド
どうでしょう、箱のサイズやファンの数(集客数)も日本のライブハウス的な感じがしませんか?
確かに、有名であったりコネがあるならば大規模フェスに出演できるのでそのクローズアップされた動画を観て「うわー、凄いバンドだ」と感じると思います。つまりは「大規模なイベントに出演しているから凄い」というある意味で洗脳の様なところもあるかと思います。逆に言うとバンドはそれを逆手に利用/活用した方が箔が付く?と言いますか、もはや音楽性以上に聴く前から「このバンドは凄いんだ」という洗脳じみたプロモーションが出来るので本質とは掛け離れていくかもですが、バンドマンにとっては大規模イベントは出演した方が良い結果に結びつく可能性が高いかもしれません
ですが普段のライブに関してはやはり日本と同じような規模感であることが上記の動画等から分かると思います
ですからデスメタルバンドの来日公演においても普段我々が出演させて頂いている様な規模のライブハウスでの来日公演となる訳です
「有名だから」、「凄いから」であっても、だからといって来日公演はアリーナクラスでの開催とかは無いです、やはり同規模なライブハウスでの公演となります
この辺りはどうしても敗戦国&島国なので「外国に憧れ的な妄想」をしやすい可能性も含め例に挙げさせて頂きました
2バンドとも大好なバンドで将来チャンスがあれば共演やお話をさせて頂きたいですね
近年海外に出て行ってみて感じたことは「国産デスメタルバンド」は自信を持ってどんどん外の世界を見て欲しいです。劣等感不要ですし、全く遜色無いですし、むしろ「日本人独特の勤勉さ」はスキル、創作能力、その他もろもろを含め発揮できると思います
バスドラム『ロゴカバー』
バンドマン向け便利グッズ(特にドラマー)の紹介です

バスドラムに付けるロゴカバーです
デザイン部は伸縮生地で、廻りはゴム生地になっていて「靴下を履く様に」サッと取り付けることができます
依頼先は「DrumSknz社」(カナダ/トロント)でオーダーメイドになります
海外で一緒にツアーをさせて頂いたSinisterがこの商品を使っていて我々もオーダーしました
Youtubeなどでも海外のバンドのライブやフェス等でこの商品を見ることが多いです
なお、DrumSknz社長のZoeさんはエンジニア出身のドラマーですのでこのバスドラカバーは痒いところに手が届くといったところでしょう
お値段は13000円+3300円(送料)+受け取り時に1200円(消費税)の合計17500円でした
オーダーの仕方はHPからオンライン上で、
①デザイン添付(サイズ選択含)
②マイク穴を開けるか否か選択
③送り先を記入
④クレカ払い
という5分くらいでオーダーできるシンプルな流れです
オーダー後、翌々日にファイナルチェック用完成イメージ図がZOEさんからメール連絡。承諾後、10日くらいで受け取れました。対応も早くこのカバーにもかなり満足しています。Zoeさんに感謝です
価格についてはバスドラにサッと貼れるというだけで17500円もするのかと思うかもしれませんが、なにしろオーダーメイドの「一品もの」ですからね
紛失や破れる様な事がなければずっと使えそうですし、この商品自体が毎日バカスカ売れる物でも無いでしょうから需給バランスを考えるとこのくらいは妥当だと思います
このバスドラ・ロゴカバー、ライブ上で是非チェックしてみて下さい!

「こんなに頑張ってるのに」は承認欲求と俯瞰力足らずの可能性
某メジャー系音楽家による「作り手の気持ちを想像して欲しい」という内容が賛否両論ニュースに
世の中は良い人ばかりでは無いですからね
悪意をもって攻撃する人もいますし意見が違うだけで全否定する人もいます
そもそも音楽は無くても生きていける娯楽
創り手にとって「何か(反応)を期待する」のはもちろん自然な事ですが達観した方が良いでしょう
繰り返しますが世の中には様々な思考を持った人がいます
「なぜわかってくれないんだ」と世直し大名をしたところで世界人口82億ですから無理でしょう
デスメタルをやってみると分かりますがもはや市場が小さ過ぎてそういう思考にまで行き着かないです
淡々と実現したいことをやってくだけです
(例/国内のコアファンとの交流、海外ツアー、リスペクトバンドとの共演等)
何かを期待してそれが大衆に響くかどうかなんて「相手がいる」事が前提ですので当事者としては淡々と自身が実現したいことを一歩一歩確実にやっていくだけだと思います
どんなに自信のある創作をしてもどうにもならない事もあるでしょうし、その逆もあるでしょうし
そういった面から見てもデスメタル系の長年大御所バンドはリスペクトしています
どこまでやっても響く範囲が限られる中で長く続けている訳ですから
きっとそういうリスペクトしている人物は「達観」している部分も大いにあるのではと思います
(余談)有名デスメタルバンドであってもメンバーの中にはフルタイムでの企業勤務の人も多いです。なのでその国の長期休暇期間(日本で言うところのゴールデンウイークやお盆休み)を使ってツアーするバンドも多く日程が重なることも理解できますし活動工夫していますね
2025新作EP『Devoid of Seraphim』歌詞の日本語対訳
1.『Coated in Lies』(真実は隠され嘘で塗り固められる)
夜明け
空虚
中傷社会
陥れる
嘘で塗り固められ
偏向主体に皆を操る
弱気をくじき叩きのめす
揚げ足取り
突き落とす
土は土に、灰は灰に、塵は塵に
夜明け
虚構
歪んだ栄誉
滅亡
疲弊
偏向と冒涜
無視を決め込む
地獄に落とす為の罠を仕掛ける
無垢は無知
正義は嵌められる
足の引っ張り合い
突き落とす
社会の破綻
土は土に、灰は灰に、塵は塵に
2.『Devoid of Seraphim』(熾天使は不在)
熾天使は不在
逃げ惑おうが
手を差し伸べる奴は居ない
弱者は常に突き落とされる
苦しみは負け犬
勝者はほくそ笑みながら
弱者を更に地獄へ突き落とす
熾天使の不在
手遅れ
ノアの方舟を信ずる者
(助かると)信じて乗った船は木っ端微塵に
それをあざ笑う者
熾天使は不在
光と影
醜い争い
人間世界との繋がりを絶ち
醜い争いをゆっくり眺めながら
チェックメイト予想のお遊びに高じるのさ
この歌詞を創ったのはコロナ禍が開けるタイミングで心情や思考を歌詞にしました
リリース音源は英詩ですが英語ネイティヴ話者では無いのでネイティヴチェックを何度も行い英歌詞化しています
歌詞を創る時は思い浮かんだ内容(殆どが皮肉や比喩ですが)を先ず日本語で綴っていきます
ライブの大阪飛ばし加速問題
表題が先日のニュースになっていました
実際問題、東京一極集中の現代において例えばメタルイベントを開催したとして
東京で100人=大阪30人の集客イメージです
仮に在住人口を中心地で比較するならば「東京23区/約1000万人」、「大阪市/約280万人」なので大体合ってますね
つまり集客数と経費が合わないから更に飛ばされるという悪循環
大阪でアングラ系ライブハウスを借りる場合のイメージですが
①50-80人規模ライブハウスを借りるのに約10万円
②100-200人規模のライブハウスを借りるのに約20万円
分かり易く示すとザックリこのような印象です
となると前売り3500円、当日4000円でチケット販売をしたとしても集客が30人だと
①は全共演バンドが交通費自腹、演奏ギャラも無償で経費トントン
②は全共演バンドが交通費自腹、演奏ギャラ無償でも約10万円の赤字です
たとえ関東や九州からのバンドであっても「交通費無し」の「無償出演」であっても上記の様に開催構造自体が難しいです
こう考えるとそもそもアングラなデスメタルのライブを開催すること自体に無理がありますよね
ましてや関東や九州から遠征しての大阪ライブとなると出演者は交通費や宿泊費用を含め基本は赤字ですので更に「大阪飛ばし」(大阪はやめておこう)の悪循環。集客が少なければその分のマーチだって販売数の分母が少ないのでニッチモサッチモ行きません
更には万一これが平日開催だと更にその半分以下ですからやはり開催構造的に難しいです
なのでビッグネームのデスメタルバンド来日公演ですら東京のみというケースが増えています
来日バンドが東京に引き続き大阪でも公演をするとなると移動の新幹線費用も掛かりますし追加ホテル代もありますし、更にキツイのが海外航空チケットも「行き」と「帰り」で発着が違う片道ずつの航空券になるので更に割高になるという
考えれば考える程に大阪でライブを行うことが難しい構造であることが分かります
まだ名古屋の方が東京とは近距離ですし可能性はありそうです
極論的には、もはや大阪開催はチケット代を東京の2倍とかにしないと難しいのかもしれませんが、そうなると今度は益々集客が難しいという”がんじがらめ”
解決方法に辿り着けていないですがやはり大阪は「地元のシーン」を作らない限り(盛り上がらない限り)難しいと思います
ただそもそも大阪のバンドは数が少ないのと、新しいバンドも「最初から諦め感」というか東京などの外へ出ていく傾向も
この事についてChatGptに尋ねてみたのですが、大阪で30人集客できる日本のデスメタルバンドはほぼ存在しないそうです
大阪出身の身としては葛藤というか、やればやるほど枯渇(毎回大幅赤字)するならやらない方がマシという思考になりがちで解決方法を見い出すハードルが非常に高いです。ライブバンドマンはやれるならやりたいですからね
足元のエフェクターをコンセント不要にする(忘備録)
このブログ内では機材更新の話をよくしています
そして今回はステージ上の「足元をスッキリさせたい」を追求しました
少し前に「2025年度分の機材更新はこれにて終了」なんて書たいた所ではありますが
これまで1種類のギターサウンドで全曲演奏してきましたが、最近は新曲を含め徐々にギターソロなどで空間系エフェクターを切り替えて使う場面が出てきました
ギターソロ等のタイミングで切り替える「足元のペダルエフェクターボード」
電源を供給するのに毎回コンセントを探す必要があり場所によっは延長ケーブルが必要だったりします
そこで足元用に「独立した供給電源」で対応出来ないかを調べてみました(リハーサル時の接続の手間時間や本番転換時間の更なる短縮も)
結果「モバイルバッテリー」を使ってエフェクター用パワーサプライに電源供給できればペダルボードを独立した状態で置けるということに気づきました
必要部材は2つ(下記)
①モバイルバッテリー(携帯充電用バッテリー)
②エフェクター用のパワーサプライに繋ぐ電圧変換プラグ(Sound Design Lab.)
【12V出力】PD-12V Type-C センターマイナス ケーブル長 30cm – Sound Design Lab. Store – BOOTH
これで足元は独立したペダルボードを置くだけでエフェクターをONすることが出来ます
忘備録としても残しておこうと思い今回綴りました
※注意点としては飛行機搭乗の際にモバイルバッテリーは「手荷物」(預け荷物不可)
過去のブログ内容に機材一式についてはその接続方法を含め詳細に書いていますので今回は省略させて頂きます(使用パワーアンプやプリアンプ、エフェクターやスピーカーを2発鳴らす手法etc.)
完全な自己満足でしかないのですが機材に関してはずっとハマり続けています
デスメタル・グラインドコアのボーカルの発声分析
以前に共演させて頂いたRipped to shreds&Houkago Grind TimeのバンマスであるAndrewさんのYoutubeチャンネル
特に今回の内容は非常に興味深く拝見↓
各バンドのデス声ボーカル担当がどのようにしてデス声を出しているのかをインタビューされています
更にはインタビュー後にAndrewさん自身が各人の手法で検証。実際に再現をトライし個別分析や感想まで述べられており非常に素晴らしい内容になっています
興味深いのがインタビューを拝見するとピッチシフター、フランジャー、ワーミー等のエフェクターを使うというケースも多いと気づかされました
当方は90年代初期にキャリアスタートしたデス声ですが当時は発声知識も情報も無く、自然に行き着いた結果の発声の仕方で現在に至るまで「生声」です
遡るとサブコン自体は1994年結成ですが、それ以前は大学入学後すぐに軽音に入ってスレイヤー、セパルトゥラ等のカバーバンド(Vo&G)をしていましたので更に古くなります
何もかもが手探りな90年代初期なのでどうやって自身がデス声に行き着いたのかは当時は考えたことも無かったので成すがまま、ソロ楽器として低音を出せるよう感覚的にやっていました
Youtube内の各人インタビューを拝見していて声の出し方が自身と「最も近いな」と思ったのはExumedのROSSさんの内容(本人説明/8:40頃~、分析と解説12:12~)です
Exumedは失礼ながら存じ上げずで彼らの音源を後追いで聴いてみましたがとてもカッコいいバンドですね、これからガッツリハマりそうです
90年初期当時はスラッシュ/デスメタルクロスーバー時代。何も分からないところからのボーカルキャリアスタートしたので(当初はダミ声と言ってました)今回改めて自身がどうやってデス声を出しているのかを確認してみました
言語化するならばExumedのRossさんの仰る「舌を丸めてそれを上に付けている」イメージです
どういう過程で自身がこのような手法に辿り着いての発声に至ったのかは当時ライブを沢山やって自然に行き着いた結果なので説明のしようがありませんが、自身にはそれが合っていたのでしょう
今後、デス系ボーカルを目指す方には参考になるかと思いましたので紹介してみました
※ちなみにAndrewさんは台湾系アメリカ人(英語、中国語、閩南語のネイティヴ話者)でIT企業の超クレバーでマルチ才能者。もはや何でも出来てしまう様な感じの方なんだろうなと思います、リスペクト人です
「好きな音楽」と「メンバー人格」の分離可否
「音楽性と人格を切り離せるか」です
これも良く出てくる賛否両論系のお話だと思います
2024年12月、SADUSはオリジナルメンバーのドラマーが起こした事件後に即解雇
(補足/ドラマーによる人工透析中パートナーへの暴力事件。日々の看病疲れで精神的に全てが嫌になり魔が差したのかもしれませんが許されるものではありません)
即解雇ということでバンドとしての責任は果たしているとは言え活動休止のままです
ファンがどう感じるかは様々で「過去の音源に遡ってまで嫌悪感」(音楽性も全否定)になるのかどうか
SADUSの時代毎の創作者については
「90年代の創作曲」はバンマスのVo&Gであるトラヴィスさんメインで「近年の創作曲」はバンマスのトラヴィスさんと解雇されたドラマーの共作
人によっては「90年代の過去曲はOK」、「近年の曲は嫌悪感」という人もいるでしょうし、この事件によって「全部がダメだ」という人も居るでしょうし、逆に音楽性と人格を完全に切り分けている人は事件有無に関わらず「全く問題無い」という人も居るでしょう
この辺は各人各様なので難しいところですが少なからず「離れてしまうファンも居る」ということに
当方はどちらかと言うと人格までは探らない様に適度な距離感を保っておく方が好きですね
「知らない」、「知ろうともしない」方が人生経験上、上手く行く事も多いと思っています
この事件はSNS上でニュースで流れてきてそのタイミングで目に付いてしまった内容ですが、私的には音楽に関しては「ビジュアル」と「音楽性」の嗜好相性です。なのでSADUSが創る音楽は好きなままでいます
そういえばDEICIDEって来日したことがありませんが(アジア自体に来た事が無い)ビザが取れないのかもしれません。過去の犯罪歴だったり歌詞内容だったり。実際、ビザを取る前の政府許可の為に歌詞を提出する国もありますからね。当方は全く悪魔主義でも何でもありませんが彼らの創作音楽(音階とリズム)が大好きです。そういう意味では人格は無視して音楽だけを聴いている方だと思います
もちろん人格まで素晴らしいなら「より好きなる」は自然な事ですがこれらはスポーツ選手でも何でも同じでしょう(すべてが素晴らしいという人は聖人です)
話を戻しますがSADUSのバンマスにとっては辛いですね。ようやく近年Nuclear Blastと契約し新譜をリリースしたと思った矢先の事件。結果としてレーベルとも即契約終了。更にはObituary等とのツアーも途中でキャンセルという悲惨さ。バンマスは精神的にもどん底だと思います
そういう意味でも「全メンバー」が健康的に成長していかないと積み上げた物が一瞬で奈落の底に落ちることも起き得るということでしょう
バンマスの心情については想像を絶しますしこの事件で他メンバーも居なくなったそう(参加しない)ですのでトバッチリとは言え、どうやって立て直すのだろうと。もはや想像出来ないです
メンバー間で「バンドブランド(イメージ)を汚す行為はあってはならない」と話し合い、予防を図る事も得策でしょう。ですが個人の生活時間帯にまで入り込むのは無理ですから最終的にはメンバー人格(人間性)の見極めも含めバンド活動を行うことになるかもしれませんね
付随して「バンド(やメンバー)が発信するSNSの内容」について
波風を立てずに「無機質に淡々と」ライブやリリース情報の発信だけをしていた方が無難なんですよね
ただ「無機質で無難な内容」は刺さるトゲが無いのでアルゴリズム含め注目度は下がるでしょう
ですが、末永く安定的に活動をするならその方がやはり安全かもしれません
なぜならば人間的な感情表現を発信すると「ポジティブに捉える人」と「ネガティブに捉える人」に分かれるからです
せっかく一生懸命頑張って自信に満ちた創作をしても感情表現をしたSNS発信の影響により、ネガティブに捉えた人からは最初から否定されたり、そもそも聴いていただく機会すら失う懸念もあります
アーティストのSNS発信に関する内容は非常にセンシティブで難しい時代になってきていると思われます
Subconscious Terrorはライブバンド
表題ですが結論としては「我々はライブ活動プレイヤーによる集団」
どういう事かというと我々はライブバンドなので「ツアーに出れるメンバー」の集団
ですので演奏技術に優れていようが引きこもりや人前では緊張して上手く行かないとか、遅刻が多いとか返信が無いとか連絡が途絶えるとかはもはや社会生活を含めライブバンドの様な少数集団活動は更に無理でしょう
加えて「会場にすら辿り着けない」程に経済生活環境が困窮しているプレイヤーだと技術うんぬん以前にバンド活動をすること自体が難しいと思います。やはり普段の生活上で問題を抱えている可能性がありますのでそもそもバンドライブ活動は難しいでしょう。環境が整えられてこそのライブバンド活動
いつもこのブログで書き続けていますが「音楽生活環境を整えられるプレイヤー」>>>>>「楽器技術」です
楽器の技術があっても引きこもり(生活がままならない)ならばツアーは出来ませんので、その場合は音源リリースのみの活動になると思います(近年、このタイプのバンドも多い)
生活環境整備がとにかく重要です
デスメタルで飯を食う訳では無いですから「自由な生活環境」の整備が出来た人しか「末永いツアー活動」は出来ないと思います
我々は現在、最強メンバーかもしれません
Vo&G/会社経営(個人裁量)
Ba/会社経営(個人裁量)
Dr/ツアーの為の都合取得がし易い環境下
(2025年6月現在)
そういえば近年、大阪のエクストリームシーンが沈黙しています
実際、大阪は「ツアーで飛ばされるエリア」にまで落ち込んでいます
我々の様なアングラシーンは尚更です
将来は地元大阪に貢献して行くべく、我々が90年代にやっていた様な主催イベントの企画も視野に入れていきたいと思います
90年代当時、我々は難波ロケッツ(現ホーリーマウンテン)でマンスリー企画していました
関東圏から中四国、九州まで活発なバンドを招聘していました
流石に毎月の開催はシンドイので「年数回」レベルで企画ができればと考えています
継続が重要だと思うので「無理の無い」(負担軽減の工夫ができる)イベントです
現況、大阪エリアでデスメタル系の定期イベントは殆ど無いと思うので最初はシンドイかも知れませんが地元アングラシーン再興の1つに寄与できればと考えています
ハードルは高いですがトライしてみたいですね
Craig Petersさん(Deeds of Flesh)の「曲を作る際のアイテム動画」
2019年再活以降の「サブコンシャステラーの曲が出来るまで」を簡潔に綴ると
①DAWにギターリフを録音し→構成を練り→ドラムを仮打ち
↓
②歌詞とボーカルを載せて曲全体が分かるプリプロ音源を作る
↓
③その後Guitar Proソフトでタブ譜を作り弦楽器メンバーへ渡す(ドラマーには「仮打ちVer.」を清書してもらう)
↓
④全員で仮録(デモ作り)をしてOKならば
↓
⑤本番レコーディング
ザックリですがこのような感じです
そして表題
最近知ったのですがDeeds of FleshのコンポーザーであるCraigさんのYoutubeチャンネル
コンポーザーにとって重要なことを多々UPされていて、最近しらみつぶしに繰り返し見ています
彼らの作曲手法や作曲時の機材の使い方が細かく説明されています
動画内でCraigさんも仰っていますが当方も含め創作時のラフはブラックボックスというか、
当方もそうですが、これらはやはり「独学要素」が多いのです
その節々に関する手法を彼は動画で説明しています
曲のアイデアに関してはあくまで人それぞれにはなりますが、プリプロ時の機材の使い方については彼から学ぶことが沢山あります
将来お会いできることが叶うならば沢山質問してみたい人物の1人ですね
日本に海外バンドを招聘する方法(興行ビザ)
どこの国から来日公演するかによって異なりますが、結論から書くと海外バンドが来日の為の興行ビザ取得に掛かる費用はバンドメンバー1人当たり約3千円(我々が海外に行く際に取得する興行ビザよりも、外国人による来日興行ビザの方が安いです)
具体的には下記4点を記入し公演会場管轄の入管で申請
✅ ①在留資格認定証明書(COE)交付申請 /0円(入管への申請自体無料)
✅ ②ビザ申請料(海外の日本大使館)/約3,000円(在住国によって異なりますが大体この位)
✅ ③書類の郵送代 /1,000〜2,000円程度(入管とのやりとりやCOE郵送時の送料)
✅ ④書類の翻訳(が必要な場合)/0円(ChatGptを使えば無料/依頼すると費用発生)
以下は①~④までの「申請フォーム」リンクです
①在留資格認定証明書交付申請書(COE申請書)
• 用途:来日するバンドメンバーの在留資格を認定するための申請書
• PDF形式: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004029.pdf?utm_source=chatgpt.com
• Excel形式: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/jlec/tjlec/enrollment/__icsFiles/afieldfile/2024/01/22/immigration_form_excel.xlsx?utm_source=chatgpt.com
• 備考:申請書はA4サイズで印刷
②招へい理由書
• 用途:日本側の招聘者が外国人を招待する目的や経緯を説明する書類
• PDF形式: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472928.pdf?utm_source=chatgpt.com
• 記入例:招へい理由書の書き方は以下サイト参考
• https://tanki-visa.com/invitation-friend/
③滞在予定表
• 用途:来日するバンドメンバーの滞在中のスケジュールを示す書類
• 滞在予定表のテンプレートは以下のサイトから
• https://meguro-law.jp/templates/templates01/
④身元保証書
• 用途:日本側の保証人が、来日する外国人の滞在中の責任を負うことを示す書類
• 身元保証書のテンプレートは以下のサイトから
• https://meguro-law.jp/templates/templates01/
留意点としては「日本語で作成」「署名・捺印:招へい理由書や身元保証書には招聘者の自筆の署名と捺印」「パスポートと一致するアルファベット表記の氏名や生年月日を間違えずに記入」「 滞在予定表には公演日程やリハーサル、移動日など、具体的なスケジュールを記載しておく」でしょうか
他に費用が掛かるとすれば自宅から入管に行く往復交通費(来日ライブ会場管轄の地方出入国在留管理局)ですね
これらのフォームは、音楽をやっている人なら自分で記入し自分で入管に持参提出できると思います
記入が面倒なら行政書士に頼むのもありますが記入代行費用で何万円か掛かると思います
ちなみに1人1申請は手間なのでバンドメンバー全員分の「申請人名簿」をエクセルで作れば添付で済むので楽です(実際、我々の海外公演時も出演バンドの全員の名簿が添付されていてそれを諸々資料と一緒にビザセンターに持って行って興行ビザを取得しました)
招聘する側は「法人」でも「個人事業主」でもどちらでも申請できますが法人がやはりスムーズ
なぜなら個人事業は「継続性」「責任能力」「資金力」で信頼性が薄いですからね
もし個人事業主で申請するなら加えて下記3点
1. 実在性・継続性の証明ができること(以下添付↓)
• 開業届の写し(税務署の受付印があるもの)
• 確定申告書の控え
• 事業内容がわかる資料(イベントのチラシ、過去の実績など)
2. 招聘・受け入れ能力の証明(以下添付↓)
• 過去に招聘実績がある、もしくはイベントの企画・運営経験があること
• 十分な資金力(費用負担が可能なこと)を証明できる資料
• 銀行残高証明
• 契約書、ギャラ支払いに関する資料
3. 招聘目的が明確であること(以下添付↓)
• 公演の具体的な内容(日時・会場・チケット販売情報など)
• 出演契約書(招聘側とバンド側との契約)
招聘をするならば「法人化」しておくと良いでしょうね
我々が実際に興行ビザを取得した時の資料(個人情報)をココに載せることはできませんが、書類としては「招聘側から頂いた捺印済フォームが6枚」+「自身で記入したフォームが8枚」でした
この計14枚の資料を「在住管轄ビザセンター」(当方の場合は大阪ビザセンター)に持って行き申請。取得まで1週間も掛からなかったと思います、あっと言う間でした
先述の通り外国人が来日する際の興行ビザは1人約3000円ですが、逆に日本人が海外に行く場合のビザ申請費用はもうちょっと高いですね。実績例を挙げると当バンドの2025年中国ツアー(w/Sinister)の際は興行ビザ1人当たり9千円位でした
この様に取得費用は国によって異なりますが、もしも「日本人がアメリカに行く興行ビザ」の取得費用は桁違いで全くの別物の様です。まだ実際に申請したことは無いですが調べると恐らく1バンドで25万~30万円くらい掛かりそうです(2025年現在)アメリカの興行ビザに関しては将来、実際に取ってみて詳細把握してみたいと思っています
上記の通り、招聘側が準備する資料の方が手間が掛かりますよね。アーティスト側は個人情報や滞在先等の記入事項はあれどもビザセンターに持っていくだけな感じです
あくまで我々は自身のバンド活動で精一杯なので招聘事業はしませんが、もしも招聘をしてみたい方や来日エージェント事業を目指す方がいらっしゃれば参考になれば幸いです
我々は「パフォーマンスする側」で頑張ります
<余談>当方、過去に約10年の海外在住歴があります。今回の様な、バンド活動における「興行ビザ」だけでは無く「留学ビザ」や「就労ビザ」、更には「外国ID」までをも取得したことがありますがSNS上で時折騒ぎ立てられる様なレベルでビザ取得について苦労した思い出は無いです。1つ言えることは「時間に余裕を持って申請する事」です、ギリギリは緊張感あると思います
世界最大級ライブ情報プラットフォームのBandsintownから見たデスメタル
Band-in-townサイトは世界最大級のライブ情報プラットフォーム
Live Music, Concert Tickets & Tour Dates Near You | Bandsintown
いわゆるコンサート発見サイト
音楽ファンにとってはスマホ等の「現在地」情報からもその日のライブ情報を取得できますし、アーティスト側もライブ告知やチケット購入リンクも付帯できます
更には「招聘」すらも出来る様にエージェントやダイレクト連絡先がほぼ掲載されています
ちなみにサイト内で「Deathmetal」(デスメタル)と検索すると下記の様な感じで出てきます
Death Metal Concerts & Live Tour Dates: 2025-2026 Tickets | Bandsintown
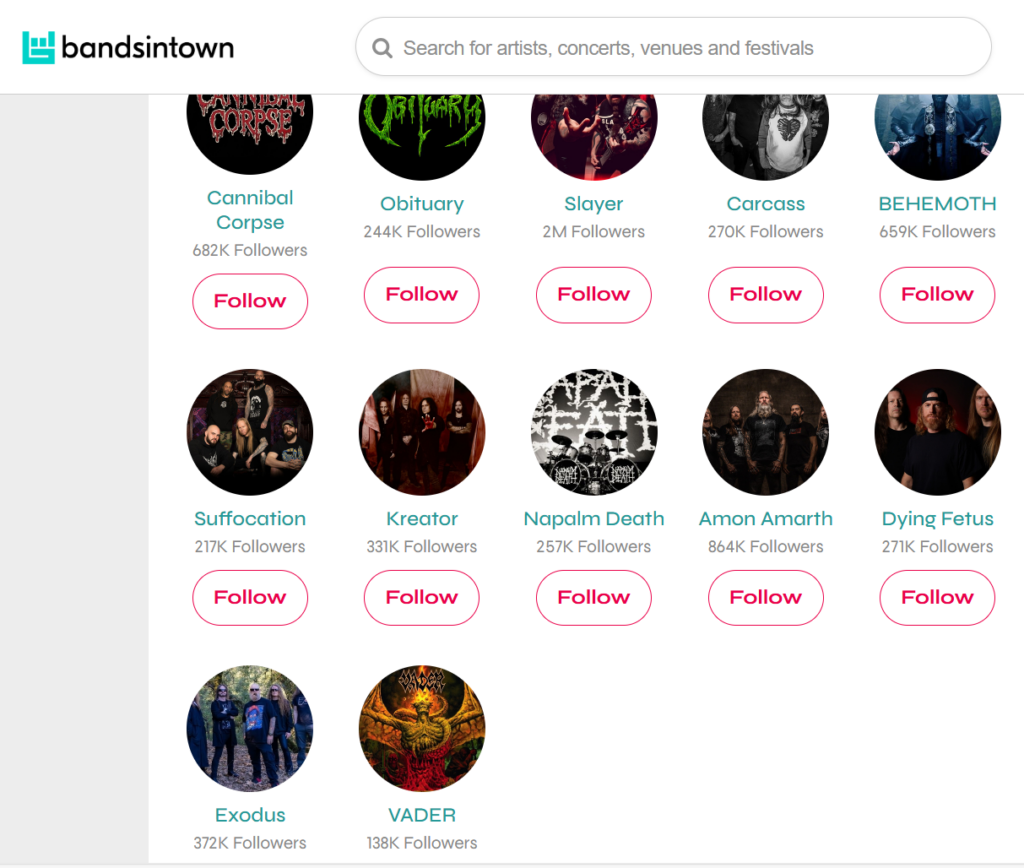
ここの「Followers」の数字が「バンドの格付け」的に「招聘する際のギャラの目安」や「集客規模の会場目安」にもなっているようです
例えばデスメタルで言うとCannibal Corpseが飛び抜けてFollowerが居ますね
例)
Cannibal Corpse 68万2千人
Obituary 24万4千人
Carcass 27万人
Napalm Death 25万7千人
Suffocation 21万7千人
Kreator 33万1千人
Exodus 32万7千人
Sinister 22万5千人
Deicide 22万3千人
Vader 13万8千人
Cryptopsy 9万8千人
Origin 7万人
Malevolent creation 5万8千人
Pestilence 2万6千人
Defeated Sanity 1万6千人
Sadus 1万5千人
Skeletal Remains1万5千人
Massacre 5千人
こう見るとCannibalに関してはObituary、Carcass、Napalm Death、Suffocationの3倍、更にVaderの5倍のギャラ相当(や集客規模)と推測しますので別格で世界的人気を誇るデスメタルバンドなんだと思います
我々は余りにも小規模過ぎるので登録すらしていませんが、ある意味で「格付けランキング的な見方」もできそうなプラットフォームではあります
ちなみにメタリカは631万人でした
つまりメタリカはデスメタルNo1であるCannibal( 68万人フォロワー)の更に約10倍規模です
こうやって格付けされているようにも見られる音楽業界
我々には縁が無いとは言え、バンド業界の上層階規模は本当にシビアな世界ですね
ある意味で商品価値的な怖さもあります
恐れ多いですが故意に我々が登録をし、それがどうなるかを探ってみるのもありかもしれませんね
その際には登録手順等を含めこのブログで「登録してみた」的にやり方を報告させて頂こうと思います
(更に更に続き)ギターのツアー全機材/荷物重量ミニマム(2025最終バージョン)
ライブで気づきがあった時にギター機材の更新をしていて、毎年機材が変わっていますがようやく2025最終版が固まりました、以下の接続です
ギター本体(3.2kg)
↓
Shure GLX-D16(ワイヤレス/チューナー付/560g)
↓
TS 808(チューブスクリーマー/約500g)
↓
Pocketmaster(マルチエフェクター/194g)
↓
Powerstage200(パワーアンプ/1.3Kg)
↓
ABY BOX(スピーカー分岐用/パッシブ/250g)
↓
会場キャビネットx2基へ接続(スピーカーケーブル2本持参)
結論としてギター本体を含めても「約6kg」の究極ミニマム軽量機材です
もはや「これ以上にやれることは無いだろう」という位のミニマム&耐久性&音質ベスト版
特に音質についてはNAMバッチできるのである意味でどんなアンプサウンドも自由自在に取り込めます
その他の機材としてはクリックを聴く用のイヤモニ機材がありますが以前紹介の通り「XV-U4の送受信機」と「ShureのSE251SSPEイヤホン」なのでこれを含めてもツアー機材が「約6kg」で完結は思いもよらなかったです(厳密にはセミハードケース本体の重量と持参スピーカーケーブルも足す必要がありますが)
ようやく自身の中では「究極」と思うところまで辿り着きました
あとは慣れて行くだけです
機材更新って、やり出すと完全に沼にハマり易いですがこれで一旦ストップしたいと思います
とはいえこれからの海外ツアーなどで使用して行くうちにまた新しい事を思い付いたりもあるのですが一旦これにて「2025年版ギター機材ライブ仕様一式」は完結です
スーツケース対策
飛行機の預け入れ重量は23kg迄/個がデフォルト
ですのでスーツケースの中に入れる荷物の重量は25kg位を目安に作られているものが多いです(それ以上の重量荷物を入れると壊れる可能性)
ツアーの際、LCC海外航空券を買う時によくある条件が「預け入れは23kgを2個まで」+「手荷物は1個10kgまで」
その「預け入れ2個まで」の内訳は必然的に「ギター」+「スーツケース」
そのスーツケースですが無理矢理35~40kgくらい詰め込んでいた(エフェクターボードやマーチ等)ので当然ながら毎回のようにキャスターが壊れていました、ここ数年でスーツケースは4個も壊れてしまいました(全部キャスター破損)
キャスター部が現地先で壊れると最悪です、滞在中はスーツケースを引きずるので腕がパンパン。
帰国後は1週間くらい筋肉痛…これを幾度と経験しています。
どうにかならないかと(勿論お金さえ払えば何個でもスーツケースを預けられますが節約したい)
そこで「スーツケースの耐久性」では無く「キャスターの耐久性能が高いもの」を探しまして
それが「世界最強」と呼ばれるキャスターメーカーの㈱日乃本錠前社さんでした
中に入れられる荷物量も増やしたいのでスーツケース自体も出来るだけ軽量が希望です
それをも解決するスーツケースが見つかりました
MAIMOというメーカーさんの軽量スーツケースです
MAIMO公式オンラインショップ|スーツケースのマイモ 公式通販サイト
MAIMOさんはナント日乃本錠前のキャスターがデフォルトで、かつ、キャスターを自分で交換可能で、更には予備キャスターまで販売されているという我々にとっては願っても無い究極版
【HINOMOTO超静音】スペアキャスター(ストッパー付き) – MAIMO公式オンラインショップ
という事で、このスーツケースの「L(MAXサイズ)+キャスター予備」(簡単に取り換え可能)が現況最強スーツケース(マーチ、エフェクター、ケーブル諸々)になりました
【進化した多機能スーツケース】COLOR YOU plus -カラーユープラス- – MAIMO公式オンラインショップ
これならツアー中にキャスターが壊れても付け替えられますし引きずらずに済みます
これは今年最大の発見と言っても良く「ツアーを更に快適にしてくれるアイテム」の1つだと思います
※裏技的な話ですが手荷物MAX10kgを超える対応として「釣り用」の「ポケットが沢山付いたジャケット」を羽織りそのポケットに入れるというパターンも

涙ぐましいかもですがこれも経費節減アイテムの1つになっています
(更に続き)194gマルチエフェクターPocket Masterの戦力化計画
「機材軽量化」の話をし続けていますが、更にその後です
194gのPocket Master(プリアンプ・マルチエフェクター・NAM対応)をライブ使用想定で試行錯誤中ですがパワーアンプに関してはPowerStage200という大出力(200W)筐体を使おうとしています
試行錯誤し続けていますが、「出音が歪みもパワーも浅い」感じがありまして
どうやら、Pocket Master側の出力レベルが大出力パワーアンプを十分に駆動させられる出力レベルに届いてないのかもしれません
そこで出力ブーストさせてみようと(出力増幅用クリーンブースターを使ってみる)
既に所有している機材だとEXIOTIC/EPブースターがありますが更に「強烈に前に出る音」が欲しくなり
色々とネット上で仕様などを調べてみるとラインレベルをガッツリ稼げそうなMXRの「MC401 Boost/Line Driver」が良さげだったので購入
結果として現況は下記の様な接続になりました
①ギター
↓
②Pocket Master
(プリアンプ・エフェクター/EVH5150クローン)
↓
③MXR M401
(ブースター)
※Powerstage200の(爆音)大出力レベルに追従させる為
↓
④Seymour Duncan Powerstage 200
(200W大出力パワーアンプ)
↓
⑤Marshall等の物理キャビネット
(スピーカー)
※ライブではABY BOXを使用しスピーカー左右2発鳴らしています
これらを収納してみると下記の様に弁当箱型バッグ1つに収まりました
凄いです、「アンプとエフェクター込み」でこのサイズと軽さはかなり魅力です↓

初期の海外ツアーの頃は嬉しがって「お上りさん」というか、浮かれて重いものでも全部持っていくみたいな感じで筋肉痛がキツかったですが現在は「質を落とさずに(むしろ質を上げつつ)どこまで軽量化できるか」を追求しています
とりあえずココまで辿り着きました
今後はギター音質をまだまだやっていく感じになりますが大枠は固まってきました
「まだまだやっていく感じ」というのはこれまでのアンプ(パワー+プリ)使用をしていた様に他楽器との周波数被りを気にしながらひたすらクリアに聴こえる音作りを突き詰めていきます
この「周波数被り軽減」と「歪んでいるのにクリアな音」に関しては時間を費やす箇所なので今後コツコツですね
共演後の関係
Sinisterと海外でツアーをさせて頂いて以降
バンマスのAdrieさんとは毎月の様にチャットさせていただいています

我々にとっては学生時代からのレジェンドバンドですから光栄過ぎるのですが毎回チャットは30分から1時間くらいの長話をさせて頂いています
ガチなアドバイスを沢山いただいていますし相談もさせて頂いています
もちろん私の方からのお声掛けは気が引ける背景下
Adrieさんから「最近どうしてる?}と連絡をくださるところからキックオフ
先ずはお互いの近況報告という流れです
サブコンのライブ状況も把握されていて「〇〇のライブはどうだった?」とか
逆にSinisterの現在のレコーディング状況や新曲もこっそりプライベートで聴かせてくださったり
当方はその時間帯、「誰も居ない部屋でペコペコしながら」おしゃべりをしている感じになります
その位リスペクトしています、なにせ青春時代から聴いてきている30年越えの大ファンですからね
レジェンドとこんなにもプライベートなお話をさせて頂いたり相談をさせて頂いたりしても良いのかという。緊張しながら失礼の無いよう言葉を選んでお話させて頂いています
我々はSinisterとは海外での共演で交流を深めた経緯がありますが「日本にもまた行きたい」とよく仰っています
次回は「東京だけでなく他の都市も廻りたい」とも
私的にはその言葉で「ギクッ」としました。
「国内シーンの状況」は良いとは言えないですからね
それを打開するには先ずは「国産デスシーン」(国産デスバンド)自体が盛り上がらない限りです
我々も演者側ですし「なんとかしたい」という心の痛さもあります
Sinisterからは「ヨーロッパに来いよ」と仰って頂いていますのでいずれは恩師Sinisterとヨーロッパを廻らせて頂ければと思いますが我々日本人としては、彼らが次回日本に来ていただくならば「活況なシーンを胸を張ってお見せできるような環境」を願います
我々国産デスメタルバンド軍団は頑張らないとです

※近年多くのレジェンドバンドと共演させて頂いていますがSinisterは我々としては別格で相性が良すぎて、人も良すぎてこんなにも沢山アドバイスを下さる方達だとは想像できませんでした。ライブや知識や技術やセンスだけでなくお話も含めレジェンドの凄さをいつも感じます、やっぱり違います。学生時代の自分からすると一緒にご飯食べたり一緒に移動したり、その上で共演が叶ったりは想像もつかない出来事ですからね
※「もう少しお話する時間が有れば深くリレーションシップが取れるだろうな」と思ったバンドはDEFEATED SANITYとCRYPTOPSY。将来、再会/共演の機会があればもう少し彼らと色々お話をしてみたいですし色々と聞いてみたいです
コンセプト不要論
賛否両論あるようなタイトルを故意に付けてみました
当方、コンセプトを決めてから曲を創るのが好きではないです
常に「出来たものが出来たもの」です
あくまで自分の中で自然に湧き出てきたものを曲として素直に創りたいです
先に指針を決めてしまうと「それに沿わなければならない」的な感情になるかもしれないので素直に曲が創れない気がします。思いついた「瞬間」を大切にしたいです
ですので、これまでにも何度も書いてきていますが我々の創作曲は常に「出来たものが出来たもの」
しいて言うならば
完成した後に共通項などが見つかり例えばプロモ用ワードとして結果的にコンセプトが付くくらいですね
サブコンシャステラーでは縛られることなく自由に創作をしたいですし実験的な要素も取り入れたくなるかもですので
曲単体は「都度インスピレーション」による創作なのでどの曲も完成してみないとどうなるかは自身でも分からないです、言うならば創りながら紡ぐ感じですし毎回そうです
以前にもここで書いたことがありますが曲構成をノートに書くようなことも無いので、あとで数えてみたら小節数が奇数だったり、その音階自体が一度しか出てこないとかも我々にとっては自然です
もしも、これがアイドルプロデュースとか他の方への提供曲とかだと逆な論理になることもありそうですが我々はオリジナル・デスメタル楽曲創作バンドですからね
12インチレコード
特にアングラ系バンドマンにとっては欲しいと思うかもしれない自身の創作品の12インチレコード
(参考:12インチレコード=LPレコード=Long Play Record、33回転、収録30分、塩化ビニール素材、ヴァイナル盤)
ただ、現実問題としてはCD販売量の1/100レベルの物流範囲かもしれません
それでも個人的には部屋の壁に飾ったりインテイリアとして置きたいなんて興味をそそられるところもあります
リリースまでは行かずとも創作記念として「自宅の壁に飾る用」として個人で1枚だけ、もしくはメンバー分だけ作ろうかななんて思い以前に調べたことがあります
やはり流石に1枚(12インチLP)だけの製作だと高価(約2万円)でしたが100枚作るなら大体15万円だったので1枚1500円位で作れますね
それでも僅か100枚ですからメンバー用とライブ会場限定の様な感じになるかとは思います。(これがもし300枚以上の製作だと数量割引で1枚当たり1,000円以下でした)※全てジャケット印刷諸々込みの料金
もし仮に「数量割の300枚」(1000円切る位の原価)を作って数量限定リリースするとしたらですが
現実的には国内販売価格で4000円は行くでしょうね
海外生産なので別途掛かる「国際物流費用」だけでは無く「関税」もありますし更にレコードショップさんへ卸すまでやるならばそこからの「卸値」もありますので販価で4000円だと右から左な費用(つまり利益までは届かない)かもしれません。なので国産バンド個人で作る人は少ないのだと思いますが
上記はあくまで「個人」で制作依頼する場合の費用なので割高だとは思います
(※ちなみに国内で生産依頼をする場合、調べた範囲では上記単価x約2倍でした)
これまでのリリース作品を自己満足の為にビニールレコードを1枚づつ作って自宅に飾って老後を過ごすなんてことを想像したりもします
ひょっとしたらバンドマンで同じような事を考える人もいるかもしれないと思い今回の内容を書いてみました
Sonicake /Pocket Master の可能性
以前ここで紹介の世界最軽量最小クラスのマルチエフェクター、Sonicake /Pocket Master
予約していた新色版(2025年6月上旬出荷)が6/5に届きました
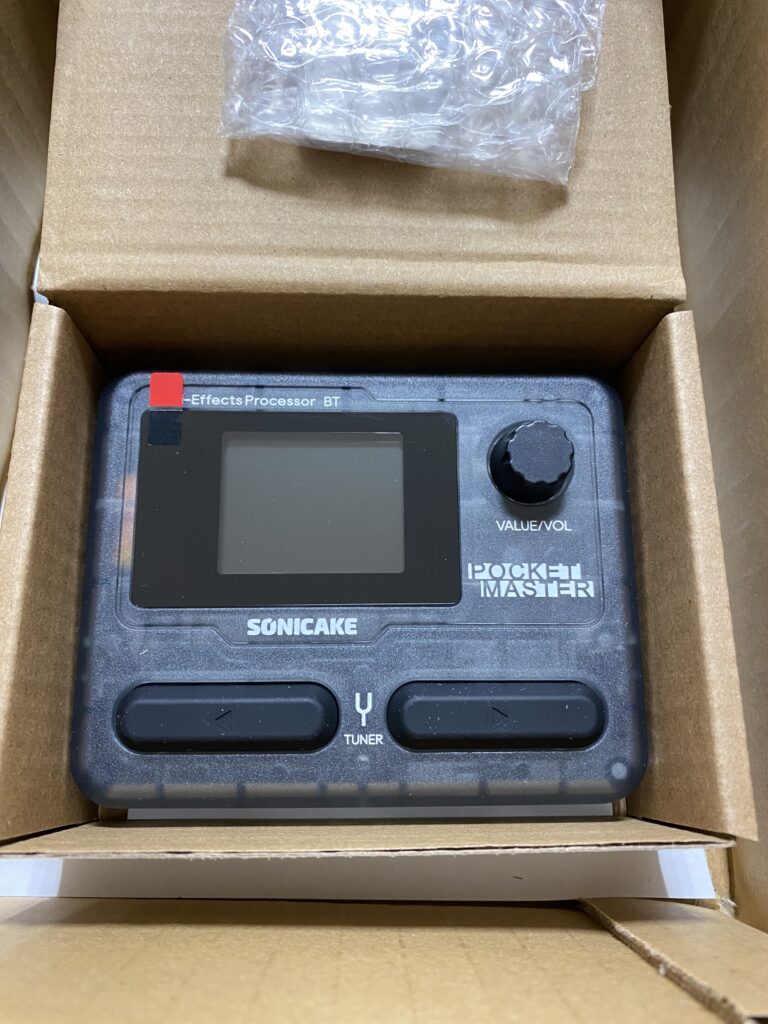

到着後即開封し、早速音を鳴らしてみました↓
(曲は当バンドの”Sacrifice of Technology”のイントロ部です)
音色パラメータはこちら↓
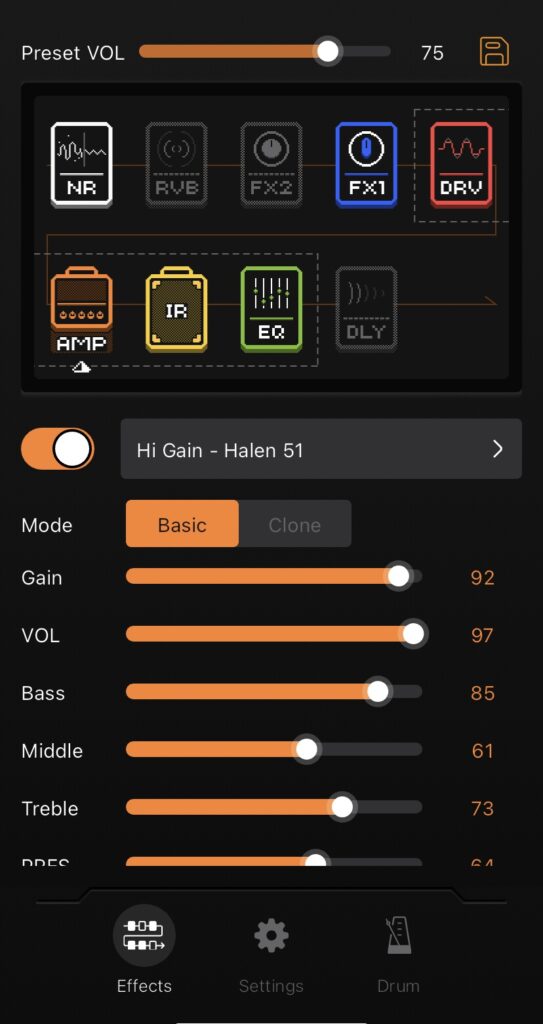
↑Peavey5150系アンプにEQとノイズゲートと少しサスティンを効かせています
ササっと触ってみた開封後1時間未満のパラメータなのでこれからじっくり音作りをする事にはなりますが、これを海外ツアーで使えるならば毎回悩んできた「預け荷物の重量オーバー」や「身体の疲労」を大幅に減らせます
なにせ194gですからね
以前書きました通り、
現時点の最軽量機材が①アンプヘッド約3.6kg+②エフェクターボード一式6kg=合計約8.6kg
これをアンプヘッド無しにして
①パワーアンプPowerStage200(1.3kg)+②ポケットマスター(194g)に変えられるならば合計約1.5kg
ナント現況よりも「約7kgも軽くなる」のでツアー時の荷物重量としてはかなり効果が見込めます
ツアーの度に重い荷物の運搬で身体がバキバキになる程に筋肉痛になっていたので非常に助かります
ローディーが居る規模のバンドでも無いですし自分の機材は自分で運ぶ身としては奇跡的な重量軽減です
そして更なる軽量化を目指すために現在オーダー中なのものがあります
新規ギターケースです
これまではJacksonハードケースで運搬(飛行機預け入れ)していましたがギターケースとギター本体を合わせると合計約10kgもあり運ぶだけで毎回肩が痛くなっていました。
これをSKBのセミハードケース(国内に無くて取り寄せ中)に変えようと思います
現況>Jacksonハードケース4.86kg+ギター本体約5kg=約10kg
将来>SKBセミハードケース2.86kg+ギター本体約5kg=約8kg
これでまた更に2kg軽量化できます
特にハードケースはウロウロしているときに身体に当たると痛く、帰国する頃には所々にアザというか…
外側が柔らかいセミハードケースなら身体への負担も楽になりそうです
上記2つの軽量化計画を合計すると現況よりも更に「9kg」も軽くなる見込みです
これは個人的には大発見ですし期待大です
当面はポケットマスターを使いこなせるよう研究してみます(特にライブでも使えるかどうか)
このマルチエフェクター・ポケットマスターですがNAM対応、つまり.namファイル形式を読み込める(実際のアンプやエフェクターをAI学習させて再現するソフト=アンププロファイラー)のでTONE3000からダウンロードしてポケットマスターに読ませアンプのクローン音色を作ることもできます
先ずは当面、使いこなせるようになりその後にライブ用の接続パターンや納得行く音作りまでの完結期間を想定すると数か月くらい掛かりそうですが楽しみですね
※TONE3000のホームページ↓
Discover Neural Amp Modeler (NAM) Profiles and Impulse Responses (IR’s) · TONE3000
※ポケットマスター取説
QME-10_Pocket_Master__Online_Manual_JP_Firmware_V1.0.1_0414.pdf
バンドホームページの重要性
バンド規模に関わらず「1つの会社」だと思ってオフィシャルHPは作ることをお勧めします。
我々の様な超小規模バンドですらこのHPを作っていますが「オフィシャルHP=公式発信」ですから必須だと重要視しています
マーチに関しては確かに大手レコードショップさんやAmazon等のECの方が大量流通しますが、オフィシャルHPから購入下さるのはコアなお客様ですしファンへの対応が出来る貴重な機会です
バンドのホームページにまで辿り着いて下さっている訳ですからね
実際、オフィシャルHPからの御購入も多いです
コツコツ更新しながらやって行くのはバンドの醸成や情報蓄積にも繋がると思います
折角興味を持っていただいたのにSNSのみの発信で肝心なHPが無いのは寂しいものもあります
当方は気に行ったバンドはHPの有無を検索しますしバンド更新情報を気にするようになりますし音源が出ればチェックする習慣もあります。こういう人も居るという。
超マイナー業界ですからコツコツ型で行くしかないですし、だからこそオフィシャルHPでの「公式発信」は重要だと思っています
他にも、バンドHP上に「コンタクト欄」(問い合わせ欄)を設けているので海外エージェントからの出演依頼はここから来ることも多いです
招聘側がファーストコンタクト時に「バンド名検索し接触する連絡先」をHPから見つけ出すことも多いととも言えます
このオフィシャルHPもDIYですがバンド活動において非常に重要な役割をしています
国内におけるメンバー募集の手法について
「メンバー募集」について、いつも不思議に思う事があります
例/都内で月2回スタジオ練習、オリジナル曲完成後、東名阪ツアー、将来は海外ライブも希望
このような感じの内容をお見掛けします
もし当方が新規活動するのであればですが、
①まずアルバム1枚分のオリジナル曲を自分で作る
②メンバーは在住地や国籍問わず「地球上」で探す
③演奏技量は各自に一任
④レコーディングも遠隔で全く問題無いです
⑤ライブは現地に集まれば在住地不問でOK(リハは現地会場で出来ますよね)
しいて言えば③は各自の高度な技量が必要です
でも、学芸会バンドでは無くプロフェッショナルなバンドをやるならば「しっかり演奏できる技量のある人になるはず」だと思います
我々の場合は更に(A)長髪、(B)生活環境整備出来る人、を探してバンドを組んでいます
「家が近い」、「近隣スタジオで定期練習」ような地域限定をしてしまうと、なかなか見つからないのでは?
例えばテクデスバンドのOrigin
近所住まいどころか、そもそもメンバーは普段住んでいる国まで違いますよね。「ツアー時に集まる」を何十年も続けています
なので「メンバーを近所住まいで探す」に拘るは不思議な文化だと思います
他にも「毎月2~3回の定期練習を行う」もどういう意味なんだろうと思ってしまいます
まさか「演奏ミスばかりあるからそれを改善するために定期的に集まっている」なら本末転倒です
あくまで個人技量は「個人の普段の練習」からですし「皆んなで集まってから練習する」では無いです
我々のリハーサルスタジオ練習は演奏と言うよりも、オープニングSEが流れた後の1曲目スタートに繋がる「間」の確認だったり、どのタイミングでMCを入れるかや、会場入り前の機材最終チェックや全体音質(機材更新があったりもするので)の最終チェックです。
なので例えば3時間のスタジオ予約をしていても演奏は1時間もして無いと思います。
スタジオ内では各自が機材の接続確認をしながらセットリスト&MC箇所相互確認や、ライブ会場でのリハを迅速に接続できるように予めセット出来ることはしておくとかの効率、次作のレコーディングの細かい話であったり、そのような「打ち合わせの場」的な使い方の方が比重を占めています
なので演奏確認の為にリハーサルをするというのは「新曲を初めて演奏する時」以外は無いです
曲の練習は個人が日頃やっておくべきことだと思っています
これらが備わり皆が意気投合できれば「新規バンド」でもすぐに走りだせるでしょう
ロイヤリティ
契約レーベルやバンド毎に違うと思いますがここで言う「ロイヤリティ」とはレーベル側が使用するバンド著作の配信や再生や販売状況によりバンド側への報酬と定義します
我々は幸いにもメタル系大手レーベルのBrutal Mind所属していますがCDやシャツリリース以外にも色々有難いサポート状況があります
MVやアートワークのコストサポートもそうですが他にもキャップやフラッグ等も作って下さっています
これもロイヤリティとして何回かに分けて(CD/シャツ/他マーチ等)送ってくださっています
我々にとってマーチは貴重な活動資源
DIYバンドなので国内外のライブ遠征費を含めマーチは「バンド活動継続の為の命綱」でもあります
逆に全然売れなければ、どんなバンドでも活動は縮小するはず、特に海外規模でツアーするとなると。
この様なレーベルサポートを始め何よりお客様からのサポートには本当に感謝しています
将来レーベル契約を目指すバンドさん向けに技術面以外に伝えることがあるとすれば「相性」
バンドもレーベルもやはり人間同士ですから「合う合わない」(普段から話が噛み合う/噛み合わない)があります
レーベルボスとは友人を超えてもはや親友ですが逆にその位「合う合わない」はあると思います
特に大手系の場合はやはり会社ですから利益を出さなければならず「儲かる儲からない」で取捨選択されることもあれど最終的にはそれ以上に「人間性が合う合わない」が最後の砦として重要になってくると思います
これから半年掛かりで準備
このブログに辿り着かれた方限定のご報告ですが当バンドの90’初期メンバーが正メンバーとして戻ってきます
これまでのサポートメンバーには感謝しています、本当にありがとうございました
今回、彼の正メンバーとしての再加入でかつ、それが「初期メンバーの復帰」という事で感涙ですし、サブコン用に機材を諸々新調して下さるという事で気合も十分。ここ数か月、彼と沢山の話をしています
有難いことに2019年秋の再活発信後もずっと気にして下さり近年のライブも来場観戦して下さっていました。過去曲は勿論の事、近年の曲も理解されていますので話は早いですしその後はトントン拍子でした
90年代に我々のライブを観て下さっていた方達にとってはタイムマシーンの様な出来事だと思います
乞うご期待下さい
↓我々にとっては希少な学生時代のライブ動画
(もっと前の8ミリビデオ動画もあったような気がしますが何処へ)
1年以上の先の話まで
出演に辿り着くまでの背景について
フライヤー等で情報公開される1年以上前に決まっていたりすることもあります
なんならまだ開催されていないフェスの「次の年(1年後)のラインナップ」まで水面下では既に決まっていたりします
これって例えば「バンドを組んだばかりの人達」にとっては内情を知らないと過酷ですよね、出演の機会を希望しても時既に遅しで「出演枠は既に無い」という
ブッキングエージェント業界の現況として
近年は1年以上先の話も多々あります
我々も公開をしていないだけでこの先10本くらい既に決まっているライブがあります
音楽ライブ業界はとにかく動きが速いです
ちなみに「某デスメタル大御所の〇〇がアジアツアーするときは声を掛けるのでその際は都合の調整を宜しくお願いします」的なものまであります。(音楽的な相性が良いのでお声掛け頂いたのでしょう)
光栄な限りですが「未来」ですからその時にどうなっているのかの不安というか、そこにプレッシャーを感じる時もあります
その時になってメンバーが都合付かずだったりメンバーの誰かが大病を患ったり、別のライブが既に確定していたりの可能性も考えてしまいますし、そこまで先の未来は予想しづらいです
なので「手を挙げての出演」では無く受動的(頂いたお話のライブに出演させて頂く)な活動が主になっている現況もあります。せっかくバンド活動しているのですから本来はガツガツ行った方が良いかもしれません
「未来のライブを想定」しながら動くのは調整面での心配毎もありますが、そこを調整する能力の高さが求められるのがバンマスの仕事でもあります
各自のスキル向上を激速貢献しているDTM
DTMに関しては2019秋のバンド再活時にその存在を知ったのですが、世の中では2010年以降爆発的に一般普及したそうです。なにせ数万円のPCでDAWが動くという手軽さですからね
我々1990年代はカセットテープに録音しながらコツコツと曲を創っていましたが今はDTMですね
若い世代の方達が「楽器が巧すぎる」のは近年のDTMの爆発的普及の影響も大きいと思います
当方DTM歴がまだ浅いですが創作やレコーディング時にとても便利ですし常日頃活用しています
主に以下の様な使い方をしています
①普段からのアイデアの貯め録り
②曲構成を練る際に仮でPC上で録音しておいたギターリフなどをカット&ペーストしながら構想展開を確認できる
③デモやプリプロを作れる
④レコーディングすら宅録できる
昔と比べたらこれをやるだけでも物凄いスピード感です。
表題の話に戻ります
DTMが一般普及したことで楽器が巧くなるのが激速になってきている背景として
①即時フィードバック、つまりPC上で「視覚的に音楽構造を把握」できるので独学でも大丈夫
②自分の演奏を録音し、聴き直すことでタイム感を含め修正力・改善力が育つ
③即座の編集が可能
④録音した波形を拡大すれば自分の演奏ミスした所を分析改善できる
⑤クリックを流しながら録音することで「合ってるつもり」だった所が「実は間違ってた」(ズレてた)等、客観視できる(前ノリ、後ノリすらのニュアンスまで波形拡大で認識できる)
⑥なんならメンバーが居なくても打ち込み等を駆使すれば1人でもリリースまで辿り着ける
他にも個人的にかなり助かっているのが「レコーディング前のプリプロ制作」です
例えばアルバムを出すとしましょう
まずは当方で「全曲分の全パートのデモ」を作るのですがこれが速いです
ドラムは叩けませんがデモ時はザックリとイメージで打ち込めるので創作時間の節約ができます。
仮デモが完成したら全メンバーに渡しプリプロへ移行していく(各自が各パートを奏でる)流れですが、これだけでもかなりの効率ですよね
話を戻しますがDTMの爆発的な一般普及は「視覚的にも音楽を理解できる」ようになり、上述の通り「スキル向上」や「制作時の時間短縮」迄の音楽全体をカバーできるような素晴らしい発明品だと思いますね
※当方使用のDTMはTASCAM&CUBASEのセット品です、何か特別なものでも無いです。しいていうならばプラグイン(ソフトインストール音源)でギターのディストーション系エフェクターやボーカルのスラップバックエコーエフェクターをインストールしている位。あとはデフォルトです
会場物販時のTシャツサイズの瞬時確認対策やその他の工夫
会場物販時のTシャツ販売
販売側(バンド側/スタッフ側)はサイズ確認をするのにアタフタと手間取ったことってありません?
と言うのが毎回「首元の小さなタグ」に目を凝らしてサイズ確認するからです
これに毎回「手間取る感じ」がしていたんですよね
一回一回タグに目を凝らして確認せずとも一瞬で「サッ!」と出したいです
その対策をしました
それがこちら↓

拡大↓
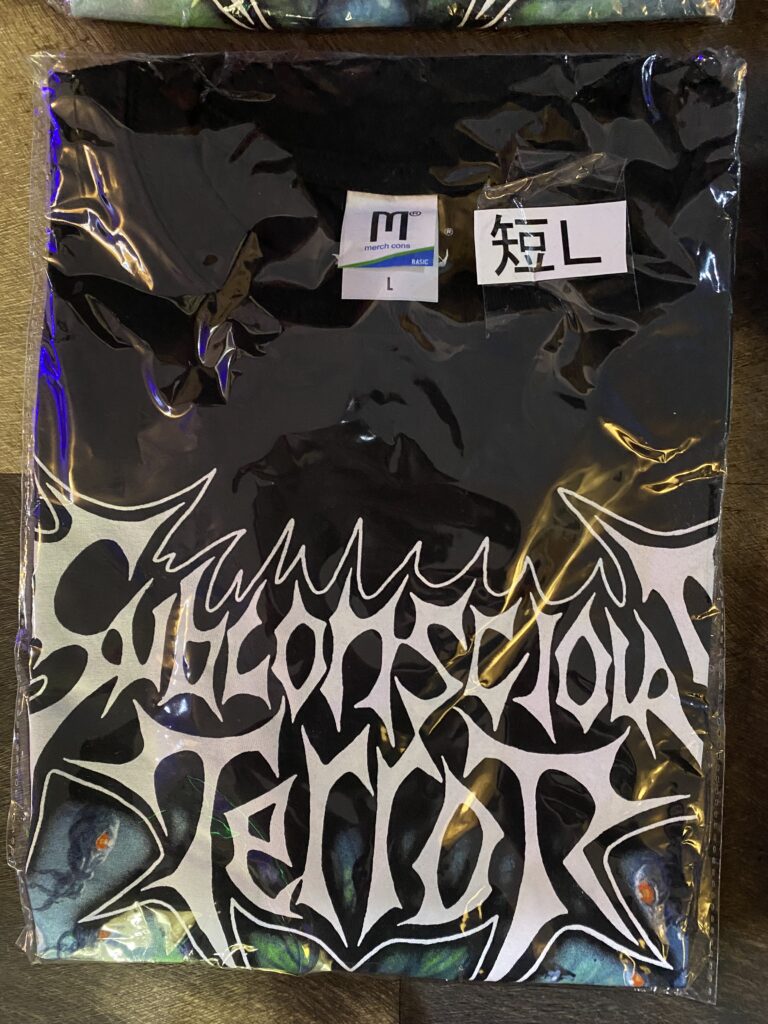
これなら一目瞭然で分かります
エクセル上でA3紙にS、M、L、XL、XXLと打ち込みプリントしてカットします
(A3ならば紙1枚のプリントでTシャツ100枚分以上)
それを透明テープで貼りました
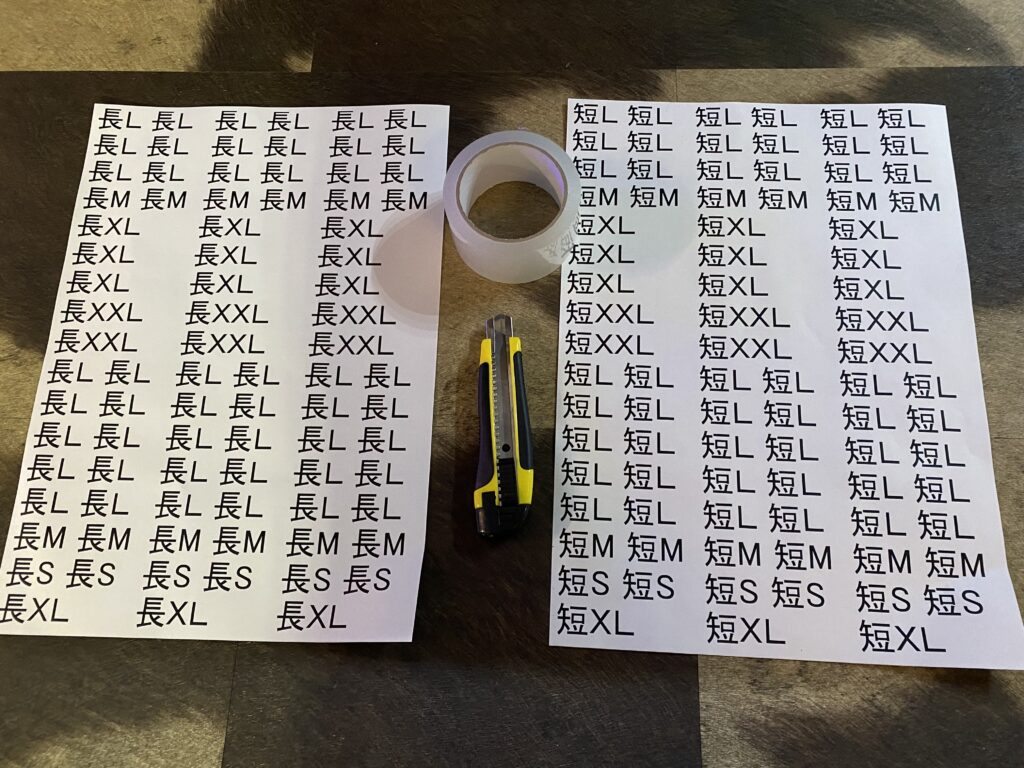
こうすることで毎回アタフタとタグに目を凝らさなくても「サッ!」とお出しする事が出来ます
写真をよく見ると「ん?」と思われたかもな表記方法かもしれません
そうなんです。
半袖Tシャツを「短〇」、長袖Tシャツを「長〇」の表記にしました
半袖の「半」ではなく「短」という表記です
何故かというと
これを作る際、最初は「半+サイズ」という表記を考えたのですが中華圏やアジア圏のライブツアーの際は「短〇」の方が現地販売スタッフも中国語的な意味ですぐに分かるのでそうしました
我々日本人も「短」表記でも「半袖Tシャツの事を言ってるのだろう」と意味は分かりますしね
これで会場物販時のTシャツ各サイズをアタフタと目を凝らして確認せずに済みますし、瞬時の取り出しが出来るようになりスッキリしました、ご参考まで
その他の工夫も紹介してみます
バンドマンによくあるかもしれない「サインペンを無くす」です
ライブ会場で光栄にも「サインをください」とお声がけ頂く事があります
中国ツアーの際は100人以上の並びサインという、おこがましい経験をしました
そこで、
お客様へ「ストレス無くサインの対応」をさせて頂く為に「我々の方で何か出来ないか」と考えました
お客様によって「ペンをお持ちの方」と「ペンをお持ちでない方」がいらっしゃいます
バンド側でも毎回ペンを持って行くのですが、いつの間にか見失う(無くなる)ことが多々ありツアー毎に購入して持って来るという背景がありました
これをどうにか恒久対策(インクが無くならない限り)できないかと
そこで存在が分かり易く、目立つ色の「ペン入れ」を購入しました。それをダイソー(100均)のカラビナで物販用CDケースに留めています

そうすれば無くなることがまず無いですしお客様でペンをお持ちで無くてもサッと対応できます。(サインが終わったあとは「ペン入れ」に戻す)
ちょっとした事かもしれませんがライブ毎に学びがあります、本当にありがたいバンド人生です
学生時代によく聞いた私的名盤
サブコンを結成しようと思った源流でもある各初期のメタリカやメガデス、スレイヤー、ディーサイド、セパルトゥラ、カニバル、モービッド、カーカス、ナパームデス辺りの超有名系では無く今回は私的名盤の様な感じで紹介してみたいと思います
90年代初中期の当時はネットが無いのでCDショップでのジャケ買い、もしくはショップ店員さんにイメージを伺っての購入、もしくは紙媒体の海外ファンジンやBURRN!誌を見ての購入がメインです
そもそもブラスビートを用いた国産バンド自体がまだ数える程の時代でしたのでそれを踏まえた中でも当時カッコいいなー、エグいなーと思って聴き込んだ海外のバンドが以下です
■まず1つ目はデンマークのデスメタルバンドInfernal Tormentです↓
Infernal Torment – Man’s True Nature (Full Album) 1995
(リンクを開くとジャケがグロいので年齢制限ログインして下さいと出ますが5秒位待つと聞けますね)
彼らは途中で路線変更したので私的にはやはりこのアルバムですね
■そして2つ目はスウェーデンのデスメタルバンドLuciferionです↓
上記Youtubeリンク先の1つ前のアルバムを買って来てかなり聞き込んでいましたが今回は次作のこちらを紹介。当時を考えると曲もセンスも秀逸だと思います
■そして3つ目はアメリカのデスメタルバンド、Mortician↓
Mortician – House By The Cemetery (1995, Full EP)
↑当時CDショップでこのEPを買って帰ったのですが「エグイ、キツイ、この世のものでは無い印象」でした。今は普通にヘビロテですね
■次はのちに有名になったバンドですが当時のCryptopsyのデモカセット(トレードでコピー入手)を聴いた時は「この速さはウソでしょう!」と目を疑いました
CRYPTOPSY – Ungentle Exhumation (Demo ’93) [Full Demo] [10″MLP]
彼らとの共演を2020年代に出来たことは感慨深いものがありました
■こちらも有名ですがアメリカのTerrorizerです
Terrorizer – Fear of Napalm (Official Audio)
↑当時は「ハードコアのブラストが人間技では無い凄い版」というイメージでした。とてもキャッチ―ですし名盤ですね
■最後は擦り切れるほどに聴いてきたアメリカのSADUSです
↑こちらはサブコンの源流中の源流といっても過言ではないでしょう。結成当初のHammer(Vo&G)とデスオ(Drum)が日々聴いていた程で今でも大好きです。Sadusはこの「chemical exporesure」、そして「swallowed in black」、「a vision of misery」アルバム全曲名曲で「毎日聴き過ぎて」と言う位です
なんだか学生時代の思い出が蘇ります
バンド音楽とビジュアルは一体感
これまでに幾度か書いてきていますが視覚は音楽性を補完します
我々の場合は黒服に長髪で統一
やはり「普段着では無く」「短髪でも無く」「非日常感」をビジュアルにおいても表現する事で創作曲のイメージを”聴覚補完”できると思っているからです
想像、創造、脳内イメージ
例を挙げるならば、世界中のデスメタル系のバンドシャツのデザインを見るとその激しさを表したデザインが多いですよね
「ハワイのビーチでのんびり黄昏ながらカクテルを飲んでいる」デザインでは無いと思います
どちらかと言うとバフォメット系であったりスケルトン系などのオドロオドロしいデザインが多いです
これもやはりその音楽性の激しさを「絵」(ビジュアル)でイメージをし表しているのだと思います
我々のCDアートワークは歌詞内容からの発展ですが、将来ツアーシャツを作ることがあれば上述の様なデザインでもトライしてみたいと思います
さて、新作「Devoid of Seraphim」が新作リリース・ウィークリー・ヒットチャート5位(ディスクユニオンHR/HM)に入ったとのことでサポート下さる皆様へ感謝申し上げます。
こういったチャートの上位の顔ぶれを見ると基本、国内においては「V系」や「ガールズバンド」が強いです
そもそも、我々はデスメタル音楽ですからそこに混ざってチャートに入らせて頂く事自体おこがましい範囲ではありますが敢えて「もしもデスメタルのバンドでチャート1位まで行く」としたら音楽性は変えない前提でそれ以外に何をすれば良いのかを仮分析してみたいと思います
それは、「V系衣装を着た」+「ガールズバンド」のデスメタルなのかもしれません
逆に言うと、そのくらい「ビジュアル」というのは音楽性と同じくらいに重要なポイント。
「カッコいい方が良い」に決まってますのでそれはそうなんですが
将来は衣装を作るのもアリかもしれませんがデス・ブラック・ゴシック系の本格的なオーダーメード衣装だと1着10万円以上はしますので、我々の様な小規模バンドにとってはなかなかのハードルもあります
なぜアングラ業界はなかなか上手く行かないのか
近年の海外ツアーでは色々な国に行っていますが毎回多くの事を学ばせて頂いています
今回は表題の「この手のアングラ業界が上手く経済的に廻りにくい背景」について
先ずは我々の様な超小規模バンドのエージェント契約(招聘型)海外ツアーパターンです
①ビザ/勿論自腹(資料は相手国エージェントから政府許可、会場許可書類などを貰える)
②日本と該当国への往復飛行機代/勿論自腹
③該当国到着後
→空港送迎有
→ホテル準備有
→食事有
→該当国内の移動費不要
→会場費不要
→機材費不要
④ギャラ/勿論無
上記は世界中のデスメタルバンドの99%がほぼ同じ様な条件だと思います。ですので遠方国に行けば行くほどメンバー数x往復飛行機代が掛かる分、バンドマンは会場物販を頑張る必要があります
そして「残り1%」
つまり超有名なデスメタルバンド、つまりはヘッドライナーの場合は①②④が”有”になります
ここで大変になってくるのが該当国の担当エージェント(招聘側)
バンド側の費用は決まっているとは言えどもエージェント側は「来場者数を推測や見込み」で会場を借りることになりますので会場費/機材費/招聘バンドのギャラ/飛行機代/ホテル代を支払った結果、全然チケットが売れずに当日を迎えるとエージェント側がもろ被り(大赤字)になってしまいます。早めの前売りで会場費の先入金を賄ったりもあるでしょうし、諸々の準備を含め物凄いストレスが掛かるでしょう。興行ですから利益を出さないと継続できませんしね
無理をせずに小箱を借りてソールドアウトを目指す方が安全かもしれませんがその分、キャパも少なくなるので全体バランスとの塩梅になるので予測の難しいところですし結果的に疲労感だけが残る可能性も
整理すると、
A)我々含む99%のデスメタルバンドは自国から該当国への往復航空費分が赤字スタートで会場物販の売上結果次第(赤字が続けば最悪は金銭的理由で活動ができなくなることも)
B)エージェント側は来場が多ければ利益確保、少なければ赤字となるギャンブル要素
C)残り1%の超有名デスメタルバンドは経費+ギャラ確保状態(あとはメンバーが有休等を使い都合さえ付けば赤字無し)
ということはC)の「1%の超有名デスメタルバンド以外」は毎回どうなるか分からない状況です
だから段々と辛くなり心が歪んで行く人がいたりするんだと思います。本当に厳しい世界です。
ちなみに我々の様なA)に属する部類で例えばヨーロッパに行くとしたら往復航空費xメンバー人数=合計100万円掛かる想定の上でライブをしたとしても会場物販のマーチが100万円も売れるのか(元が取れるのか)という背景があり赤字確定想定で敢行する感じになります(メタリカ位のバンドなら全然あるでしょうが)
いつも伝えていますが上記を踏まえると音楽をどんなに熱く語ろうが四畳半アルバイト生活で「世界を目指す」みたいなのは非現実的でしょう
会場に辿り着くことすら出来ない(往復航空費すら無い)、自立した移動が出来ないプレイヤーは残念ですが非現実的な舞台
以前にも書きましたが海外でも単発ライブならまだしも、例えばヨーロッパツアー2週間ならざっと150万円~200万円はバンド側で自己資金を用意できないと難しいでしょう。資金が無い時点で熱く語ろうが世界を目指すなんて言ってもそもそも会場に辿り着く事すらできません
次に我々の様な超小規模バンド側からの立場を考えてみましょう
例えるなら会社でいう中間管理職の様な感じです。ヘッドライナーを立てつつ、招聘くださったエージェントに失礼の無いように、それでいてしっかりパフォーマンスして帰ってくるです
そもそも我々の様な超小規模バンド(前座)の場合は「居ても居なくても」ヘッドライナー公演は成立しますからね
更に冷や冷やするのが出演する限りは公演が成功して欲しい訳です。前座立場を踏まえつつも必死で公演をプロモーションさせて頂きます(&チケットが沢山売れますように祈願)
つまるところバンド側は「1%の部類に入らない限り」活動をするにあたっては自己資金準備が永遠に続き「中間管理職」の様な立場も永遠に続きます
なので疲弊してフェードアウトするバンドも多いのでしょう。無尽蔵にお金が続く人は別ですが
バンドをやっている人からすると「よくそんなに海外にバンバン行けてるなー」と思われる反面、逆に海外ツアーをバンバンやっているバンドを目にすると「うわー、凄いなー」と思いますし、その敢行心にリスペクトしかありません
一番良いのはメンバー全員が富裕層でしかも365日が自由に都合も利くバンドです
そういう人ならどこまで熱心に創作したりレコーディングしたりしても大丈夫だと思います
ですが、そんな人は殆ど居ないのでそのオチとして結果「1%」になる訳ですが…
叩き上げプレイヤーの強さ
最初は右も左も分からず、ライブをしながら「成長をすることの出来る」プレイヤーは強いと思います
これは何も楽器の巧さだけではなく、ハードな移動だったり機材運搬だったり現場でのイレギュラー対応だったり、ステージプロットやバンド全体の音作りだったり、そもそもの機材選定だったり
これらを経験しながらも「迅速に洗練しコツを掴んで行くセンスのある人」は特に強いです
例えばですが楽器系Youtuberで「巧いなー」「凄いなー」と思うプレイヤーが居たとしても、バンドをやっていない個人系のYoutuberだと実際のライブでどうかは分からないですよね
やはりバンドはアンサンブルですし「現場で学ぶセンスの有無」も分からないですしね
他楽器全体の音との調合であったり、ノリであったりが実際はどうなのかだったり
PC打ち込みでの完結型音楽の多い現代
近年はデスメタル界でも多い様でCDや音源がメチャクチャ超人レベルで凄いと思ってネット上で「LIVE」と打ち込んで検索すると出てこなかったりも(音源のみリリースでライブはやっていない)
そうなってくるとPC上で音階を切り貼りしながら尋常じゃない曲を創っているのではないかと疑念が湧くこともあります
取り組み方はあくまで各人各様ですし「ライブで示せ!」、「目の前で見せてみて!」と言っているわけでは無いのですが識別は難しいです
以前から書いてきていますが「我々はライブで演れない様な曲は創らない」のでそういった違和感を感じたのかもしれませんね
生身でやれる音楽をやり続けたいです
度胸と積極性
楽器が巧いとか、創作が巧いとか、ビジュアル統一感が良いとか…
その辺りはそもそも皆んな巧いです
先日「今、勢いに乗っている」と大変ありがたいお言葉を頂きました
これは①海外ツアーをしたり、②大御所バンドのサポートアクトに付かせて頂いたりが挙げられます
つまり「環境」が上手く行っていることが大きな要因です
この現環境は「運」と「度胸」だけです
突然、海外エージェントから「こちらのイベントに出ませんか?」と連絡が来た際に、即答で「Yes!」と返事が出来るかどうかのレスポンスであったり、出演が決まったならばパフォーマンスは勿論、現地キーマンや現地ファンとの交流をしっかり行ってから帰国できているかだったりです
そうすることで後々に噂が広まりまた別のエージェントから連絡をいただくという連鎖式
我々はこのような進め方をしています
ただ、お声掛け頂くだけの出演では無くこちらから能動的に出たいと思うフェスがあったとして
以前、気になる海外イベントに連絡をしたことがありました
結果的に「コネ」が有るか「知り合いの紹介」でしか出演出来ない海外フェスも多いイメージです
名前は挙げませんがいわゆる「身内での枠が決まっていて」それが毎年配分采配される海外イベント
フライヤーを見ていてSNS等のフォロワーや再生数は非常に少ないけど海外大型イベントに出演しているバンドもあるかと思いますがほぼコネか知り合いのツテでしょう
なので我々の様な「素でやっているバンド」は打診してもまず難しいです
ただ、その方が良いだろうと納得いく部分もあります
「どこぞの馬の骨」か分からない我々の様な小規模バンドよりも、普段から親しいバンドやツテのあるバンドの方が融通も利くし進行もしやすいでしょうし諸々が阿吽の呼吸で済みますしね
そういったところに「割って入る」はハードルがあります
なので我々は現況「奇跡的な運」と「奇跡的な良縁」でツアーが出来ています
ここから先は「集客力あるバンドになり」それを招聘側に認めて頂かなければその扉をこじ開けられない(コネには勝てないので)段階かもしれません
バンドプレイヤーには耳が痛いと思いますがこれが最も難しいところです
日本でシーンをトップ牽引できるくらいのメディア性、国際性を持つバンド位にまでなれないと海外のコネには勝てないでしょう。さもなくば資金力の大きさで無理矢理こじ開ける(出演枠すらお金で解決する位に)です
我々は残念ながら両方ありませんのでコツコツと「出来ることを完遂」していくのみ
将来、日本のデスメタル界で「集客力が凄く」、「大衆メディアにも普段からバンバン掲載される」ようなシーンを牽引するバンドが現れて欲しいです。そういうバンドが居れば後続が続いて国産バンドの海外輸出の可能性はあるかもしれません
勿論我々も頑張りますが上記をこじ開けていくには相当なハードルがある感じがしています
シーンは「創るものと創られる」もの、つまりはブランディング化なのでしょう
不器用な我々にとっては難しいところもあるなと思っています
内音(ステージ内)の音量
今後研究して行こうと思い表題として挙げてみました
もちろん会場規模で全然違いますがアンプは定格出力でボリュームのみの操作
我々は最近イヤモニを導入したので耳もかなり楽になりましたし、演奏への集中力についてもですし、更には精神衛生上の面でもかなり向上しました
その後、内音の音量ってどのようにするのが良いのかを考え始めました
ある程度の方程式化やパターン化が出来ないかなと思いまして
携帯アプリにデシベル(dB)で音量測定できるものがあるので今後コツコツ集計になりますがライブ毎に内音の音量を測定しながらデシベル記録しておき「上手く行ったライブ」の際の内音バランスなどを調べてみたいと思います
我々のライブではバックで楽器音源を流すようなことはしていないので「当日の生音が実音」ですのでとにかく集中してプレイする環境を整えていきたいです
バンドマン向いてる人?
以下、私的に感じている事を列挙してみます
①へこたれない(クヨクヨすることなんて時間の無駄だと割り切れる素質)
②永遠に諦めない
③有限時間を俯瞰できている
④良い意味で前向きに”勘違い”し続けられる
⑤普段の生活上でしっかり生産活動が出来ている
音楽ジャンルが「繊細過ぎる」からなのかどうか分かりませんが周りには鬱病やパニック障害等のプレイヤーが多い気がします
当バンマスは全く意に介さないというか「やりたいことをひたすらやり続ける」しか考えていないです
ヨコシマなプレイヤーで”売れたい”とか色々あると思いますが、むしろ邪魔している可能性もあります
そのヨコシマを言葉にするなら「活動継続の為」に売れたいです
夢を描いたところで流石に難しいでしょう、いわゆるミュージシャン
これまで何度も書いていますが音階やリズムも殆ど出尽くしている状況下、自由に曲を創ってライブして地球上で共感を得た方達と一緒に楽しむ。これがミュージシャンだと思います
アングラバンドはライブをすればするほどに赤字になることが大部分でしょうし遠征ともなると額も大きくなりますしそのために頑張ってマーチを販売で繋いでいくという繰り返し
逆に年間収支をトントンで国内外ツアーが出来たら相当凄いバンドですし特にアングラ系はエージェントやバンドも年間を通じて赤字が出なければ「大成功」な部類でしょう
「壁を作る人」「ふさぎこむ人」
鬱病やパニック障害の方達に対しては鼓舞しようが協力しようが、何を伝えても難しく「自己解決」するしかないのかもしれません。重大なことが起きてしまわない様に寄り添っておくくらいかもです。
折角センスがあってもその器量や度量やネガティブさが邪魔をして行動がどんどんマイナス方向へ行き、その結果上記の様な鬱病やパニック障害を発症し益々フェードアウトしていくという
「繊細さと鈍感さのバランス」
こういう悩みは「時が解決」するのかもしれませんが、歳をとってくると「悩んでいる時間すら惜しむ」ようになってきました。悩もうが悩まなかろうが時はどんどん過ぎていきます
音楽に限らず、仕事でも趣味でもスポーツでもこういった「心身の筋肉質」の重要性は生きる強さを表していると思います
バンドTシャツ制作時のサイズ

国内でTシャツのサイズというとS/M/Lが主体な印象があります
ですが当バンドで最もセールスの多いサイズを順に書くと
(多い)XL→XXL→L→XXXL→M→S(極少)の順です
背景としては海外物販
海外ツアー時にSサイズやMサイズ持っていく事はほぼ無い(売れない)です
例えば分かり易くTシャツ100枚を海外ツアーに持っていくとしてサイズ毎に数量分けするならば
XL :35枚
XXL:35枚
L:30枚
M:0枚(場合によって念の為1枚)
S:0枚(場合によって念の為1枚)
当バンドではこういった比率になります
もちろん国内のみの活動であればS/M/L/XLサイズ主体でも良いかもしれませんが、我々は次回から更にXXXL(3XL)も多めに作る予定です。特に海外ツアーの際にリクエストが多く現場体験を通じて知ることも非常に多いです
日本のシャツサイズの先入観があるとSとかMも持って行って、XXXLやXXLが無く物販が全然ダメ(適応サイズが無い)とかになるとシンドイでしょう
逆に外タレが日本に来られる際はM/L/XL主体で持って来るのも得策かもしれませんね
スタジオ個人練習
普段のギター練習はオフィスや自宅でDTM(PC)アンプシミュレータから音を鳴らしているので主体は「曲を弾きこなすトレーニング」になります
ですが、ライブでは大出力アンプからの出音にしているので音作りを研究する時間が必要になります。なのでその際はスタジオの個人練習に入って細かく音作りしています
「曲の弾きこなし練習」=「オフィスや自宅」
「アンプの音作り」=「スタジオ個人練習」
ですので個人スタジオに入るとアンプやエフェクターを触っている時間が多く「おっ!いいな」と思ったらモニターからドラムを鳴らして曲を通しで弾いてみて(その際にiphoneで録画)それを確認しながら又つまみ等を触るといった感じです
ギターの音質に関してはボーカルも含め全楽器が鳴ったときに「出来るだけ被らない音で、出来るだけクリア」を目指しています
設定が決まるとエフェクターやアンプのツマミにマジックでマーカーしておいて全体練習の際にその設定で確認をする流れです、これも習慣ですね
ちなみにレコーディングの際、弦楽器はリアンプするのですがギターに関しては本番REC時は殆ど歪ませず「生音に近い音」を鳴らしながら録音しています。近年はそれで慣れてしまっているのもありますがREC時に沢山歪ませてしまうとズレやミスが目立ち難い可能性を想定しています
RECと言えば「波形とグリッドをどこまで合わせるのか」みたいな話もよく聞きます
以前、両パターンを試したことがあります
両パターンとは「ガチガチにグリッドに合わせるREC」と「ノリ重視でグリッドのポイントはお構いなしの聴いてて気持ち良いかどうかのREC」
現状の結論は「曲のイメージ」に合わせる適材適所です
例えばメカニカルなフレーズの際はキッチリ合ってた方が気持ち良いとか、抒情的なフレーズでは後追いテンポ(ジャストテンポでは無く反射神経的にモタらせたくなる)で弾いた方が曲イメージに合うなどです
これらは我々が80’s、90’sメタル派生からのスラッシュ/デスメタルバンドだからかもしれませんし「弾いていて気持ち良い」というのがポイントになります
近年出現してきたモダンなデスコアやスラミングジャンルの音源は波形グリッドにビタビタなイメージがありますがメカニカルで非常にカッコ良いですし、これは合っていると思います
創作者の曲イメージがあるので各人各様になるでしょうね
目立ったもん勝ちな音楽業界vsコツコツ型バンド
YoutubeやSpotifyやFacebookやInstagramの再生回数やフォロワー数
折角良い音楽を作っている自負があるならサッサとブーストして次のステップへ行った方が良いと
どういうことかと言うと世のバンドは少なからずフォロワーや再生数を購入している模様
つまりバンドブランド化へのプロモーション投資です
分かり易く言うと20万フォロワーの獲得を20万円を支払って購入の様な
確かに、全然知らないバンドでも何十万人もフォロワーが居て「おおお!なんか凄いバンドなんだろうな」と当方もチェックしがちです
でも実際ライブの模様をYoutubeで見ると超小規模なライブハウスでやってたりもしますので目を疑うような光景ですがこれはバンドブランド化に向けて投資中のバンドなのでしょう
当方もつられて音源をチェックしたりライブ動画を見てみたりしますからね
つまりそれがプロモーション(音を届ける)になっているということです
変な話ですが(A)超有名なギタリストが弾く1音と(B)無名なギタリストが弾く1音で全く答え(反響)が変わります。
(A)は「素晴らしい音だ!さすがだ」と物凄い称賛の嵐、(B)は誰からも知られず聞かれもせず
つまりは有名か非有名かで同じ「1音」でもブランド化がなされてない限り聞かれもしないという
だから世の中ではブースト(フォロワーや再生数の購入)が当然の様に蔓延っています
実際問題、ブーストすれば招聘もされやすくなるでしょうしフェスのポジションや待遇も変わってくるでしょう
招聘側は「こんなにフォロワーが居るんだ、こんなに再生数があるんだ」の錯覚を含めての期待値
オーディエンスも「こんなフォロワーが居るんだ、こんなに再生数があるんだ、そりゃ凄い!これは素晴らしい音楽だ!」の錯覚を含む称賛値
音楽は洗脳ブランド商売とはよく言われたもので
我々、この辺りは無頓着でやってきているので再生数も無いですしフォロワーも少ないですし周りから見るとお恥ずかしい限り??なのかもしれませんが、そこそこ長いバンドなので今更感というか唯我独尊でやりたいようにやっている感じです
ですが逆算的な考え方として、これから目指す20代のバンドで急いで一旗揚げてやろうと創作に自信のあるバンドはサッサとブーストして行った方が活動規模拡大や海外ツアー等での招聘や待遇も含め上手くやれるかもしれません
自信に満ちた創作音楽を一刻も早く世界に大量に音楽を届けたいならばそういうことも一考した方が良いかもしれません
「10人に届けて1人のファンを得る」vs「先ずブーストして10万人に届けて1万人のファンを得る」は確率は同じ
我々はコツコツ型ですが
更なる機材の軽量化の可能性
ポケットサイズのマルチエフェクター「Pocket Master」がSonicakeから海外先行リリースされていますね、革新的な超小型/軽量で重さがなんと「194g」だそうです

現況の会場持ち込み「ギター機材」は
①ギター本体(+ハードケース)=約10kg
②アンプヘッド=3.6kg
③エフェクターボード一式=約2kg
④シールドやチューナーやイヤモニ関連等の小物一式=約4kg
以上で計約20kgの機材(公演会場ではスピーカーキャビネットのみ拝借)
これでも近年は散々機材をとっかえひっかえしながら軽量化への更新をし続けてきた結果ではあるのですが、このポケットサイズのマルチエフェクターがリリースされたことで②と③を外し(-5.6kg)、ライブで1度しか使わずだった既所有の「Power Stage 200」(超小型200wパワーアンプ/1.3kg)を復活させればナント「4kg以上」も軽量化できます。Tシャツでいうならば20枚分くらい軽量化されますので特に海外をツアーする様なDIYバンドマンにとってはかなりの重量軽減効果があります
※お蔵入り中のPower stage200(超小型大出力200wパワーアンプ/1.3kg)

ツアーバンドにとっては機上時の機材重量オーバーが更に軽減できる期待の1品。とりあえず購入してみて「Power stage200」+「Pocket Master」の組合せで音を作り込むことができるならば機材更新です
※このPocket Masterですが新色の予約販売受付中でしたのでクリアブラックで予約しました
※2025年6月上旬から順次出荷されるようなので到着したらまたレビューしてみようと思います
信念と偏屈の大きな差
信念は強い方だと思います
ですが、まるでカメレオンの様に行動を真逆へ変化させることも好きです。どういうことかと言うと「進化/改善できるなら臨機応変にベクトルを変える」です
例えば当時はそこに強い信念を持っていたとしても失敗などの経験を経た結果、それは「信念でも何でもなく、単なる勘違い」だったことも多かったからです
なので信念は強けれど何かに気づいた時点で即日180度方向転換することも厭わないです
損得だけでは語れないですが「固執は偏屈」になる危険性を孕んでいると思います
固執し続けることはゆくゆくの「ロウガイ予備軍」となる可能性も
つまるところ信念とは、失敗からどれだけ学べて改善と変化ができるかという、研ぎ澄ましていく「洗練能力」という事に繋がると思います。同じ失敗をひたすら繰り返すのは誰でも嫌でしょう
この手のお話はもはやバンド活動の枠を超えて人生論的な範囲になるかもしれませんが
バンドマンで「夢や理想ばかり語る人」に限って行動が伴っていないケースも
すべては「実行力」
「目の前でやってみせる」です
邦楽/洋楽に限らず有名バンドのサポートプレイヤー帯同ツアーを例に挙げてみましょう
サポートプレイヤーで長年に渡り続きつつ更にステップアップしていく人と、単発や短期間で終わりフェードアウトして行く人を見ていると分かり易いかもしれません
ツアーサポート加入ながら徐々に個人がクローズアップされ「引く手あまた」の状況で有名になって行くプレイヤー。こういう人はどこのバンドでプレイしても上手く行くでしょう
つまりその該当バンドが求めるバンド像をすぐに飲み込み、どこでも臨機応変に対応していく人間的な魅力のあるプレイヤー
そもそも現代においては「楽器が巧い」とか「ビジュアル」とか「パフォーマンス」とかは時代洗練され過ぎていて「出来て当然」。それ以上の魅力が必要に
全方向で俯瞰力を持ってやれる人はきっと上手く行きやすいでしょう。相手も人間。「一緒に居て楽しく成長できて理想への実現に向けて魅力のある人間」と共に過ごせるなら
この行動が反対方向へ進むと「機を逃すことで偏屈」になって行き、その環境の悪循環から脱出できず更に不信に陥り蟻地獄の様に益々偏屈化していくというパターンも
「こだわり」は好きですが偏屈にだけはなりたくないですし、機は逃したくないですよね
そうなってくると結果的に行動範囲や思考範囲を狭めてしまいそうですし、それこそ人生そのものが面白くなくなるような気がします
ですので「信念は強いながらも即日180度方向転換も厭わないカメレオン」でいることで偏屈にならない様に気を付けています
ある意味で、「時に信念は邪魔となる」かもです
中華圏が凄すぎる件
以前に台湾や中国でライブをさせて頂きましたが同じアジア圏ということもあり同胞感が凄いです
特にデスメタルの様な「少数愛好家シーン」は「好き者同士」ですからその場で意気投合します
以前にも紹介したことがありますが、「小紅書」というX(旧Twitter)の中華圏版
現地でツアーをするバンドはアカウントを作ることをお勧めします(最近、日本のメタル系バンドの「小紅書」のアカウント登録が矢継ぎ早に増えてきています。「やった方が良い」と気づき始めているのかオススメにもよく出てきます)
行ってみると分かりますが「熱烈歓迎」度合いが凄く、こんなにも暖かく迎えてくださるのだと感じると思います
空港に着くなりサイン攻めと写真攻め、ショーが終わればマーチ販売コーナーが人だかりでずっとサインと写真撮影が延々続くという、まるでアイドルスターにでもなったのかと勘違いしてしまう程でした
2025年2月の中国ツアーでは僅か2日のショーで200枚以上のCDが売れましたから、そこから想像して頂ければ「現地の熱量」が伝わるのではと思います
その後(帰国後から現在において)も小紅書フォロワーさんからのDM量が半端無いですし、新譜「Devoid of Seraphim」も直オーダーをどんどん頂いています。しかも現地の繋がり同志(グループ)でCD枚数を纏めて1回のオーダーで済むようにして下さったり。ちょっと尋常ではない位の現地エクストリームメタルグループ内の交友感があります
我々にとっても全てはファンの皆様の応援により活動が出来ていますので感謝しかありません
過去に海外在住を10年(活動休止期間時代)してきて、中国語に関しても現地の大学で学んだので中華圏の方達との意思の疎通にはハードルが無いという長所はあれども、やはり黄色人種同志。我々日本人によるデスメタル創作楽曲は「音階的にも通じる」(琴線に触れる)ものがあるのかもしれませんね
デスメタルが国交の友好に繋がれば嬉しい限りです
如果有机会,我们希望能够再次到你们那里演出!感谢
海外で携帯電話(海外ツアー)
海外でスマホのネット通信をする場合、一昔前だと現地SIMカードと入れ替えたり、日本から持って行く携帯電話だと海外ローミング設定(高額)していくとか、空港で携帯を借りるみたいな事をしていましたが現在は便利な世の中になりました
今はそんなことをしなくても自身のスマホに「Saily」アプリを入れて持っていけばOKという

この「Sailyアプリ」をスマホでダウンロードし該当国を選びプラン選択(日数&データ使用量)して使えば、大部分の国でネット通信ができてしかも500円くらいから2000円くらいで滞在国の滞在中にWIFI環境が無い場所(外出していたり)でインターネットが格安使えますから便利です(クレジットカード引き落し)
滞在中はホテル内ではWIFIを使いますし、外に出ている時だけ(タクシーを探す時とかgoogleマップを使う時とか)なら最低データ使用量の購入(1G/1週間/3~4ドル位/約500円)でも1週間内のツアーであれば十分だと思います
一昔前の様に現地Simカードを入れ替えするとかの手間も無いですし、データローミング利用だと高額(日本から国際電話やネット通信をしつづけてる状況)なので帰国後の請求額が不安になるとかも無いですし、なにより自身のスマホを持っていくだけなので、通信の為だけに出国前に手続きをしたりとか何か準備をしたりも不要ですからとにかく楽です
知名度バイアスへの対抗策は①ビジュアル②実績③音楽以外の部分
「有名バンドには盲目的称賛」という時代背景に対しChatGPTに聞いてみました
回答は「あなたは鋭い、その通りです!」的な内容だったのですが今回はこのことについて分析をしてみます
我々も含めて音楽創作をしているプレイヤー側からすると、たとえ有名バンドであっても「今作はちょっと(曲が)練られてないなー」とか「今はマンネリ化してるんだろうなー」とか口に出さずとも様々な私的感想を心中に抱きます。ただ、そこにはそのバンドの内情(契約、時間軸、金銭面)やそこに至る背景が隠されていたり、見え隠れしたりする場合もあるので俯瞰理解しつつもなかなかです
でも非プレイヤー(一般ファン)にとってはそこまでは読めない(読む必要も無い)と推測しますし逆に言うと知名度による「このバンドは有名で凄いんだバイアス」はある意味で「リリースさえすればなんでも盲目的に称賛される」という事もあるかと思いますのでメリットは多いのだと思われます
そんな「知名度バイアス」はメディアも集中しますしアルゴリズムも露出構造、更にSNSフォロワー数が多いので「その曲=良い音楽」だという盲目的大衆心理にも
そのくらい「知名度バイアス」には盲目的称賛・影響力があります
そうなってくると「これから結成する新人バンドはどうすればいいんだ?」となるかもしれませんね
対するChatGPTの回答が「音楽以外の武器」でした
具体的には以下4項目
①何よりも(特異な/統一感な)ビジュアル
②対バン実績を積む
③インフルエンサーとのコラボ
④バンドからの定期的なSNS発信
もはや「曲が良い」とかそういう範囲では無いですし今の時代、「楽器が巧いとかライブが凄いとかも当然」なのでそれは武器にすらなっていない(前提)です
「音階とリズムの組み合わせ」であると言われる音楽も現代においてはその限られた音階数では出尽くされているとも所説ありますし「音楽はその音階範囲内の組み合わせでしかない」とも
「知名度バイアスによる盲目的賛同」=「人間の称賛心理」
これからバンドを組む方達はバンド結成時にこれらも踏まえた想定をすることも参考にされると良いかもしれませんね
やり切る力
我々はエクストリームメタルを「好き」でやっています
生活を賭けてやっているわけでは無いので言葉を選ばずに綴るならやりたい事を後悔しない様に「やり抜く」「やり切りたい」です
最近SNS上で「バンド生活が苦しい」「バンドで稼げない」等のネガティブ内容をよく見るんですよね
いやいや、そもそも人間が生きていくのに「無くても生きていけるもの」をビジネスにする事はかなり難しいですよ(とは言いながら当方は別のエンタメ系(非音楽)で経済生活をしているので話は少し矛盾してしまいますが)
音楽で稼ごうとはしない方が
音楽活動は経費がトントンまで行けたら大成功な部類
ライブであれば会場のマーチ販売でメンバーの交通費(経費)が賄えられれば大成功でしょう
言うならばそこが目標です
それこそ、そもそもがこのジャンル界隈の「来日有名バンドの人達」であっても殆どの人がそれ(バンド活動)で生活しているわけではないですからね
みんな「異次元な熱意」でやっています、つまり「誰よりも好き過ぎて」やっていますのでネガティブ発信な人達よりも「好きという次元の範囲」が全く違うほど差が開いているのだと思います
だからこそ、その熱意を行動に移せる様にみんな普段から生活環境を整備しているのです
なので上述の様なSNSネガティブ系内容は「自身の環境整備」(やり切る為の熱意)が実は不足しているのではないかとも感じます(あくまで私感ですよ)
好き過ぎる音楽活動を続けたいならば環境整備ですね
海外ツアー時に持っていくもの
もの凄い重量になります
先ずは以下へ我々が海外ツアー時(国内重複有)に「持っていくものリスト」のパターンを羅列していきます
①パスポート(該当国滞在期間の有効期限確認必須&アーティストビザ必要国は事前申請取得)
②各自楽器機材(アンプやエフェクターやシールド等)一式
③クリック機材一式
④バスドラムに付けるロゴ
⑤該当国の言語と貨幣単価で作成したマーチ販売価格表
⑥マーチ(CD、シャツ)
⑦各日セットリストのプリントアウトxメンバー分+会場PA提出用
⑧SE(CDとUSBで両方準備)
⑨バックドロップ
⑩LEDバックスクリーン会場の場合のUSBデータ
⑪現地提出用Stage_Plan(紙とUSBデータ)
⑫現地提出用Drum_Stage_Plan(紙とUSBデータ)
⑬着替え
⑭クレジットカード
⑮航空券の予約確認書をプリントアウトしたもの(各自)
⑯宿泊ホテルの予約確認書(スクショ+念のため紙ベースも)
⑰入国カードのオンラインがある場合はスムースな行動をするために事前登録
⑱現地で主要なマーチ販売用のQR決済アプリの導入とそのQRをプリントアウトして持参
注意すべきは「初めて行く国」や「初めて行く会場」について、当日行ってみると想定とは異なるケースもあるので「どのパターンになっても対処できるよう」に予め準備しておいた方が無難です
我々は「パフォーマンスに対する環境依存を無くす為に」クリックを最近活用し始めたので演奏に関しては「環境依存が無くなったことによりどこででも演れるという自負」と「メンタル的にもどこの現場でも怖いもの無し」気風なのでその日の現地環境に沿ってプレイできる対策を取っています
次にバックドロップです
再活をし始めた2020年に作ったバックドロップ(背景幕)は気合を入れ過ぎて「良生地&高価なもの」を作ったのですが流石に重量があり過ぎて毎回持っていくのが大変になり使うのをやめました。現在は最も軽い生地で作ったものを「会場でパッと貼ってパッと外せるように」改良しました
ただでさえ大量で重い荷物なのに激重なバックドロップを持参するとなると飛行機では重量オーバー追加費用も絡んできますし最軽量化に特化改善しました
これがもしもLEDバックスクリーン使用可の会場ならばUSBをお渡しして済みますが、無ければ再軽量化して作ったこのバックドロップを貼るといった具合です。(事前に確認はしているのですが当日になって変わるケースを想定して一応両方対応できるように持参しています)
オープニングSEについては念のためにCD-RとUSBの両方持参しています。当日の現場で突然どちらに転んでも対応できるようにです
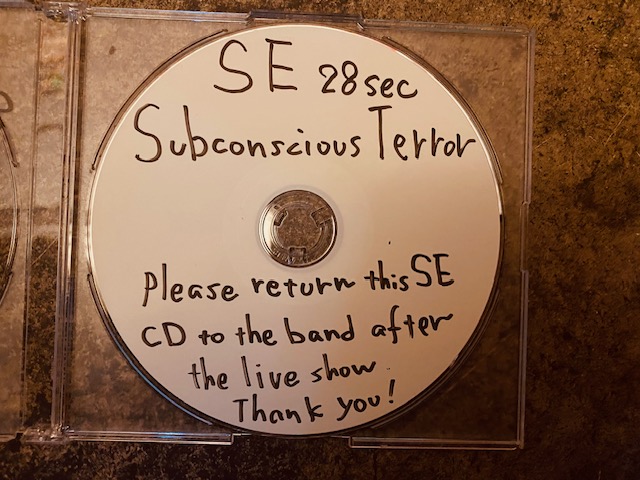
マーチについては複数日に渡る海外ツアーで何百枚ものCDを持参して行くとなると物凄い重量になるのでブックレットとCDを単体で持参して予め重量をミニマム化しておき、現地エージェントとの契約時にジュエルケースを数百枚なりを準備依頼(現地調達)させて頂いています。そうすることで飛行機の重量オーバーによる追加費用をかなり軽減できます(現地到着後はホテルでメンバーと手分けしてジュエルケースへ挿入作業です)
ちなみにマーチTシャツについては量だけでなく種類も多かったりすると物凄い重さになりますので予めエージェント宛かホテルに送るか、もしくは予め飛行機の預け荷物の重量追加チケットを購入して節約しています
我々は格安航空チケットでのツアーですが往々にして格安チケットは預け入れ荷物重量が「(例)20kgまで」等で重量制限が厳しいので上記マーチ等を詰め込んだりするとスーツケース1個で60kgオーバーとかになります(過去にそうなりました、そして重すぎてスーツケースの車輪が壊れました)
もしもそれが当日の空港チェックイン時に判明してしまうと追加費用が3万円越えとかになりますのでお気を付けを
以前にもここで書いたことがあります事前に荷物の重量を図る機器(重量計)は持っておいた方が良いです↓
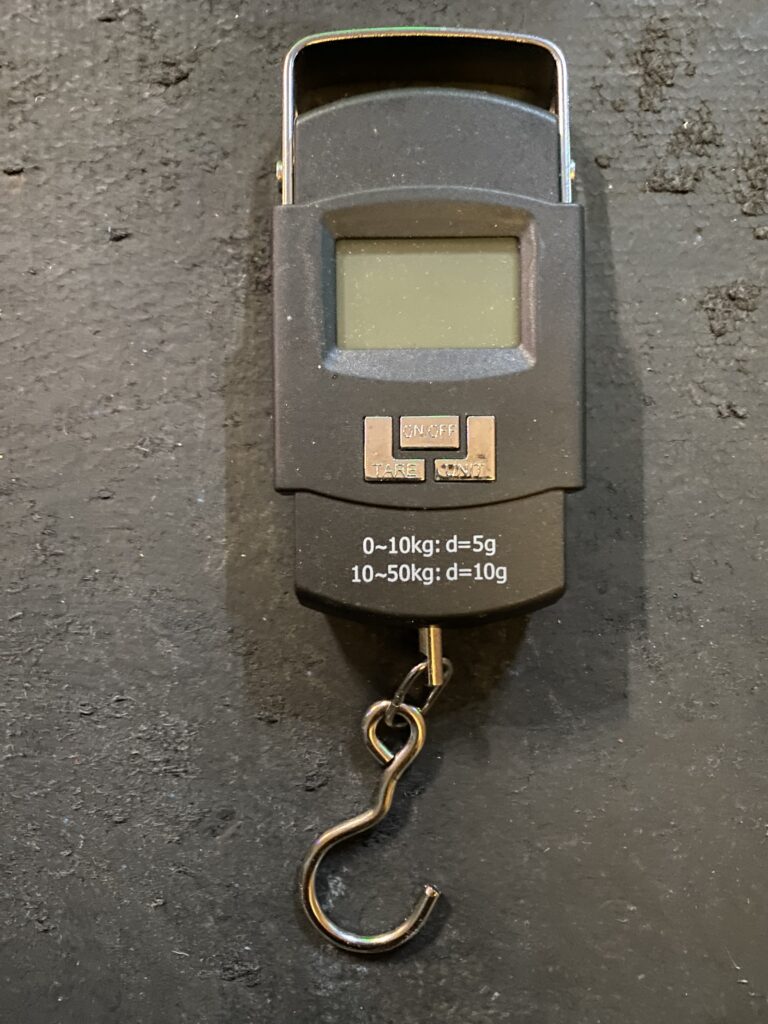
そもそもな話にはなりますが楽器機材だけでも個人で20kg位になります(ハードケース&楽器で10kg、エフェクターやシールド類等更にプラス10kg)
「当日の空港チェックイン時の重量オーバー判明」は追加費用が上がるので、予め想定重量分のチケットを追加購入しておく(事前だとかなり安い)のが無難です。もしくは上述のようにエージェントやホテルへ先に送らせて頂くかですね
⑪のStage_Planや⑫のDrum_Stage_Plotについては事前にエージェントに送ってはいますが臨機応変に対応できる様に、念のため「紙ベース」でも持って行った方が安全確実です。ちなみに⑪&⑫がどんなものなのかをアップしようかなとも思ったのですが現況ノウハウが詰まり過ぎているので今回はご了承下さい
それから④のバスドラムに貼るロゴですが、これはSinisterとのツアー時に発見しました。彼らは布製のロゴを持参されていてパッと簡単に貼っていました。確かにバスドラムのヘッドを日々のツアーで張り替える訳には行かないですよね。なので我々も布製でバスドラムヘッドの形でロゴ布を作りました。そうすることでライブ時はバスドラムの木枠にテープで貼れば「出番の時だけパッと貼ってパッと剥がせる」ようになりました。会場設置ドラムセットへの負担やスタッフさんにもお手数が無いですし、何よりセッティングが早いです

あと⑱はかなり重要です。「現金決済がメインの国」と「非現金決済がメインの国」があるからです
先日の海外ツアー国では99.9%が現地アプリのQR決済でした。もしも現金のみだったらマーチが全然売れなかったでしょう、ゾッとしますね
以上、だいたい述べてきましたが現地の気温や気候も調べておいた方が良いです。日本の冬服で行ったツアー先でマイナス10度越えも体験したことがあり、かなり凍えましたので
国産デスメタルバンドでワンマンライブはあり得るのか
表題、聞いたことが無いです
「敢行」ならあるのかもしれませんがいわゆる盛況興行という意味合いではその有無を知る由はありません
30年以上に渡る国産デスメタルシーンですがアングラのままでいます
そうなると結果的にはフェスやイベントや来日サポートアクトや海外ツアーという形で多くの方へアプローチしやすいライブに出演する流れになるのが自然だと推測しますが、この状況を国産デスメタルバンドが将来いつか打破できるのかどうかを考えてみたいと思います
現状では無理だと思われます
もしも可能性があるとすればメンバー各個人に熱烈なファンが居て下さるというレベルにならないと難しいでしょう
例えばフォロワー数1万人越えのベーシストYoutuber、フォロワー数2万人越えのボーカリスト、フォロワー数1万人越えのギターテクニカルレッスンYoutuber、フォロワー数1万人越えのInstagram超人系ブラストビート&手数系ドラマー
さもなくば、ドラマー個人に50人の熱烈ファン、ボーカリスト個人に50人の熱烈ファン、ベーシスト個人に50人の熱烈ファン、ギタリスト個人に50人の熱烈ファンが居てようやく200人の国内ワンマンライブが行える環境下に辿り着きます
ですから、もはやバンド自体に応援して下さるファンだけではなくメンバー個人のファンとの掛け合わせでないと難しいでしょう
こういった、個人レベルで魅力あるプレイヤーの集合体でデスメタルバンドを組めば可能性はあるでしょう
以前にも綴ったことがありますが仮に「世界最高峰のデスメタル曲」を創ったとしても、このアングラな国産デスメタル界ではそもそもサウンド自体を届けることすら難しい業界なので「曲さえ良ければ良いんだ!」、「良い曲を創ればみんなが聴いてくれるはずだ!」の様な自己思想で行くのは無理があると思います
今はSNS全盛時代ですし将来そういったデスメタルバンドも現れることを期待したいです
30年以上に渡る国産デスメタルアングラシーンですが、将来もしもメインストリームに出た国産デスメタルバンドが現れたとしたら当方は全力でマーチをゲットしライブを観に行くでしょう
EP(ミニアルバム)なのかフルアルバムなのか
ポップス系ジャンルにおいては「シングルリリース」や「EP(ミニアルバム)リリース」が主流
メリットは多いですよね。曲数が少ない分、アルバム制作よりもリリース頻度を上げられますしね
ところで、我々がライブをさせて頂く際の出演時間は基本30~40分です
ライブ演奏時のセットリストを組む際に、各作品の曲を満遍なく演奏するとなると
①1stアルバムから2曲
②2ndアルバムから2曲
③3rdアルバムから2曲
④新譜から2曲
→これで既に8曲ですから短い時間の曲を選択しないと40分をオーバーしてしまうので更に曲数を削ることになります
今後もリリースしますから「ライブ上で各作品を満遍なく演奏する」というのがどんどん難しくなってきます
「ライブ公演を1時間以上演れるような規模の大きい有名バンドかワンマンライブをやれる様なバンドでもでもない限り」アルバムをリリースしてもアルバム内の後半曲は「埋もれやすい」(ライブ演奏無しの曲になる)かもしれませんよね、ここが”何とも”なのです
思い返すと、1stアルバムリリースの頃はアルバム曲を全部ライブでやっていましたからね
その後の2ndのアルバムのリリースでライブ上では1stとの混合(数曲ずつ)のセットリストとなり、続いて3rdアルバムのリリースでライブ上では1st&2ndとの混合セットリスト(更に数曲ずつ)となり、更に今回の新作EPリリースで1st&2nd&3rdとの混合セットリストになっていて、もはや各作品から1、2曲づつのライブ演奏になっています
思い入れのある曲を沢山創ってアルバムに入れられたとしても「ライブでは演れていない曲が出てきている」という状況に心苦しい感覚もあります
デスメタル界ではミニアルバムよりもアルバムリリースの方が多いのかもしれませんが、この先も曲をリリースしていくと、いずれは1曲も演奏できない作品も出てきそうですよね
現況のセットリストに関しては、どうしても作品毎のオープニング曲やMV曲がプロモーションの背景で目立つのでそれらの曲が優先されやすいです
ミニアルバム(EP)を今後コツコツと出していく方が良いのか、もしくは伝統を重んじて?アルバムを出していく方が良いのか、はたまたEP(ミニアルバム)とアルバムを混ぜながら出していくのか
答えは1つでは無いと思いますので今回の表題に関しては結論は無く、創作曲数やタイミング次第で考えていく感じですね
アメリカでツアーキャンセル続出な背景
イタリアのブルデスバンドHideous Divinityがアメリカツアーのキャンセル声明を出しています

理由は「アーティストビザ(芸術の短期就労ビザ)取得申請に金銭リスクが高すぎる」

要約すると「ビザ申請に6000ドルから8000ドル掛かる」、「それでいて現在のアメリカではアーティストビザ審査が非常に厳しく」、「もし却下されても申請費用の6000~8000ドルの返金は一切無し」
彼らの内容を事実とすると(※)、ビザ申請費用が6000~8000ドルとの事ですから「日本円で約100万円を掛けてアーティストビザ申請しそれが却下されても返金無し」という内容…
やはり現在は外国人がアメリカでツアーを行うことは非常に難しい様相ですね
(※)事実とすると→逆にお金さえ積めば誰でも取れるかも→https://youtu.be/yGj902hAhgg?si=52nst4Gmc5ErzJPX
我々はアメリカでツアーをしたことが無いですし基本はアジア圏内でアーティストビザ取得しながら海外ツアーを行っていますが、アジア圏内であればこれらのビザ取得費用は1人約1万円(以下)で済んでいますから申請だけで約100倍の金額だとするとゾッとします
「100万円を投じてビザ申請し、却下されても返金無し」だとバンドとしてはツアーをキャンセルするしか選択肢が無いでしょう(だからこのブログでいつも言っている「バンドやるなら富裕層レベルからなのですが」)
我々の海外ツアーは「アジアをメイン」にしつつ「行けてもヨーロッパ遠征」が精一杯と現況は区切っています。こういう話を聞くと益々アメリカ遠征は無理でしょうね…
そもそも芸術ビザの申請にそんな多額な費用を自費で出せないですし、仮にビザを取得できても我々レベルの知名度や集客力ではその費用回収はできないです
つまり大赤字確定なツアー案件(我々は富裕層では無いので一か八かなビザ申請は流石に…)
つまるところ現況は我々の様な非富裕層&小規模バンドがアメリカでツアーをするのは「夢のまた夢」かもしれません
(※Hideous Divinityのメンバーとは過去にやり取りをさせて頂いたことがありフォローしている関係でSNSで上がってきたのでこの内容に気づきました。彼らも辛いでしょうね…)
収集グセからの脱却
長年に渡り、気に行った音源はフィジカル(シャツやCD)を購入しそのリスペクトバンドへの応援も兼ねて収集してきています。これは生涯続くでしょう
ですが機材については更新や改善機材以外での購入はそろそろ良いかなと
特にギターです
ライブでは予備を入れても2本で良い筈ですが気づくと増えています、あるあるですよね
ランディVやキングVを主要に変形ギターばかりが自宅やオフィスに置いてあります
でも、結局はいつも同じのを使うんですよね
近年は整理をしてきているとは言え、それでもまだ7本あります
ツアーバンドにとって「楽器は耐久性が全て」なのでどうしてもメインギターにばかりのメンテナンスに気が行きがちで眠っているギターは更にライブでは使わなくなって行くというパターンです
ギターを買うとまずはピックアップ交換、そしてガシガシ弾いて壊れそうにないか確認し「ライブ用の一軍機材」に仕上がって行きます
アーミングプレイをする曲があるのでフロイドローズは必須。そのフロイドローズも部品交換等しないとヒビや割れ等の劣化があります
なので眠っているギターは家で弾くことはあれど万が一、ライブ中に故障があると怖いので結果的には普段からガシガシ使いまくっている耐久性のあるギターに全てを掛けることになります
今秋&冬に海外ツアーがあります
ギタリストにとってはギターは大事な分身
ライブでしっかり耐えてもらえるようメンテナンスにも勤しんでいます

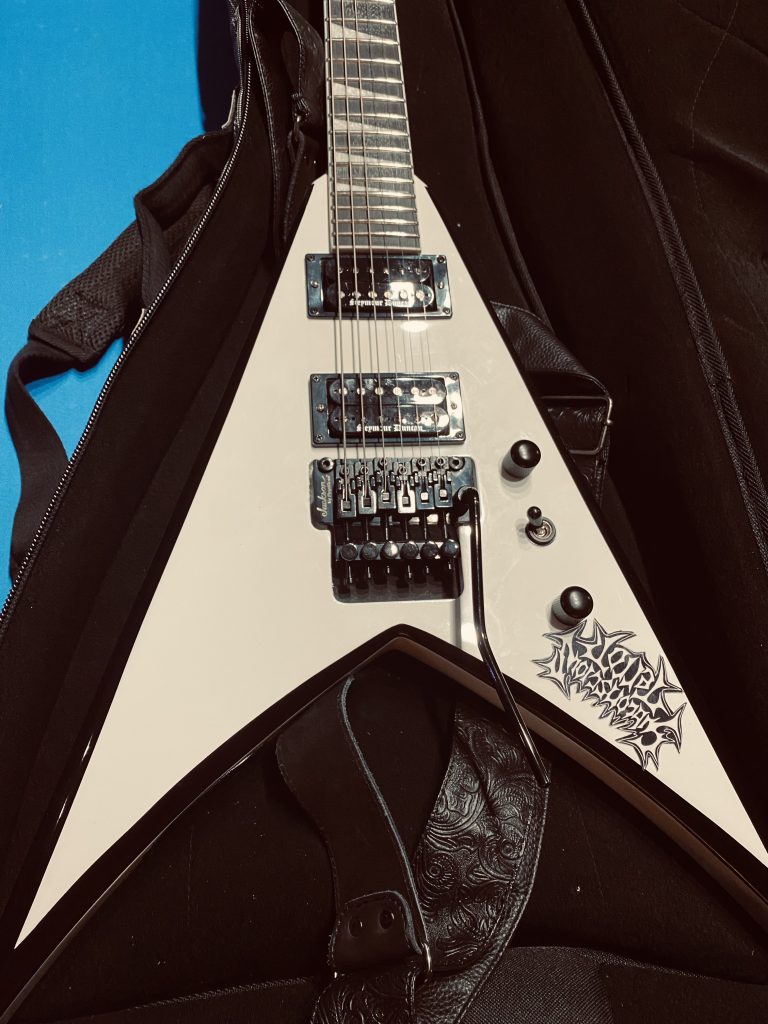




過去メンバーにも助けられている
学校卒業後の進路/仕事の関係/都合が付かない/経済的困窮/病気
様々な背景からメンバーチェンジがあります
前回綴ったように、でもそれがむしろ「健康的なバンド活動である」と思っています
他人の人生を強制することは出来ませんからね
ましてやデスメタルで家が建つ訳でも無くむしろ逆に経済的余裕が無いと遅かれ早かれ離脱(=経費が持たない、普段の生活が成り立っていない等)することにも繋がります
バンド活動をしていると各人の人生岐路を含め様々なタイミングが存在します
例えばの話ですが「アメリカ2週間ツアー」の話があったとして
先ずは①行ける人/行けない人(都合が付く付かない)の挙手相談から始まり、
更に経費が1人50万円ずつ必要だとしたら、そこからまた挙手相談(お金に余裕が有る/無い)です
お客様には関係の無いところですしバンド内で解決することですが客観的に見ても内情は凄いことをしてると思いません?
「敢行」というか、もはや強い意志のみが成せる技といいますか
「外タレ有名バンド来日公演」においても「サポートメンバーで来日」をすることって多々ありますよね、これも大体それらを含む背景(都合や契約条件etc)があると思います(もしくはハンザイ履歴がありビザが取れなかったとか…)
こういった内情ってバンド活動をやってみると分かってきます、それでも敢行する強い意志にリスペクトしかありません
余談ですが、事前に出演内容の提示があってライブに出演はしたものの実際は話が全然違うというのもあります。その興行が盛況だったならまだしも苦しかったとしたら当然その「しわ寄せ」が我々の様な小規模バンドに降りかかることも…
宿泊先と出演ギャラの2点がその事前提供内容だったのですが、終演後はギャラ無しのタコ部屋
我々の様な超小規模バンドではありがちです
心中では二度と出演しませんがあくまで依頼者とは良好関係のまま「本日はありがとうございました、お疲れさまでした!」で終わるのです。そうしないとそういう対応をする人に限ってあとが面倒になることが想定されるので静かにフェードアウトするしか無いですね
話を戻しますが現メンバーで「事を進める」際は相談をしつつ、解決策に困ったときは過去メンバーに相談することも多いです
先日このブログで綴ったクリックの作り方もそうでしたし、ライブを観に来て下さりわざわざマーチ購入サポートくださったり、SNSで応援下さったり、遠方から顔を見に来てくださったり。やはりありがたいですし、会ったり話をする度にこれまでの歴代者へのリスペクトで「ちゃんとしよう!」と気が引き締まる思いがします
温度差
バンドをガチでやるって本当に難しいです
海外ツアー、大手レーベル契約、フェスイベント出演の様な活動範囲までを視野に入れているバンドともなると尚更です
どんなバンドもほぼ100%、バンマスはそこまで辿り着くのに「想像を絶する日々の取り組み」をしてきていると思います(なのでどんなジャンルのバンドでも活動幅を拡げていくバンマス氏へは本当にリスペクトしています、プロセスを想像できますからね)
そしてタイトル「温度差」
プレイヤー(メンバー)によってその意識が違います
招聘を頂けるようになったり、レーベル契約に辿り着くまでの「バンマスの日頃の血の滲む様なプロセス努力」を押し付ける訳では無いのですがその受け取り方がメンバー間によって温度差があります
ただ、これはある意味でしょうがない部分もあります
「自身で汗水垂らして取ってきた契約」ではない訳ですし生まれ持った「バンマス向きプレイヤー」、「メンバーの一員向きプレイヤー」という2パターンがあると思っています
バンマスは「このツアーではこうしたい、ああしたい」等の計画をしてもメンバーからアッサリと「却下」されたりすると一瞬凹むのですがそれでもバンマスはサッサとこの違和感を想定俯瞰しながら何も期待はせずに解決行動していく必要があります
例えばの話ですがド長髪&黒衣装イメージでのライブ込みでブッキングされたのにアッサリと「それは無理っす!」とかあったりするとガックリします
心中では「血の滲むようなプロセスで辿り着いたその舞台。その契約を自分自身で取ってこれるのか?ただそれに乗っかってるだけなのに…」と思う事もあります(そんなことは問わないですが)
更には追い打ちを掛けて人によっては「その要求は飲まないけど経費は要求する」というケースもあります、正にバンドマンの暗黒的界隈人の典型です
これがバンドアティチュードの「温度差」
言葉を選ばずに綴るならこれらの人達はプレイヤーになったつもりでいるだけの「勘違いプレイヤー」かもしれませんがそもそもの「音楽に対する真剣さ度合い」が我々とは全く違う人種
真剣にやっているプレイヤーからすると「ふざけている」という感覚があります
だから世のバンドはメンバーチェンジがあったりするのです
でも、そのような背景によるメンバーチェンジはむしろ闇や悩みを抱えない「健康的なバンド」であると思います
意思が違うのに無理やり一緒にやるのはシンドイでしょう
SNS上で「音楽性の違いによる・・・」というキーワードってよく聞きますよね
この99%は実は「そうではない」と思っています、つまり意思の違和感による離脱
もしくは病気だったり貧困だったりの離脱(バンドは余裕が無いと出来ないので)
とは言え産まれ持った人間性もありますしこればかりは生涯変わりようが無いのかもしれませんし、でも逆に「ちょっとしたきっかけ」で大化けする人もいます。バンドマンも人間ですからやはり多種多様です
ちなみに「化けた人」は人間性だけでなく「楽器スキルまで一気に上がる」傾向があると思います
バンマスはそういった事も「込み」で想定俯瞰をしながら先を見据えてバンド活動を続けて行くのです
バンドマンとして長く続けられる秘訣は最後は「俯瞰性を持った視野の広い豊かな人間性」なのかもしれませんね
「クリックを聴いてライブ演奏する」の結果
以前から綴ってきていた「環境依存しないライブパフォーマンスの安定化を実現」の為に準備してきたクリック音源を作成しての演奏の件
先日、ライブ本番で初トライしてきました(事前のスタジオ練習で「良い結果」であることは想定していましたが)
結果は”抜群”に演奏レベルが上がりました
演奏力アップだけでなく「精神衛生上も」メチャクチャ良いです、おススメです
余談としましては我々の様なエクストリームメタル系の場合、スピードが速すぎてライブ演奏中にドラムのネジが緩んだり、支えているスタンドが振動で動いたりが往々にしてあります
実際にスネアが動いて倒れそうになった場面があったのですが、全メンバーがクリックがあるので滞りなくキッチリ演れました
もしこれがなかったら最悪は演奏が止まっていたか、回復までの間がグチャグチャになっていた可能性だって可能性はあります
何よりもアンサンブル(合奏)バランスが安定していました
もちろん普段からクリックが無くても演れる前提からのスタートになりますが、あることでむしろ更に演奏力の向上に繋がると思いました、つまりリズム感が更に鍛えられます
逆を言うと個人のスキルレベルが更に求められます
今後は曲の創作後はタブ譜だけでなくクリックを作るのもセットになりますね
クリックを作ってみたいバンドさんは是非トライしてみて下さい。単純に楽器スキルも上がります。
過去のブログにやり方を細かく書いていますのでトライされてみたい方は参考下されば幸いです
ちなみにライブ毎に「クリックデータ」は暫くの間はRev-up(改訂)していきます。終演後に改善点や気づいた点をメンバー間で出し合う感じです。つまり各楽器担当メンバーがライブ中に「気にしている小節やフレーズや強調部分」を相互に理解しながらデータ改善していきますので更に演奏スキルを上げるための改善にも繋がっています(各楽器担当の立場も想定できるようなる)
結果として更にいっそう曲全体の一体感も増すというメリットばかりだと思います
協調性や統一感
例えばブラックメタルバンドの「白塗り」(コープスペイント)ビジュアル
音楽イメージとビジュアルの統一性を持たせているのだと思います。こういった「視覚性」は聴覚補完も含め大賛同しています。アーティストとしてパフォーマンス意識の高いバンドだと思いますし素晴らしい取り組みだと思います。
何よりも演者は「お金を頂いてお客様に見て頂くという立場」ですからバンド内で統一された視覚内容(服装や髪型等)は言うならば「正装」です
衣装や髪エクステや鎧の様な服装やスタッズ(トゲトゲ系)もアーティストの正装として採用されるケースが多いと思います、音楽性を視覚でも表現するイメージは特にライブでは非常に重要ですからね
なので1人だけ「僕だけは素顔&ジーパンを履いて出演します、白塗りもしません」はバンド内で通用しないでしょう
一般企業勤務も同じです
出社規定がスーツ着用なら短パン&サンダル&ジーンズでは出社しないでしょう
ましてや対価である給料をもらう訳ですから社内規定に沿った服装規定での勤務になると思います
バンドマンの場合も「見られる」立場ですから尚更、重要視されると考えています
我々がサンダルにアロハシャツを着て短髪でブルデスをやるイメージは無いと思います
音楽性イメージは各バンド各様スタイルではあるのですが我々は結成時から黒服長髪で一貫しています
結成時からこれまでの歴代メンバーに対するリスペクトも込めて守り抜きたい拘りあるポリシーの1つ
そもそもお客さんが会場までわざわざ足を運んでチケット購入されパフォーマンスを観て下さる訳ですし、更にはCDやシャツなどへの消費も下さっている方々もいらっしゃいますのでその「感謝対価」だけでなく「お見せする限りは当然ながら正装でのお出迎え」です、アーティストであればそうでしょう
なので「ビジュアル面」=「音楽性と同じくらい」に非常に重要なポイントとして考えています
「対お客様向けのエンターテインメント関連」は全てに同じことが言えるでしょうね
結果/ライブでギタースピーカー2発(左右)
このブログで以前に書き綴った「シングルギターでありながらステージ上で左右のスピーカーキャビネットから2発鳴らす方法(繋ぎ方)」の件
リハでは十分に試してきましたが先日のライブ本番で「その繋ぎ方」で初めてパフォーマンスしました
結論は「メチャクチャ良い」です
先ず第一に、最前で観て下さっているお客様にとってはステージ左右のギターアンプからダイレクトに音が聴こえるのでギター側から観てもベース側から観ても均等サウンドな想定なので、どこからの角度からのお客様でもバンド演奏の音量バランスが最高でした、なにしろ迫力ありますよね、ドーンと前方全体に音が鳴るので
これは今後必須機材パターンになります
今回は国内ライブハウスさんでマーシャルキャビネットとJC120をお借りして繋ぎました
音質的な所感ですがJC120側はそのアンプ特徴から少しトレブル(高音)領域が強めでしたがマーシャルのコモッたギザギザ感と上手く混合してくれていました
とは言え事前にスタジオリハでそれも込みで想定して音を作り込んできていたので「そうなるだろう前提」ではありますが外音(後方のお客様側まで聴こえるように設置してあるスピーカー)も良かったです
初トライでしたが当方にとっては大発見的なことでした
次は海外でライブがあるので左右がマーシャルスピーカーで演れる想定があり、こちらも結果を楽しみにしています
シングルギターでバンドをされている方にはオススメです!
センスvs試行回数
センスは産まれ持ったもの
大谷翔平さんと同じ時間を同じように練習しても同じ成果は得られないでしょう
そういうものです
よもやま話になりますが大学受験時代
勉強が苦手でした
でも行きたい大学があり模擬試験を受けたりするのですが到達点に達しませんでした
それをどうしたかと言うと
「寝なければ良い=時間で賄う」として、到達点に達している人の2倍想定で受験勉強をしていました
表題に戻りますが「試行回数」です
「くじ引き」でいうなら当たるまで「くじを引く」です
なぜこんな話をしているかというと試行回数5~10回で挫ける方に出会いまして
当方なら先ず1000回やってから挫けようと思ったからです
この辺が人によって感覚が違うのだと思います
音楽に関して言えば、10個のギターリフアイデアで曲を創るのではなく、先ずは1000個くらいのギターリフアイデアからようやく10個が採り入れられるくらいです
なので試行回数に対する感覚が全く違うのだと思います
それをセンスというのかどうかは分かりませんが、創作期間中はそれを努力しているとも感じませんし苦痛も無いですし、もはや呼吸レベルな日常感覚です
変なのかもしれませんが音楽に限らず普段何かを遂行しようとした時、他人が10個考えるなら少なくとも先ず1000パターンは想定しておこうが身についてしまっています。でもきっと全てにおいて想定を含んだ「試行回数」は重要だと思います
あとは「最悪なパターン」と「一か八か」なパターンを想定し、そのチャンスやタイミングを「逃さない」です。それまでは心理的な揺れを上手くコントロールしながら普段を無感情に動くです
上述内容は数値的では無くニュアンス的な部分も多々ありますがですが、もしもセンスを覆したいなら試行回数を他人の1000倍はやることをお勧めかもしれません
どこまでも挫けない「根性」
音楽配信(ストリーミング)
iTunesやSpotify、Bandcampなどのデジタル配信
2ndアルバム以降は全て配信されています
「デジタル配信はしない」というバンドも多いかもしれませんね、特にこのジャンルだと
我々の判断は「プロモーションとして活用しよう」という現況の結論です
「偶然発見される可能性」やライブやフィジカル音源への興味の前に「一度聴いてみようという可能性」であったり
特に「デジタル配信やってます!!」的なことは強調していませんが検索すると出てきます
Youtubeが同じ役目をしているかもれませんが応援下さる方がデジタル版をアルバムごと購入下さったりストリーミングなので収益化もさせて頂いているのでありがたい存在です
我々そもそもが超小規模なバンドなので音楽配信をやってもやらなくても効果の判断というのは分からないのですが配信が無ければ基本的にはCD等フィジカルでしか聴けないのでアリだと思います
とはいえデジタル配信期間にも期限があり更新されなければそこで止まります(聴けなくなる)
「ライブ」は更に機会は希少ですが、出来るだけ様々な場所で演れたらと考えています
少ないながらも地球規模で「俺の国でもショーをやってくれ!」というメッセージ(DM等)を頂くことがあり海外エリアも可能性があれば増やせていければと思います
バンドSNS
バンドSNS発信は本当に苦手ではありますがプロモーションツールとして世界中のアーティストが活用しています
バンド系SNSだと世界的には①Instagram→②Facebook→③X(旧Twitter)の順番で効果活用されているようですが日本の場合は特殊文化なのか、むしろ逆順でX(旧Twitter)から順に優先活用されている印象がありますね
海外から来られるバンドさんにとってはこのXが筆頭という日本独特文化への事前知識が無いと来日プロモーション不足の可能性懸念も
折角の素晴らしいバンドなのに来日したことすら知られていないということもありえそうです
アングラ系はプロモーション力も弱いので「先ずは人に届ける」→そこから「取捨される選択肢を残す」ことすら難しいので極論的には「魚の居ない海で釣り竿を垂れる」という可能性も
これがもしも「有名なバンド」であれば新曲が出る=「盲目的に大称賛」(良かろうが悪かろうが)、「来日すれば大入り」という流れは恐らく覆らないでしょう
確かにジャンルによらず「〇〇が有名」となるだけで聴いてみようとなりますし「〇〇が今話題」となるだけで見てみようとなります。今の時代は「有名であるかどうか」が第一優先な印象もあります
つまりそこ(周知)にすら辿り着かないのがアンダーグラウンド系たる所以ではあるのですが
エージェント契約からの学び
先日、某海外エージェントとツアー契約しました
これが本当に勉強になりました、素晴らしい内容でした
待遇については勿論ありがたい内容ですが何より「細部にわたるまで」1つ1つを確実に相互確認しながら進めていくという契約でした(既締結済)
「条項内容に曖昧さが無い」のでむしろ我々も安心感があります
コンタクトを頂いて以降の打合せのやり取り内容も都度曖昧さの無いクレバーな文章でしたしキッチリしたエージェントさんであることが理解できました、早くお会いしたい気持ちで一杯です
過去にはExodus、Morbid Angel、Marduk、Dismember等も招聘されておりツアー先の国(現地)で初めてお会いすることにはなりますが丁寧なビジネスをされる方であろうことが想像できます
2025秋のツアー案件ですがこれからアーティストビザを取得申請しガッツリ修行ロードしてきます
このツアー、共演バンド含めかなりキツイ系(激速ブラスト)ブルデスツアーになるでしょう
告知をご期待下さい!
生成AI音楽 vs 人力音楽
表題の件、対立することは無いでしょう
なぜならば我々の様なバンドマンは「自分達で創って」「自分達で奏でる」ことが好きだからです
やりたい人はやり続けますしね
とはいえ生成AIはデジタルアートだけでなく音楽でも既に相当な成長を遂げています
以下2点のソフトをダウンロードすれば「明日から貴方もAI音楽家」のような感じです
◆音楽生成AIの「Udio」
Udio | AI Music Generator – Official Website
◆動画生成AI(MVなど)「Hailuo AI」
Hailuo AI: Transform Idea to Visual with AI
◆上記ツール使用例
https://youtu.be/OzXafFUekl0?si=6Zx8_LjBWj18kl9X
Youtubeで色んなMVを観ていたのですが概要欄に上記2点使用の音楽が出てきたので紹介してみました
これらは無料ツールだと制限も多いようですが、とはいえ月額使用料が僅か1000円台ですから維持費年間2~3万円で、1人で出来るバンドの最終形態かもしれませんね
この業界を否定するものでもありませんしむしろ新しい流れ(新陳代謝)ですし、いつの間にか生活の中で馴染んでいくのだと思います
「人力音楽」と「生成AI音楽」
奏でたい人は人力、CMなど商業向けにAI音楽など、各自の音楽の楽しみ方になっていくでしょう
最初からこれにしておけば的なイヤホン
イヤホン(イヤモニ)について色々と試してきていましたが辿り着きました
最初からこれにしておけば良かった的なヘドバン系バンドマンにとっては優れものアイテムです
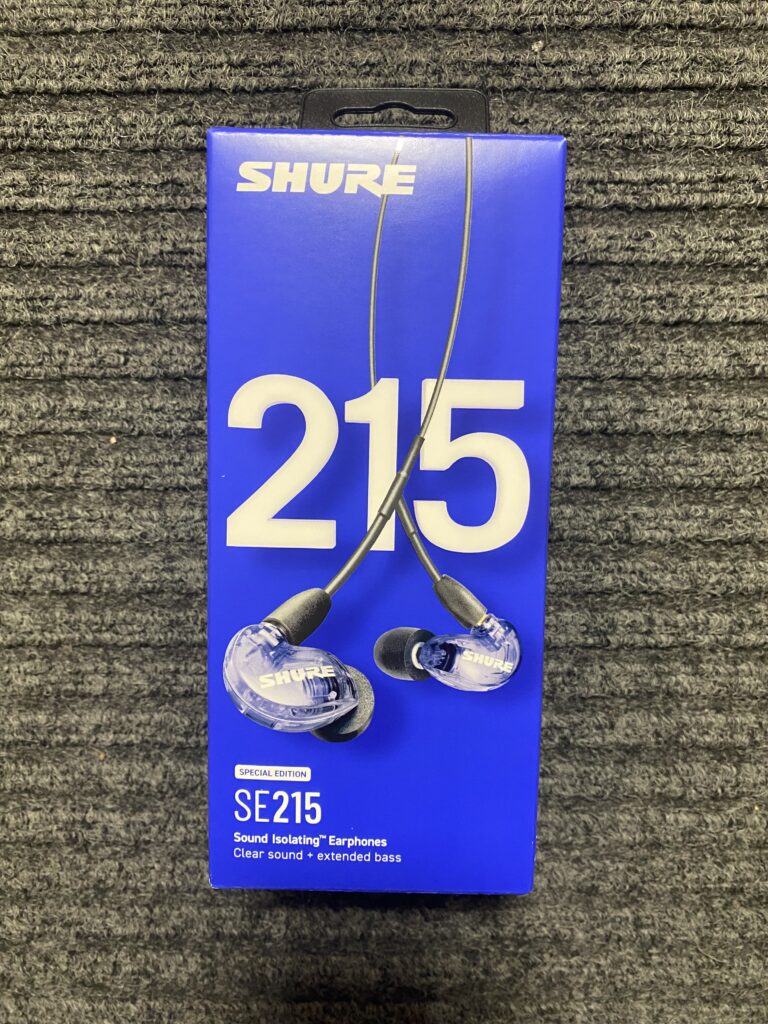

いわゆる「SHURE掛け」と呼ばれる耳に引っ掛けての使用で固定感が抜群です
更には後頭部側で「キュッ」と頭の形に締めることができるパーツが付いているのでヘドバンしようが外れる気がしないです(しかも長髪なので見えませんしね)
固定感だけでなく装着感も非常に良くてコードが擦れた時の雑音も無いです
激しいスポーツでも使えるのではと思います
型式はSHURE 215 Special Edition(パープル)です
Special Editionは通常版のSHURE 215よりも低音がプラスされています、耳の疲労感も少ないです
ライブ使用の場合、イヤモニと言うとどうしても消耗品的な扱いにはなるのですがコスパに関しても価格帯が15000~16000円ということでガチ系の5万円~10万円するようなイヤモニだと高価で怯みがちですがこれなら万が一、何かトラブルがあっても予備を持てますしコスパを含め非常に満足しています
国際物流+関税
世の中のレーベル契約バンド
「夢」の大手海外レーベルとの契約に浮かれて興奮している暇があるならしっかり交渉や計算をしましょうというお話です
我々は超小規模バンドながら光栄にも大手レーベル契約しています
レーベルボスにはものすごく親身にお世話になっていますし、よっぽどのことが無い限り今後もレーベル移籍は無いでしょう
件名ですが手元用の2025新作マーチ(CDやTシャツやロングTシャツ)が到着しました
重量が100kg以上あります
この運送費についてはバンド側で持つ契約です
国際物流+関税で約20万円でした
結構凄い金額ですよね
とはいえ、手持ち用マーチの国際物流費まで支払って下さるレーベルは無いと思います(=我々の様な小規模バンドは特に)
バンドとして先ずこの運送費+関税分を頑張って手売りしていく事から始まります
「バンドで飯を食う」は流石に全く考えたことはありませんが、こういった背景もあることを特に夢を見ているバンドマンは現実俯瞰して頂ければと思います。細かいことですが重要です
何度も繰り返し言うようですがガチ系活動バンドをやるならばスタート地点が先ずは「富裕層の遊びレベル」でないと難しいかもしれません
前回ブログ内容の「どんどん決まって行くライブ」でも書きましたがバンド活動は自己資金の潤沢さがなせる技とも言えます
「ライブしたい」、「海外ツアーしたい」、「活動幅を拡げたい」ならば尚更、バンドを組む前に事前準備です
音楽才能や楽器スキルやビジュアルなんてあって当たり前ですし(みんな巧いです)、その先の部分をどれだけ見据えて事前準備や環境作りができているかなのかもしれませんね
余談ですがアートワークはJon Zig氏です。DisgorgeやSuffocationなどのアートワークを手掛けているタトゥー界の世界レジェンド。これはレーベルボスが依頼下さったのですが本当に感謝です
↓CD

↓シャツ

↓未開封/今後ツアー時の手持ち用ストックとして
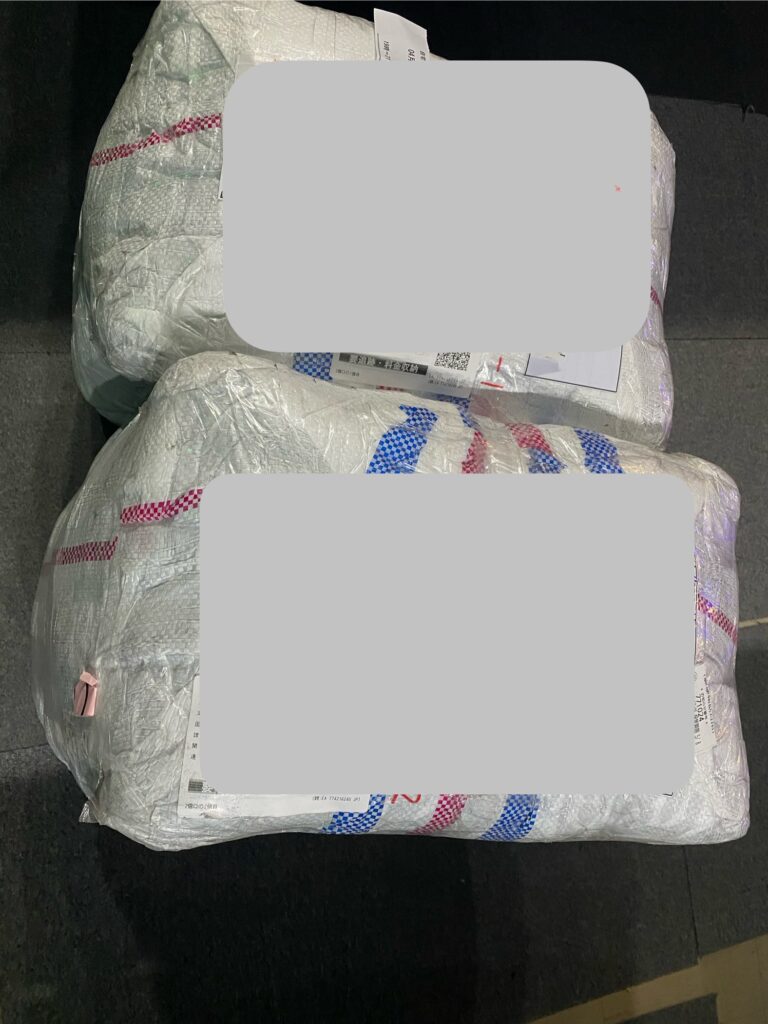
どんどん決まって行くライブ
情報解禁前を含めどんどん矢継ぎ早にライブが決まっています
その中には都合が付かずであったり、他要因から断念したライブが今年だけでも約20本(お詫び申し上げます)
結果的に2025年度において実際に出演させて頂くライブは12本前後のライブになる予定です(我々にとってはありがたくも想定以上に増加)
ということはつまり、断念したものも含めると全遂行ならば年間30本越えになっていた状況です
海外からの引き合い(=ライブ出演依頼)がどんどん増えています
毎回ビックリするんですよね、初回は全く面識の無いエージェント氏から突然出演依頼のメールを頂く訳ですが非常に嬉しいと共に基本的には断念したくは無いです、光栄なお話ですから
とは言えやはりメンバーの都合次第で決まります、ただこればかりは致し方ない部分もあります
実際海外ツアーとなると平日を含めた移動期間も込みになりますので「全メンバーが行けるかどうか」が常に課題になってきます(国内であれば朝一出発でも全国を当日会場入りできますし)
そのような背景からメンバーの誰かが1人でも都合が付かずなら「代打」つまり「ライブツアーメンバー」を探すことも検討しますが「突然すぐに誰かにお願いが出来るのか」というハードルもあります(曲を覚えるところからですからね、ましてや短期間だと)
ちなみに我々の様な超小規模バンドが海外エージェントから頂く出演依頼が「どのような契約条件」で話がを頂くのかですが、殆どのバンドが明かしていないと思いますので今回敢えて綴ってみます
明かさない理由は恥ずかしいからなのかプライドなのかは分かりませんが(そもそもわざわざ明かす必要も無いですしね)我々は特にそういった事情は無いのでそのまま以下へ。むしろ綴ることで当バンド側の提案も含むので
<契約基本内容>(下記は海外エージェント対応下さる内容のベースとなる内容)
現地空港送迎経費
ホテル経費
食事経費
アーティストビザ
該当国内での移動経費
共有バックライン経費(アンプスピーカーやドラムセット等の機材の貸与)
なので「日本から該当国への往復航空チケットは自腹」が基本です
但し既に繋がりあるエージェントで前回出演が盛況だったり、相当な良好関係を築けたりしていた場合、次回から「日本から該当国への往復航空チケット費用までをも用意」してくださったりします。これについては本当に感謝しています
繰り返しますが我々の様な超小規模バンドは海外ツアーにおいて「全経費」に加えて更に「演奏ギャラ」なんて夢の話です
余談ですが上記アーティストビザの取得は相手国からの許可書類やフルネームリストに政府印が入っています。これを事前に国内の住居管轄のビザセンターに行って写真等を用意して申請するのですが、当方は大阪のビザセンターに行って手続きしました。確か5営業日で取得できたと思います。費用は8000円を切る位でした。このアーティストビザ取得費用は自己負担。
そもそもすべての経費を持っていただけること自体が「奇跡」の様なありがたい状況なのです。上記経費に加えて渡航先迄の往復航空費や演奏ギャラまで全てとなると我々レベルで100万円単位になる事もありますし、そもそも我々が現地会場でそんな大きな金額のチケットを売り上げられる知名度も無いので無理があるのです
ちなみに以前にも書いたことがありますが「海外の大規模デスメタルフェス」で2,3日に渡って20バンドや30バンド出るようなイベントにおいて経費を出して下さるのは「ヘッドライナー」だけか「最大でもフライヤーの上位2列目まで」ですね
他はいわゆる「勝手に行って勝手に帰国する」全自己負担が基本です。それはそうですよね。そうしないと興行成立が難しくなりますし、ましてや非有名バンドであれば「出演させて頂ける機会自体」がバンドプロモーションであり出演実績になる訳ですからね
そのような背景から「能動的」にブッキングしていく大規模フェスやライブだと全自己負担のケースも大いにあるかとは思います(上で述べたフェスのフライヤー下段系バンドで「勝手に行って勝手に帰る」ケース)
相手側(エージェント側)からお声掛け頂く(出演依頼の)ケースでの全自己負担というのは流石に無いとは思いますが
他のケースも挙げるならば例えばヨーロッパツアーなどの「陸続きの国跨ぎライブ」をツアーバス(寝台ライナー)で廻るような際は一緒に動く他のバンドと経費を割り勘ししていくなどもありますね。それがもしも大御所(有名バンド)と廻るなら前座ポジション(=我々)であればその分の経費を負担することももちろん前提となります、おんぶに抱っこのプロモーションツアー立場ですからね
このように小規模デスメタルバンドがツアーをガンガンやるというのは「メンバー全員の都合」と「経費」次第といいますか、どんなにやりたくても先ずはこの2点をクリアしていく必要があります
なので現実面もしっかり考えながら動くことになりますね
デスメタル黎明期における先人達の年齢と以降
90年代初中期のスラッシュメタル&デスメタルのクロスオーバー期、いわゆるデスラッシュ時代から活動しているバンドは創始者含めオリジナルメンバーが高齢化(当バンドも含むですが…)
これからの5~10年で一気に引退年齢に差し掛かります
例えば当方が30年以上も聴いてきているDEICIDE
彼らは少し上の世代ですがDEICIDEの中心人物であるグレンベントン&スティーブアシェイムは60歳の手前に差し掛かってきています。メンバーの入れ替わりによる若返りを図りつつその活動を保っていますがバンドとしてはあと数年で活動歴40年になるバンドです
以前はCD全盛期時代でしたので上手く活動をやれてきたと思いますが今はストリーミング時代。彼らは近年、自身の生活を含めた利益保護の背景であろう新レーベルへ移籍しています。恐らくですが近年はライブ出演もかなり吟味している(選んでいる)でのはと推測します。彼らだって経済活動が成立しなければバンド活動が出来なくなるので、このブログで散々書いてきていますが正に「自衛」だと思われます
話を戻しまして「黎明期バンド群の大量引退時代」が間もなく来るでしょう
その時にこれからの若手デスメタルバンドがどのようにして活動していくのかという分岐点も迫っていると推測します
現在(2025年)においてはまだ彼らの様な巨大デスメタルバンド群が存在し牽引しているので「これからのバンド」はそのヘッドライナーツアーに参加したり、彼らのイベントに出演させて頂いたりして沢山の人へ音を届ける活動幅を拡げていくことが出来ますが、そういった巨大な立役者達が大量に引退したあとは、もぬけの殻とまでは言いませんが新しいバンドが出てきても初っ端で挫ける(出演機会の減少や興行規模の縮小)、つまり初段階での集客面を含め更にアンダーグラウンド化(小規模化)していく可能性があると思います
ですので「ライブ演奏」を一度に沢山の人に届ける仕組みの小規模化はマイナー音楽バンドマンにとって将来の課題になるかもしれませんね
なのでこれからはバンド結成後はライブ活動を行う前に先ずはMVやストリーミング等でバンドブランド化(先ずは曲を届けて知名度や人気に火が付いて)以降にようやくライブ活動を行うという流れなのかもしれません。短期的活動ならまだしも長期的活動視点で考えると「需要が無いところに提供しても」という辛い状況も
ましてやデスメタルバンドのファン層も高年齢化しています。
「ファンも高齢化」しているという事は当方も含めマーチコレクターやマーチ青田買い的な購買力も減衰していく可能性があります
将来の「若いバンドと若いファンがメインな潮流」というのは大変素晴らしいことですが購買力(人件費や物価上昇によるチケット高騰化は避けにくいと思われる)と言う意味では苦戦する可能性も大いにあるでしょう
その為にもこれからのバンドマンが活動を末永く続ける際は更に「環境自衛」していく必要があると考えています。バンド活動をやればやるほどに細って行くのを避けるためにも
解決方法はいつもここで書いている「音楽活動を続ける環境作り」になってはしまうのですがやはり強いのは自営業プレイヤー、メンバーが夫婦のバンド、不動産等の不労所得があるプレイヤー、教授や医者や大企業幹部。機動力と経済力を持ったバンドで固めていくのは1つのアイデアです。そもそも大衆向けでは無い音楽なので深く考えてどこまでも「自衛」もしつつ活動幅を拡げていくです
キャリアのあるバンドやキャリアのあるメンバーは今のうちに若い世代の人達にバトンタッチする流れを組んでおいた方が良いかもしれませんね。将来、シーンの小規模化は避けられないのかもしれませんが脈々と続いてほしいですね
当バンドも二十代半ばのメンバーが在籍しています。若いうちに海外ツアーだったり黎明期バンド群との共演だったりの早い舞台経験を積むことであったり将来の引継ぎをどんどんしておきたいと考えています
ライブ上での余裕の無い動きを減らしたい
去年(2024)の浅草デスフェスト出演時に我々のライブを動画で撮って下さっていた方いらっしゃったようでYoutube上にあることに最近気づきました。ありがとうございます、嬉しいです
出演者としては客観的に観ることのできる貴重な機会(自身では撮ってないことも多く)
そして表題ですが先ずは「動画の最初の0~3秒辺り」を観てみてください
「大きく肩で深呼吸している」のが見えました
自身は覚えていませんでしたがこうやって見直すとやはり相当なプレッシャーを感じていたのでしょう
当日の背景として雪の影響で新幹線が大幅に遅れ、我々は出演時間のギリギリに到着
既に開場していますのでお客さんも多数いらっしゃる状況下で慌ててステージに上がり機材を持ち込みセッティングをしてそのまま本番を迎えました
「肩から大きく深呼吸」するこの動きですが、演奏曲が速い曲ばかりなのもありますがセッティングをしながらも心を落ち着かせて頭を整理することに対する時間的余裕の無さへの焦りで極度のプレッシャーがあったのだと思います
他パートも同様、ボーカル兼速弾きギターも肉体の動きと精神分離がしっかりしていないとプレッシャーが凄いです
少しでも脳内バランスが崩れるとバラバラになるのではという怖さがあり強い意識を持ちながら演奏し続ける必要があります
例えになるか分かりませんが時速200kmで走りながら千手観音の様に他の事も同時遂行していくような感覚でしょうか
なので脳内の整理が追い付かなければ「もつれて終わり」のようなプレッシャーもあります
ただこれは「まだまだ余裕が無い」という事なんですよね(反省)
この動画は重要なヒントになりました、重ねて感謝申し上げます
日頃から3,4つの事を同時にやる訓練であったり突発事項にも臆さない想定トレーニングに努めていく必要があります
ギタースピーカーキャビネット2台同時鳴らしにトライ
表題の内容をずっと研究していました
我々シングルギターバンドですがライブ上でのギターの音圧(迫力)を更に付けたいと思いまして
どうしてこんな事を考えたのかですがライブイベント出演時、ツインギターバンドの前後にプレイすると気づき易いかもしれませんがシングルギターバンドとツインギターバンドでやはりギター音の迫力が違う感じがしました。ツインギターバンドはその名の通り2本のギター音が鳴ってる訳ですからそれはそうなのですが
それでもどうにかならないのかと解決方法を考え、試行錯誤をしながらようやく行き着いたのが以下の2通りの手法(海外用と国内用)です
【主に国内用】
国内ライブハウス設置ギターアンプは「ジャズコーラスJC120」と「マーシャル」が主要です。コンボアンプであるJC120にサブコン使用持参アンプヘッド(大出力)を直接繋げる訳には行かないので(アンプが飛ぶ/故障する可能性)それを解決する必要があります
どうするかというと、先ずはアンプヘッドのスピーカーアウトから常設マーシャルキャビネットへ普通に繋ぎます。そしてもう1つは「アンプヘッドのLine Out」からマイクケーブルでジャズコーラスのインプットに繋ぐです。これで2発のキャビネットを鳴らせます。これに気づくのに時間が掛かりました。(細かい話になりますが当方使用アンプヘッドの背面にはPhone端子もあるのですがプラグ変換してJC120に繋ぐとアンプの仕様上、停止します。つまり片方しか鳴らないです)
↓サブコン使用アンプヘッドTHR100Hの背面
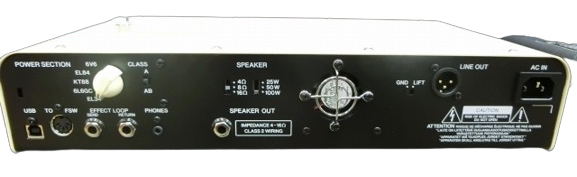
↓その背面のLine out拡大部(ここからマイクケーブルでジャズコーラスのインプットへ)

【主に海外用】
海外のライブハウスでは逆にジャズコーラスが殆どなく「マーシャルキャビネット」や「メサブギーキャビネット」等を拝借できるのでこちらは簡単です。持参アンプヘッドのスピーカーアウトからABYボックスを繋ぎYモード(分岐出力されるAとBを2つ同時出力するモード)に設定しそれぞれのスピーカーキャビネットに繋げば2発鳴らせます
用意するものとしては当日の環境次第とは言えどちらのパターンでも臨機応変対応できる様に以下携帯
①主に国内用/マイクケーブル20mx1本(ケーブルが長い理由はステージの左右にキャビネットを離して置きたいからです)と通常使用のスピーカーケーブル(数m)x1本
②主に海外用/ABY BOX
③主に海外用/スピーカーケーブル2本(内1本は上記理由と同じく20m位の長いものを用意)
→追記:のちに③のXLR変換プラグを入手しましたので①が不要になり更に機材軽量化しました
参考)ABY BOX↓(左側にAとBが見えると思いますがここから出力分岐できるので2台分のキャビネットにケーブルを繋げます。要はスイッチャーの同時出力エフェクターですね)

これでシングルギターながらも迫力ある前面サウンドが出せると
次回のライブから早速、2台のスピーカーキャビネットからの同時鳴らしで本番を迎えたいと思います
バンド活動「疲弊して行く人」と「疲弊して行かない人」
当バンドは1994年結成し1998年休止、そこから2019年秋に再始動し現在(2025年)活動中です
早いもので再起動(2019年秋)したところからでも5年以上が経過していますね
その5年の期間にアルバム2枚、再発アルバム1枚、DVD1枚、間もなく発売されるEP1枚の計5枚をリリース
国内外含むライブ活動も同時にやりながらのリリースですのでマイペース型バンドにしてはアクティブな5年
この5年という期間だけでも周りを見渡すと様々なバンドがフェードアウトしたり、解散したり、休止したり、活動縮小したりを見てきました、目まぐるしい程に。
この「バンド生命の移り変わりが早い」原因について
私的ですが大類分析すると「疲弊する人」と「疲弊しない人」でその分岐点があると思います
例えばよくあるのが「メンバーが見つからない」という常套句ですがこれは他責。探すならば先ずは自ら100人位は声を掛けに行ったのかどうかです
以前にも書いたことがありますが「地球上」で探せば誰か居るはずです。よっぽど特殊な奏法や人間業とは思えない様な超人テクが必要でもない限り
さもなくば極端な言い方にはなりますが「100万円出すのでサポートお願いします」と地球上で募集すればきっと見つかるでしょう
何度も繰り返し書いてきていますがバンド活動は富裕層の遊びレベルを想定した上で(やればやるほどもしくは活動幅を拡げれば拡げるほどに資金枯渇していくのが前提で)バンドを組まないと幾らやっても最後は承認欲求や思い描いた青写真とのギャップetcとの闘いでメンタルが弱い人だと思考や活動方向が歪んで卑屈になり活動が更に難しくなると思います
承認欲求と言う言葉が出たので付随しますが「売れたい」というワードを発する人がいますよね。であればボカロや邦楽ポップなどをやることをお勧めします。1人でDTMで自宅で作れば制作経費や人件費は殆ど掛かりませんし、イマドキならばわざわざメジャーレーベルを探さなくとも自分でYoutube等で挙げられるのでそこで聴いて下さる方々にジャッジメント頂ければ自身の才能や運の有無が分かると思います
飄々(ひょうひょう)と綴っていますが「そういうものだ」と俯瞰しているからかもしれません
「ビジネス的に釣り合わない(ギャラや経費)から(ツアー等)やらない」という様な事を言えるのは超有名バンドだけで我々の様な小規模&非有名系バンドとは別世界であり別次元のお話です
ちなみに当方の普段の生活。会社経営してるとはいえライブ活動日以外は休み無しで働いています。基本的にはライブ当日とその移動日が唯一の休暇。これもバンド活動を続けたい情熱からです
ですので「メンバーが見つからない」とか「方向性が合わない」とかは本気でバンド活動したいのかな?という疑問もあるかもしれません
「将来はロックスターになる!」みたいな、そういった少年の様な気持ちのままでやるのももちろん良いのかもしれませんが、いい大人ならばもっと俯瞰して現実を見据え「プレイできる舞台があること」だったり「海外ツアーできる舞台があること」だったりを汲みし諸々を飲み込んだ上で自身の活動幅やプレイ幅、スキルの幅etcを拡げて行った方が自身の音楽活動や経験値に悔いを残さない、つまり「やりたいことをやれる音楽人生」だと感じています
ただ、そのステップをクリアした経験の先にも更に資金力や機動力等が必要な事が段々と分かってきます。なのでそのステップにすら辿り着かない手前の時点で「疲弊する人」は折角の音楽センスが生かせなかったという事になるかもしれません
これらを1つづつクリアして行ったとしても、それでもその先にはまた次から次へと新しいハードルが出てきます。そこでまた疲弊し脱落して行くバンドもありますので長く継続しながら幅広く活動できるバンドの数は完全に「ピラミッド型」。まさに篩(ふるい)に掛けられているような
結果としてそれすらをも超えて行ったバンドは「一過性」では無く(数年でフェードアウトの様な)、長年に渡り幅広く活動を続けているバンドなんだと思います
「バンドで疲弊しない人」になる為に必要なことは「異次元な情熱」は前提ですが「活動バランス感覚能力の高さ」「機動力と資金力」「他責にしないこと」ではないかなと感じています
カバー曲の難しさ
Youtube上では「カバーしてみた」動画が沢山上がっていますね
原曲者にとって「曲をカバーされる」というのはきっと嬉しいことだと推測します
当バンドの2025年新作「Devoid of seraphim」内で初めてカバーを収録しました
カバー曲はDeicideの『They are the children of the underworld』とCARCASSの『Tools of the trade』です
手前味噌になりますが2025年5月21日国内リリースですので気になった方は是非入手下さい
表題に戻りますが「カバーするって難しい」です
単なるコピーでは無いといいますか
特に古い曲だと当時のニュアンスまで含めてどのようにカバー演奏するか
Youtube上で何十年も昔の曲をカバーされているのを観て当時のニュアンスまで出せている人は凄いと思います。今風のクリック&無機質なカバーでは無く表現力のあるプレイヤー
今回のカバー曲についてもギターに関して言えば当時のカーカスやディーサイドの暴れん坊の様な荒々しいニュアンスだったりホフマン兄弟(DEICIDE)、マイケルアモット(CARCASS)の、あの当時のタッチやニュアンスを出したいです
幸運にも当時リアルタイムで彼らを聴いていたのでその衝撃的な記憶をできるだけ忠実にカバーしたつもりでいます
90年代はクリック&DTM未普及時代でしたし特にギターに関しては良い意味で原曲の「走りやモタリ」が往年のファンには堪らないところだと思います
コアなファンにとってはその当時のタイム感(良い意味での走りやモタリ)が胸に何十年も刻まれていてそこが正に琴線に触れる気持ち良いポイントだったりします
出来るだけ忠実に表現したいと思ってレコーディングしました
今後Brutal Mind(レーベル)の Youtubeチャンネルや他のストリーミングサービス等でも公開されると思いますので是非聴いてみて下さい
カバーをリリースするに当たっては著作権料が必要です↓
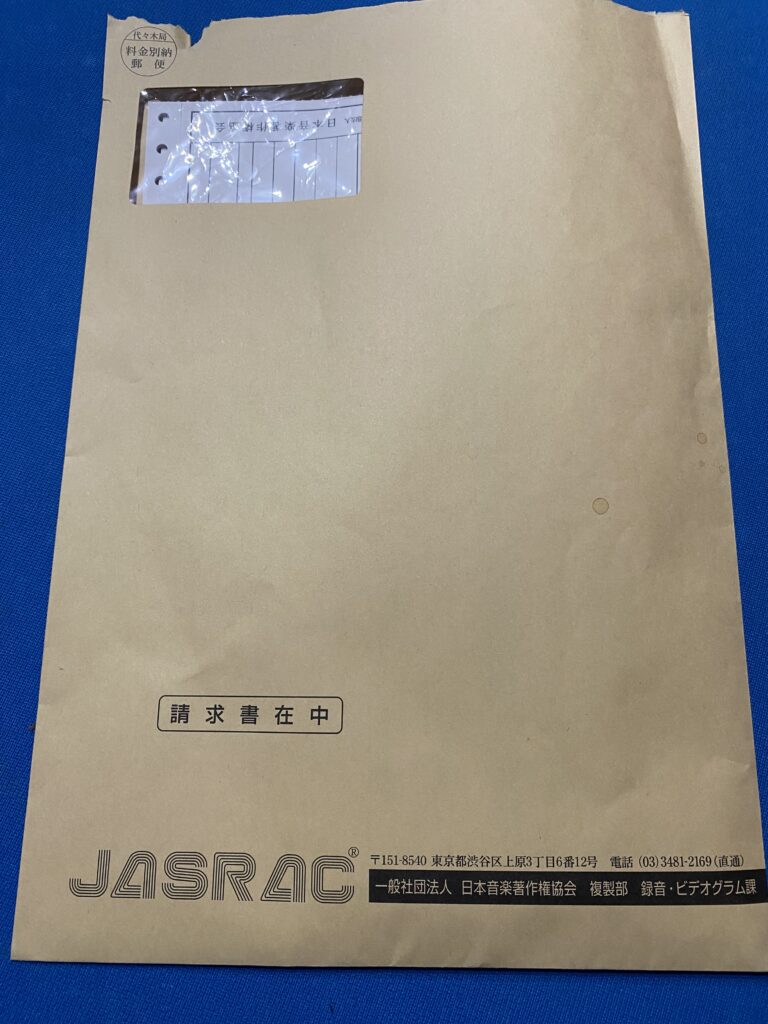
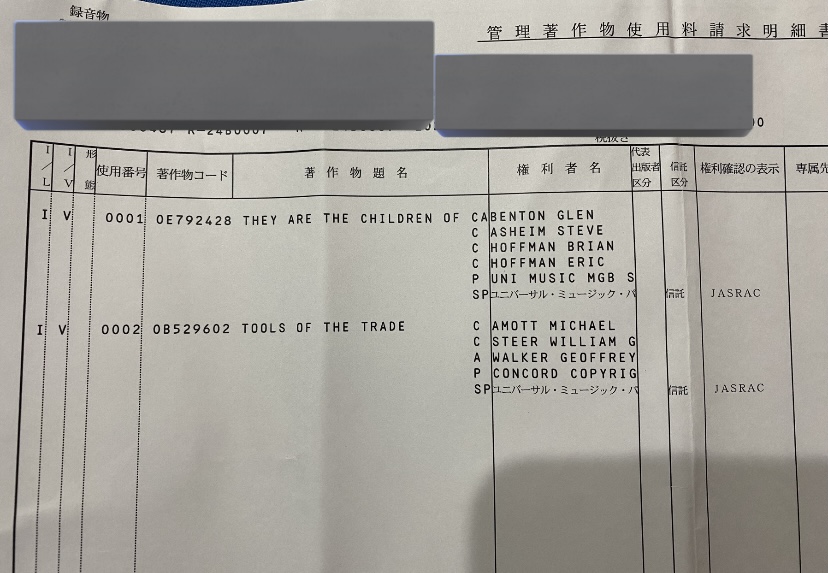
個人情報もあるので伏せている箇所もありますが、日本音楽著作権協会を通じて著作権者であるDEICIDEとCARCASSのメンバーへカバー認可を得ています
いつか作曲者本人に聴いて下さるような事があれば嬉しいですね
我々もそうですが、彼らのコアファンは当時のニュアンスまで感じ取っているリスナーも多く、やはり耳が敏感(判断も厳しめかも)なのでカバー曲を収録するのは緊張感もあります
ギターに関して言えば今ではネット上にギター譜面がいくらでも出てきますが「そうではないな」(そうは感じなかったな)と言う部分もあり、自己流”耳コピー”を含めて90年代に聴いていた当時のニュアンスも大切にしながらレコーディングしましたので是非聴いてみて下さい
「太い音」とは
太い音ってどうやって鳴らすのか工学的に知りたいです
デスメタルだと近年の筋肉系プレイヤー出現やその激しい音楽性イメージからガシガシと強く弾く様なイメージがあります
当方も学生時代からこう言った「先入観」だけで何も疑問を持たず動物的にギターを弾いてきました。でもそれって実は長年に渡って「逆のことをやってきているのかもしれない」という疑問が湧いています
工学的な説明が出来る人が居らっしゃれば研究論文など見てみたいです
あと「ピックアップの高さ」(弦振動を拾う幅)や「弦の太さ」って実際の音の太さとどのような相関があるのかもイマイチ分からないですし説明が付かないです。こちらもやはりイメージ先行です
単に「みんながそうやってるから」という先入観だけでは無く工学的な説明が欲しいのと果たして本当にそれが正しい方向性なのかという疑問も続いています
現時点でのセッティングをどうしているかというと先ずはピックアップと弦の近づき具合は「いわゆるノーマル設定」(楽器屋さんでの定期メンテナンス依頼)
でもそもそも「ノーマルの概念」も分からないですよね。「見た感じが普通(な隙間)」だからなのか…
以前Youtubeで速弾き系プレイヤーを参考にノーマル弦高では無く「弦高を下げてみた」ことがありましたが暫くすると「弦がビビる」(フレットに当たって音が共鳴)ってしまい「これはライブでは使えない判断」ですぐにやめました
あと、さらに分からないのがピックキングの強さです
デスメタル系だから「ガシガシやった方が強いニュアンスが出る!」とか「ピッキングで歪ませるんだ!」という言説をSNSで拝見するのですが果たして本当にそうなのかなという疑問です。イメージでは確かにそんな感じもしますが工学的にどうなんでしょうね
興味深い動画を紹介します。動画ポイントは疑問開始の4:20頃と対する回答箇所の6:20頃、その核心部分に迫るかもしれない部分の6:40頃です
こういう会話は非常に興味深いですし、こういう議論をして下さるのはありがたいです
諸々を踏まえての現況は以下です
【前提】
①ギターの弦高セッティングは楽器屋さん定期メンテ依頼の「ノーマル」状態
②ピックアップはリアフロント共にダンカンのBlackWinter(パッシブ)
その上で太い音(+輪郭クリア)を出すために現在している事は以下です(将来はまた変えるかもです)
①先ずは音作りが第一
→出来るだけ歪ませず、加えて全体楽器との周波数?が被らない様な音作りです
→この音を単体でギターだけ鳴らすと歪みが足りなくてツマミを沢山上げたくなる感じです。つまりジジジジ系(ディストーション低音ガッツリ系)では無く、あまり歪ませずにパカパカ&カリカリした感じです(Low極端下げ、Mid極端上げ、High&Treble上げ)
→ギタリストであれば歪みが全然物足らないと思うような音かもしれませんがライブ経験上、合奏したときに最も輪郭がクリアに出る(埋もれない)と行き着いたので
→何をやってるか分からない程の低音歪みの場合、特にライブ上では曲が単調に聴こえてしまいそうなのと、ましてや(輪郭が非クリアだと)ギターリフも生かせないと考え「パカパカ&カリカリ」した音に行き着きました。「何をやっているのかが分かり易い」を好んでいます
②ピッキングに関しては以前は強すぎたのを「一定化」に努めるです
→「アタックが強すぎると”芯”が無くなり音像が分かりにくくなる」という上記動画の言説に基づいて現在進行形で改良すべく練習中です
そうそう、このリンク動画を見て思い当たるフシがありました
当バンドの2nd「Reprogramming」アルバムレコーディング中、曲名「Monstrous Mediocrity」(再録版)のギター録音時の出来事なのですが、ピックのアタック音をピックアップが拾い過ぎて「キキキキの様な弦が擦れる様な音が録音されていて聴き直した時にその箇所に違和感がありました。結果、やはり気になり過ぎて録り直しました。その録り直し時に「軽いピッキング」にしてみると音像がクリアで芯があって綺麗に聴こえるようになりました(そう感じました)
これは実は大きなコツだったのかもしれません。正に「先入観を覆す真反対」な回答です
あの時はそこまで深く気づいていませんでしたが音作り以外でも実はピッキングアタックは軽ければ軽い方が良いのかもしれません(まだ結論には至っていませんが)
「軽い」の概念がまた何とも曖昧で抽象的ではあるのですが恐らく「ピックの重さバランスを出来るだけ崩さない様に弾く」のではと私的推測しています
ちなみに「弱い(軽い)アタック」って難しいです
指に感じるピックの重さ(五感)をかなり研ぎ澄ます必要があると感じています
舐めるように弾くというかピックが弦を通り過ぎた後の隙間についてピックバランス(重さ)を崩さずに減らすというか。更には最初の1音目に入るアタックタイミングにも相当気を使うようになります
不幸中の幸いか「学生時代からピッキングは強い方が良い」という先入観でやってきましたので「大は小を兼ねる」といいますか工夫しながら練習しています
どちらにしてもやはり工学的な説明が欲しいです
なんとなく思うのが「アタックが強い」=「弦が揺れる幅が大きい」のでつまりその分、音階も狂いやすく、ピックアップはマイクですから強く当てれば擦れる音も拾うでしょう(さきほどの「キキキキ」というピックと弦が擦れる音)
更にはアタックが強いと、例えば「ドレミファ」の「ド」音を弾いたとしてアタックが強すぎることで弦の揺れ幅が大きい分「ド♭」や「ド#」になってるかもしれませんよね
その為に世の中では音の粒を抑えるコンプレッサーというエフェクターが存在するわけですが、むしろ音の粒を揃えて弾きこなせる技術がアップして行けば要らないかもしれませんよね。むしろコンプを使わなければニュアンス(感情)も出やすくなると思います
考えれば考えるほど深いですし難しいですね、ピッキング論
研究論文等(概念では無く工学的見地での)があれば深く読んでみたいです
AIに質問してみた「イヤモニは片耳or両耳?」
以前から書いてきた、クリック音を聴きながらライブをすることで「環境依存と他責を無くす為の自衛」の件ですが、他の人達がどのようにやっているのか分からないのでChat Gptに質問してみました
結果的には現時点で正解であろう道を歩んでいる様相でした(願望含む)
まず前提として、我々のクリックは世の中の多数バンドがそうであろうカウベル音で作っています。そしてカウント系の掛け声は男性verと女性verを曲展開の中で使い分けています
今回はそれ以外にずっと気になっていた「クリック音とガイドトラック(元音源)の音量バランス比」についてChat Gptに質問してみました
(意味不明だとアレなので分かり易く説明するとクリック音のバックに元音源をうっすらと掛けた音源(ガイドトラック)ファイルを作るんです。なぜならば、そうしておかないとクリックだけだった場合、万が一間違えると永遠に間違えたまま演奏してしまうことにもなりかねないからです、それも自衛の為ですね
この質問に対するAIの回答はクリック音:元音源=7:3から8:2の音量バランスでした
他にも疑問が湧き続けていたのが「イヤホンは片耳だけにするのか」どうかです
つまり片耳だけイヤホンをして、もう片方の耳は実音(外音)を聞きながらの方が良いのかどうか。ただ、それだと耳が混在してクリック音が聴こえ難くなりズレやすくなるリスクもありますよね。となるとやはり両耳イヤホンの方がリズムキープしやすいとも思えます
この質問に対するAIの回答は「ドラマーはほぼ全員両耳傾向」、「他パートは片耳or両耳の人が半々な傾向」でした
ただChat Gptの言う「他パートは(片耳/両耳)半々傾向」という回答にはまだモヤモヤ感が残ります
結局、片耳or両耳のどちらが良いのだろうと
これに対するAIの回答は「現場環境(会場大小や会場設備等)で変わるので、解決方法としては会場リハーサル時に両方のパターンでやってみて片耳でも大丈夫なら片耳、難しいなら両耳」がオススメとのことでした
いやはや、このように瞬時シュミレーションできるのは本当に凄い時代(時間効率)になりましたね、一昔前なら全パターンやって経験から導き出す感じでしたが
告知疲労
音楽創作やライブ活動をするのが好きな訳ですがSNS等の告知プロモーションがとにかく苦手です
音楽向けマーケティングは完全な門外漢でこの部分で精神疲労を起こすことが多々あります
勿論バンドマンはライブや新譜リリースをするとなると嬉しい訳ですから皆さんへそれが伝わり更には琴線に触れる方がいらっしゃれば殊更に嬉しいです
ただ我々の様な非有名&小規模なバンドともなるとそういった拡散力の様なものは全くありませんし、気づかれないままという事が往々にしてあります
「悪名は無名に勝る」という諺がありますが「知られなければ存在すら分からない」ですからね
4月に大阪でライブがあります。3バンド出演ですが主催(の方のバンドも出演)は外国人で初来日。我々も含めて失礼ではありますが非有名バンドの来日公演です
これ、、どうみても殆どの人が告知にすら気づかないのではという懸念もあります。日本開催ですし日本人バンドである我々は必死で告知をしていきますが果たして影響力も何もない我々が宣伝して効果があるのかとも。それでも必死でやらせて頂きますが。情けない部分ではあります
今の時代、先ずは売名行為が必須みたいな世界で嫌ですが知名度がない限りこういったプロモーションサポートが難しい面も事実としてあります
出演バンドの当方からするといつも主催者に申し訳ない気持ちでいっぱいになりますし、ただただ興行が成功することを毎日祈りながら出来る限りの告知しています
とはいえこれもバンマス能力値の低さが露呈しているとも言えますし、かといって不得意分野は他の方にお願いしたい方が良いと思っています
「広報が得意な方」を募集したいですね
ライブ機材のパフォーマンス安定化(更新版)
ライブ経験を元に都度機材更新していく感じなのですが、以下は近年の海外ツアーや国内ライブで気づいたライブパフォーマンス手法の最新版です
①環境依存への自衛用として「クリック音源制作」&「イヤモニ機材」の使用
②ライダー(Stage Plan)を充実させ現場での拝借機材を最小限にまで追い込む
そして以下はこの2点の詳細内容です
①に関しては以前にも書いた通り「環境依存を無くす」です。どこでやっても一定以上のパフォーマンスを実現したく「他責にしない自衛」です
②の「現地での拝借機材を最低限にする」ですが、例えばギターパートなら(1)スピーカーキャビネットと(2)コンセント差込口のみを会場にて拝借依頼。もちろんアンプヘッドを含めて他の機材は全て自前持参。唯一、拝借するスピーカーキャビネットですがそれを繋ぐスピーカーケーブルもやはり持参です。万が一、備え付けのスピーカーケーブルがたまたま接触不良していて音が割れるとかも防止&自衛できますよね。更にはキャビネット側インプットジャックの接続不良まで想定懸念するならば接点復活材も持参しておいた方が良いでしょう。あとボーカルについては「マイクスタンドのみ拝借」(マイク持参)です。とにかく現場の方達への負担軽減も含め「ライブの音は出来るだけバンド側の自責に追い込む」ことが重要だと考えています
とにかく環境依存&他責にしたくないのです、出来るだけ何も拝借せずに実行できる様に努めたいです
前提としては「折角足を運んでくださったお客さんへお見せする」のですからパフォーマンス低下要因となるかもしれない事項は予め極限まで取り除いておく事がバンド側の責任であると思ったからです
外音(お客さん側で聞こえてくるスピーカーからの音量バランス)についてはどうしても会場PAさん依存ではありますが少なくともバンド側の要因は最小限に抑えることが出来ると考えています
今後も引き続き「どこでやってもパフォーマンスをMAXに追い込む」を追求していく所存です
※参考/アンプスピーカー専用ケーブル( BELDEN/9497)↓

※参考/イヤホン(Shure/SE215 Special Edition)↓
SE215 Special Edition – 高遮音性イヤホン – Shure 日本

バンドマンの2分化思考
「音楽を聞く人」と「実際に(バンドを)やる人」で思考が違います
我々自身、バンド活動している側なので今回は「バンドをやる人」側の視点で書いてみます
これが非常に興味深く、完全に真っ二つに分かれる傾向にあります
どういうことかと言うと精力的に活動すればするほど「遠ざかるバンドマン」と「更に近づくバンドマンの二分化です
面白いですよね
例えばビッグバンドとの共演や海外ツアーを「おおお!頑張って!」とメッセージくださる方
逆に「嫉妬なのかどうなのか遠ざかる方」に二分化します
後者は「自分(のバンド)に必死過ぎて余裕がない」のだと思いますが、我々は完全に前者なのであくまで(後者については)推測の域を脱しませんが
でもこれは恐らくです敗戦自虐文化の醸成によるものもあるかもしれません、いわゆる「出る杭…」や「同調圧力」的な
「前にならえ」「体育座り」等、幼少時から皆と同じ動きをするという長年の風習です
海外だと自国の人間が出る杭になればなるほど称える(よくやったぞ!)文化な傾向ではありますが
個人的にはKrueltyやDefiled、そして他の果敢にも海外に出て行くバンド群や国内シーンで勢力的に活動されているバンドを観ていていると称賛しかないですし本当に頭が下がる想いです
常に「すごいな、よくやってるな」、「バンマスやバンドメンバーの能力値が高いのだろうな」と感じますしリスペクトしかないです
なぜならば「実際にそこに辿り着くまでの過程を想像理解できる」からです
「苦労」と言う言葉は使いたくないので言い換えるならば「想像を絶する想い」がそれを実現させているのだろうと思います
もっと言葉を選ばずに言うならば「出来るものならやってみろ」という感じでしょうか
海外ツアー、海外フェス、国内ツアー、来日公演サポートetc
これらはそのバンドマンの「強い意志」と「行動力」で成り立っています
ある意味、そんな部分で嫉妬なんてしている時点で「やはりそこまでのバンド」でしょう
やりたければやれば良い(やってみせれば良い)訳ですからね
単純ですが「実行できないのは他責か言い訳」です
実行しているバンドはきっと「音楽バンド活動が好き過ぎる度数」や「音楽活動に対する熱量」が周辺のバンドマンよりも宇宙レベルで高い人達なのだと思います
だからそこを乗り越えてくるんですよね
そういった「やれるものならやってみろ」を実現している(国産の非商業ベクトル音楽=これで食える訳でも無いのを予め分かっていながら精力的な活動を止めない)バンドには頭が下がる思いで我々も少しでも近づくべくやっていきたいです
すべては「音楽活動に対する熱量の差」
正に音楽バカですね。恐らくその先に行き着く最終地点は「音楽は(廻りも何も)気にせずやりたいように自由にやる」だと思います
感謝
「ライブ出演のお声掛けを頂く」というのは感謝とともに「いつもドキッとして焦り」ます
まず第一に「嬉しい限り」なのが前提ですがその瞬間、いつも焦るのが都合確認
1人でも都合が付かなければ出演出来ないわけですからね
ここは毎回ヤキモキする部分でもあります
もちろんフルタイムでデスメタルバンド活動をやるというのは現実的には難しいので「その都度GOできるプレイヤーが行く」しか選択肢は無いのですが
今年だけでも断念しているライブが複数あります
特に期間が短いとツアーサポートメンバーを探すにも時間が足りないです
この辺はバンドをやっている人は常に遭遇することなのかもしれませんが
なのでライブ活動に能動的に動くのが難いと思うタイミングもあります
本来であれば「待ち」ではなく自ら動いて出演していく方が良い筈
こういうことをブログに書くのは本当に後ろめたいですが、折角のお話を棒に振る様なことがあるとその都度心が痛みます
なので能動的にライブ出演の為にアクションすることについてはビビッてしまう部分があります。本当に情けないところではありますが
これまでSubconscious Terrorは決まったライブに穴を開けたことがありません。いや、正確には90年代に一度ありました。大雪で高速道路が閉鎖され機材車ごと高速道路上に閉じ込められ道路上で宿泊せざるを得なかった横浜7thアヴェニューでのライブです、こればかりはどうにもならない状態でした
決まったライブ(告知されたライブ)に関してキャンセルと言うのは不慮の事故や交通機関停止でもない限り出演しないというのはあり得ない信条でやっています
告知された時点で我々は(限りなく)100%出演します
バンドマン同志での活動手法競合はない
アメリカはコロラドのエクストリームメタルレーベル、Dark Descent Recordsのオーナーのマットさん
彼がSNS上で「同じ志を持つものへ手法を教えることを競争脅威とは思わない」、「手法を隠すことは単なるエゴに見えます」と
彼の元へ「これからレーベルを起業したい人」から、運営手法や製造などに関する質問が多いそうで個別回答されているそうです
当ブログも同感だったので取り上げさせて頂きました
ありがたくもバンドマンの閲覧も多いこのブログですが、我々がバンド活動において気づいた手法、コツ、ヒント、経験、現実面(経費等)で実経験してきた内容がメイン。これらが何かのヒントになればと思いながら書いてきています
そこから更に上手く活動できる人が出てくれば又そこから学べますから、むしろありがたいですよね
「音楽は創作物」
各人各様のサウンドがある訳で活動手法のノウハウを知ったところで競合はしないので(あくまで自分達の意思や行動次第です)ノウハウとして秘める(隠す)理由すらないと考えています
経験して学んだことはこれからも書いていきたいと思います
(マットさんとは以前から少しやりとり等繋がりがあります)
逆手にとれるかどうか
SNS含むインターネット全盛時代においては広告に掛ける投資額の大きさで音楽を告知するというのがマストになってきています。近年は更に拍車が掛かっています
昔なら口コミやライブハウス活動からコツコツと幅が拡がるバンドも多かったですが
現代はストリーミングサービスやDTMの普及、更には楽器が出来なくてもアプリやDAWで誰でも作曲が出来て簡単にリリースまで出来ます。音楽マニアがディグる(発掘する)とはいっても日々アップデートされる「新しい音楽リリースの渦」には「気づかれる」ことすら難しくなっています
アングラバンドをやっていると葛藤する部分でもあるかと推測します
例えば、どんなに素晴らしい音楽を創作しても推しだすプロモ費用が無いとか、逆に「パパパッとPCで創った音楽」を5000万円くらい掛けてプロモーションしてサクッと大規模フェスに出演し、その大御所ポジションを築くといったようなことも
我々の様なアングラ系はそもそもの規模が小さいのでそういった世界とはなかなか縁がありませんが、それでもこのジャンルにおいても富裕層や資金力を持ったバンドが前進しやすいです
メンバー全員が富裕層で楽器スキルもありビジュアルも揃えれば活動規模のステージ進歩は早いと思います
受験や企業勤務での出世競争と同じくピラミッド型です
更には資金力の大きさも加わったのが音楽ビジネス
以前にこのブログで書いたことがありますがプロモーションの為にヨーロッパを大御所バンドと一緒に廻るなら「とりあえず自己資金170万円を用意しましょう」という内容がありました
厳しい様ですが現実問題として「4畳半アルバイト生活のバンドマン」でその理想をかなえるのは難しいと思います。つまり「地元ローカルのライブハウスでチケットノルマを追いながら、いつもの友達を呼んで精一杯活動する」という「枠」から出ていく事に困難が伴うと推測されます
このブログでこれまでに何度書いてきたことか分かりませんが「末永く幅広い活動をするバンドをやりたいならば普段の生活の自由を勝ち取ること」が前提で必須。さもなくばやればやるほどに先細ると思います
とはいえ現代は情報量も多くクレバーな人が増えていますので10代の内から上記の内容(環境整備)に気づき(もしくは親が教える)、着々と実行していくバンドマンも増えています
昔ならば後先考えずに音楽活動に突っ走るという感覚がありましたが、今はその辺りも先予想をしながら行動できるので、ある意味で有限な人生時間を効率的に使うことが出来ますよね
あとどのくらいの期間、バンド活動が出来るのかは分かりませんが現代の情報量と上手く融合させながら効率についても考えて行きたいです
つまるところ活動内容策定&時間効率を先に想定する能力値が高ければ高い程、例えばアルバムを出せる枚数も増やせますし(常に中長期スケジュールを立てながら行動できるので)結果として長所は多いと思います
推奨:バンマスをやってみる
バンドマンがバンドマスター(バンドの組織リーダー)を一度はやってみることをお勧めします
なぜかというと全体を見渡す能力が身に付くからです
作詞作曲、コンセプト、ビジュアル、ライブ、ツアー、機材、エージェント交渉、レーベル交渉、流通、レコーディング手配、Mix&Mastering手配、アートワーク、中長期ビジョンの策定、メンバー探し、活動資金、言語能力、SNSの発信手法etc
やはりその前提には先天性というか、産まれ持った俯瞰を含むセンスが必要です
とは言えども、後天的にもある程度は鍛えることは可能だと思います。当バンマスもバンマス能力値は低いですが”必死でもがいて”います
バンドマン生涯に渡って「自分の担当パートを奏でる(だけ)」で音楽人生を終えるのか、バンマスまではやらずとも常に全体視野で音楽活動が出来ているのかを認識をしておく事は音楽人生を更に豊かに出来ると思います
こういったことも普段から考えて行動すると音楽活動をしていく中で楽器スキルの向上や創作のアイデア、果ては自身の音楽人生の将来ビジョンにまでゆくゆく影響を与えて行くものだと考えています
恐らく各プレイヤーごとにあると思うんですよね、例えば地元ローカルで末永くやれれば十分満足したバンド活動と言う人もいれば、将来はいつか海外ツアーや海外フェスなどの舞台を踏んでみたいなどの野心をもった人も
それは各人各様の思想ですので自由で良いと思いますし、私的にはこれは先天性だと思います。つまりは生まれた星の元。大谷翔平さんの10倍練習したら彼よりも活躍できるという訳ではないとの同様。ジタバタしたところで先天性が強く、やはり収まるところに収まるはずです
遺伝ガチャや親ガチャといってしまうと元も子もない話になりますが、後天性的に上手く行く人というのは「実は強運という先天性」を持っていたからかもしれません
実際「努力」と言う言葉は本人にとっては努力をしてるとすら思わないですし、それが全く苦とも思わずむしろ楽しんでいますからね
「ギュイーン」と鳴らすアーミングの部品
叫んでいるかのようなギターのアーミング・サウンド
楽曲内でこのアーミングサウンドを使うのでフロイドローズ構造のギターを使用しています

このフロイドローズですが経年劣化も含めブロックやネジが壊れるとチューニングがすぐに狂います
消耗品としては高価な部類ではありますがやはり音が狂うのは違和感や不安を生みますので乗せ替えやフロイドローズ部品の交換は定例行事としてメンテナンス経費計上しています
ライブ中に破損なんてしたら目も当てられないですからね
「ライブでの使用楽器はとにかく頑丈で壊れにくい」が第一優先事項になります
これまでの使用ギターメーカーはほぼJacksonの一択(BC.Richもありますが)でプレイしてきていますが近年はJackson廉価品(入手しやすい量産品)にピックアップを載せ替えての使用が主要です
大好きなメーカーなので言いにくいですが工場出荷のデフォルト版フロイドローズ(添付写真)はちょっと壊れやすいです
購入後、暫くはこのデフォルト版フロイドローズを使うのですがやはりその後は純正フロイドローズに載せ替えるタイミングが発生します
そんなフロイドローズも近年はアップグレード版(カラーや材質や耐久性)のバリエーションが沢山出ています
「次はどのパーツに変更しよう」とパーツ選びに悩んだりする時間もとても楽しいのですが、ライブを行うバンドにとってはやはり「とにかく壊れにくい楽器」が第一優先になりますね
環境依存を減らす(安定したライブパフォーマンスの実現)
ワールドツアーをしているような百戦錬磨のバンドからは本当に沢山の事を学べます
海外各国の会場環境や屋内外環境を問わず、安定した絶対王者的抜群アンサンブル演奏の実現を追求していきたいです
今回はSinister帯同海外ツアーの際に直々に教えて頂いたテクニカル面での秘訣の1つとなるであろうお話を紹介します
(以下は我々がこれからその秘訣の実現に向けての準備も兼ねたお話ですのでその後に改善される内容も含みます)
Sinisterはそもそも世界的レジェンドバンドであり「各個人の技術力もワールドクラス」なのが前提で話を進めます
Sinisterメンバーの中でもテクニカル面を司っている現行ドラマーのSimonさん
プロドラマーであるSimonさんですが普段はドラム講師をされています
Simon Skrlec – DRUMMER – YouTube
ツアー期間中、食事や楽屋等で彼に根掘り葉掘り質問をさせて頂いていたのですがタイトルの「環境依存を減らす」についての質問に対する彼からの回答が「クリック演奏」でした
これまでの我々のライブは「せーの!」でドラムの音に合わせて「聞き耳を立てながらライブ演奏」をしてきました。その事を伝えるとSimonさんからは逆にビックリされました、「えっ?噓でしょ」と…(会場環境次第で「聞こえない」とか「技術トラブル」があったら終わりじゃん…)
つまりワールドクラスの百戦錬磨なツアーバンドは環境依存を避けたクリック(メトロノーム音)を聴きながらライブ演奏をするがスタンダードなのでしょう。そうでもしないと環境次第でライブがボロボロになることもあり得ますよね
かといって、他責にならないよう事前の自衛は必須です
確かにYoutubeなどで有名アーティストのライブを観ると耳にイヤホンが付いていることが多いですよね(デスメタル系バンドは長髪メンバーが多いので分かりにくいですが)
その瞬間に「これしかない!」と思いました
(現代のバンドマンからは「今頃そんな事に気づいたの?」とツッコまれそうですが)
バンドは合奏である以上、各自の当日の調子の良し悪しだけでなくステージ内での音の聞こえ方であったり様々な要因でバランスが崩れやすくなる可能性もあります
「今日は調子が良かった、今日は調子が悪かった」を極力無くしたいです
それらを断ち切る方法の1つですね
逆に言うならば環境依存がほぼ無い以上は「個人の楽器スキル依存」でやり切ることになります
我々は帰国後、すぐにクリックデータを作成しメンバー内で改善しながらライブ用のクリック音源を作り上げました
ライブの際にこのデータを利用しインイヤーモニター(いわゆるイヤモニ)で全員がクリックを聞きながら曲を合わせられれば環境依存での演奏バランスを崩す可能性は大きく減らせます
更に加えて2つの利点があります
①精神的な安定(当日の現場環境次第でどうなるか分からない等の不安減少)
②リハーサル時間の更なる短縮(環境依存が減るので基本はセッティング確認で済む)
他にも、会場規模が大きくなるとドラムから聞こえてくる生音とボーカルやベースの立ち位置に距離があるので音が遅れて聞こえてきます。勿論そのために”転がし”と呼ばれるモニタースピーカーが存在するのですが更にジャストで安定した演奏をしていくのならば必須になってくるのではと
次回ライブからこのシステムを採用しどんどん改善を重ねて行きます
そういうのを研究したりするのもライブバンドの醍醐味というか楽しいですね
他参考↓(クリックを聞くとは)
https://youtu.be/H9R41D9-U78?si=2H97YvXxLhSA6PDp
音楽的影響はいつまで?
音楽的影響を受けたのは若い頃(10代、20代)
現在は何かのバンド音楽にインスピレーションを受けるというのは無いですね
もしかしたらあるのかもしれませんが、基本は生活環境の中で思い付いたアイデアで創作します
お恥ずかしながら近年のデスメタルバンドの知見が乏しく周りの友人から教えて頂きその際に聴いてみるかYoutubeでおススメや関連で出てきた音楽を聴いてみるといった具合
デスメタルバンドをやっているのにデスメタルの話題になかなか付いて行けないという
メタリカ初期、メガデス、スレイヤー、初期ディーサイド、初期カーカス、デス、セイダス、初期ナパームデス。自身がエクストリームメタルジャンルで青年期に琴線に触れて耳に残っている音楽はこの範囲
近年はSNS等で流れてきたバンド(新しいものも)を聴かせて頂いたりもしますが、どちらかというとチェックするのは楽器スキルトレーニング系や機材情報系が強いです
創作は自身の中(脳内や心中やその時のタイミング)で行われるもの
生きてきた環境の中で発想し紡いで創るものだと思います
ただ、それが正解かどうかは分からないですしそもそも正解や流行を求めている訳でも無いマニア音楽ですので時流に流されないマイペースな自己流創作になります
ライブ不要論??
ライブを開催すると招聘側、バンド側も契約条件によっては赤字でどんどん疲弊していくという悪循環がまことしやかに…
打開策としての結論は前回ブログの通りパトロン、スポンサーではあるのですが、逆に開催する側やバンド側は「無理はしない」に尽きると思います
「赤字が続くのでバンドが続けられない」は本末転倒です
確かに音楽が好き過ぎるという情熱がそこまで振り切ってしまう背景もあるとは思うのですが継続させることが何より応援下さるファンへの恩返しなのです
我々は2020年の再起動後、レアキャラ的なライブ活動をしていますが正に上記を逸脱しない様に気を付けています
ですが、やる時はズドンと一撃フルパワーなライブにしています
もちろんCDが一枚1万円の代物であればバンドでもやって行けるでしょうが新幹線や飛行機、ホテルやリハ、全てを賄いながらマイナー音楽を物販の売り上げでやり続けるというのはそもそも矛盾
以前に書いたことがありますが当バンドは全メンバーへ経費支給しています
たとえ当日のライブ会場で1枚も物販が売れなくてもです
カレントメンバーはもしかしたら今は気づいてないかもしれませんがいずれそれがどういうことか(=対価を得るプロプレイヤーとしての責任と自覚)が分かる時が来るかもしれません
当バンドの活動はライブやレコーディング毎にバンマスで費用を持ち、バンマス自身は物販勝負という、ある意味ギャンブルなのですがこれは俯瞰しているから。バンド活動はそれも込みで自己責任でやるしか選択肢はないですからね。自由に好きにやることがバンド活動。もちろん我々の創作音楽に自信を持っていますし、それが例え勘違いだとしてもお構いなしです。むしろ自信の無い音楽を創作するくらいないら辞めた方が良いと思っています
メンバーへの経費サポートはセンスのある人が経済的要因で音楽を諦めるというのが嫌だから(散々見てきているので)というのもあります、とにかく続けて欲しいです
自身に経済的余裕があるとは言いませんが、なんとかそれができる範囲で生活しています
ただし、メンバー募集で「経費等保証します」と言ってしまうと幾らでも加入したいという人が出てきそうなので大げさに書きたくは無い内容ですが
これらはあくまでサブコンシャステラーという音楽の為に必死でプレイして下さるメンバーへのリスペクト対価
とは言え、もちろん音楽でご飯を食べているわけでは無いのでバンドメンバーが時代毎に失業や結婚や病気や親の介護等で離脱があるのはしょうがないですし、GOできる人が行くです
冠名(バンド名)が生きている限りはバンドを継続させる責任も感じています
後に離脱/脱落することはあっても以前のメンバーとの交流は今も続いていますしライブを観に来てくれたりサポートやアドバイスを貰ったりもありますからね
来年は数か国を跨ぐツアーも予定していますが、今から資金を含めた準備計画をしていく感じです
「バンド活動」って夢が無い様に聞こえてしまうかもですが我々はそこをノラリクラリと上手くやって行く自信は持っています、身体が動く限り
音楽活動は創作センス、ビジュアル、ライブ、スキルだけではなく総合的な部分で成長していく必要があることに一刻も早く気づき、どこまで俯瞰しながら行動できるかだと思います
マイナー業界の興行
音楽ではないのですが以前にマイナー競技系の世界大会を自分の会社で開催したことがあります
興行自体は上手く行きましたが、運営以前の準備の多さ、投資金、スタッフ確保、選手へのホスピタリティ、進行、閉会、その他に想定されうる事項の事前解決と対策など、掛ける時間と資金とその報酬の見合わなさは音楽興行と類似していると思います
何度かやるともはや悟りを開いた仙人にでもなったかの様に淡々とやれるようになりますが、経験が浅いと心が折れたり鬱病になったり心が歪んでキレ易くなったり
そもそもがマイナー業界ですから儲かるというものでもなく最悪は「なぜこんなにも貢献してるのに」と逆ギレしてフェードアウトというケースも
理想と現実のギャップでそうなるのでしょう
更には火に油を注ぐように「これだけやったのに」と思っても世の中には批判する人だっていますからね
ただこういった経験は本来、人間的成長のチャンスではあるんですよね
好き度合いが勝ち続けていればこの苦しいプロセスを潜り抜け続けて行くと徐々に達観というか俯瞰して行動できるようになり事前に自己防衛しながら痛い目に合わない方法を見つけ出していくという
この世界大会は主催が世界協会、主管が自分という状況なのですが自身も選手なのに参加はしませんでした、やはり無理でした。あまりにも忙殺されすぎて余裕が無かったですし興行を問題なく進行させ安全に閉会式までたどり着くことに集中することで精一杯でした
「興行の成功」とは(1)「安全」と(2)「収益」と(3)「ホスピタリティ」の3つだと考えています
音楽の興行で考えてみると日本ではなかなか難しいことが分かります
(1)「安全」→痴漢行為や暴力行為の撲滅
(2)「収益」→チケット代と箱代と招聘に掛かる資金と集客のアンバランス
(3)「ホスピタリティ」→痒いところに手が届く様なおもてなし度合い
この中でも(2)は本当に難しいと思います。ましてや近年はアーティスト都合のキャンセルも聞きますし招聘側としてはやり切れないですよね、全てが水の泡…
やはりパトロン、スポンサーが必要でしょう
ではそのパトロンやスポンサーですが「存在」するんですよね。世界大会を開くにあたっては巨額資金が必要だったのですが自己資金だけでなくパトロンさん、スポンサーさんに沢山援助頂きました
なので例えばデスメタル業界においてもデスメタルが好きな大企業の社長だったり、デスメタルが好きな富裕層の方だったりが「いるはず」なんですよね。その方達を最大限にリスペクトしながら巻き込んで行くことができれば国内でも何かできるかもしれませんね
我々は自分たちのバンドの活動だけで精一杯なのと現状その器量が無いので招聘興行はしませんが仮にやるならばパトロン、スポンサーの目途が付いている前提の選択肢になると思います
ですので個人招聘であったり、自身がバンド活動をしつつ招聘興行をされている方達には本当に頭が下がる思いです
好きだけでは難しいのがマイナー業界たる所以かもですね
潮流
先日中国ツアーをしてきました
まずはこちらのリンクを(当バンドツイッター)↓
https://x.com/japanterror/status/1890006249095516274?s=46&t=2I5Lyt1HU-2lgjUe4LBUAg
現在、現地ではエクストリームメタルの波が始まっています。まるで日本の90年代のバンドブーム時代かのような錯覚を起こしました
そもそも人口が日本の10倍ですから日本で100人のライブハウスなら現地は1000人という単純計算
人口市場規模の大きさが全てを凌駕しています
我々は初めての中国ツアーでしたがまるで大スターになったかのような、勘違いも甚だしいほどの盛況でした。たった2日のライブでCDは200枚以上も売れ、国内移動も飛行機、送迎車もベンツ移動etcで待遇のすべてがVIPでした
つまり中国ではエージェント、ライブハウス、バンド、全てが10倍の経済で動いていると考えるならば我々の様なマニア音楽ですらバンドで上手くやっていけるのではと勘違いしてしまいそうになる程です
将来的には世界中のバンドが中国を求めて市場を耕しにいくのではないかと推測します。そのくらい、衝撃的なツアーでした
その中でも重要なこととして1つ言えることは「言語」です
中国語が出来れば中国語が出来ない人の10倍は売れると思った方が良いでしょう
当バンマスは過去に中華圏での大学留学経験や在住経験(約10年)があり今回のツアーでもMCや物販、現地SNS発信含め中国語でも対応をしましたが特に日本人が中国語をしゃべるというのは一気に距離感が縮まります。突然仲良くなるような同胞的な感じでした
我々は今回、プロモーションの為にツアーが始まる直前に中国版X(旧Twitter)のバンドアカウントを作りました
これもかなり大きかったです。
その中国版X(小紅書)上でライブ前日に「上海へ到着!明日お会いしましょう」と一言呟いたのですが

それだけでインプレッションが10万(添付写真の眼マーク部分)を超え500近い「いいね」です
これ、ビックリしますよね。特に我々の様な小規模で無知名度なバンドにとっては
そして公演当日を迎えてのライブ中のMCですが
最初はやはり日本語や英語を使った方が外タレらしいかなと思いつつも折角なので中国語も使ったのですが中国語でMCをした途端、反応が100倍が大きい状況でした
とにかくみんなビックリしていました
当方、純日本人ではありますが難語以外は外国人であるとは気づかれない、ほぼネイティヴ発音。なのでMC中の中国語はインパクト抜群でした。期間中、現地のエージェントやスタッフからは冗談で「この人は中国人」と紹介されていましたがPAさんや初めて会うスタッフの方達とのやりとりもスムーズなので楽です
そうなってくるとライブ中の盛り上がる歓声だけではなく、ライブ終了後もダイレクトにお客さんとの会話が成立する背景から何百人とサインや写真を撮る状況になり本当に嬉しかったですね
メンバーも最初は困惑する程のサインや写真攻めでしたが良い経験になったのではと思います
現地言語を操れるのは大きな武器になります
物販もそう。通訳を通さず全て我々で中国語対応しましたのでお客さんから直接ライブや曲の感想を聞けたり、メタルシーンの話をしたり、とにかくライブ以外でも盛り上がりますので言語が出来る事は物販の売り上げにも大きな影響があると思います
将来、中国の規模はメタルシーンにとって救世主になるかもしれませんね
有限時間を大切に
前回ブログの中で出てきた「有限時間を大切に」について
先ずは以下へ当バンドの再起動後の時系列を書いてみます
◆2020年再起動と同時に「Reprogramming」アルバムリリース
↓
◆2021年1stアルバム「Invisible」の再発リリース
↓
◆2023年「Chaotic Diffusion」アルバムリリース
↓
◆2025年新作リリース予定有
その間に「Brutal Mindレーベルと契約」「Cryptopsy、Defeated Sanity、Skeletal Remains、Sinisterの様なレジェンドバンドとの共演」であったり「海外ツアー」も行いました
これだけで丸4年も掛かっています
現在20代でバンド活動への野心を持ったプレイヤーが居たとして上記を眺めてどう思いますか?
もっともっと詰めて活動していかないと一瞬で30代になり、40代になり、50代になります
我々はマイペース型バンド活動スタイルなので逆に反面教師として理解いただいた方が良いと思います
つまりは有限時間をどれだけ有効に使いながらバンド活動を行っていくかです
前提としての音楽センスだったりスキルだったりの比率が大きいとはいえバンド活動ができる年数はあっと言う間に過ぎて行きます
敏感な青年時代のセンス(五感)は活かした方が良いです
沢山曲を創って沢山ライブして沢山音源を出していくです
自身の音楽人生に悔いの無いように
日々沢山考え日々音楽を浴びながら有限時間を効率的に「音楽ライフ」を過ごしていただければと
そんな事を思う年齢になりました
当バンドのカレントメンバーはバンマス以外20代前半~半ば
若気の至りはあれども強い意志を持ったプレイヤーであることはヒシヒシと感じていますし責任重大であることも承知しています
老害にならない様に気を付けながら活動していければと思います
EUに関する世界的ブッキングエージェント契約の仕組み?
先日ヨーロッパのデスメタルレジェンドであるSinisterとツアーをさせて頂きました
期間中に彼らとの歓談の中で「将来我々がヨーロッパでツアーをするならばどのようにリーチして行くと良いですか?」と伺ってみたところ「Avocado Booking」と「Massive Music」を紹介頂きました
ヨーロッパのメタル系二大ブッキングエージェントです
仕組みとしては我々の様な超小規模なバンドは先ず700ユーロから800ユーロをエージェントへデポジットし例えばカニバルコープス等のヘッドライナーによるヨーロッパツアーの下にサポートでつかせて頂くような感じだそうです
確かに我々としても行った事の無い場所(クラブやライブハウス)に直接ブッキングコンタクトを取るよりも安心感がありますよね。更にはヘッドライナーが居ることで集客面やジャンル相関性においてもプロモーションがしやすいと思います
もちろん渡航費などの諸々は自費からのスタートとなりますしそこから実績を積んでいく必要があります。いわばバンド版の丁稚奉公スタートの様なイメージでしょうか
仮にヨーロッパツアーを敢行するとしてその費用シュミレーションしてみると
(1)約12万円(800ユーロ)→エージェントデポジット
(2)約60万円→メンバー3人往復格安渡航費(仮にスペイン起点で東方向へ国を跨いでいくとして)
(3)その他、保険やビザ、食事等諸々28万円
そこから更に忘れてはならないのが、、
(4)「ツアーバス」(寝台ライナー)の費用(ここでは仮に2週間で70万円としましょう)
上記金額を合計すると、つまりバンド側で先ずは最低でも事前に170万円の資金準備をする必要がありそうです(以前のブログにも書いた通り「金持ちの道楽レベル」からスタートできる位の資金能力も音楽の才能)
そこで我々の様なペーペーのバンドがこの多額な経費である170万円を補完するべくライブ会場でツアーシャツを売るとしましょう
現地会場の物販でシャツを売るならば単純計算でも340枚(xシャツ@5000円=170万円)は売れないと赤字になりますね。とはいえ本来はTシャツ原価もありますので「500枚ソールド」でようやくトントンを考慮した方が現実的でしょう
そして仮にポーランド、イタリア、スイス、スペイン、フランス、ポルトガル、ドイツ、ベルギーの8か国(大都市は二日連続でライブ)で12回公演するとしたら1会場につき最低でも40枚(x12公演)はシャツが売れないと赤字です
ヘッドライナーでもない無知名&小規模バンドな我々からすると相当ハードルが高いと思いますし実際にそんなに上手く行かないだろう(大量には売れないだろうも含め)と先想定もしつつ、その結果に対する自衛(資金準備)も考えながらの行動となりますね
更には「そもそも何百枚もの物販Tシャツをどうやって持っていくんだ」という課題もありますよね
スーツケースに詰めて自分で持って行くといっても飛行機に乗せる重量オーバー費用も相当な額になるはずです。なので現地のシャツ工場にあらかじめ依頼しておく想定も出てきますがそれはそれで制作マージンも発生します
我々日本人がヨーロッパツアーをするということは資金準備力だと思います
「ヨーロッパツアーに行ってきました」とSNSで拝見することがありますが帰国後は見えない所で赤残を埋める為に必死で働いているなんてこともあるかもしれません。ですがむしろその活動野心にリスペクトしかないですしバンドをやっている立場からしても「バンド活動が好き過ぎての行動」だと推測しますし「情熱が凄い」の一言です
現実的なお話ばかりになりましたが
逆にここを打破して行きながら世界中の各バンドがステップアップしているのも事実ですし、そういう風にやっていくのが海外バンドの自然な流れの様です
もしかしたらこのブログに辿り着かない限りこういった内容を知れないかもしれませんが若いデスメタルバンドプレイヤーや次世代プレイヤーのヒントになれば幸いです
有限時間を大切に
我々はいつかSinisterメンバーを訪ねて現地EUで会えたらと思います
※寝台ライナー(ツアーバス)についての参考↓
ショーが終わると機材を積んで次の国へ寝台バスで移動していきます
https://youtu.be/pS3Npz4yXMc?si=J7IVvnnRSJnTydAC
https://youtu.be/5CmC_kDh2WM?si=wNGr5sadWdMLJ7Mu
レーベル最終契約
いわゆる「レコード会社とのリリース契約」時はかなり細かく精査確認してから合意する必要があります
ISRC等の歌詞やサウンドに関する申請は事前にバンド側でやるにしても分かりやすい一例としてレーベル契約はフィジカル品だけでなくデジタルの版権をどうするのかも擦り合わせが必要ですしシャツやCDのレーベル側のストック数やバンド側の持ち数の把握もそうですし、こういった事を契約内容の中で「少しでも曖昧さ」を残したままにしてしまうと後でおかしなことが起きたりする可能性も
かといってバンド側の主張の仕方がまずい(強い)と相互が気持ちよい関係値でリリースできなくなる(例/プロモーションが弱くなる等)ということも想定しながらやる必要があります
バンマスもしくはメンバーの誰かがこういった契約内容に関しては非常に高い能力値を持っている必要があります
浮かれている場合では無いのです
知見が無く分からないのであれば先輩バンドにアドバイスを仰ぐも良し、今ならネットからも沢山情報を集められますし色々と勉強してみると良いかもしれませんね
自己防衛というかむしろレーベルとの関係を上手くやっていく為にも必要不可欠な1つだと思います
我々日本人の独特な性善説のやりかたではすぐに足元をすくわれるでしょう
ですがそうは言っても良好な関係値を保って行く必要がある訳ですから人間としてのバランス感覚が必要となってきます
脳疲労を1億回起こすくらい思慮深く相手のことも考えながら進めて行く必要があります
なかなかハードではあります
追記:他にも「工場プレス前のデザインに関するレーベルとバンドの相互確認」は最も重要です(ファイナルチェック(我々はレーベルのデザインチームがブックレットのレイアウト制作をして下さっています)例えばブックレット内のスペルが間違えてるとかの基本的な部分だけでは無く、最後にシレっとコピーライトの部分が異なっているとか。とにかく最後の最後まで気を抜かずにあらゆる箇所を今一度、隅々まで精査する必要があります。これはいやらしい話では無くレーベルとバンドの関係値を健康的に良好でお互いが気持ち良い方向に保つためでもあります。(以前にミスをして結果作り直すことになってしまった経緯があるので強調追記しました)
ビジュアルの重要性
音源だけでなく生のライブでも聴覚補完として重要なヴィジュアル
SNS全盛の今、より一層バンドカラー、バンドイメージの重要性をかなり感じています
遠くからでも「あのバンド」だと分かるくらいに
我々は基本は黒軍パン、長髪、変形ギターというビジュアルです
90年代からのバンドなのでベーシックスタイルと言えばそうなのかもしれませんが
現時点ではまだ想定できていませんが近年海外ツアーをしてみて分かったのは、ビジュアルに対しても独特なバンド用のオーダー衣装があった方が更に良いのかもしれません、そう思い始めました。
遠方から観戦に来られる方達も多く、我々が精一杯出来ることとして演奏やMCは当然としてだけでなく観戦全体を満足して頂ける様にビジュアルも含めた最高のライブにするのが演者の使命ではないかとも
オーダー衣装というと二の足を踏みがちですが今後検討の余地はありそうです
デスメタルはボーカルも楽器として
作品として歌詞は存在すれどもデスメタル系のボーカルは楽器色が強いと思います
ディーサイドやオビチュアリー等多くの英語を母語とするデスメタルバンドのボーカル
実際のライブでは楽曲に合わせて「吠えている」
歌詞カードと照らし合わせながらYoutube等で彼らのライブを見ても該当するその英単語を発しているとは思えないです、サビを除いては
青春や恋愛や共感などを歌う訳ではないエクストリームメタルミュージックはボーカルも含めて全体を音楽として聴くイメージが強いと思われますしそれで良いのだとも思いますし違和感も無いです
低音な声を追求したりグロウル追求したり、つまりボーカルもトレーニングをしながらそのテクニックを磨くといった様な楽器感があります
「曲に合った声(質)」
デスメタルジャンルの究極なボーカルはこれだと思います
Youtube等で彼らのライブを歌詞カードを追いながら観てても殆どそうは言ってない(吠えている)ですが、やはり「楽曲全体の響き」としてのボーカルという立ち位置である場合が多いのでしょう
そもそも「低音デス声の存在」は単語をクリアに述べるのとは矛盾する方向の声質ともいえますしね
曲創りを続けると最終的にどうなるのか
私的には未知の世界です
これまでの当方の創作曲はまだ100曲超えていませんしね
洗練されるのか、変わらないのか
一つ言えることはブルータルでスピード感を持ったことをやり続けたいです
例えばメタリカ
キルエムオールからアンドジャスティスまでがいわゆるスラッシュメタルでブラックアルバムからヘヴィロックへと大きく音楽性が変わりました
例えばカーカス
リークオブからハートワークまでが所謂グラインドコア&デスメタルの流れでスワンソングでヘヴィロックへと。ただし彼らの場合は当時レーベルとのいざこざや様々な要因もあるとは思いますが
このようにクリエーターがガラッと創作内容を変えてしまう(変わってしまう)をリアルタイムで目の当たりにしてきています
どういう心境の変化は本人に聞かない限りその真相は分かりませんが商業的にそうしたのか、心変わりがあってそうしたのか
かと思えばスレイヤーの様に初志貫徹バンドも
ギタリストではマーティフリードマン氏(元メガデス)やマイケルアモット氏(カーカス)やホフマン兄弟(ディーサイド)が好きなプレイヤーですが発想って変わって行っていますよね
これらの辿る道を見ていてですが
我々の場合はブルータルでスピード感をもったデスメタルバンドであることは変わらないと思いますが創作音階についてはもっと洗練していきたいとも
そうなったときに「洗練」という意味がどうなっているかは未知な世界でもあります
とはいえ、我々は出来た曲が出来た曲なのできっとスレイヤーの様な初志貫徹なバンドなのかもしれません。
スキルについては向上心が強いのでテクニカルな方向やリズムトリックは取り入れて行きたいですね
我々の様な非有名小規模バンドでも良い意味で招聘される可能性のあるバンド
結論を先にいうと「卒なくキッチリ演奏をやり切れるバンド」です
曲が良いとか悪いとか以前に「ライブパフォーマンスを滞りなく当日の催事を全うできる」こと
リズムキープがおかしいとか、演奏がズレてるとか、普段の言動がキレているとか、ライブに穴を開けるとか、連絡が取り難いとか、やりとりの機転が利かないとか、そういう類は「使う側」(=招聘する側)としても危なっかしいので難しいです
やはりプロフェッショナルなバンドであるならばその場を卒なくやり切れる能力を持ったバンドであるかどうかは最低限の条件だと思います。学芸会バンドでは無い訳ですからね。
それが出来て初めて実績であったり今後の活動ステップアップに繋がって行く可能性
なぜこう思ったかですが近年CryptopsyやDefeated Sanity、Skeletal Remains、Sinister(予定)といったビッグバンドとの共演で「卒なく催事をこなせる」、「エージェントとしっかり関係を作れる」(ちゃんと話が出来て約束を守れる)という能力が非常に重要である(当然)と再認識したからです
近年はバンド資料を送るような場面においては見られ方が変わってきていることを肌で実感しています
以前なら「どこぞの馬の骨」感が強かったので体当たりでしたが今は返信が来たり反応があったりします
この辺は曲が良いとか悪いとか以前の問題であり一歩一歩バンド実績を積んでいくしかないのだと思います
あとバンドマンは皆んな気にはしているとは思いますがバンド全体のビジュアルです
やはりバンドカラーがあった方が使う側もイメージを捉えやすいです
我々はオールドスクール系ですが黒軍パンに黒シャツ(+長髪)でずっと統一してきています
それがバンドカラーなので
ですのでバンド活動は「ただ曲を創って」「ライブをしてれば良い」とはまた違うのかもしれません
バンドの全体像を作れてこそなのかもしれません
理解と限界突破の繰り返し
「楽器のスキル」ってどうやって身に付けているのでしょうか
巧くなるかならないかはセンスなので元も子もありませんが少し考えてみたいと思います
(センス:例えば大谷翔平さんの10倍練習したら野球が巧くなる訳ではないので)
当方の場合は3パターンです
①「うわー、これは凄いな」「琴線に触れるな」と言った曲があった時にコピーしてみる
②限界突破して身体がキツくなり腕が止まるまで速弾きし続けるを繰り返しそれをデフォルトにしていく
③超速弾き系はスローで一音一音を鳴らし脳内で仕組みを理解する時間をしっかり作りつつ、デフォルトの激速スピードで練習する
ほぼこれですね
そこから先ですが
毎回ライブ演奏毎に気になったところ(ミスし易い)をメモしているのでその部分を強調しながら繰り返し練習して更に習熟させていきます
独特な練習方法なのかもですし、それが合ってるかどうかは分かりませんが
ちなみに創作時ですが、脳内でこういった音階を弾きたいからという創り方もしているのですが、その際はかなりキツイです。自作曲なのに弾けないというところから練習していくのですが意志が強いので必ず弾けるようになるまでやります
今回は「仕組みの理解」と「限界突破の繰り返し」練習方法のお話でした
貧すれば鈍する
上記動画(特に後半)、言い回しも切り込む感じなので賛否両論ありそうですが概ね同意です
このブログ上でも散々書いてきましたが「余裕を持って心豊かに生活が出来て」いてこそ「良い音楽活動」や「良い創作活動」が実現できるという
「貧すれば鈍する」とはよく言ったもので余裕が無いと精神衛生上でも創作や活動に対するアイデアや視野を研ぎ澄ますことが難しくなると思います
これまでに何度も何度も書いてきていますが普段の生活を豊かに自由に過ごせる環境作りが出来る事も音楽センス
これが出来れば「普段の仕事があるので連休利用しないとツアーに出れない」とか「気難しい上司と掛け合って有給申請で調整しなければならない」の類は関係無く自由設定で海外ツアーに2,3週間出て行ったりも可能となります
但し全メンバーがそういった生活環境(フルタイム活動)というのはハードルが高いので現実問題としても世界中の多くのバンド(有名/非有名を問わず)はサポートメンバー対応などの工夫をしつつツアーに穴を開けない様に(欠員の無い様)している訳です
そもそも我々の様なバンド活動は「やればやるほどに経済的負担が増えて行く方向」
なので言葉を選ばず、乱暴な表現をするならばバンド活動は「金持ちの遊び」からの派生
「好き勝手にやりたいことをやる」活動とも言えます
例えば「冬にハワイにゴルフをしに行く」として
掛かる金銭負担をサポートしてくださる様な奇特な人はなかなか居ないはず。バンド活動もこれと同じで「好きでハワイにゴルフをしに行く」が基本ですから自腹活動だと思います。それと同じニュアンスです。それをもしも全額負担下さるような方が居たとしたらエンジェル投資家なみの好待遇だと思います
これらを経済的観点からもう少し進めて話をするならばですが、
考えもみて下さい
例えば「世界的アーティストにアートワークを描いてもらう」って自腹(高額)で払えますか?という
例えば「世界的エンジニアにミックスマスタリングを依頼する」って自腹(高額)で払えますか?という
レーベルに所属していてレーベルから予算が貰えるならば良いですが無所属のDIYバンドだと自己負担でしょう
Money is Powerとまでは言いませんが普段からそういった「音楽に漬かれる生活環境作りができているか」です
もしも4畳半アパート&アルバイト生活をしながら将来の夢を見て活動していたとすると上記の実現は非現実的だと推測しますしハードルも高いと思います
そもそも貴バンドの音源リリースの為にお金を払ってくれる様な奇特で天使の様な人は稀です
やはり自力でそれらをやれる位の能力が必要になってきます
ガチでやりたいならば「ガチでやれるための準備を日頃からしていますか?」という事にも繋がります。その準備をせずに「なぜバンド活動が上手く行かないんだ」と心が歪むのは、非情ですが正に「貧すれば鈍する」の典型かもしれません
例えば「普段が九州在住で遠征をして東京でライブをする」としましょう
メンバー4人の交通費や宿泊費が最低経費だとして
キャパ200人のライブハウスとして当日のライブ会場の物販で貴バンドのCDが当日に100枚も売れますか?
残念ながら多分売れないと思います
という事は活動をすればする程に経済的負担があるということに…
バンド活動をするという事
言い換えるならばこう言ったことも含めての活動であることが前提なのを先に理解&事前把握をすることで後の活動計画(シュミレーション)も立てやすくなりますし、それでも最終的には収まるところに収まると思います
「好きな音楽を好きに創作しつつマネタイズ出来ること」も「音楽才能」の1つだと私は思っています
ただ、ここで言うマネタイズとは音楽で生活の費用まで賄うという意味では無く「音楽活動を末永く続けられる」為の意味合いです。あくまで生活はまた別の話です(=それは自力)
特に我々の様な音楽は売れる為よりも「好きでやっている」が限りなく100%に近いですからね
デスメタルという非商業音楽方向なサウンドでそれをどこまで近づけられるかは(音楽活動を潤滑に末永く行うためのマネタイズ)日頃の絶え間ない生活環境の工夫が必要でしょう
SNS活用
当バンドはSNSの活用が苦手です
有効&効果的に使えているバンドは素晴らしいですよね
言うなれば「無料プロモーションキット」ですから我々の様な小規模DIY系バンドにはリリースやライブ告知等が無料で行えるのは非常に有難い存在です
大手SNSを全体視野(地球規模)で見てみると音楽系告知は以下の様な私的イメージです
・国内主要→X(旧Twitter)
・海外主要→Instagram(+Facebook)
世の中の音楽バンドの規模は非情ながら「フォロワー数とストリーミング再生回数で判断されるビジネスモデル」なので我々の様な規模の小さいバンドの場合はフォロワー数も当然少ないので例えば海外エージェントにツアーを依頼する際、資料にSNSリンクを付けるケースが多いのですが先ずそこで弾かれる可能性があります。つまり、少なくとも万単位のフォロワー数が無いと「土俵にすら上がっていない」と言ったようなケース
海外エージェントはビジネス。日本の様な「赤字でもやる、応援招聘する、以前お世話になったから招聘する」といった人情や性善説(人が良過ぎる)での招聘はほぼ無いです。もちろんこういった我々の持つ「日本人魂」は本当に素晴らしい限りではありますが島国から一歩外へ出ると厳しい現実も待っています
基本、やるなら「全て自分でブッキングして自腹で勝手に行って勝手に帰ってくる」です
もうすぐSinister帯同の中国公演があります(このブログを書いている2025年1月中旬現在)
今回のSinister中国公演帯同ツアーに関しては良縁に恵まれエージェントのボス氏が我々を好待遇で迎えて下さります
前日入りでの全出演者との食事会を含め、上海公演の次の日は天津までの移動新幹線がグリーン車で滞在期間中の宿泊ホテルも至れり尽くせり。更には物販関係までサポート下さる至れり尽くせりなおもてなしを頂き申し訳ないほどの好待遇
ただし、これだけの「おもてなし」は奇跡的なことであり通常は「あり得ない」と考えた方が良いでしょう。今後足を向けて寝れない程に様々な手配とお世話をして下さり感謝しかありません
余談ですが(ここがバンドマンならばキーポイントかもしれませんが→)ツアーが決まって以降、ボスとは普段から日常会話をする関係になっています。なんなら私用をさておいても「即返信」は当然ですし、未だお会いしたことも無いのに既に親友関係
「何かをやる必要がある=即日」が基本で、この世界もやはり信頼関係がとにかく重要です
こういった信頼関係にまつわる話を遡ると我々の所属しているBRUTAL MINDレーベルも同じ事が言えます。レーベルボスが東京に用事があり来日のタイミングがあったのですが、仕事を休んで遠方からすかさず会いに行き個室で会食歓談しました。考えてもみて下さい、そもそも来日下さる事自体が稀な訳ですからそのタイミングで日本に来て会いに行かないという選択肢は無かったです
そう言えば稀に「エージェントを紹介して欲しい」とか「エージェント契約条件を教えて欲しい」と聞かれることもありますが「少なくとも当方がやっている位に相手を思いやりながら親身な付き合いが出来るのか」に対する疑問があるような人への紹介は難しいです
その後に「配慮の無い、変な奴を紹介してくるなよ!」と当方との関係にも響くので…
話が逸れそうなのでSNSの件に戻りますが14億人口の「中国での音楽系告知SNS」がどうなっているかですが、先ず現地ではX(旧Twitter)やInstagramは使わないです(正確には使えないです)
なのでX(旧Twitter)やInstagramで「中国でライブしますので是非観に来てください!」といくらツアー告知をしても殆ど意味がないです
ではどうやって告知をしていくのかですが
その答えは「小紅書(Red Book)」という「Instagram(画像&動画)+Amazon(商品購入)」の様なアプリです
現在、地球上を席巻しているのでご存じの方もいるでしょう。登録ユーザー3億人越えだそうな世界規模の超巨大SNSです
我々としては気づくのが遅く、若干今更感もありますがこの度せっかく現地でツアーをさせて頂きますので良い機会ということでバンドアカウントを作りました(現地エージェントにライブ告知アプリとしてやった方が良いと勧められました)

現地ではX(旧Twitter)やInstagramやFacebookはほぼ誰も見てない訳ですから「中国でSinisterとライブします、是非観に来てください!」なんてTwitterやInstagram上で告知をしたところで…
というのもあります
実際、この「小紅書」を覗くとデスメタル系だけも膨大な情報量がありライブ日程などの音楽系プロモも沢山出てきます。もっと早く気づけば良かったのかもしれませんがこれからコツコツやっていきたいと思います
ただ、先述の通り当バンドはSNS活用が苦手なのでどういった内容でUPすることが表現として効果的なのかのワードをなかなか思い付けないので難しい所ではあります
もし興味があれば上記のQRコードからSUBCONSCIOUS TERRORの小紅書を覗いてみて下さい
できればフォローもお願いします!
センスのある人は諦めないことが重要
10代20代でガチのバンド活動をしているセンスあるプレイヤーは諦めないことが重要
精力的にライブをしたり音源リリースをしたりしつつも、徐々に30代が見えてくると将来を悲観したり考え込んだりしがちだと思われます。そこでセンスを活かしきれずにフェードアウトするのは持ち腐れですよね
諦めない為の1つ目は「クリエイターである」こと。つまり楽器は出来るけど作詞作曲は出来ないとなると「どこかのバンドに入る」以外に選択肢が無くなってしまいます。なのでやはり作詞作曲が出来るプレイヤーの方が長く続けられる可能性はありそうです
創作が出来るというのは他にも利点が多く、例えばリハーサルやライブの際も作曲が出来ることで他のパートへの配慮やテンポタイミングも思慮しながら演奏できます
「この人との演奏は合わせやすいなー」とか感じることがありますが正にそれだと思います
2つ目は何よりも「(音楽活動ができる)生活環境作り」。これさえ整備できれば思う存分創作に時間を費やしたり、練習に時間を費やしたり、思う存分に海外を含むライブツアー活動をしたりが叶い易いと思います
センスのある人が「諦めてしまわない」為にも上記2点に関し私的にはそこに尽きると思います
レコーディングし終わったばかりですが
SNS等でも既報通り昨年(2024年)に次作のレコーディングを終えています。現在リリースに向けて準備中なのですが、その後もすぐに次のアイデアが溢れるように出てきていてラフデモ作りを始めています。我々の場合はラフデモ→プリプロ→レコーディングの流れですが第一ステップであるラフデモ作りをしています
「発想はタイミング」
思い付いた時にどんどん進めます。常に瞬間的なんですよね。「ヨシッ!これから曲を創るぞ」では無いです。他のプレイヤーはどうやって創作アイデアが思い付くのか分かりませんが当方の場合はタイミングを大事にしていて思い付いた時に一気に作ります。ですのでタイムマシーンでも存在ない限り二度とその音階は創れないですしその瞬間に湧いたアイデアが(自身の)琴線に触れた時の感覚で創作を紡いで行きます
創作は本当に楽しいですね
一生涯を純粋に音楽を楽しみながら活動していきたいです
健康的なバンドの成長
メンバー内での健康的なバンドの成長という視点で書いてみます
①バンド内連絡事項におけるレスポンスの速さ
②情報の保守
③積極的な活動の参加
④自立した経済活動
①は一般企業で働いている方もそうでしょうし友人との付き合いでもそうでしょうし返信や回答のホッタラカシはそもそも人間として信用を落とすことになると思います。特にライブスケジュールやレコーディングスケジュール関連なんかもそうですよね、ジャッジメントが必要な際にホッタラカシだと先に進めませんので
②は例えば情報公開前に個人的にSNSで匂わせたり掛け持ちプレイヤーが兼ねているバンド側に情報漏洩したり。これらも信用を落としますし掛け持ちプレイヤーが最もやってはいけない事の1つですから今後お声が掛かることは無いでしょう。一般企業でいうところの競合会社への機密事項漏洩や客先への製造原価の漏洩と同じレベルかと思います
③否定的な言動。この時点で遅かれ早かれ続かないでしょう
④は「言わずもがな」かもしれませんがデスメタルで飯を食うは非現実的です。できるだけ充実した人生を送りつつ表現豊かに楽しく音楽活動をしたいですね
色々と挙げてみましたが「信頼関係」がもっとも重要であり、そこに「目指す視野の一致団結」が加えられることでバンドが健康的な成長を生むと考えています
「目指す視野」に関しては音楽性だけでなくどのような活動の幅を持った視野(分かりやすい例だと:地元活動or海外まで視野、セルフリリースor大手契約etc)で進めて行きたいのかをしっかり共有しながらやっていくことかもしれません
海外で過ごした約10年
当方は過去に約10年海外で暮らしていました(帰国後にサブコンシャステラーを再起動)
日本の様な性善説で生活できる様な国は珍し過ぎるので今回は自身の経験に基づき海外慣れしていない日本人が海外ツアーで気を付けることや準備物などを書いていきたいと思います
先ずは飲水ですね。海外ツアー中の体調不良だけは避けたいのでミネラルウォーター必須です。海外慣れしていない人は歯磨きの際もミネラルウォーターで良いと思います。ちなみに氷の入った飲み物も免疫力が無いとすぐにお腹を壊す人も多いです。氷をミネラルウォーターで作っている飲食店は少ないので(ほぼ蛇口の水で氷を..)
次はポケットを膨らまさない事。財布が入っているのがすぐに分かるようなのはやはりリスクがあります。歩いているとポケットに手を突っ込んでくる人もいます。他にもよくあるのがリュックサック。例えば電車の切符を買う際、そーっと背後に近づきチャックを開けて中身を取られるパターン。この辺は定番といいますか経験談。あとは日本人独特のモーション。ペコペコお辞儀するような動き。これはすぐに日本人だと分かりやすいのでリスクを伴うケースがあります。
残念ながら当方も過去に海外路上で幾度か襲われたことがあります。逃げ切るか抵抗せずに差し出す事が身の安全確率が高いと思います。なお友好国ではない場合、警察に相談しに行く事自体が更にヤブヘビとなるケースも想定しておいた方がよいかもしれません
あとは交通機関。アジアでよく見る乗り合いのバス(ジープ等)。運転手とギャングが手を組んでいるケース。お金を持っていそうなお客が乗ってくると運転手が携帯電話でギャングに連絡を取りわざとその乗り合いバスを襲わせるパターン。その後に運転手とギャングが山分けするという。これも過去に経験。
更にタクシーの1人乗りは特にリスクがあります。海外在住時、友人と一緒に飲食店でご飯を食べていたのですが、その友人が用事があり先に帰るとなり1人でタクシーに乗ってしまったのですが、運転手からナイフを突きつけられました。前を走っている車と詰まってスピードが落ちた瞬間に無理やりドアを開けて飛び降り逃げ切りましたが…
他には飲食店で出てきた料理にケチを付けるのはオススメしません。個人的には諦めるしかないと思います。例えば「この料理に髪の毛が入っているから変えて下さい」のケース。倍返しというかその料理に唾やタン、ゴキブリ等が入って戻ってきたり金額をボッタくられたり。なので諦めて別の料理を頼むか機嫌よく会計を繕い店を変えるが無難かもしれません
郷に従うとはよく言ったもので上手く乗り切ることが重要です。日本の様に「叩く」をやってしまうと身の安全が確保できなくなるケースも。あくまで海外では我々は外国人ですからね(日本は特殊過ぎると言いますか日本人同士で足を引っ張ったり徹底的に叩く文化が根強いかもですが、それは銃社会では無いから幾ら人を叩いても反逆されないだろうという精神なのかもしれませんね)
次はバンドマンとしての持ち物関連です
<持ち物>
①パスポート(有効期限の確認必須)
例:半年以上有効期限が無いと入国不可の国などもあるので要注意です
②パスポートコピー
③VISA
④航空チケット予約書のコピー
⑤アプリ決済の準備(キャッシュレス)
⑥クレジットカード
⑦マスク
⑧気候に合わせた着替え
⑨楽器機材一式
⑩国によっては変圧器
⑪携帯電話etc
ザックリとこういった感じでしょうか。あとは楽器機材の配列を「複雑にしない事」と「頑丈な機材を選ぶ」ことでしょうか。もちろん出国前には断線や接触不良などが無いかメンテンナンスに出しておくこともオススメです。メタルギタリストであれば必須である「ディストーションエフェクター」は予備で1つ多めに持っていくのが良いかもしれません、故障や盗難を想定して万が一の為に
ちなみにマーチ関連は先に現地に送るかスーツケースになんとか入れて持っていくかになると思いますがスーツケースに入れて行くならば空港で荷物を預ける際に重量オーバーになってしまうと追加料金が必要なので先に送る場合の郵送料金と比較をしながら対応。あらかじめ下記の様なグッズを持っておく事もお勧めします。
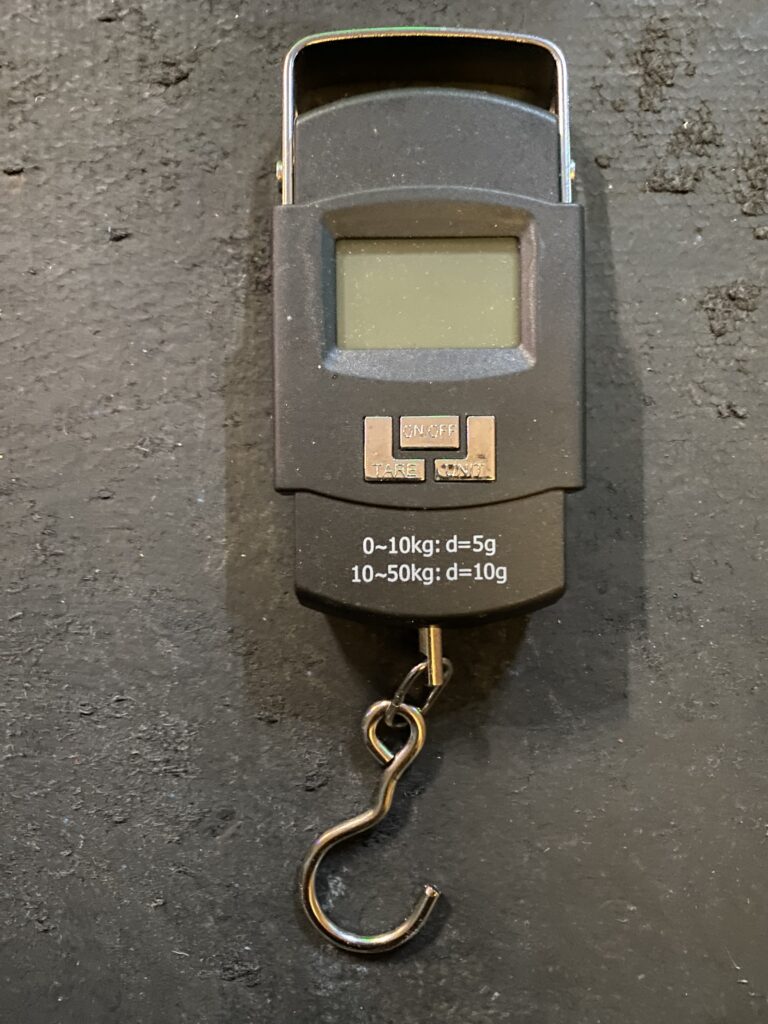
↑記憶が曖昧ですがこの重量計はAmazon等で1,000円もしなかったと思います
※ちなみにSinisterツアー帯同(海外)の際、我々は重量オーバーやスーツケースが嵩張るのを低減する為にバルク(CD単体とブックレット単体)でスーツケースに入れて持っていきます。今回は御好意で現地主催者がジュエルケース(プラスチックのCDケース)を準備下さっているので宿泊ホテル等で手分けして挿入組立てするという具合です。こちらも参考までに
次は現地での衛生関連について
先ほどの飲水関連で触れましたがペットボトルのミネラルウォーターですら偽物も多く出回っていてそれでお腹を壊す人もいますので現地での周りのみんなが飲んでいる水などの確認推奨です
それから水道水の水は日本とは違い「硬水」である国が多いので例えば洗髪をする際のトリートメント剤等は使い慣れたものを日本から持っていくのが良いでしょう。さもないと髪の毛がギシギシに
特にお腹が弱い人は滞在中、火がしっかり通ったものを食べたり等の工夫をしながら体調管理をしつつ安全で健康なツアーを心掛けて乗り切って行きましょう
※日本人のパスポート所有率が17%(6人に1人)らしいです。世界的にも稀にみる所有率の低さですが(外国に行く人が少ない)逆に考えると日本での生活があまりにも良いとも言えそうですね
兼パートプレイヤーの練習方法
ボーカル兼ギター、ボーカル兼ベース、少ないですがボーカル兼ドラム
こういった2パートを兼ねて担当しているプレイヤーは普段どのように練習しているのでしょうか
当バンドはボーカル兼ギター(バッキング&リード)形態ですので当方のやり方を話してみます(ただし、それが合っているかどうかは分からないです)
例として「まだライブパフォーマンスした事の無い新曲」を弾きながら歌えるように習得していくという内容で挙げてみます。最初は本当に苦しいです。というのが作曲時はギターで創り、後にボーカルを載せて行きますので「同時に歌いながら弾く」のは後から付いてきます。なので分離&反射反応できる様になるまでトレーニングする必要があります。
まず1ターン目としてはドラム音源を聴きながらギターだけを通して繰り返し弾いていきます
そして2ターン目としては口を動かしながらギターを弾いていきます
その際に「口の動き」と「指の動き」の連動違和感の有無を確認します。つまり口と指が分離して反応出来るようになるまで行かないと片方が”もつれて”しまいます。同時反応なので違和感があればその部分を繰り返し修正していきます
そしてようやく3ターン目で実際にマイクで発声しながらギターを同時に弾いていきます。加えてギターソロもありますからエフェクター類の切り替えも含めてのアクションが必要。こちらも反射反応できるまでトレーニングして行きます
この1ターン目から3ターン目までをひたすらグルグルと繰り返し練習していき「どこかでもつれる箇所」が無いかを確認し見つかれば修正しながら反射反応できるまでトレーニングしていく流れです。自作曲といえども反射反応できるまでかなりの練習量が必要になってきます
そうこうしていくと最終的には殆ど無意識反応出来るようになり、ギター音階が大きく移る際にフレットを眼で見るくらいでパフォーマンス出来るまで行き着きます
脳内意識が強い時(確認をしながらプレイしようとすると)は大体リズムがモタります。考えながらやっているとスピードに間に合わないです。脳からの指令と肉体反応までのディレイ(遅れ)の差がモタりに繋がると考えているので反射反応が重要だと思います
もっと言語化するならばボーカル(発声)とギターの指の動きが自覚思考から外れて行き、無意識に近い状態で反応していくです。あくまで当方の場合なのでそれが合っているかどうかは分かりませんが
近年はYoutubeが出てきたので例えばNecrophagistの様なテクニカル系バンドのボーカル兼ギターのライブ映像を観たりして「口と指の分離の仕方」+「目の動き」なども参考にできそうですね。
その上でドラムリズム(聴覚)に合わせて体感タイミングを取ることになりますのでトレーニングあるのみです。我々はテクニカルなんておこがましい範囲ですが上記の様な「テクニカル系の兼プレイヤー」はただただ凄いと思いますしリスペクトです
それでも音楽ならば
「いわゆるサラリーマン」という経験は人生上で僅か何年かしかやったことが無いです
昔はバンドマンと言うとアルバイトしながら4畳半のアパートに住んで路上ライブからスタートしてのサクセスストーリーの様な事もあったかもしれませんが、現代においてはそれが現実的では無い事が分かると思いますし、末永く活動したいならば「よりクレバーな立ち回り」が必須です
デスメタルバンド活動で言うならば、例えば長髪でやりたいとか、海外ツアーをしたいとか、大手海外レーベルと契約したいとか「10代20代のデスメタラーバンドプレイヤーが思う描く様な夢物語」
これを現実化させるならば「自由な生活環境作り」がなによりも第一です
当方1か月家を空けてのツアーも可能です。ですがそもそも全メンバーがそれが可能というのはほぼ無理でしょうし、そんな人だけでバンドを組むなんて難易度が高すぎます
諸々を俯瞰しているのでバンドマンの夢を壊すようで恐縮ですがフルタイムでやるならば会社経営(自由が利く)か資産家です。あるいは最低でも実家があり(居住費が固定資産税だけで済む)、更に何か不労所得(マンション所有で家賃収入有り等)を持っているなど
人生100年時代において20代のガチ系バンドマンによくある将来の行く先を懸念して思い悩むケース
地元ローカル活動ならばサラリーマンをしながら趣味として週末活動をやって行くでも大丈夫でしょう。ですが視野の広い活動を続けるならやはり起業
それも無理ならば…つまり音楽でしか生きていけないという極論ならばですが。
流石にデスメタルで生きて行くのは無理なのでサイドプロジェクトででも音楽をやるしかないでしょう
例えばですがボカロ系
ドラムを打ち込み、ベースも打ち込み、ギターは自分で弾いて、歌は初音ミク等のボーカロイド。
もちろん生まれ持った創作センスが前提ですが
あとはバズるまでひたすら100曲でも200曲でもどんどん創って例えば毎日YoutubeやSpotifyに最低1曲はUPし最終的にマネタイズできるまで365日創作&曲リリースして行くでしょうか。これは食うための音楽ですね。自由を得ながら生活をするということはその位は努力とも言えない範囲だと思います
サラリーマンを殆どしたことが無いと先述しましたが自由な人生時間を得るための思考は誰よりも考え抜いてきたと自負しています。自由生活を夢見る10代20代のガチ系プレイヤーさんには是非上手くいって欲しいですしそれを手に入れて欲しいです
10代20代のプレイヤーの中で、どれだけやっても上手く行かないことが起因し自暴自棄になったり鬱病になる人も多いです。非情ですがそもそも音楽がどんなに好きで、誰よりも好きであってもそれで生活するのは困難です。ましてや現在はストリーミング時代ですから更に難しいでしょう
だからこそ末永く音楽活動がやれるように環境作りを上手くやって欲しいです
その暁には24時間365日デスメタル三昧な生活環境が待っていますよ
以降の目標
現況はギターバッキング&リードギター&ボーカルという3役でライブをしていますが、そろそろ曲中で細かくギターサウンドを切り替えながらライブを行いたいと考え始めています
これまではギターアンプの上にエフェクターボードを載せたまま、ライブの最初から最後まで一切音を切り替えたりすることなく1つの音でプレイしていました。ですがやはり音色も曲に合わせて変えながらプレイしたいと思うように
とはいえ、歌いながらギターの音色(エフェクター)も適宜切り替えて行くというのは至難の業。少なくとも不器用な当方にとっては。なので少しづつ段階的に音色の切り替え数を増やしていくというプロセスで今後トライしてみようと思います
思い立ったら即行動なので最近はフットスイッチを始め空間系を含むエフェクター類をどんどん揃え始めています。最終的にはどの組み合わせになるのか分かりませんが自分の中で完璧と思えるまで試行錯誤しながらしっかりプログラムを組み込んでいきます。やり慣れるまでを考えるとイメージ的には2年掛かり位で目途を立てられればと(無意識でサクサクと音色を切り替えながらライブ演奏できる位まで)
お楽しみに
アニメやアイドルやビジュアル系などの日本文化を前面に推しだす
そんな人が居るのかどうかは分かりませんが日本人でもしもエクストリームメタルで商業的に成功したいなんて思う人は「アニメ+アイドル(女性)+AV(文化)」の融合
特に欧米由来のメタル系ジャンルは肌の色と言語が大きく影響しますので黄色人種である我々はハードルが限りなく高いです。実際欧米では我々が日本人なのか中国人なのかなんて分かりませんよね。単に黄色人種という一括りです。男性でしたらXjapanの様なビジュアル系でエクストリームメタルを推しだす様なこれも日本の独自な音楽文化な格好でしょうか
海外から見た日本は「食」と「性善説」と「アニメ」と「AV」と「清潔」と「細かい作業」が文化として突出していると思います
そこから音楽と結びつけるならば極論的には際どい衣装を着たアイドルがデス声やアイドル声で歌って踊ったりもするエクストリームメタル。これは道が開ける可能性(海外フェス等でも見た目で日本文化が分かりやすいので日本人代表枠にもなりやすい)もありますし楽器が出来ればなお良しです
もしも黄色人種&男性で正統派デスメタルや類系エクストリームメタルを上記の類でやるならば相当の覚悟をもってやることになります。資金力は第一として創作や楽器テクは超優秀で当たり前。それでいて英語での意思疎通は最低限
将来、この辺りをも凌駕する男性による次世代国産デスメタルバンドの出現には期待して行きたいです。我々は上記と方向性が違うのでの諸々の視点で俯瞰しながら自由に活動させて頂いていますが「創作をしてリリースしてライブをさせて頂く」という現在の活動環境に本当に感謝しています。支えて下さるファンの皆様のお陰です
曲の書き方
当方、どうやら作曲の仕方が特殊なのか少数派の様です
「みんなどうやって曲を作っているんだろう」とYoutube上で検索してみました。その類は沢山出てくるのですがその中の殆どが「先ずは構成を作る」とのこと。
これに大変ビックリしまして。当バンドの曲は構成から作ったことが一度も無いです。
このブログ上でこれまでに何度書いて来たか分かりませんが「出来た曲が出来た曲」なので、出だし(イントロ)からコツコツと紡いで行って最終的に曲として完成しています
なので所謂「Aメロx4小節→Bメロx4小節」みたいなのは作る時も(完成した後も含め)書き出したことが無いです。ですので曲によっては一度キリしか出てこないギターリフもありますし6小節だったりも多いです。
構成を紙に書き出してから曲を紡いで行くというのはやったことが無いので分かりませんがどうなんでしょう、将来機会があればトライしてみるかどうか。青年期から曲は脳と身体で覚える手法でやってきているので紙に書き出して構成を作ったり把握していくのは当方にとっては未知の世界。新しい感覚が生まれるのであればトライしてみても良いかもです
むしろ当方とは逆のパターン、つまり作曲手法として多勢だと思われる「構成を先に練ってから曲を書く人」は当方のパターン(構成無しで紡いで行く手法)でやってみるのも新鮮で面白いかもしれませんね
今思うとサブコンシャステラーの初期曲は7分越え、8分越えの曲が当たり前の様な感じでした。曲を紡いで行った結果、つまり「出来た曲が出来た曲」です。作曲手法を学んだことは無いですし思い付くまま紡いで行く手法が現在まで続いています(ただ近年は曲の長さに関しては今はその半分、3分半くらいをめどに書いています)
音楽の知り合いが少ない
これが良いことなのか悪いことなのか分かりませんが、普段の生活環境において音楽関連の知り合いが極端に少ないです。そもそもデスメタルジャンルを聴く人自体の絶対数が少ないのでそうなるのかもしれません
ですので普段は音楽とは全く関連の無い友人や親友達と過ごしています。ただ逆に創作やライブ準備等の際は集中できるんですよね。メリハリというか自分だけの世界を持つことは発想力の維持というか想像力を養えるというか。ですのでサブコンシャステラーというバンドで活動する時のみ切り替えてデスメタル活動に没頭しています
もしかしたらですが生活や人生すべてがデスメタルだと続いていない性格なのかもしれません。もちろん人それぞれだと思いますが
決め打ち的にデスメタル時間を作ることは創作の面においても発想の豊かさを維持できるのかもしれませんし逆にもっと接した方が良いのかもしれませんしこの辺は分からないですね
実際問題、創作をする際は周りの音を一切シャットダウンして創るので。とは言いましても普段の生活では音楽自体、一日あたり8時間以上聴いています。ジャンルをシャッフルした状態で何万曲を垂れ流しての聴き流し生活です。それこそジャズフュージョンからヒップホップ、ロックやハードロック、J-POPから民謡音楽、そしてメタルからデスメタルまで様々な音楽が常に流れている環境で生活をしています。当方にとって音楽は何にも誰にも左右されない自由行動であり末永く続けていきたいですね
インタビュー慣れと語彙力
インタビュー原稿を書いています
海外メディアからの依頼(英語対応)ですが毎度ながら熟慮しがちなんですよね。インタビュー慣れしているプレイヤーだとスラスラと行くのだと思いますが
慣れているバンドマンであれば聞かれるであろう質問をあらかじめ予想できていたり頭の中で常に整理されている具合でしょう。パターン化とまでは言えないにしても、いつでもすぐに答えられるという準備もバンドマン資質の1つ
特にバンマスともなるとバンド全体の視野も含め、偏らず、そして正直な気持ちをインタビュアーに対してしっかり伝えられる能力が必要になってきます
ましてや世に公開されるインタビュー記事ですからバンドとしてはプロモーションでもありますし見て下さる方達へ言語化した状態で気持ちを伝えられる手段ですからややもすると慎重にもなりがち
以前はインタビューの都度言葉を選ぶのか、選ばないのかというヨコシマなことも考えたことがありますが結果的には今の気持ちをそのまま正直に伝えるがやはり生感がありますし原稿を作る際の思考疲労感も無いです
我々は殆ど海外からのインタビューです(残念ながら日本でのインタビューは少ないです)
我々日本人、既に日本語が出来る訳ですからあとは「英語」と「中国語」が堪能なら地球上どこでも大丈夫だと思います。このブログ上でしつこく書いてきていますがバンドマンは外国語は出来た方が良いです
当バンド、インタビューを含む全ての音楽活動への対応において基本的には「即日回答」か「次の日には回答する」です。それが無理なら「いついつ迄に回答する」というデッドラインをあらかじめ決めてからのやりとりをしています。対応が遅いとフェードアウトされますね、特に海外では。つまり徐々に連絡が途絶えて行きます。「機会は逃すべからず」なのと「プロフェッショナルな対応」に尽きますしバンド活動のコントロール能力は非常に重要です
ドラムが巧いとは
ドラマー募集しているArchspireやBenightedの後釜探しについて
「新しいドラマーを見つけるのが難しいのでは」という世間の話題がありましたね
他にもAbortedやDark Funeral、Spawan of Possesionの各ドラマー氏も強烈ですよね、万が一抜けると探すのが大変(ライブで曲を再現して行くのが)だろうなーと思います
激速系デスメタルにおいては超人的ドラムスピードで叩けるプレイヤーがとにかく際立ちますのでバンドの花形であり代替が難しいという特殊な音楽かもしれません
そういう意味ではこのジャンルでは「ドラムが巧い」という定義が「超人技」というイメージもあります。確かに地球上であのスピードで持続力を持って叩ける人なんてそうそういませんよね
当方ギタリストでドラムは叩けないので一般リスナー視線になりますが「ドラムが巧い」のステップとしては以下のイメージを持っています
①何はともあれ先ずは「リズムキープ」(メトロノームの様なリズムで叩ける)が凄い
②次に「音価」(ドラムの音を発声させるタイミングから音を切らすタイミングの技術)が凄い
③その先には「トリッキーさや手数や変拍子」が凄い
④最後は「人間技とは思えない超人系スピードと持続力」が凄い
先ほど挙げたドラマー各氏は④に辿り着いた上で更に高みを目指している様なプレイヤーだと思われますのでそうそう居ないでしょう
だからなのか、このエクストリームメタル界においては「ドラマーの個人名が際立って有名」と言うバンドも多いですよね。つまりスピード系デスメタルはまさにドラマーが「花形」のジャンルです
超人系ドラマーはまだまだ将来の可能性(需要)を秘めていると思われますが、生まれ持ったセンスが辿り着く道(練習で誰でも到達出来るものでも無い)なのでどうしても少数派にはなるでしょう
需要
定期的に話題に上がる「需要が無いのに精力的にライブ活動をしてどうするの」というお話です
賛否両論が沸き起こるべく刺激的な内容ですので都度話題として上がってくるのでしょう
この件をあえてじっくり考えてみたいと思います
・魅力が無ければ需要は無い(魅力があれば需要はある)
・需要が無いならこちらから供給していく(供給側から仕掛ける)
この2つは永遠に延長線を辿りそうな雰囲気もありますがSNS最盛期の現代においては需要を先に作るが総合的に上手く行く可能性がありそうです
実際問題、ローカルエリアで友達を呼んで定期ライブをしていてそこにバンドへの需要があるのかという完全なる身内感。この辺は長年バンドをやっていて思うこともあります。我々は少し変わってるかもですが基本的に友人を呼ぶライブはせずにやってきています、純粋なファンを求め共感くださる方たちとエクストリームメタル音楽を共有させて頂くという意味でライブ活動をしてきています。1994年の初ライブの時だけですね、「人生初ライブやるので記念に」ということで学校の友人達を誘って観にきてくれたという。なので友人を呼ぶライブをやり続けるパターンはややもすると「ライブをした」という経験だけで終わる可能性も。純粋なファンサポーターが居なければ徐々に活動経費などの経済的問題だったり、メンバー間で心が揺れたりして離脱していくケース。やはり「バンド側からの魅力を出せるところまで」は自力が必要で「自己責任前提による魅力作り」が必要です。もしもそういった事を求めないのであれば自己満足方向的なライブ活動でも全然良いと思いますし、それをバンド活動が充足しているとメンバー間で認知していれば問題無いですしそれで良いのです
我々は1990年代、ハイエース機材車に寝泊まりしながらずっとツアーしていました。そして2020年代の現在は要所でのライブ活動方針へ移行。需要と供給も併せて俯瞰しているからです。やみくもにやって上手くいくならば良いですがそうとは限らないとも。そこには沢山の犠牲もありますしまさかデスメタルで家が建つわけでは無いのであくまで末永く活動していける環境作りを優先しています
年齢を重ねるにつれ「創作」が更に楽しくなってきたんですよね。ずっと続けていきたいです
需要と供給の話に戻りますが以前にも書いた通り「音を届ける」が何よりも先決。Youtubeやインスタ等、いくらでも音源発信の方法はありますよね。それですら再生回数が全然回らないのにライブしてどうするんだと。冷酷ですが需要が無いという世の判断です。だから近年は故意に炎上を狙う様な人も出現してくる訳です。我々の場合どちらかと言うと創作を続けていきたい心理に傾いてきています
とはいえもちろんライブ出演のチャンスがあれば全力で行いますし、そのために常に準備をしています。ですのでむしろその1回のライブに賭ける想いの強さは更に増してきています
賛否両論の話に戻りますがライブをすることで魅力を増やす(サポーターを増やす)という考え方もあるでしょう。ですが「ワンマンでやる以外(既に魅力がある)」は多数出演のイベントとなりますのでそこからのきっかけとなると元々集客力のある有名バンドとの共演がやはり総合的には音を届ける範囲が広がるチャンスだと思われます。漫才の劇場等と同じですね、前座があって大トリがあっての様な
ありがたくも近年は来日アーティストの前座や海外ツアーに関しても有名人の前座での出演機会が増えています。本当にありがたいことですしプロモーター氏には感謝しかないです。つまり音を広範囲に届ける事ができる可能性を探るバンド活動。ただこれまではお声がけ頂くという奇跡の連続でしたが今後自発的行動も必要です
あとフィジカル品に関しても国内流通網があっても海外流通網が無いのであれば「作る」です。せっかくYoutube等で気に行って下さった方が居たとしても物理的な供給が出来ていないのはバンド側の責任。我々も海外流通はまだまだ弱いです。以前にも書きましたが海外ファンからはバンドオフィシャルHPからの個人オーダーで一枚ずつ郵送しています。あとは海外はBrutal Mind USAとその本拠地Indonesiaのネットショップからも販売サポート頂いています
例えばカニバルコープスのCDやシャツはおおよそどこの国でも自国のネットショップですぐに入手できると思います。勿論需要があっての流通網とは言え、それでも自分達でやれるところまではやれているのかという前提。海外流通網だって今なら幾らでもネットで情報を探せますしね。なのでバンド活動が上手く行かないと不満を口に出す人はそれらの事すらやって来なかったからという逆説的な可能性もあります。俯瞰力を持って様々な角度からの思考行動により音楽活動は成立するものだと思われます
レコード会社の状況
エクストリームメタル系だと最大手はCentury Media(ソニーが親会社)だと思います
Century Media Records – YouTube
Century Media Records – Quality in Metal
Youtubeのチャンネル登録者が277万人という超巨大エクストリームメタル系レーベル
なのですがエクストリームメタル市場はやはり規模感が他の商業音楽とは違い、難しいというか視聴回数を見ると到底登録者数の277万回再生には程遠い「何千回だったり何万回だったり」のストリーミング
これが何を意味するかですが「売るだけ」レーベルでは経営が厳しいという現代です
逆にむしろ我々が所属しているBrutal Mindはチャンネル登録者数は数万人ながら、みるみるレーベル規模が巨大化しています
どういうことかというとアジアのレーベルは大手欧米レコード会社からのマーチ受託をビジネス化している背景もあります
アメリカやヨーロッパのレーベルはアジアのCD工場やシャツ工場に制作受託が主要ですので信用のあるBrutal Mindを含むアジア系列のレーベルへのライセンスリリースを含め大手レーベルからの受諾制作もあるのでそういったレーベルは活況ですし勢いがあります
特にLPレコードは中国のレーベル受託が独占
そういった意味でも我々の所属しているBrutal Mindレーベル(インドネシア)は現在、総合的にはアジア最大規模のビジネスを行っているエクストリームメタル系レーベルかもしれません
Brutal Mindのボスとは日頃、日常会話していますがとにかく忙しい日々の様ですし近年は更にリリースが目白押しですよね、止まらないです。これはボスのビジネスの才能ですし付き合うと分かりますが本当に良い人です

↑写真は当バンド3rdアルバム「Chaotic Diffusion」アルバムでBrutal Mindレーベルとのリリース契約第一弾時にボス(中央/Deni氏)との会食の一コマ
そんな目白押しなリリースラッシュのハザマでプレス工場のラインに乗って我々のアルバムもリリースに辿り着くという感じです
ちなみにこれも以前に書いたことがあるのですがバンド側は契約時点で「アー写」、「DDP(CDプレス用データ)」、「ブックレット記載情報や歌詞」、「アートワーク」は全部そろった状態でオールインワンがベストです。更にはMVも既に作っている状態であとはレーベルYoutubeチャンネルから流していただくだけで済むまでが当然だと思っておいた方がこれからの新規バンドはレーベル契約に辿り着きやすいと思います
実際、自分がリリースラッシュのレーベル経営社長だとしたらそう思いませんか?
言葉を選ばずにいうならば「デモがどうだとかミックスすらしていない音源等の中途半端なマテリアル」な時点でオーディションには落ちるでしょう
といいつつも1作目を契約して以降、ちゃんと信頼関係が築ければ次作以降はかなり甘えることもできます。次作のMVやブックレットレイアウト等諸々全部デザインチームへお願いできる関係にまで辿り着いています。なので逆に移籍が難しい面もありますね、情も湧きますし。他のバンドはどうやって移っていくのか分かりません、いわゆる出世コースみたいな「移籍ごとにレーベル規模が上がる」みたいなケースって多いですよね、我々はやったことが無いので知見がありませんが
ミックスマスタリングにおけるサウンド確認方法
バンドマンがエンジニア氏へミックスマスタリング依頼をしそのサウンドを「耳」で確認する際の我々のやり方です
以前にも書いたことがありますが作詞作曲レコーディングまではバンド内で完結し、ミックスマスタリングだけはエンジニア氏に依頼しています
その理由は第三者が入った方が音質のみならず全体として纏まりが良い結果となる傾向だからです。つまりミックスマスタリングに辿り着いた頃には「もやは自分達の楽曲を聴き過ぎている」ので、自分の世界に入りすぎるというか狭い領域での思考になりがち。音質の良し悪しや全体バランスについても迷いが生じやすいと考えています
なので基本的にレコーディング後は信頼の置けるエンジニア氏に頼りっぱなしです
これが功を奏してか独りよがりにならないサウンドと言うか、改めて客観的に聴き直すことができますし次に生かせるような新たな発見も
尚、次作に関してのレコーディング用ギターですが2nd「Reprogramming」&3rd「Chaotic Diffusion」アルバムでの使用ギターから変更、更にピックアップも変更したのですがかなり良いです
以前にも紹介したことがあるのですがそのピックアップはセイモアダンカンのBLACK WINTER(パッシブ)です。以前にも増して鋼鉄ギターサウンドとなり今作の楽曲イメージ通りな仕上がりです

※ライブ前の配線/断線確認やネック調整、ピックアップ交換等の日頃メンテでもお世話になっているESP系楽器店さんで数年前にこのピックアップを紹介いただいたのですが的中でした感謝!
そしてようやく表題の件に辿り着きましたが当方は少なくとも6種類以上のスピーカーで繰り返しサウンド確認をしています
(1)Iphone(携帯電話)で聴く
(2)PCのスピーカーで聴く
(3)自宅のオーディオシステムで聴く
(4)Sony等のヘッドフォンで聴く
(5)ダイソー100均のスピーカーで聴く
(6)JBL/Anker等のブルートゥーススピーカーで聴く
などなど出来るだけあらゆるタイプのスピーカーで繰り返し聴いて総合確認しています
更にはこれは個人的嗜好になりますが大広間でミキサーを繋いで超大型のパッシブスピーカーから爆音で鳴らしたりもしています。でもそれは環境依存になってしまうのでやはりIphone等の携帯電話から聞こえるサウンドを基準にするのが現代の主要だと思われます
創作した曲が再度客観視(聴)できるタイミングであるミックスマスタリング期間は非常に楽しいですね
日を跨ぎながら毎日何十回も聞きなおした結果
先日、新譜用のボーカルレコーディングを終え毎日何度も聞きなおしています。そして納得行かない結論になりました。結果、全部録り直します。ボーカルは本当に難しい
スタジオを取り直しての「ゼロからボーカルの録音をし直す」って想像するだけでも果てしない工程が待っている不安感も襲ってきますが納得できない精神状況ではリリース後に後悔するので
楽器とは違い生身の人間が発する声はそのタイミングも含めて上手く録るのが難関で更には英詞ですから注意も必要
今回のレコーディングでは直前に1小節ずつAIに読ませながら何度も何度も発音確認しつつ録音しています。事前に英語電子辞書やIphoneの読ませ機能を酷使しながら覚えてはいますが、それでも録音時は1小節毎にこまめに録音しています
これらをゼロからやり直すとなると果てしなくて精神的に追い込まれそうなところもあるのですがやはり後悔はしたくないので全部録り直します。あとは時間との闘い(ミックス開始の設定期限)もあるので寝ても覚めても没頭し続ける近況ですが乗り切ります
バンドマンは郵送作業の習慣づけ
本オフィシャルHP内リンクにオンラインSHOPがあり我々のマーチ(CDやシャツ、DVD等)をダイレクトで購入が可能です
このオフィシャルオンラインショップ経由でオーダーが最も多いのは海外からの個人購入です
国内においてはAmazon、楽天、Yahooショッピング等のオンラインショップやディスクユニオンやタワーレコード、HMV等で取り扱って下さっているのでオフィシャルHPからのオーダーやライブ会場以外でも皆様に入手しやすい様に務めています。改めて皆様のサポートありがとうございます
海外からの個人オーダーですが本当に有難い限りですし何より「よくぞHPにまで辿り着いてくださった」というのが先ず第一にあります。「何としてでも入手したいという強い気持ち」に感謝です
これまでに色々な国へ発送させて頂きましたが個人オーダーですから基本はCD1枚づつを梱包(シャツ同梱も多いですね)して送り状を添付し郵便局発送しています
他のバンドマンがどのように個人オーダー品を海外へ送っているのか分かりませんが我々は日本郵便の国際郵便一択です
送り状内の内容物欄にはケース付きCDの重さ(g)、Tシャツの重さ(g)、原産国、更には「HSコード」(輸出統計品目表コード番号、例/CDだと8523299000等)を書く必要があるのですが何年も送り続けているとかなり速いスピードでサクサクと送り状を書けるようになります。その際に添付する英語でのお礼文内容も定型化し所感をプラスアルファしています
↓↓海外個人オーダーさんへ発送時のお礼文の例(あくまで我々の場合)↓↓
Hello there!
Thank you so much for purchasing our music! Your support means the world to me. Knowing that my work resonates with you is a tremendous source of encouragement and motivation to keep creating. I hope you enjoy the music, and I truly appreciate your support for independent artists.
With heartfelt gratitude,
Subconscious Terror -hammer-
最初の頃は送り状の作成にしてもお礼文の作成にしてもかなり時間がかかっていました。それよりも重要なのは「早くお届けすること」が購入者にとっては最も嬉しいことですから海外出荷の迅速対応手法を確立する必要がありました。今ではオーダーが入ると当日か次の日には出荷されています。国によりますがどうしてもある程度の日数は掛かりますから即出荷が何より。そして購入者には予めメールで「発送の旨」と「送り状の問い合わせ番号」を連絡させて頂きますので「海外個人取引」に安心感を持って頂けるよう心がけています。そう考えると「海外への個別出荷対応の習慣化」もバンドマンの必要スキルの1つかもしれませんね
デスメタルボーカル
デスメタルボーカルの発声については完全に自己流です。なにせ学生時代にまで遡りますし当時はデスメタルバンドは国内ではまだ希少でしたしヘビーメタル&スラッシュメタル全盛時代。その発声の仕方については情報やメソッドも何も無いのですから当時は「いわゆるダミ声派生」からのスタートになりました、とにかく「激しさを出す」という抽象的な感じでした
今は医学的に?デスメタルボーカルの発声方法を教えて下さる所もあるようですね。ネット上では「のどぼとけを下げる」だったり、「口の中で横に膨らます」だったり「顔を上に向ける」だったり色々見かけますが個人的には現在も特に意識が無いですが言語化できると良いですね
ちょうどつい先日、新作向けのボーカル部分のレコーディングを終えました
結果的にはこれまで通り自己流の継続でした
一応は録音する際にふと思いつきで顔の向きを変えたらどうなるのだろうと「上を向いたり下を向いたり」をやってみましたが特に変わりはなかったです
ライブの際はギターを担いでいるので顔の向きについてはどちらかと言うと基本は下向きです(ギター指板を見たりするので)
結果これまで通りライブと同じ声質(再現性)になるように?顔を下向きで録音しました
恐らくですがどこまで行っても「持って生まれた声質」(+年齢)になるのかなとも思います
ちなみに好きなボーカリストといえばクリスバーンズの初期が一番好きです。90年代のクリスバーンズのあの声は個人的には非常に魅力的です。ただ、現在(SixfeetUnder在籍)の彼の声質ついてはやはり年齢なのか、それともあの声を長年に渡って出し過ぎたからなのか「声の中に含有された粘り気」の様な部分がかすれて減少している感じがあります。やはり電気を通す楽器とは違いデスメタルボーカルは「生身」ですから声質維持は難しいところはあるでしょうね(そんなクリスバーンズですが当時のその後、カニバルを脱退してしまい後釜としてMonstrosityのコープスグラインダーフィッシャーがカニバルに入ったときは衝撃過ぎました。今ではフィッシャーはカニバルの顔ですが当時はクリスバーンズが凄すぎた事もあり後釜としてのプレッシャーを含め大変だったのではと勝手な想像をしています)
賛否両論すら俯瞰できるかどうか
先ずはこちら。的を得ていますし鋭い表現も含め冷静判断
お次は「夢を追う」系、若い志にリスペクトです
上記2つの動画を最後まですべて見てみることをお勧めします
我々の場合は上記とはまた違う思考を持ち合わせていますがどちらかと言うとROOM3さんの動画に近いもしれません
つまり常々このブログで書いてきている通り「やりたい音楽」や「やりたいバンド活動」はそれが出来る生活環境作りのセンスが重要
AmebaのYoutube「夢を追うバンドマン」の方では普段はバイトをしながら「いつか大きなフェスに出演したい」を含む理想論
現実問題として冷酷ではありますが以前にも書いた通り、夢を描いて「続けていれば声が掛かるなんてことは無い」です
もちろんワンマンで既に1000人集客力があるとかSNSで既に万単位のフォロワーがいるとかであれば別ですが
海外では「Pay To play」つまり「Buy on Slot」(出演枠を買う)もしくは自腹での出演が普通です。既に有名人でもない限り、またはコネでも無い限り大舞台に立つことすら、そこに事前競争があります
極端にいうならば億万長者のバンドマンがイベント主催者に「100万円出すから超有名バンドの大トリの前でパフォーマンスさせて」と言えば名も無きバンドを出演させるよりも収入メリットがある訳です
興行はビジネスですからその100万円で会場費がまかなえるなら当然ながらその100万円を出すバンドを推しまくるでしょうし、その後も「是非出て下さーい、何卒!」とスリスリと声を掛け続けられるでしょう
Abemaの「夢を追う」って既に自力での集客力やSNSやYoutubeやSpotifyフォロワー数があってこそ
例えばもしも、厳しいバイト生活のバンドマンをやっている状況下だとして「5万人の大型フェス出演枠が100万円で売られている」としたらどうしますか?
億万長者はお小遣いレベルで出演するでしょう
やはり音楽は届いてナンボですし何よりプロモーション(音を届けられる機会)になりますからね
幸か不幸か、我々の様なデスメタルという希少系ジャンルの場合はそういった範囲での資金競争は余り聞きませんが自腹は普通だと思います
例えばアメリカ往復xメンバー3,4人で1週間のツアー。航空費込みで100万円としてもそれは99%自腹です。航空費用までのサポートがあるバンドは既に集客力があり、更に(大手)ブッキングエージェントとの契約が上手くいった暁の様な話です
エージェント契約が無い場合は招聘者からの「現地空港着後から現地国内の生活をすべての面倒を見て貰える(帰りの空港まで送迎)」レベルのサポートが精一杯なスポンサー範囲だと思います
ちなみに下世話な話になりますが海外フェスなどの大々的なポスターを見ると大体イメージは掴めます
一番上の列にあるバンドは航空チケットや現地生活(ホテルや送迎等)までサポート
二列目以降は自腹経費が基本、そして現地内の生活サポート(ホテルや食事)までがMaxのサポート
三列目以降は…
逆にいうとガチでバンド活動をしたいなら上記の様な資金を含めた活動をするための環境整備のセンス有無を問われているのと同義とも取れます
普段が一般企業の勤務でアメリカ2週間ツアーをパッとできますか?みたいな。更にはその為に「いつでも旅立つことのできる資金準備」はできていますか?それでも勇気あるなら是非出演してみてください、でもその結果は自分たちのパフォーマンス次第ですよと
誰も助けてはくれないですし重ね重ね書いてきていますが「たとえ世界で一番凄い曲」なるものを作っても「誰にも聞かれなければ」(音を届けられなければ)結果は得られないでしょう
なのでバンド活動を積極的に行うのであれば生活環境を整えられることがとにかく重要だと思います
特にOSDM系は長髪の人も多い(長髪での一般企業での勤務・出勤が日本では難しい)ですし、如何にこのジャンルが希少種であるかも分かりやすいかもしれませんね、ただ実際には元が富裕層な背景でやれている人(もしくは社長業)も多いと思います
ですので海外に出て行っているバンドは本当に苦労していると思いますし、その行為自体が本気の活動と捉えることも出来ますしリスペクトです。我々は富裕層ではないので亀足コツコツ活動ですが…
音源バンドとライブバンド
ありえないくらいにスピードが速いバンドや、果たしてライブで実現できるのだろうかの様な音源
特にテクニカル系音楽では増加の一途
AI判別もあるようですが例えばYoutube上で「バンド名+Live」で検索して沢山出てくれば「ライブバンドだなー」と思いますし検索して出てこないと「音源だけなのかな」という心理も働きがちかもしれませんね
更にはややもすると音源はテクニカルで凄いけど実際のライブは巧く無い?(粗い/弾き切れない/叩き切れない)を勘ぐってしまうかもしれません。これはバンドマン目線になりますが
我々の様な生粋の生バンド(人間による創作でかつ、ライブ活動をするバンド)とは界隈が違うのかもしれませんし今はAIでも作れる時代。もはや楽器すら弾けなくても曲は創れる時代ですからそういった音楽市場もありなんだとは思いますが
創作と同じくらいに「ライブがエグイ」というのは我々にとって目指すところです
「ギターボーカル/3人編成」(当バンドと同じ編成パターン)でライブが巧いと思ったバンドがこちらDying Fetus、正にガチプロですね。
(※ギターボーカルのジョンギャラガーさんのパフォーマンスから吸収できることは、歌の無いところはリズムに頭を合わせたり、ギターを少し前後に振る感じです。つまりこれ以上、身体全体大きく揺らすヘドバンは演奏が乱れる可能性も考慮し年数を重ねて洗練されてきたパフォーマンスなのでしょう。シングルギターは凄く気を使いますし、乱れるとすぐに全体バランスが崩れますしね、リスペクトバンドです)
楽器のスキルアップとリリース枚数(曲数)の関係性
2024年11月現在、レコーディングが佳境なのでそう思ったという節もあるのですが、レコーディングはどんどん経験を踏んだ方がスキルアップが速いかもしれません
創作とは違い、録音する際の弾き方や叩き方がその都度勉強になることが多いです
アタック音だったり粒ぞろえだったり
現代では録音したあとに音の波形まで確認できるのでズレ具合も含め自己分析が可能、吸収できることが非常に多くレコーディングが終わった後はスキルアップした気がします
結果的に「次作は更に上手くなって録音したい」とモチベーションも益々上がります
確かにレコーディング期間ともなると毎日8時間練習するような、寝ても覚めても楽器を持っている様な感じになるので単純にその分のスキルアップもあるのかもしれませんがともかく楽しいです
もしも曲数の多いアルバム単位での創作が大変というのであれば曲数を減らしたミニアルバムをコツコツ出していく事でレコーディング経験を増やすのも良いかもしれませんね。つまりはとにかく慣れること
今回は「レコーディング慣れ」は楽器のスキルアップにも繋がるという内容でしたが録音した新曲自体も後のライブリハーサルや本番ライブでどんどん洗練(ブラッシュアップ)されて行きます
ボーカルのレコーディング
ボーカルのレコーディングは毎回試行錯誤しています
ボーカルも勿論DIY自録りです
その際に課しているのは「ボーカルは防音室で録る」です
つまり音楽スタジオの個人練習予約からのスタートになります
入室後、マイクとDTMを接続し密閉型モニターヘッドフォンで新曲を聴きながら録音していきます
ここから先は現在も試行錯誤中なのですがスタジオの部屋の「広さ」や「縦長構造」や「四角形構造」などの空間の差による影響ってどうなのか。これは分からないです
必要なボーカル録音が全部で8曲あるとして「今日は4曲分のボーカルのレコーディングをした」と。そして次の日に続きの5曲目から録音しようと思った時にやはり同じ部屋じゃないと何かがおかしくなるのかどうか。分からないです
ちなみにボーカル録音する際にマイクを手で蓋うというのはやっていませんが、近年は掟破り的にそれやって録るボーカリストもいらっしゃるそうですし、マイクと顔の角度や近づける距離についても掟破り的なパターンを含め、結果的に理想の声質が出ればよい訳ですから先入観に捉われず自由なやり方でOKでしょう
1人で防音室スタジオに籠って試行錯誤しながらやってきているので何が正解で何が不正解かは分からないです。ひょっとしたらエンジニア氏がその自録りしている現場を見るとおかしなことをやってるなと思われるようなこともしてるかもしれませんが
ちなみに現新作の「Chaotic Diffusion」アルバムのボーカル録りも上述の通りスタジオ個人練習に入ってのDIY自録りですが、特に不満無くむしろ非常に満足しています
ちなみにボーカルレコーディング代ですが自室だと空調や外の音(声)が入るかもなので一応「防音室」で録音したいです。なのでスタジオ1人練習に入ってそれが1時間600円。なので8曲を3時間で仕上げたとして1アルバム1800円くらいですね
上記アルバム時のギター、ベース、ドラムは全て自室自録りなのでレコーディング代は0円です
我々の様な小規模バンドにとってはレコーディングDIYは重要な経費節約の大きな要素になります。そしてマーチシャツやCDプレスはレーベルに依頼するという塩梅です
バンド活動を上手くやっていく為に水面下で色々と工夫するのですが、大手レコード会社がREC&プロモ予算を取ってみたいなのとは違うので、我々の様なアングラ界隈ではおおよそのバンドが上記の様な工夫をしながらかもしれませんね
(余談ですが)ボーカルを録るときは歌詞をA3の紙に大きい文字でプリントしそれを目の前において録っていますがページをめくる音については伴奏タイミングでめくればその部分はカットできますから大丈夫ですね
Defeated Sanityの新譜がエグ過ぎる
Defeated SanityがSeason of Mist移籍しての第一弾のこちら
ドラマーのリリーグラバーさんのジャズフュージョン出身からのデスメタルはもはや「音の最果て」の領域
カレントメンバーが良く揃えられていますし現在がバンドとしての一番良い状態だと思います
むしろ結成30年越えで今が音楽的に黄金期という私感です
幸運にも今年2024年8月に彼らと共演をさせて頂き観戦させて頂きましたが、この新譜のツアーは本当に観たいですね
「音の最果て」に行きつく人たちの音楽かもしませんね、テクニカルブルータルデスメタルジャンル
後継者
Subconscious Terror自体は結成30年のバンドではありますが現行メンバーは主宰以外は20代半ばです
彼らは一生懸命にバンド活動における仕組みや経験を積みその要領も含め吸収くださっています
これは将来のバトンタッチも見据えているのですが先人が失敗経験を含め、できるだけ最短距離でミュージシャン活動が出来るように事前に蓄えておいた方が良い知見や経験を得て下さっています
なので恐らくですが彼らと同年代のプレイヤーよりもかなり早いスピードで様々な体験が出来ていると思います
レコーディングの進め方だったり、アーティストビザの取得だったり、海外ツアーだったり、来日アーティストのオープニング出演だったり、リハーサルだったり、ライブまでの段取りのやりとりだったり
これらはすぐに辿り着いて経験できるものでも無いかもしれません
視野はもっと多方面に渡るのですがゆくゆくはこういった知見や経験を自身の人生自体にも活かして頂きたいです
もちろん、最後は「自身の意思の強さ」が成せるミュージシャン活動ではあるので清い言い方をするならば脱落するも脱落しないもとにかく自由主義です
平日にライブをする可能性や特に海外ツアーだと平日込みでの移動も出てきますからね
なのでミュージシャン活動をするならば生活環境(音楽活動が出来る環境)の整備が一番重要であることをこのブログ上でも常に説いてきています
そして彼らも将来だんだん分かってくると思いますが「幅広いバンド活動が出来ている事自体」が実はとても奇跡的な経験であること
サブコンシャステラー自体、長い休止期間あれど結成してから30年が経ちます
残念ながら振り返ると当時の人たちは殆どいません(今後も益々希少種になるでしょう)
ですので、まだまだこれから沢山の経験や知見吸収して行きながら是非とも後世に国産デスメタルの血を受け継いで頂きたい想いはあります
そういえば次次作の創作もキックオフしました
果てしないデスメタルロードはまだまだ続きます
ミックスマスタリング
レコーディングしたデータのミックスマスタリングはエンジニア氏にお願いしています
一時期は自分でやろうともしましたが
背景としましては作曲段階からレコーディングが終わるまで既にずっと聞き込み過ぎているので自分の耳での客観的判断が出来なくなる懸念も含め第三者に依頼させて頂いています
以下のマテリアルをエンジニア氏に48khz/24Bit形式でお渡ししての依頼です
①ボーカル
②コーラスボーカル(被さる箇所や掛け合う箇所や声質を変えたスクイール系等)
③ギターリフ(バッキングA)(主に低音系)
④ギターリフ(バッキングB)(主に高音系)
⑤ギターソロA(空間系エフェクターを掛けたり重ねたり用)
⑥ギターソロB(バッキングの後ろで鳴らすソロ用)
⑦ベース
⑧ドラム
⑨SE(イントロなど)
ですので基本は9トラックです
ギターはステレオサウンドにするのに2本のギターを被せるのでトラック数が多く、ましてや我々はシングルギターなのでRecする量がかなり多くなるので大変ではありますがその期間は集中しての力技でとにかく弾きまくるです。ただレコーディングをすることでライブ時にはその曲のスキルが上がっている等のメリットは多いです
ちなみに⑨のSEも自作ですがこれは創る時は全体イメージ膨らませながらなので楽しいですね
そして全体音質としてはこれまでの最新音源が我々のサウンドの基準としています↓
できるだけ各パートが分離されたクリアな音源を目指しています
そうそう、デスメタルのボーカルはミックスで何をするんだという疑問もあるかもしれませんね
マイクで拾った音はあくまで「生声」です
ライブではスピーカーから響いていますから自然エコーされていますが、マイクで拾った完全な生声をそのままCD用に落としこむのは流石にちょっとなんともな感じになってしまいます。余りにも生声すぎて
そこで我々の場合ですが「Slap Back Delay」を掛けて頂く様にエンジニア氏にお願いしています
そうすることで曲の中でボーカルがなじむ(ボーカルに残響を付ける)ので少し広がり感が出てきます
ギターサウンドやベースサウンドは各担当の好みを反映させつつ、あくまでクリアにしたいです
全体音像としては我々がライブ時にPAさんにお願いする内容同様、キック、スネア、ボーカルが前に出ているがベースとなっています
ギターに関してはチューニングを落としてはいるものの(全音1音半下げ)、高音リフも多いのでギターの音階が埋もれて輪郭が分かりにくいというのはこれまで特に懸念したことが無いですね、あまり歪ませていないのもありますが
マスタリング前には各曲ごとの頭出しから終わりまでのTIME(例/A曲03:46)が決まりますので、その際に同時に当方でISRC(著作権)申請しています
ISRCとは曲ごとのID(全情報)の様なもので割り当てられた曲番号の取得なのですが数日で取れます
そして各曲番号をエンジニア氏に伝えDDP(With/PQシート)で納品(曲名やアルバム名、作詞作曲者名、著作権番号等のすべての情報が入っているファイル)して頂きます
ですので別途Wavファイルで1曲づつ納品して貰うとしても、Press For CD(CD用のマスターフォーマット)であるDDPで聴くには「DDP再生プレイヤー」を持っている必要があります(フリーの再生アプリもあります)
実際問題、大手レーベルは殆どDDP納品です
WAVファイルを一曲づつWetransferやギガファイル等のファイル転送サービスで送るのは手違いの元(例/曲順間違いや曲間の秒数)にもなりますし、やはりCD工場に1ファイルを送るだけでプレスできるというのはバンド側からのレーベルへの配慮でもあると思います
昔の様にマスターCD-Rで郵送でのやりとりの必要もないので本当に便利になりましたね
この辺は自力で調べながらたどり着いた内容ですがバンドマンは事前に知っておいた方が良いでしょう
という事でこれで新作音源制作が完了となります
他にも事前準備としてはミックスマスタリングをする頃にはアートワークやアー写も既に準備出来ていて歌詞カード等を含めブックレットのデザインも出来ている、あるいは同時進行しているが望ましいでしょう
そしてCD工場のプレス納期から逆算して流通リリース日を決めて行く訳ですがプロモMVやマーチ用シャツなどの事前準備もそうですしリリースパーティをやるならば、そのライブスケジュールも段取りできていると尚良いでしょう
特に新曲はライブのセットリストにも入っていくのでリハーサルも行っていきます
この段取りの中、唯一の懸念があるとすれば何かが大幅にズレる(何かの納期がズレることになる)ことにより全ての進行がズレていくことでしょうか
このあたりはプロフェッショナルな進行を心がけていく感じですがそれをも先を見越しておく能力が必要になってきます(何度か小さい失敗を重ねてきた過去の経験から近年は基本全てサバを見て進めています。希望通りに進むのはなかなか難しいです)
そしてミックスマスタリングが終わり目途が立てば早々に次の創作に取り掛かりますので、ライブ演奏以外でも日常的に年中何かをしている様な感じかもしれません
バンド活動は常に全体視野でスケジュールを立てていく必要があります
特に我々の様な小規模バンドは基本的に全行動がDIYですので各個人の力が非常に重要になってきます
その「個人の力」をちょっと冷たい感情で表現するならば普段から「常に何事にも期待しない」、「希望をしたところでそうはならない事も事前にサバを見て動く(保険を掛けておく、決して騙すわけでは無いのですが)」ところをスタート地点として思案した上で結果として全てがハッピーで終わり「やり切れたかどうか」、達成できたかどうかです
この部分の思考についての妄想や夢見心地は不要です
周りを見渡すとレコーディング後に脱退する人っていますよね、そういうのはこれが原因だと思います
我々はその経験はありませんが(というか、そうならない様に常に俯瞰とサバ読みしています)どこかのタイミングでこじれるのでしょう
とにかく言えることは「淡々とリリースまで進行できる手配能力」です
ですから常に俯瞰した全体の把握や全体進行の筋道をケアしつつ冷静に計画実行する事(結果までたどり着く)が好きな人はバンマスになることはお勧めかもですね
日本のデスメタルシーンは地を固める時期に来ている
コロナ禍後は来日バンドが目白押しでパンク寸前の様な勢いが続いています
近年の円安影響はあるとしても日本はビジネスが成立し易い見立ても往々にしてあるのだと思います
でも、もうそろそろ日本のエクストリームメタルバンドは自信を持って世界をリードする気概が出てきても良いのでは
戦敗国として長年に渡り自民族をひたすら卑下しつづけ、洋楽を奉る文化が根付いてはいますがもうそろそろ良いのではという
「国産デスメタルバンドでメインストリームを創っていく」
リスペクト見本としてはパンクバンドのHEY-SMITHを主体としたHEY-SMITHxColdrainxSiMイベント・それから他にも10-FEET主催の京都大作戦や同じくHEY-SMITH主催のハジマザフェス。彼らは自分たちでシーンの文化醸成をされていますよね
こういった例を模範にそろそろ国産デスメタルもトライしてみることは次世代に繋いでいけることも可能性としてはあると思います
私感ですが「洋楽だけが好きな人」、「日本のデスメタルは認めない的?な方」はその殆どが見た目の可能性も。乱暴な言葉で表すならば「日本人がやるからダサい」という長年の戦敗国自民族卑下レッテルといいますか。もしかしたら肌の色もあるかもですが「音楽的な部分では平等」です
2023年にクリプトプシーのサポート出演をさせて頂いた際、国産アンダーグラウンドシーンでは普段見ない方達の来場も多くいらっしゃいました。大変嬉しくもサインを求められたりマーチを購入下さったり。そこから次のライブへ繋がったりもありましたので潜在的には受け入れて下さるのだと思います
つまりその「境界線を解いていく事」は可能だと思いますし、そうなってくるとシーンの絶対数は10倍、100倍となるはずです
その糸口を作る為にも上記のHEY-SMITHの様な、その国産デスメタル版で王者的(集客力)なバンドが最低でも3~5つ居て欲しいですね
そしてそういった視野を持つ活動をするバンドがどんどん出てきて欲しいですし多ければ多いほど良いですので、そうなってくると国内シーンも侮れない状況になると思います。デスメタルを好きな日本人が全体協力しながらシーンを創り上げるしか無いでしょうね
生きている間にそういう日本の景色を見てみたいです
ピッキング位置やピックアップ(フロント/中間/リア)
今回はギターピックアップの「リア/フロント選択」、「弦のどの部分で弾くか」についてです
当方のギターピックアップは2つ装着しています
そして①フロント、②中間、③リアの三種類の音色が選べます
昔はリア固定でしたが「近年はフロント固定」でプレイしています
3種類も音色の選択肢がある訳ですが紐解くと
■フロント(前方ピックアップ)は、ブリッジから離れた分(指版に近い側なので)弦の振幅が大きいので緩いというか甘めな音がします
■中間はその名の通りリアとフロント両方の音を拾って電気信号に変換します
■リア(後方ピックアップ)は、ブリッジ(弦を止めてある最後部)に近いので弦の振幅は小さくなりますので硬い音に
当バンドはシングルギター(バッキングもソロも)であることやリフをクリアー(ここで言うクリアは歪よりも原音に近い)にしたかったのと、かつ曲テンポが速く、スウィープもあり、その上で歌いながら弾くという目まぐるしさからピックアップを切り替えながらの演奏(バッキング/ソロの都度)は複雑
シンプル&機材耐性を信条な背景もありますが「リハーサルやライブで録音したものを聞いては改善」をひたすら繰り返し行きついたのがバンド全体で音を鳴らした際のギターはフロントにした方が各楽器の音色(周波数)が被らずに聞こえ「全体として一番しっくりくる」という結論になりました(あくまで当バンドにおいてですが)
メタルバンドというと「リア固定一択」というプレイヤーが多勢だと思います
実際、当方もその「先入観」で長年リア固定でした
確かにギター単独で弾く分にはリアで気持ち良いけど、バンド全体でやると埋もれる様な感じがしていたんです、その解決方法の1つになりました
こういった「バンド全体で音を鳴らした時の分離」で悩まれているプレイヤーは一度お試しを
セレクターを切り替えるだけなので手軽ですしね
以上よりピックアップは「フロント固定」でプレイしています
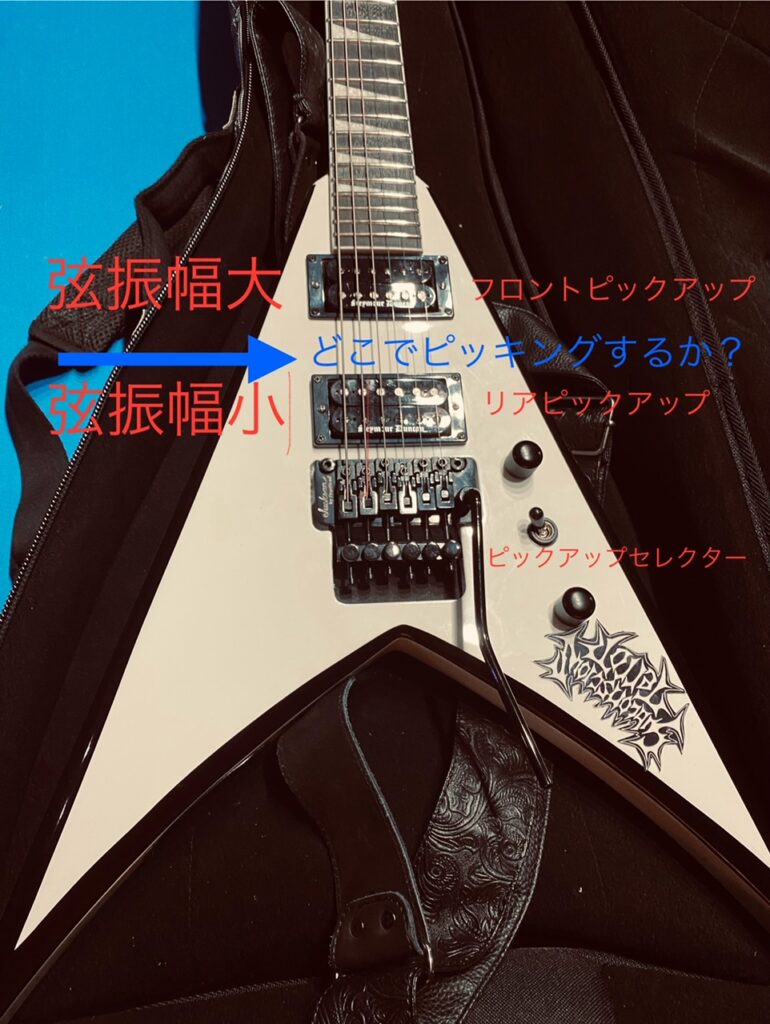
尚、使用ピックアップはセイモアダンカンのBlack Winter(パッシブ)です
(なぜアクティブピックアップからパッシブピックアップに変えたかは以前に書いたことがあるのでここでは割愛させて頂きます)
次に「弦のどの辺で弾くか」です。「ブリッジ(後方側)に近い方」でピッキングするのと「指板に近い方(前方側)」でピッキングするのでも音が変わってきます
DTM所有者ならば録音して波形を見てみると力加減を同じ具合に弾いても「弦のどこで弾くか」で波形が違うと思います
ここはニュアンス含めて難しいところですよね
例えば「ブリッジから何センチ何ミリくらいの所」で「つまはじかれた弦」(ピッキング)は音が良いとかの私感があります
これも試行錯誤なのですが「ちょっとずつズラしながら毎回録音し」それを反復比較で聴きながら気持ち良い音が鳴る場所を見つけ出しその「良い音が鳴る部分」に対し、ギターにマジックで「印」を付け、そこを狙って弾く癖をつけています。マジック「印」の上でピックが当たるよう身体に染みつくまでトレーニングですね
なので逆算的にブリッジミュート位置もマジック印(ピックを当てる指先位置)からの、こぶしの必然位置(手指の大きさによる)になりますね
これは指が長いとか短いとか(こぶしの大きさ)の影響差もあると思います。つまり弦のどの部分でピッキングするかを決めても手の大きさ次第でブリッジミュートする位置もある程度決まってしまいます
ですから同じ機材でも人によって音が違うのはこういった要素もありそうですね
自分の中でのベストを探す旅は続きます
臨機応変
先日のライブでの出来事
台風の影響で新幹線が遅れ「入り時間」に間に合わず、リハーサル時間も間に合わず、会場到着時は既に会場オープン後でお客さんが既に多勢の状況(動かずに停止して閉じ込められた新幹線内では主催者とは随時連絡を取り合いながらベストな進行方法を相談しつつ)
このような緊急事態で会場に入りギリギリ本番の15分前に到着するという出来事がありました
タイムテーブルもありますし他の出演バンドに迷惑を掛けるわけには行きません
急げばギリギリタイムテーブル通りに進行できるという緊張感の中でのセッティング
既にパンパンに入場されたお客さんの目の前でいそいそと楽器や手荷物を直接ステージに持ち込みセッティングという緊急事態です(楽屋に手荷物を置きに行く時間もないですから)
手際の良さと心理的な焦りを含めたトータルで臨機応変さが必要になります
即座にメンバー各自セッティングを急ぎ「音」を出します
その際には「ステージ内のモニター音量」を確認する作業がどうしても必要になります
ステージの広さだったり立ち位置によっては何も聞こえないと(例/ドラムが聞こえない=楽器隊は聞こえないからリズムを合わせようが無いetc)いうこともありますので演奏がまとまらない要因にもなりますし非常に大事な確認作業となります
お客さん側で聞こえてくるスピーカーを「外音」と呼び、ステージ内で聞こえてくるスピーカーを「内音」と言います
上記は急いで「内音」の調整をしている状況の動画です。
既に入場されているお客さんを目の前にしてなので緊張しています
15分前到着ですからそのまま本番を迎えたというプロセスですがやはり内音に関しての十分な確認への戸惑いもあります
そして下記の動画はステージ内に自前のiphoneをそばに置いて録画していてたのですがボーカルのそばに置いたこのiphoneの録画を見てお分かりの通り、ボーカルが殆ど聞こえない状態で最初の1曲目を歌い終えています
お客さん側に向けた観客スピーカー(外音スピーカー)では聞こえていますのでご安心をば
その後、どうしても自分の声が聞こえないことが気になりその不安を払拭するために1曲目から2曲目に移るタイミングでPAさんに内音のボーカルのモニター音量を上げて頂くべく合図をしました
その箇所がこちら(動画の23秒から)
この動画の23秒あたり
マイクを指さしてその指を上に挙げる仕草をしています
その後、心理的安心を得てパフォーマンスすることが出来ました
このように、お客さん側に向けたスピーカー(マイクで拾った)音量(全体のバランス)とステージの中で聞こえてくる音量は全然違います
「バンドマン側(ステージ内)での音量」と「お客さん側で聞こえてくる音量」のギャップを確認できる良い例だと思いましたのでUPしてみました
バンドマンはとにかく常に想定外(今回は台風影響での交通遅延)も含めた臨機応変さを身に着ける必要があります
更に付け加えるならば以前このブログでも書いたことがありますが楽器/機材はとにかくトラブルの起きにくい「頑丈な機材」を使い、常日頃からガチガチにチューニングもしておくことも必要ですね。チューニング時間の短縮も含めて
こういった事態が起きた時に万が一、更に機材トラブルがあると大変ですしメンタル的にもよくないです
繰り返しですが「当日のセッティング時間短縮」や「他方面へ迷惑を掛けない」ためにも「日頃からの臨機応変さ」と「頑丈な機材選び」(日頃からの機材トラブル回避想定)の研究は重要だと思います
結果的に当日は気持ちよくライブをさせて頂くことが出来ましたしお客さん、会場スタッフ、主催に感謝の気持ちで一杯な一日を過ごさせていただくことができました
アーティストビザ
入国が難しい国でのアーティストビザ(For commercial performance visa)取得中です
バンドライブのパフォーマンスで行く短期就労ビザですからちょっと特殊ということもあり、ネット上でもやはり情報が少なくて体当たり的に一歩一歩進めました
とにかく資料作成が難関で記入量も非常に多く9段階までありました
年収、学歴、親家族構成(親の生年月日や住まい等も)から始まり、勤務先、勤務先代表者、連絡先などはまあ良いとして何気に苦労したのが証明写真です
コンビニ等に設置されている証明写真の機械ありますよね、そこでビザ用に撮って提出してもダメ(受付不可)でした
証明写真の背景は白が条件だったので証明写真機で白を選びましたが完全なオフホワイトでは無いということでダメ(申請NG)でした
どうしたかと言うとPC上で背景部分をオフホワイト加工してようやく通りましたが、まさかそこで躓くとはでした
写真を撮る際は長髪をオールバックにし、オデコ、鼻、耳の形が分かるように撮影(特に耳の形状が映っていることが重要)もちろんアクセサリー等は不可
証明写真の背景条件が白なので着る服は白以外(当方は黒シャツにしました)で鮮明に撮りました
そして申請の際にはエージェントから事前に頂いた※招聘状(公演日時や出演者リスト、責任者、招聘会社、政府許可印etc)を添付するのですが、それに沿って招聘会社詳細情報(住所、電話番号、代表者姓名、emailアドレス等)の資料も作ります
この招聘状が無いとアーティストビザの申請が出来ないです
※招聘状・・・予めエージェントに全メンバーのパスポートコピーやバンド資料を送り該当国の政府に該当会場での公演と出演を許可された招聘状。その政府許可印が付いた招聘状にはメンバーパスポートの姓名が記されていますので、あとから他メンバーに変わる事は難しいです。もしそうなると招聘状の取り直しになりますから「後からの出演メンバー変更はほぼ無理」&「強引にやるとしてもエージェントに多大な迷惑を掛ける」ことになりますね
申請に際し、不明点はエージェントのボスとチャットでやりとりしながら進めました
余談になりますがエージェントボスとのこういったビザ関連でのチャットやりとりは冗談も絡ませたりしつつやって行くと関係構築が深まる(更に仲良くなれる)のでお勧めです。そしてやはり外国語は出来た方が良いです
あと、滞在時の宿泊ホテル情報(ホテル名、住所、電話番号)記入もありましたがこれらはエージェントがホテル/交通/食事等を既に準備/予約してくださっているので頂いた情報をコピペするだけで済みました
ちなみに犯罪履歴や社会/政治活動履歴や軍関連の所属履歴有無などの確認もありましたよ
これら全てを知見ゼロからやってみて
申請資料作成の完了までに丸2日かかりました
やはり海外公演は物凄い多くのプロセスを踏んでいます
テイラー・スウィフトさんみたいな世界的有名アーティスト(誰でも知ってる=審査通りやすい)が桁違いな商業ツアーを行うのとは訳が違い、我々レベルの超マニアックなデスメタルのバンドがアーティストビザを取得して海外公演するって、もはや「心意気が成せる技」かもしれません
今回のアーティストビザ取得過程で思ったのはこれを毎回やりながら海外を廻っているバンドにはリスペクトの念が更に増加しましたし根気がすごいです
そうそう、今年(2024年)大阪で共演したDefeted Sanity(ドイツ)の来日公演
当日お会いして更に超ファンになったのですが「ツアー前のビザ準備とか大変だったんだろうなー」と改めてその苦労も含め彼らへの尊敬の念があります
将来ヨーロッパをツアーできるようなことがあれば彼らと廻りたいです、そのくらい大ファンです
就労ビザを取得して海外公演に行きつくまでには「曲を作ってレコーディングしてリリースして」だけではないプロセスが沢山ありますし、そもそも全メンバーがツアースケジュールの都合(仕事を休むなど)を整えるところから始まり、そこから無事に全員がビザ取得できた上でようやく海外ツアーが可能
Defeted Sanity来日公演は興行的に成功しましたが万が一、こういったプロセスを踏んでかつ集客がキツかったらバンドもエージェントもホントにシンドイと思います
話を戻しますが「申請がヘビーな国のアーティストビザ取得」をバンドマンはやってみることをお勧めかもです
やり方が分かると今後の(審査が緩い?国の)アーティストビザ取得はスラスラと取れるような気がしますし、妙な?自信もつきます
ちなみにですがヨーロッパ諸国で周辺国を跨ぎながらツアーをするとなった場合はどうなんでしょうね
したことが無いので分かりませんが、それぞれの国ごとにアーティストビザが必要なのかどうか?
もしそうだと事前準備が結構大変ですね
ちょっと話が変わりますが「ビザの関係で来日公演が中止」という話を近年よく聞きます
そうではないことを信じたい前提として…
ひょっとしてですが
「申請が滅茶苦茶面倒だからギリギリまで放っておいた」
「ギリギリになって申請したら間に合わなかった」
「ギリギリで申請した上に不備で差し戻しされ修正申請したら間に合わなかった」
だと辛いですね
それらの対応が怠慢であったことは本人は言わないとは思いますがエージェントは怒るでしょう
確かに今回の我々のアーティストビザ申請も丸二日間を掛かりっきりでようやく作成完成したので忍耐力もいると思います
我々心配性なところもあって安全を見て公演三か月以上前に準備申請。万が一の差し戻し修正があっても二か月余裕ありますからね。それらをギリギリまで放っておくというのは怖すぎます
ただ、ビザ申請が早すぎるのも取得後の有効期限が短期だったりするのでこれはこれで塩梅もあるのが厄介なところでもあります
ということで「アーティストビザの取得は結構大変」というトピックでした
今回、実際にやってみてですが特に我々くらい超小規模なデスメタルバンドでアーティストビザを取得して海外ツアーしてる人達は本当に少ないと思いますがそういうバンドに対しては「よくやってるな」とつくづく思いましたし、そういったバンドさんには改めてリスペクトです
みんなデスメタルのライブ演奏をするのが好き過ぎなガチですね
追伸:本件のビザ取得に関する海外公演ですが間もなく主催者から発表されると思います。我々サブコンシャステラーにとっては初の1000人規模のお客さんを前にするパフォーマンス、楽しみです
良曲とは
音楽曲の質を数値化できない以上、明確な基準は無いかと思われます
ここでいう質は音質ではなく楽曲です
これを数値化するならば「他人の耳への琴線に触れる絶対数」ということになるでしょう
デスメタルの場合は難しいですよね、そもそもがマニア音楽でありその中でも極端な音楽性
デスメタルと言う希少ジャンルまで行きつき、それでいてかつ琴線に触れるまでですから数少ない同志ですし、洞窟探検で殆どの人が入口で引き返すような場所の一番奥にあるといいますか
それは本当に低確率だと思いますし更にはそこからの熱量でライブを観に行ったり音源を揃えて行く様な所まで辿り着くという
普段の生活上では当方の周りに「デスメタルが好き」あるいは「デスメタルを聴いている」という人は1人も居ないですがその確率を考えると納得がいきますね
人の音楽の好みは「琴線に触れない限り」たとえデスメタルの紹介をしてもその場限りです
あくまで本人、つまり自らが興味を持った上でその音楽を掘っていくという自然発生的なものだと思います
ですので普及というのはあくまで「紹介」まで。本人が琴線に触れない限りその先は難しいでしょう
当方は10年以上某スポーツ競技のコーチをしています。かれこれ2000人以上をコーチングしてきましたが眺めているとやはり「自らが琴線に触れた人」だけがずっと続けています
逆に続かない人は「やってみたけど実はそこまででは無かった」です。勿論、向き不向きもありますのでそれを自らが感じ取った結果「続かない」も往々にしてあるでしょうから強制は不要です。あくまで「紹介」で十分だと考えています、本人次第です
これがもしも儲け主義(レッスン料)ならば「やってみたけど琴線に触れなかった人」にまでどうにかエコひいきしながらレッスン料金を頂き続けるということも出来なくは無いですが、そうはしないです、あくまで紹介まで。
そのスポーツ競技ですが自身が初めてやったときやはり琴線に触れガッツリとハマりました。外国がメインの競技だった事もあり世界的に有名なコーチを探してはその国にまで行って教えを請いに行き、更には日本を飛び出し海外移住して競技生活をしていました、これもまさにドはまりですね
話を戻しまして「紹介」と言うと当方はメタリカのマスターを友人が聴かせてくれた(CDを貸してくれた)のが起点。ディストーションギターサウンドと速いスピード感がもろに琴線に触れ、次の日にはギターを購入していましたから相当な衝撃だったことが未だに思い出されます
それまでは音楽というとテレビで観る一般的な歌謡曲くらいでしたから相当なものですよね
「まさか自分が音楽に興味を持つとは」という出来事でした
音楽に限らず「習い事」が続かないケースは恐らく琴線にまでは触れてないのでしょう、どこかで強制感があるのかもしれませんし「やり遂げる」だったり「深く理解したい」までの感覚には行きつかなかったという
その琴線に触れる度合いが強烈な人程、のちの個性や人生を賭けるまでしてしまうという
世の中の興味事の全ては「琴線に触れる」かどうかだと思います
そしてそれが人生へも影響を与え続けていると
逆手
海外ではものすごい人気や評価を誇る海外のバンドが日本ではそれほどでもないケースや逆に日本で先に流行り、本国ではそうでもない海外のバンド
興味深いものでそうなってくると、もはや音楽とはなんぞやという。その地域の文化や民族性などを踏まえた上での琴線に触れるということなのでしょうか。趣向は国によって共通ではないとも言えますし、あとから国内で火が付くというのは「有名だから聞く」つまり「その音楽を知名度によって皆に届けることができるようになったから聞かれ始める」というケースも考えられそうです
代表的な話としてよく上がってくるのはQueenでしょうか
イギリス本国では評価が散々だったのが日本で先に火がついて後に流行るというケース
他にもイングヴェイ、ミスタービッグ、ディープパープル、スコーピオンズ等も日本で火が付いたバンド群と言えるでしょう
日本のメタル系文化
ひょっとしたら同じように上記を逆手に取ると「日本のバンドも先ずは海外で火が付いて(ツアー等で)後に国内へ逆輸入」という方向性もありそうですね
実際、我々がリリースした音楽を分析をすると特に南米とヨーロッパでのストリーミングが上位にいてそこから日本やシンガポールなどアジア圏が続いています。もちろんメタルリスナーの人口数もあるので一概には決定づけられませんがChaotic Diffusionアルバムをリリースした際はその国のTop10やTop100に入った国も欧米系でありました
将来は欧米ツアーもチャレンジしてみたいですね
通る道
面識無く一方的に知っているバンドさんにて恐縮ですがネット上での記事↓
https://kokeshi.bitfan.id/contents/206876
ご自身の心情を吐露されておられることがとてもよく伝わってきます
「学生卒業後はフリー兼ミュージシャン活動」という我々の世界ではよくあるケース
素晴らしいチャレンジですし当方も同じでした
ただ引き換えに苦悩も一緒に歩まれていることも垣間見えます
サブコンシャステラーも学生時代にバンド結成
そして卒業後も就職活動はせずに休止する30歳の手前までフリー兼ミュージシャン活動
思い出すと楽しい思い出ばかりですが「人生」という意味で考えたときに。
活動休止後の当方は就職して働いてみたり、更にその後にはスポーツ競技系で海外に約10年移住していました。そして帰国後の生活が落ち着いたタイミングで再活動という流れです
今のタイミングで思うのは「悔いの無い様にどんどんやったらいい」と思います。
ただし当時の自分に今の思考をアドバイス的に伝えるならば「その代わり、好きなだけ音楽が演れる環境作り」に勤しむことでしょうか
音楽が好き過ぎて演者にまでなっている人は途中で挫けてもいずれ再活する可能性が高いです
聴くだけでは済まないくらいに好き過ぎるのですから
記事を拝見している現状は「葛藤」だと思われます、どれだけ頑張っても先が見えないといいますか
バイトしてシンドイ生活して集客も難しいしマネタイズも難しい、必死でライブしたり曲を作ったりリリースをしたりしてもどうにもならない事への苦悩というか
これは恐らくある程度の年齢になると諸々を俯瞰できてくるのだと思いますが若いときは夢中すぎて全体が見えにくいのかもしれません、当方もそうでした
逆に(音楽に)「純粋過ぎる」ことが返って困難な道を選んでしまうことも
酷ですがメインストリームの今は「Spin数」(再生回数)と「知名度」で決まる音楽業界です
なぜなら以前にも書いた通り仮に「世界で一番すごい曲」なるものを作ってもネット上で世界中に溢れる楽曲群の中では(知名度が無いと)誰も気づかないからです
更に足すならば〇〇という有名フェスに出たとか世界的有名なバンドと共演したとかの承認欲求を満たすような部分(箔を付ける)をバンドプロモ履歴書として謳い自己プッシュするかです
バンド活動は大きく2方向に分かれていそうです
・野心無し…ローカルでやれる範囲でやっていく(割り切り型)
・野心有り…無理してでも活動の幅を更に広げたい(割り切れない型)
リンク先の記事は後者だと推測させていただいたとして…
実際問題としてこれ(後者)は本当に難しいと思います、理由は先述の通りです
例えば100万回再生されているYoutuberと100回再生のYoutuberが仮に「同内容の番組」を作ったとしても全く称賛度合いが変わってきます、その現実が辛いところですが
故意にもっと極端な例を挙げてみましょう
当方が曲を作り、当方が作曲したことを一切隠し、それをカニバルコープスが音源としてその曲をリリースしたらどうなるかです。下手するとカニバルコープス(というメインストリームバンド)が出した音源だから称賛される可能性まであるかもしれないという現代の怖さがあります
つまりはSpin数と知名度で決まるという
知名度があるからその音源を届けられる可能性があるのは残酷ですが
この辺をどこまで俯瞰して活動できるかです
詰まるところやはり冷静に、そして淡々と音楽活動をやれるための環境作りをしていくに尽きるかもしれません
これも以前に書いたことがありますが例えばCentury Mediaクラスの大手とレーベル契約したいといっても無理ですよね。なぜなら土俵にすら上がれていないからです。
つまり「現状(契約前)でワンマンでライブ1000人集客できてますか?」とか「Spotifyのフォロワー数は5万人いますか?」とか(数字は適当です)
超一流企業に就職面接する際に聞かれる学歴とか経験の様なアレと同じ感覚です
上には上がいるという残酷さを見ることになりますし「これまでにそれだけの努力はしてきましたか?」と問われた時の回答が出来る状況をつくって来れたかという。さもなくばコネクションでしか難しいでしょう
ここは葛藤の部分かもしれませんね
ではどうしたらよいのかはこれまでのブログ内(レーベル契約関連の題目etc)で沢山述べてきていますので割愛しますが、1つ言えることはエクストリームミュージックバンド活動で飯を食うは無理と割り切る度胸
野心が強い人ほど葛藤するとは思いますが逆にそれだけ野心が強いならば他方面でもマネタイズできる能力がありそうです
そっちでどんどんマネタイズしながら自分がやり遂げたい音楽に「野心投資」していく
ちなみにうまく活動出来ているバンドにはメンバー内に1人以上そういったキーマンが居る確率が高いです、全員がそうだと一番強いです
某海外有名バンドは全メンバーが超一流企業の富裕層でライブ後はそのツアー先の国でバカンス休暇をしてから帰国という羨ましい限りですね笑
ましてやデスメタルの様なアングラジャンルだと尚更かもしれません
カニバルコープスクラスでも家族まで養うのはギリギリか共働きか等の市場環境
それでもこのジャンルではメインストリームバンドですから成功者と言えるでしょう
これをどう割り切れるかというのは今は葛藤で周りが見えないくらいの状況かもしれませんが「時が解決」してくれるかもしれません、応援しています!
残酷ついでに残酷な裏話的ですが富裕層の子や高学歴で将来生活はなんとかしてみせるというバンドマンも現実的には多いです(田舎からギター1本背中に担いで東京へみたいなパターンはアツいですし当方は好きですが)
国内でも成立出来るのか否か
約1か月をフル稼働でツアーするという海外のデスメタルバンド群のフライヤーを常々見て思うのが


そもそもメンバー全員が普段の仕事の休みが取れるのかだったりといったところから始まると思います
上記はSuffocation、Abortedの最近のツアーポスターを例に挙げさせていただいています
もちろん彼らだって地方に行けば小さなミュージックバーの様な場所も廻る感じです
そこでですが、1か月を毎日廻り続けることの出来る国産バンドってどの位いるのだろうと思うことがあります
これは音楽性や楽器スキルなどのウンヌン以前の問題で、そもそもそういう生活ができるメンバーが居るのかというところからのスタートになると思われます
上記はアメリカツアーのフライヤーですが、これを国内で考えてみましょう
仮に1か月(30日)をかけて47都道府県の内(分かりやすく)30県をロード(ツアー)して行くとして
しかもそれが可能な(都合が付く)メンバーも存在すると仮定して
達成する必要条件が大きく2つ
(1)廻れるだけの活動資金を貯められているか
当然ながら30県となると東京、大阪、名古屋、福岡の様な都市圏だけでなく中四国東北なども廻りますし、週末は1か月の内に4回しかないわけですから大部分を平日も含めてのツアーになります
現実問題としてローカルエリアの平日でのライブは動員も難しいと思います
つまりは持ち出し資金(経費)が相当額必要になってくるでしょう
以前、国内の地方にカーカス、同じく国内の地方にカニバルコープスが来日したことがあり、動員が数十人でした。メンバーの移動費やホテル代等を考えると大赤字です。彼ら自体は招聘(経費&ギャラ契約)されている身なので大丈夫だとしてもエージェントは超大赤字ですしビジネスとしては次は無いです
(2)体力/気力/協調性を含む自己管理能力
全メンバーが毎日移動をしながら夜な夜なライブをしていくだけの体力/気力/協調性が必要です
ツアー後に脱退する人をよく聞きますがこの能力の欠乏が主因だと思われます
それに加え、もしエージェントが居ない(ギャラ保証契約等の無い)自己資金バンドのツアーであればツアー後の赤字借金による脱退や空中分解や仲違いもよく聞く話だと思います。外交的には音楽性の違いによる脱退だとしても内情としては主な要因ではないでしょうか
上記より結果的にマーチ物販のファンサポートに掛かっていることが前提ならざるをえない可能性もあるでしょうし更にメンバー全員の体力気力協調性が必要になってきます
そういう意味でもこういったツアーフライヤーを見る度にとにかく凄いと思います
そんな環境を作れているバンド(全メンバー)は音楽性以上に尊敬しかないです
想像するだけでもその存在自体がどれだけ奇跡のバンドであるかとも思います
常々書いてきていますが活動幅を広げるならば楽曲センス、楽曲スキル、メンバー環境なんてあって当たり前の上で更に上記の様な体力/気力/協調性/活動資金を備えつつバンド活動を続けられる(途中脱落者はいるとしても)と言うのは下手すると「生まれた星」と「縁」(人生上で誰と知り合うか)と「強運」が最も重要なのかもしれません
過去に某スポーツ競技に長年身を置いてきましたが天才センスの持ち主でも途中でフェードアウトして行く選手を沢山見てきました。傍から見てもその遺伝子(センス)を活かせずに消えて行くのが勿体ないと思うくらいに。つまり「将来世界を獲れると言われた逸材競技選手」でも上記の何かが不足していたために消えて居なくなるというのを散々見てきました。やはり何か1つが欠乏しているとどこかのタイミングでフェードアウトするか、その器の範囲内で小さくまとまるのかもしれません
デスメタルの様なマニアックなアングラバンドの活動というのは正に奇跡の連続です
活動を続けさせていただいていることに日々感謝
オールドスクールデスメタルOSDM
いわゆる90年代前後のスラッシュメタルとデスメタルのクロスーバー時期における当時はデスラッシュとも言われていたころからのデスメタルを指すのだと思われます
「思われます」というのが我々自体がその当時に結成&活動のバンドなのでオールドも何も無く、当時はそれが新しい音楽であり創るものすべてが新しい感覚でしたしそれを体感していた時代に音楽を作ってきたのでそういった感覚自体が無いのです、感性そのままです
ここ数十年、新世代によるリバイバル的OSDMバンドも多く出現しています
代表的なバンドはSkeletal Remainsでしょうか
非常に素晴らしいバンドでリスペクトバンドの1つです
ですが恐らく..
我々の様な世代からすると当時の塗り直しで斬新さについてはノーコメントという人もいそうです
でもこれはしょうがないですよね、当時に生きてきた人と後追いになってしまうのは生まれてきた世代ですからどうにもならないです
当時の音楽をリスペクト下さり後継者として再消化し活動している訳ですから嬉しい限りですよね
以下はあくまで個人的な話ですが
メタリカのマスターやスレイヤーのレイニンブラッドから続くセパルトゥラのビニースザリメインズ&アライズ、カーカスの初期数枚、モービッドの初期数枚、ディーサイドの初期数枚、テロライザーの初期、サフォケイションの初期、カニバルの初期、ブルータルトゥルースの初期、、、
肌感的にはあの辺りでここで言うオールドスクールは完結していると思っています
その後にデスのインディビジュアルが出てきてテクニカルデスメタル化していった流れで更にその後にはネクロファジストが出てきたという(更にその後はピロピロ系激速デスメタルの出現でアングラ細分化)
当時はその後にパンテラのメインストリーム出現があったりニルバーナのグランジ全盛の流れによりガチ系デスメタルの芽がもう少しで出そうで出ずの様な感じで更にアンダーグランド化していくという体感でした。ちなみに学生時代にかじりついて観ていた深夜放送のMTVにはスレイヤーは勿論、カニバルやカーカス、セパルトゥラも流れていて毎回VHSビデオ録画して繰り返し観ていました、ネットも無い時代ですし情報に飢えていました
我々の現在の楽曲について
人間は歳をとりますから生活環境や考え方の変化を含め年齢と共に作る曲も変わってくるのが自然だと思い自然に身を任せています
故意にオールドスクールを作るとはならないですね
あくまでオリジナル作品しか作りたくないですし何々が流行ってるからそれに寄せるみたいなのは無いです、商業音楽では無いですからこだわっても良いのではないでしょうか
これまでこのブログ内で何度か書いてきていますが当方は不器用なので「出来たものが出来たもの」にしかならないです
むしろ狙ってオールドスクールを作ったりするとそれはリリース後に自身が楽しめないかもしれません、つまり曲に感情やその瞬間の想いが無いような気がします
あくまで作曲は「感じた今を作る」です
そういった意味でも今の若い世代の方たちが当時の音楽に刺激を受けてインスピレーションされた音楽を作るというのは不思議な感覚でもありますし正に引き継がれる音楽の歴史です
功罪
■90年代はラジカセにギターリフを録音しながら作曲していました
それをみんなで覚えてスタジオで通していくという
■現在(2020年代)はPCにギターを繋いでギターリフを録音しながら作曲しています
ものすごく便利になりましたし普段のアイデアのメモ代わりにもなります
■90年代は譜面に起こすなんてことはしたことが無く記憶が全てでした
■現在(2020年代)は作った曲をサクサクPCソフトで譜面に起こすことができます、便利です
今回はその「功罪」について
90年代は一発録り
1stアルバムのInvisivleもパート毎の一発録音です
クリックの様なメトロノームも無しで録音しています
ドラムが無音状態でギターリフだけが鳴る箇所なんて一か八かの身体リズムでしたし。
そもそも知識も無くその発想もなかったというのもありますが…
そして現在、2020年代の録音は何度でも好きなところからやり直せます
何なら1小節毎に弾き直すことは勿論、モニター波形を見てズレている所を修正することすらできます
音楽制作業界の現代は無機質気味
ピッタリとメトロノームに合わせた音楽が世にあふれていますし、逆に人間味を出すために故意に少しズラすまであるそうなのである意味で何でもありですよね
ですので有機的な音楽というか、むしろその塩梅が逆に難しくなってきたという矛盾もあるようです
私的にはやはりライブに勝るものは無いと思っていますが「音源」はリリース後に世に残って行くもの
近代のデスメタルバンド(テクニカル寄り)の音源を聴くとピッタリ過ぎるくらいピッタリな(リズムに乗った)音源が多いと感じています
この舵取りをどうするかで我々も思案することがあります
とは言え、もちろん流行に左右されることは無いのですが「なるほどな」と感じる瞬間もあります
個人的にはキメの部分がキッチリ決まっていれば途中の波はありかもと思っています
俗にいうグルーブというのか分かりませんがライブ感というか
言語化するならば「激しさを表現するために待ちきれないハシリ気味感」というか
考え出すとキリがありませんが
ただドラムに関してはやはり人間ができる範囲でピッタリ(タイトな録音)行きたいです
何故かというとデスメタルジャンルの場合、音源もライブも殆どがドラムで決まります
「ドラムがタイトで巧い」から「音源として全体が際立つ」という。
そういう意味でもドラマーは大変ですよね
そしていよいよ間もなくレコーディングが始まります
最終的にどんな音源が出来上がるのか、非常に楽しみです
全力投球
ライブ出演の招聘を頂いたら全力プロモです
もちろん出演させて頂く限りは全力パフォーマンスですし多数のお客さんが御来場いただいた方が嬉しいですしね
これは演者の主催者に対する責任だと思っています
「興行が上手くいくこと」がイベントの持続性に繋がりますので演者としてはイベントを精一杯アピールするのは自然なことでしょう
物販に関しても当日のライブ会場で「ぼーっと」している暇があるなら一枚でもプロモです
「購入下さる可能性」=「応援下さる可能性」
我々の様な小規模バンドはメンバーによる手売り
その物販の際は自身がトップセールスマンになりきること
物販会場での声掛けも含め「音源をお客さんに届ける」が重要なことは以前にも書いた通りです
特にフィジカル系はライブ後も思い出に残りますよね
自身も観た後にシャツや音源を買って帰ります
そして何よりもそれが結果としてバンド活動の持続性を生むことにも繋がります
曲が生きている限り
来日バンドにしてもツアーバンドにしても、そのライブではベースが誰々のサポートだったとか、ギターは誰々のサポートだったとか、はたまたサポートボーカルだったとかは多々ありますよね
考えてみたらそれはそうなんですよね
特に我々の様なアングラ系の音楽の場合は各人の生活スタイルの違いもありますし、それで食べているわけでは無いのでその日は都合が付かないとか、経済的に厳しいとかで脱落していくプレイヤーも自然
日本の場合は珍しいくらいに正メンバーのみで活動みたいな、ある種の執着的な部分もあるので違和感があったりするかもですが
メタリカくらいまで行けばまた違う(固定)でしょうが、アングラ系は複数バンドを兼務しているプレイヤーも非常に多いです
Nileのベースボーカル氏は現Morbid Angelのギターで更にはIncantationのライブサポートもしているマルチ3兼職
他にもあるのが海外ツアーの際、サポートで現地プレイヤーを雇うケース
例えばベースとドラムは正メンバーが現地に行ってボーカルとギターは現地プレイヤーにお願いする様なスタイル
結局はバンドがアクティブであることを示せていてそれを現地のお客さんに生で音を届けられていることがポイント。これに尽きます
分かりやすく極論でいうならば例えば4人で往復100万円かかる海外渡航費だとしたら、2人で行って半分の50万円にし、現地で残りの2人をサポートで雇うことで負担経費が軽減され、それ故にその現地に行けてライブが実現できるということも(それが本望ではなくとも)
この辺は演者視点になりますが、来日バンドでバンマス以外はサポートプレイヤーなんていうケースも往々にあります
これがもしも全メンバーで来るとなると経費的に来日の実現は無かったもあるでしょう
そういう意味でも日本に来てくれる気概あるアングラ系バンドはかなり貴重ですし、それでも来られるというのはアティチュードとうか意地というか、ライブに穴を開けないという気骨を感じます
天才系異次元プレイヤー
人間技ではない様な強烈なプレイヤーっていますよね
特にテクニカルデスメタル系ジャンルにおいては本当にすごいプレイヤーだらけです
Neurectomyはヴォーカルギターがこれを歌いながら弾くという↓
ですがやはり活動継続が課題となるケースが多々
ましてやライブで再現していくとなると例えばツアーなら全パートのメンバーが超人系でかつ普段の仕事が休めて国によっては興行ビザを取ってのワールドツアーならば実現への道はハードルが高いでしょう
そもそも楽曲を演奏できるメンバーを揃えられるのかというところが起点ですから
とはいえリスナーとしては「うわー、凄いなー」となりますし当方も好んで聞いています
他にも考えられるのが「異次元で巧い人」(天才系)はどこか変わっているというか協調性を含めバンド形態で活動をすることに意外とハードルが有ったりもしそうです、これは推測ではありますが。
個人的にはSpawn of possesionを観たいですね、異次元ドラマーの1人。余りにも凄すぎます↓
リンクは彼らのドラム視点動画ですがこのバンドはギタリストも異次元系。リスペクトバンドです
DVDリリースまでの道のり
リリースまでに時間がかかりました
なぜかと言いますとリーフレットに問題があり全て作り直したからです
その経緯ですが「ライブDVD」はCRYPTOPSY日本公演時のサポートアクトで出演させて頂いたときの映像でそこは問題ないのですがリーフレットにクリプトシーのロゴやフライヤーが掲載されていたからです
彼らの肖像権を含め使用許可が必要になりますよね。そういった経緯がありリーフレットを再制作する工程を通じてのリリースの運びとなりました
ようやく胸をなでおろす気持ちですが無事にリリースできてよかったです。こういったことは今後しっかり我々もチェックするという自省も兼ねてここに記しておきます
激速・激熱なライブですので是非チェックしてみて下さい↓

pay to play
SNSで”Pay to play”という言葉を拝見
なるほどつまりはbuy on slot、例えば大型フェスや有名バンドの前座として出演する為にお金を払って出演するという意味でしょう
我々はまだそのケースでの経験が無いので詳細までは分かりかねますが合点が行くというかショービジネス的にも意味がありますね
(1)バンドとしてはプロモーションになるので広告費用として計上しパフォーマンスを頑張る
(2)主催側としては箱代やヘッドライナーギャラや機材費用の補填の1つに
確かに結果的に双方がプラスでしかないですね
しかもお金を払って出るわけですから主催側も大物バンド側も「出てくれて(経費)有難い」と思うでしょうし
このシステム、日本では聞きませんが海外では自然な歴史のようです
ただ金額のイメージが掴めないので誰か知っている人がいれば相場を聞いてみたいですね
もしも将来我々にそういった話があったときはいったいどのくらいの規模でどのくらいのpay to play(金額)なのかを確認してみます
こういったケースは対費用効果も想定しますが例えば好きでしょうがないリスペクトバンドとの共演の夢が叶う様なシチュエーションであればバンド活動資金を貯めておいてプロモーションパフォーマンスとしてのPay to playにトライしてみるのも良いかもしれませんね
そういえば、以前からふと思うことがあって
近年は突然出現してすぐに知名度が高いバンドって往々にして存在しますよね
もしかしたら上記の様なプロモ最短コースとしてこのような出演方法を取っているのかもしれません
逆説的かもですが知名度が先でないと世界中に溢れるほどの音楽の渦に埋もれてしまうという考えもあるのかもしれません
特に新人バンド(全く無名でこれからのバンド)は上記の様なPay to playは効果的かもしれませんし、パフォーマンスが良ければ主催やヘッドライナークラスのバンドが気に入って下さり招聘されたりのコネクションチャンスもあるかもしれません
とはいえ音楽性第一
最終的には観客の方が楽曲やパフォーマンスを判断するわけですから、その場に立つ事はある意味で〇✕を付けられるようなジャッジメント要素も想定され、不安もあるかもしれませんが万が一、ダメ出しならむしろ改善点が見つかったということで進歩すればよい訳です
話が逸れますが
「俺たちの音楽を聞いてくれ!」というワードをSNS等でたまに拝見する事があります
ちょっと俯瞰した見方かもしれませんが「聞いてくれ」と言いつつそもそも「自分達の音を届ける努力はしているのか」と思うこともあります
聞いてくれと言われてレコードショップに行ったけど無かったではそもそも「聞いてくれ」に対する反応は難しいですよね
むしろバンド側が「聞いてくれ」の為に「どこまで届ける(流通の)努力をしてるのか」も活動の情熱
お店への流通が困難であればバンドオフィシャルHPから購入できるようにだったりライブ会場で販売したり様々な工夫はできるはず
後半は首題内容が変化してしまいましたが届ける為にやれることは色々とあるんだと思います
カバー曲
カバー曲は歌謡曲などで多いですよね、往年の名曲などを今の世代の歌手がリバイバルしたり
著作権使用等がどうなってるのか、はたまたカバー曲をやってみたいと思った時に
どうすれば良いのかを以前に調べたことがありました
今回はその備忘録です
先ずはJ-WID(作品検索サービス)ですね
ここで歌手名や曲名などを検索して「録音」が可能かどうかを確認
録音がOKなら申請書に書いてJASRAC申請するという非常にシンプルな流れです
★紙に書いて郵送申請する場合の申請書リンク↓
★オンライン申請も出来ます↓
例えばCDにプレスするならば1枚当たり〇〇円という形で著作権協会を通じて原曲者に著作権料が支払われます
なのでバンドに直接コンタクトして「貴方の曲をカバーしてもよいですか?」では無い筈です
これってカバーされる側も著作権料が入る訳ですから嬉しいでしょうね
どなたか、我々のカバーをされてみませんか?なんて冗談はさておき。
つまり、リスペクトバンドの曲をカバーする事はそれが原曲者への応援サポートにも繋がるということになりますので、むしろ「カバー推し」というパターンもあるかもしれませんというお話でした
「閃き」とは
過去の曲は二度と作れないです
つまり「その時、その瞬間」の閃きで音階ができていますので
ただ、時折思うのが精神世界の広がりの中で何もないところから創るって怖いというか
普段の生活環境や人生観、直観、様々なイメージからの「閃き」で創り上げていくとはいえ
我々はコマーシャルソングをやっているわけでは無く、それを狙って作るようなことはしないので自由に想像しながら「できたものができたもの」になります
ベースとなるものは「激しい、速い、琴線に触れる」の3つでしょうか
そして最終的に「耳が心地よい」です
次の作品は創り終えていて最近は更にその次の創作に入り始めました
これらもやはり「できたものができたもの」になります
今回の内容は、ふと作曲時の精神的な面でのバランスを取っていく何か良い秘訣が無いかなと思い現状の自分のやり方を分析する意味で書いてみました
一年後、五年後、十年後にどうなっているかを読み返し振り返ってみたいと思います
Archspireドラマーオーディションの件
Archspireのドラマー氏の脱退ニュースで彼らは現在オープンオーディション中ですね
グラヴィティブラストやスイッチブラストが多用されている曲群なのと何よりテンポが速いので(誰でも出来るわけでは無い)オープン・オーディションとなったのでしょう
パッと思い付くならばBenighted、Aborted、Brodequin、Origin、Dark Funeral、Desecravityのドラマー氏でしょうか
とはいえ彼らも自身のバンドのツアーがあったりもするでしょうし現実的には掛け持ちが出来るのならばといったところでしょうか
彼らが「フルタイムのバンドであること」が逆にネックにも
仮にArchspire楽曲を叩けたとしても例えばツアーを1か月遂行していく都合が付くドラマーなのかであったり酷な話ですがこれだけで食べているわけでは無いので自由勤務体系の仕事を持っていて普段の生活が維持できた上で活動が可能なのか、もしくはバンド活動のみにフォーカスを充てられる程の富裕層であるか等のハードルも
他にも飛躍した例になりますが仮に日本人プレイヤーがやるとなると最初から移住する前提(ビザのクリアと意思疎通言語も)で行かないと、集合する度に都度高額な海外航空チケット費が掛かりますしスポット参加ならまだしもフルタイムでの継続は難しいかもしれませんね
テクニックが特異なスタイルのバンドの場合、欠員したときにそういった諸々のハードルも出てきそうです。Archspireの活動継続を切に祈いますし、きっと乗り越えて下さるでしょう
バンド運営
結論からですが「全てを自分たちでやれた方が良い」です
もちろん曲作りや歌詞作りは前提ですがレコーディング、キービジュアル、服装、アー写、ライブ、ストリーミング、Youtube、アートワークデザイナー探し、ミックスマスタリング、著作権登録、SNS、エージェント、フェス関連等々
1つでも抜けがあって「出来ない」があると「やりたい活動」に何かほころびが出るかもしれません
特にレコーディングに関しては自分達で完結できる時代ですしISRC(作詞作曲者登録)などの割り当ても自分で出来ますし、itune等も簡単に曲名の登録はできますし、ミックスマスタリング後はDDPマスターを自分で工場依頼すればCDを刷れますし、Tシャツも自分で制作会社を探せば作れます
やったことが無いのであれば全行程を一度やってみることをお勧めします
自身で全工程を把握した上で行動することで相手の立場も理解しながら進めることができますし、その後にレーベルにお世話になる際もスムースに行くと思います
1つの物事がどうやって完成して行くのかに興味を持つこと
例えばですがエンジニア氏にミックスマスタリングを依頼する場合
事前のトラック数の相互確認であったり、弦楽器はDry納品(リアンプ)なのかどうなのかとか、ドラムはMidi納品なのかWavなのかとか、ボーカルはDryなのかどうなのか、リファレンス音源や全体把握用の仮2mix Wavを用意し忘れてないか、いつ頃にそれを依頼するのかの事前スケジュール交渉、レーベル所属ならばリリース時期と逆算してレーベルへの納品計画が上手く進行できているかどうかの管理であったり、納期3~6か月は見ておいた方が良いアートワークデザイナーとのアートワーク完成までの交渉や、そのアートワークがリリース時期とどのような擦り合わせが出来ているか等々
我々が2020年にリリースした「Reprogramming」アルバムはセルフレーベルを立ち上げた上で全行程を自己完結したアルバム
四半世紀以上も音楽から離れていたので先ずは全工程を自己理解することから始めようと考えた背景があります。右も左も分からない浦島太郎状態での依頼ですので、もしかしたら「ちんぷんかんぷんな事」をしてるかもしれないと思ったのもありますし先に現代式のやり方を把握してみようと思ったからです
結果的に我々にとっては「Reprogramming」アルバムの制作は仕組みの理解にもなっています
バンマスをやるならばこれらは全体把握として必須だと思いますし、バンマスでなくともこれらのプロセスを理解しておくことはバンド全体のプラスになると思います
特に我々の様な小規模アンダーグラウンドバンドはDIYで全てを自分でやれることは活動を末永く続けるための強みとしてもお勧めだと思います
曲が年数を重ねると変化するケース
よくあるのがギターソロ
創作者であってもCD音源とは少し違うようにギターソロを奏でるプレイヤーも意外と多いのではないでしょうか
基本となるギターリフやドラムなんかもCD音源とは少し違うパターンになるケースも
これは創作時にプレイしたときから、年数を重ね「弾きこんで(叩き込んで)そうなっていった」ということは往々にありそうです
他にもメンバー交代がありそのプレイヤーの個性で変わることもあるでしょうし、ライブを重ねることで変化して行くこともあるでしょう
結論的には最新ライブでのそのプレイがその楽曲本体
我々は基本は「CD音源そのままを表現したい」ではありますが「生演奏時はこうした方がより表現力が増すだろう」と感じたときは試行錯誤したりもしています
プレイヤー的にはこれが非常に楽しかったりもしますが、そのまま(音源通り)やって欲しいというサポーターの方もいらっしゃいますしこれは塩梅になるでしょうね
そして近年は「創作タイミングで譜面を残しておくこと」をしています
創作は殆どが「一瞬の閃き」になるので後日それをどうやって弾いたのかで再考するケースも。
譜面作成はオススメかもしれません
添付は次作某曲のTAB譜の一部
既に譜面化しています
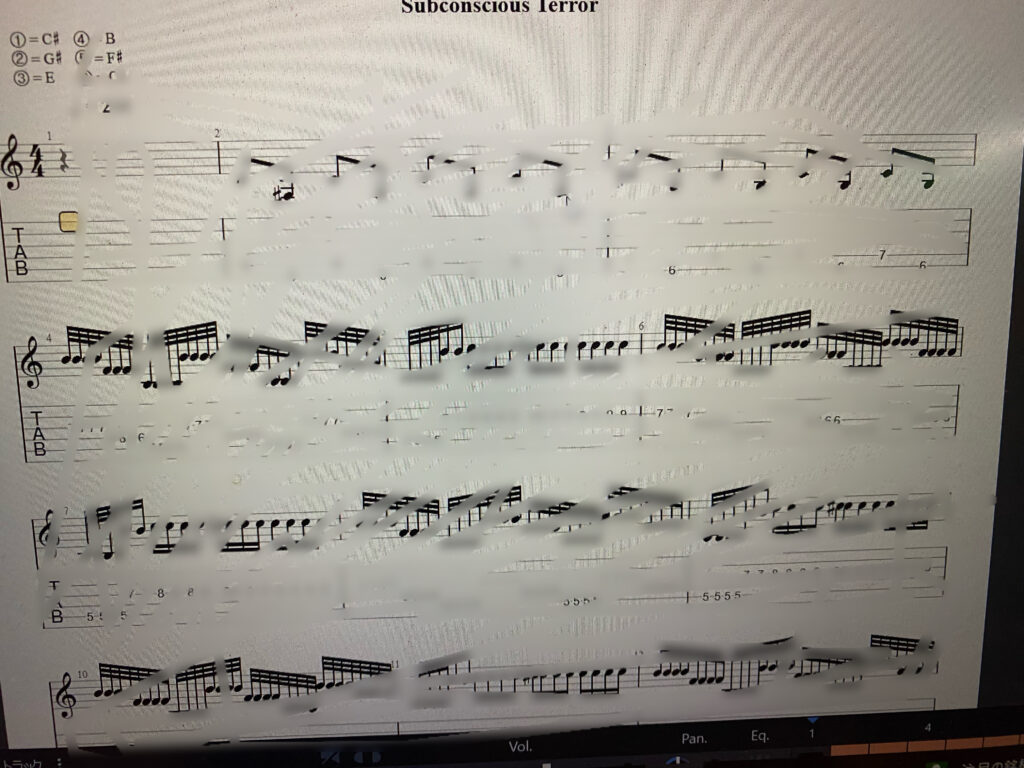
マイナーがマイナーである理由
マイナースポーツ競技界
誰かが活躍すると同業界選手は嫉妬が凄くなんなら失敗を願うまであります
そしてどうにかして足を引っ張ってやろうとする場合も
つまりは「活躍が面白くない」という狭い領域な話ではありますが。
これは「マイナー業界がやはりずっとマイナー業界である」ゆえん
もしも世界的に活躍し、その競技選手人口の10倍や100倍以上のサポーター(ファン)がいればようやく諦めるでしょう
たとえば野球だとメジャーリーガーの大谷翔平選手
雲の上の存在くらいにまで到達しない限り足を引っ張ろうとする業界も
これを誤解を恐れずにマイナー音楽界に当てはめてみると
デスメタルでいうと国内において世界的に活躍している「絶対的日本代表バンド」は不在です
つまり普段からアリーナクラスでライブをやっているようなデスメタルバンドは知る限りではいないと思います
もしもこういったバンドが出現すればきっとメインストリームに上がってくるかもしれませんし、そうだったらいいですよね、シーンは盛り上がるでしょうし願っています
我々の場合はその辺に関してはかなり俯瞰しているところがあり何にも属さず徒党も組まず単独でのアクションが基本というと語弊(実際は表面に出ないまでもバンド仲間など)がありますが、あくまで自然に身を任せつつ「自由に音楽を創作する」、「機会を頂くことがあれば全力でライブをする」、「自己表現を目指す」の3つを柱に活動しています。ですので何かをしてやろうみたいなのは無いので亀足なマイペースな活動なのですがその類は野心あるバンドにお任せしていますし、それよりも創作と表現を優先しています。きっとなるようになるんだと思いますし自由にやりたいですね
年齢層
先日の台湾公演(2024年8月30日)
お客さん層は限りなく100%近くが20~30代の若者で女性も非常に多かったです
それでいてマーチ(CDやシャツ)もひっきりなし。勿論、海外では我々は外タレ扱いになりますので滅多に観れないだろうという御贔屓もありますが購買欲も強かったです
国内に目を移すと一足先にプレイヤーもお客さんも高齢化が進んでいますが、上記の空気感を国内にも持ち込めれば若いプレイヤーと若いお客さん層にも訴求することが出来ますね
この差はなぜでしょう
ライブハウスへ足を運ぶ台湾の人達から感じたのは
「ちょっと怪しげな雰囲気の場所に冒険しに行くような」
「文化の違う異国人もいるし雰囲気も刺激的」
「でも、中に入ったらみんなが仲間で一緒に騒いでお酒飲んでワイワイできる」
これって、日本の80-90年代で言うところの「ディスコ」のイメージです
なんだか「行けば楽しそうなところ」、「ちょっと不良っぽく」、「でもオシャレして行こう」の様な
そんな感覚がありました
腕を組んで眉をひそめながら見る人は皆無でとにかく汗をかいて皆んなと遊んで帰る
曲を知らなくても関係の無い「遊びスポット」の1つ
これはそもそもそうなんですよね。
ただ、長年の醸成なのかどうか、国内のライブハウスは世の中では敷居が高い様に捉えられているのかもしれません
ちなみにこの日は当日券だけでも相当数来られました
「おっ、なんか今日は外タレの激しい音楽系のライブじゃん、ふらっと行ってみよう」も。
思い出すのが当方学生時代、その日が何のイベントかも気にせずに暇を見つけてはライブハウスに行っていました。「行っていた」というか「遊びに行っていた」が正確です
自分にとっては夜の遊び場という感覚でしたし生の音楽を思いっきり浴びて帰るという
これが段々とそうではなくなり、現代においては「ライブハウスへ足を運ぶ為に何か月も前から」準備し「気合を入れて、いざ、行かん!」の様に軽い気持ちでフラッと寄るイメージが無くなってきたのだと思われます
これらは長年に渡り醸成されてきた日本文化ですからすぐに変わることは難しいでしょう
ではどうすれば良いのか
それを改革というと大げさですが
やはり今となっては世の中では敷居が高いイメージが付いていると推測するガチガチの箱(ライブハウス)というよりも、それこそレストランやバーなんかでバンド演奏を日常的に浴びれるところに行きつくまでがその改革には必要になってくるかもしれません
つまりライブを観に行く事への重さを軽くすることです
それこそ「ご飯を食べに行く」ノリや、ついでにバンド演奏を浴びれる様な身近さがあれば
文化の醸成については何十年も掛かる結果だと思いますしそれこそ国(文化庁等)を含めた動きになるでしょう
当方、一応そういう筐体(ライブも出来るバー)を所有していますが基本宣伝をせず知り合いベースでの利用ということもあり、今のところは年数回の利用にとどまっています
それを強く推してない背景としては周辺の専業/生業ライブハウスさんとの関係(そんなのが出てきたら邪魔ですよね)もあります
もしも改革をガチで目指すならば全方向視点(影響、メリット、デメリット、課題解消etc)を1つづつ取り組み、その実現をゴールとするならば国や自治体をも巻き込んで行く必要があるかもしれませんね
国内デスメタルシーンにおけるリスペクト人
以前に”リスペクトバンド編”を書きましたが今回は”人”です
(1)はるまげ堂&Obliteration Records主催の関根さん
ご自身がバンド活動をされているだけでなくレーベル運営やイベント運営までされています
これは尋常ではないアクションですし正に「デスメタルで飯を食べている人」という、国内においても超希少人物であり国内アンダーグラウンドシーンにおけるレジェンドの1人ですね
(2)EVP(Evoken de Valhall Production.)主催のYamaさん
TOP | EVP4U – メタル系ライブイベントチケット予約・販売サイト
デスメタルを含むエクストリームメタル業界において来日アーティスト招聘をされています。
アングラシーンをビジネス化するのは本当に難しい訳ですからそのアクションには頭が下がる思いですしご自身もバンドをされていますし、同様に正に「エクストリームメタルで飯を食う」を実行されている方ですね。(関西の方で実は30年くらい前にライブ等でご一緒していたことが後で判明しました)
(3)Cks Productions主催のZumaさん
TOP | Cks Productions (cks-productions.com)
以前の「リスペクトバンド編」で既出ですが再度。KRUERTY主催のZumaさんです
年中をご自身のバンドで海外ツアーされながらも来日招聘イベントも行うという
もはやセンスが異常能力値を叩き出されています
(4)海外(台湾)/Bad Moon Rising主催のニックネーム”文文”
Bad Moon Rising 惡月上昇(@bad_moon_rising_taipei) • Instagram写真と動画
台湾でエクストリームメタルシーンを盛り上げようと台北で孤軍奮闘中の彼。海外バンドがアジアツアーをする際に台湾でライブするケースでは彼がキーマンとなって動いています。(音源販売もされていて我々の音源CD等も台湾では彼のところから購入することができます)
台湾のメタルシーンは非常に厳しい市況がありながら彼の持ち前の明るさとセンスで毎回素晴らしい公演を見事なまでにやり切っておられます
ライブハウス事情ですが台湾/台北中心地(日本で言うところの東京渋谷駅近)には杰克音樂という名のライブハウスがあります。このライブハウスのオーナーはエクストリームメタルのDharma(達磨)のドラマー氏(インタビュー→NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【DHARMA (達磨樂隊) : BHAISAJYAGURU】 – Marunouchi Muzik Magazine)ということもあって特にメタル系はここで行われることが殆どだと思います。経営的にはアイドルイベントを主体に屋台骨を作りメタルイベントも並行して開催。これもオーナーセンスですね
ちなみにこの杰克音樂という台北のライブハウスですが中に入ると入口で二手に分かれていて2ステージ、つまり2つのライブハウス(大/小)が存在し更には1部屋練習スタジオまであります。これにはビックリしましたし楽屋も含めて非常に素晴らしい造りのライブハウスでした
ということで今回は実際に出演させて頂いたことのある方々を紹介させて頂きましたがアングラシーンを盛り上げていきたい情熱人、そして縁の下の力持ちをされておられる方達を是非引き続きご支持応援くださいませ
アンダーグラウンド系デスメタル国内レーベル&ショップ
今回は我々の様なアングラ・デスメタル系の音楽商品を取り扱って下さるレーベル・ショップ紹介です
◆東京/Obliteration Records・はるまげ堂
→「Asakusa Deathfest」というイベント名で海外からも多数出演する国内最大級アンダーグラウンド・エクストリームミュージック・ライブイベントも主催されています
◆大阪/AVR(Amputated Vein Records)
◆大阪/めたる屋 S.A.MUSIC
めたる屋S.A.MUSIC (metalpesado.com)
◆主に関東圏/Diskunion
ディスクユニオン|レコード・CD・DVD・音楽ソフトの通販・買取 (diskunion.net)
ショップについては皆様の方がきっと詳しいと思いますが長年アングラシーンをサポートくださる貴重なお店です
付随余談になりますが、かれこれ90年代にまで遡ると地元大阪の心斎橋(三角公演近く)にはディスクヘブンというお店があり学生時代はかなり通っていました。
当時はネットも普及してなかったので陳列されているデモテープやCDのアートワークと睨めっこしつつ、店員さんによる手書き説明メモを見ながらイメージを膨らまして買うという、いわゆる「ジャケ買い」の手段でした
とにかく聴いてみないと分からないので当時(学生時代)は毎月10~20枚の音源(デモテープやCD)を買い漁っていました
他の情報収集としては音楽雑誌のバーン、ヤングギター、アングラ系ファンジン紙を毎月読み漁りデモテープトレードなんかもしていました
とにかく手探りの時代ですからね
その中でも強烈に思い出すのはCyptopsyのデモ
あまりのブラストビートの速さに驚愕した記憶があります
これをどうやって入手できたかというと後に活動を開始するVomit Remnantsドラマー氏(バンマス)との出会いです(※サブコンシャステラーが2020年春、再活初年度はサポートドラマーも務めて下さいました)
当時の彼はまだ高校生でありながら遠征(それ自体が凄い)してサブコンの大阪ライブを観に来てくださっていて、彼にCryptopsyのデモテープ等を含むマニアックなデモテープを多数頂きました
彼はあの当時に海外バンドと手紙のやりとりでテープトレードをされていたんですよね(当時は1人ブラックメタルバンドも主宰)。当時の日本では誰も入手できないであろうエクストリーム音源を多数所有されていました
彼は後に日本を代表するデスメタルバンドとなっていきました、リスペクトバンドです。
あとはサブコンシャステラー創設時のドラマー、デスオも当時から知見が凄かったです。当方と知り合う前からDevastationやSADUS、Napalm Death、Terrorizer、Cannibal Corpse、DEICIDE等をバリバリ聴いていてメタリカ、メガデス、スレイヤー、セパルトゥラくらいしか知らなかった当方には驚きの連続でした
音楽は縁ですね
↓下記は当時のファンジン紙のsubconscious terror紹介例(感謝)
(デスメタルというワードがまだ一般的ではなくデスラッシュというワードも出てきていますね)
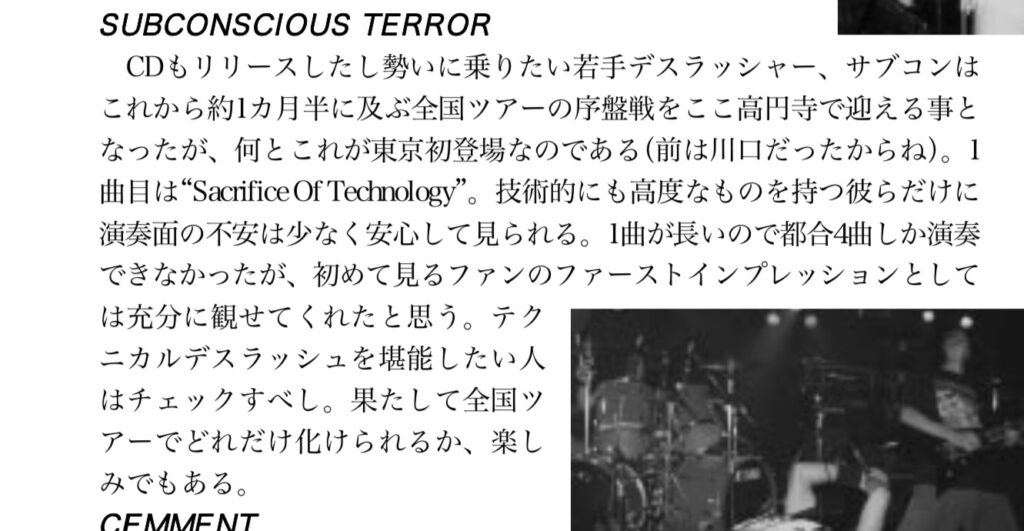


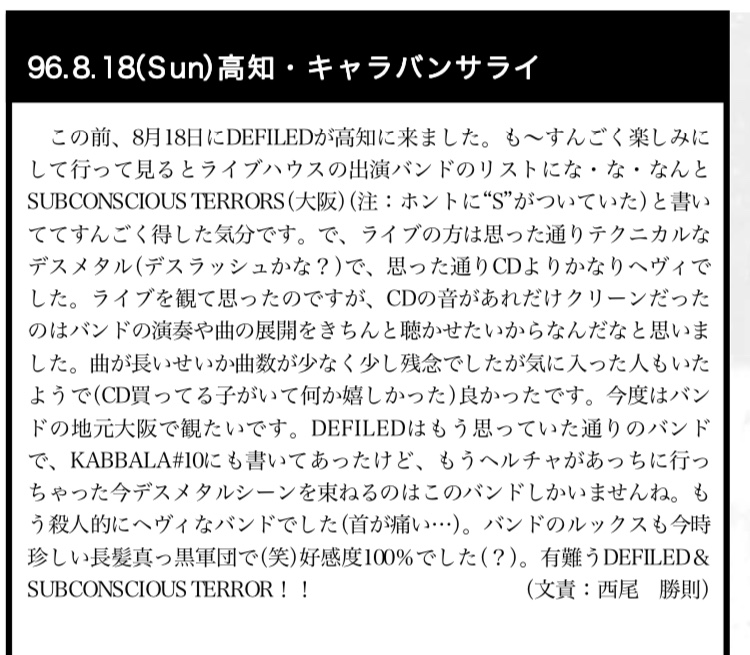
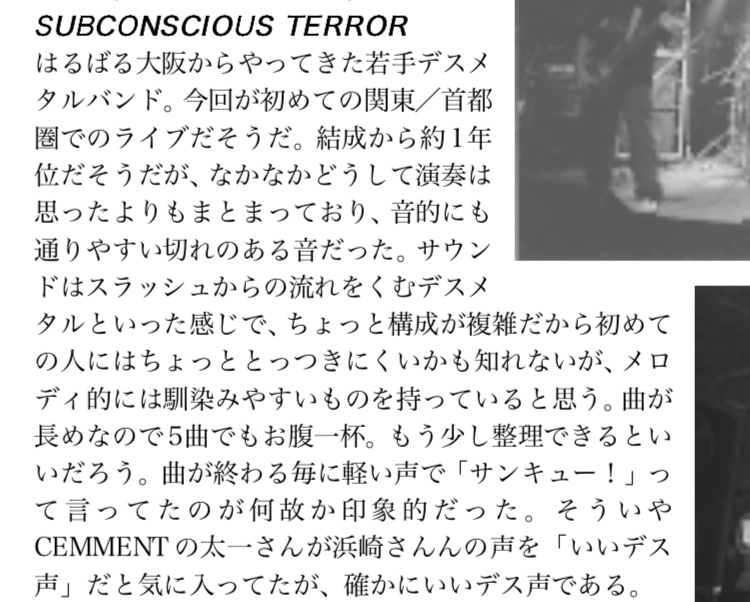
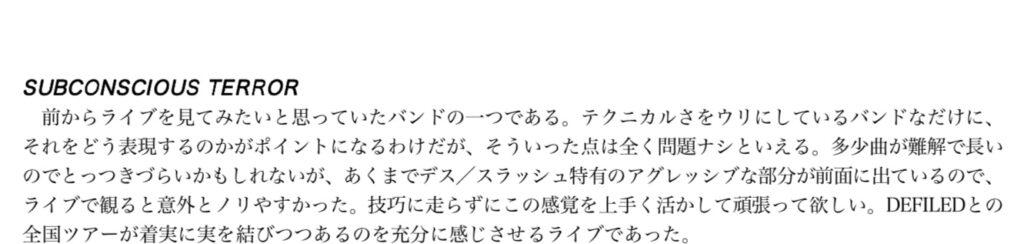
バンド名義での”Active”は止まらない
バンド名義活動で”Active”状態を保持するならばバンドアンサンブルを確実なものにすることが重要
歌謡アイドルグループであればその本人でなければならないかもしれませんが、我々の様なエクストリームメタルバンドの場合は誰がバンマスで誰がギタリストでなければならないかはあまり関連づかないかもしれません
デスメタルでいうとDEICIDEの場合、ギターリフマスターのホフマン兄弟が抜けてもDEICIDE名義はバリバリ活動していますし、Cannibal Corpseもカリスマ、クリスバーンズが抜けても更に活動の幅を広げています
あくまで「バンドの名前」(バンド名義)と「その曲群」が主人公です
元も子もないですがそもそもバンド名義は個人ではないですからね
決まったライブに穴を開けない事
これもバンド名義がアクティブを示す重要な行動だと思っています
ですのでメンバーが欠員したからライブをキャンセルするはバンド名義に対する機会損失になってしまうかもしれません
当バンドにおいても、仮にバンマスが抜けてもサブコン名義の活動継続を願っています
ヘドバンしながら演奏をする
当バンドの場合、創作曲は「完成したものが完成したもの」になるので創作中にライブ中のヘドバンを想定して曲作りが出来ないでいます
ライブ中は頭を振る余裕が殆ど無く、必死で演奏のアンサンブルに集中しています
この辺りを上手くコントロールできればと思うことが多々あります
ですがライブにおいてのビジュアルは音楽性を表現するのに非常に重要だと考えていてライブでは「視覚的」にもその音楽性を感じて頂きたく服装等も整えています
我々はライブ上においては「スピード+曲音階+視覚的な激しさ」の融合をもって楽曲への聴覚補完も含め楽曲全体を表現したく、足を運んでくださった方々へ琴線に触れて頂きたい想いがあります
今後も更に強化して行きたいです
振り切れる度胸と好き具合
バンドの知り合いでヤキモキしながら活動している人がいます
結論的には「どうしたいのかが定まっていない」のでしょう
例えば商業音楽ならば「売れたい」でしょうし、我々の様なアングラ系ならば「界隈で長く活動できる環境を整えたい」です
そして首題がその答えです
当方は会社経営をしています
潰れずに3社あって長年続いていますのでビジネスの流れには乗っているのでしょう
なぜ続いているのかですが運的要素がほぼ100%に近いくらい「運の良さ」のみです
努力はしたことが無いですし幸運だけで長年やりつづけている状況です
仮の例えですが、どんなにおいしいラーメンを作ってもその店が潰れることもあります、やはり運です
では、その運をつかむにはどうすれば良いかですよね
考えても考えてもその答えは分からないのですが、「振り切れる度胸」と「誰よりも好きであること」
現状はこの2点に行きついています
これをバンド活動に当てはめて行くと「振り切れる度胸」と「誰よりも好きであること」の『度合いの差』になると結論づけています
アメリカをツアーしているバンドを羨ましいと思うなら「だったらそれを自分がやればいい」
それだけです。
「やりたいのになぜやらない?」という事になります
そこは度胸や好き具合だと思います
たまに聞くのが「俺はやりたいけどメンバーが居ない」
これは正に言い訳といいますか本当に実現したいならば探すまで諦めない情熱があるはずです
他力本願は実現が難しいですし情熱不足とも言えるでしょう
貴方よりももっと情熱をもって活動している人たちが実際に沢山いるということの裏返しとも言えます
以前にも述べたことがありますがメンバー募集は地球上で探せばきっといるはずです
自宅周辺でメンバーを探す必要性を感じたことはありませんし、国籍や言語も気にしていません
意思があればOKです
ちなみに楽器のテクニカルな部分(スキル)に関してはセンスの比重が高いとは言え、やはり意思の強さ次第で出会うべく人と出会うことが出来れば豹変する(楽器上達が可能)と思っています
「度胸と情熱が誰よりも強い」、これに尽きますね
小所帯の優位性
我々の様な小規模で、かつアンダーグラウンドミュージック活動をするバンドの場合、バンドメンバー人数x掛かる経費が大きく左右されます
例えばですが、ライブで大阪ー東京間を新幹線移動するとして
◆3人編成バンドの場合、「大阪→東京」往復1人27740円x3人=計83220円
◆5人編成バンドの場合、「大阪→東京」往復1人27740円x5人=計138700円
上記で約55000円の差異ですからCDが2000円だとするとライブ会場で約28枚売れてようやくこの差異を埋めることが出来ます
これが海外遠征ともなると相当な差異が生まれますよね
特に我々ぐらいマイナーなバンドの場合、招聘くださるエージェント側もサポートフィーを出す際にその分(人数経費)が少なくて済みますので喜ばれるという特典もあります
現況のサブコンシャステラー編成人数は3人で足りているのでそれで十分やれていますが、編成人数の多いバンドほど活動の大変さは想像できますし凄いなとリスペクトしています
今回はお金に関するいやらしいことを述べてみましたが経費面でバンドメンバー内が崩れる(経費負けが続きバンドが継続できなくなる)のだけは避けたいですね、往々にしてよく聞く話なのであえて書いてみました
ライブ時における音のクリアさの重要性
以下、先日の台湾公演でのSubconscious Terrorのライブ音質についての言及を頂きました
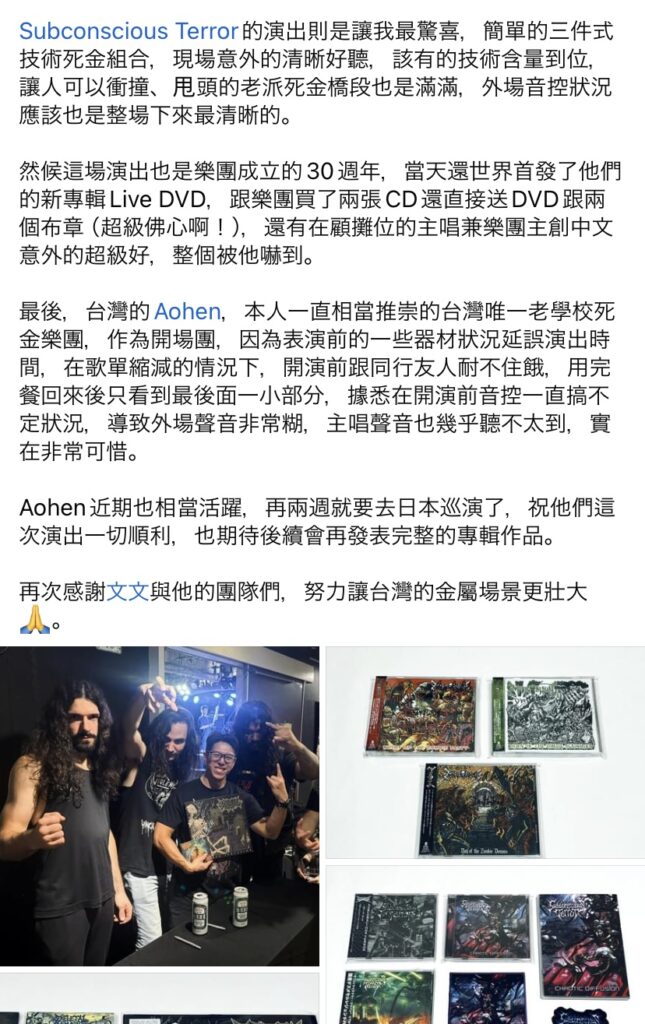
要点のみを挙げると「出演バンドの中で最も音がクリア」
これは以前、本Blogで述べた通りですが「各楽器の音域を被せない」を徹底しているに尽きます
特にギターはカリカリなくらいに歪ませないというか、とにかくベース音やドラム音に被らない音作りの研究
これまでも書いてきていますがヤマハのクリーンアンプにディストーションペダルの歪みを少しです
せっかく頑張って楽曲創作をしても例えばギターの低音域がきつ過ぎたり、歪ませ過ぎたりすると、
もはや音階の輪郭が無くなり全体で何をやってるのか分からない現象になります
できるだけCD音源を再現したいです
確かに音がクリア過ぎるが故に演奏ミスをすると思いっきり目立つ(タッチ音まで聞こえる)のですが、それもライブ修行の場ですし誤魔化せないことは後にどんどん反省と改善をしていけます、つまりバンドとしてもレベルアップが期待できますのでモチベーションアップにも繋がります
バンドアンサンブルが進化していく1つのヒントになるかもしれませんね
海外での商業公演に関するビザや準備
現況入国が難しい国での商業公演を来年(2025年)に予定しており着々と準備を進めています。
1000人規模の大型公演x複数回を予定していますが、やはりすべての行程をクリアするのには十分な準備期間が必要になります、つまり出演日にたどり着くまでの過程で諸々の手続きがあります
海外での商業公演の際は、「アー写」や「(※)メディア掲載記事」、「歌詞提出」、もちろん「パスポート」(パスポート有効期限ももちろん国により条件があるので半年以上残っていることは最低限の前提)もそうですしそれらを含めて代理人を通じ相手国の政府側へ申請し出演許可を得る工程があります
エリアによっては会場使用許可が下りずに公演会場(都市)を変更するケースもよく聞きます
特に歌詞に関しては検閲が厳しい国もあります
殺人的な歌詞や差別的な歌詞や政治批判などの歌詞は審査落ち(商業公演ビザの申請が通らず)もあるので気を付ける必要があります。幸い我々はそういう歌詞ではないのでクリアしましたが不安であればエージェントに相談すると良いでしょう
先述の「(※)メディア掲載記事」提出とはなんぞやですが
バンドオフィシャルHP上にはわざわざ「メディア」というリンク先を作っていて普段からコツコツと「メディアに掲載されたこと」を載せています
Media – 【OFFICIAL】SUBCONSCIOUS TERROR
海外ツアーは、いわゆる企業勤務の海外出張ではなく「パフォーマンスで行く短期就労ビザ」なのでこれらは「あなたが本当にプロミュージシャンである」ことの証明書類の1つになります
ですのでメディア掲載記事についても商業公演ビザを申請する際はすぐに提出できるように予め備えておき、必要な際にはHPからサッとプリントすればOKにしておけば慌てずに済みます
どうしても我々の様な規模の小さいバンドの場合は、こういった手続き等の過程を自分たちでこなして行く必要があるので全てDIYが基本になりますが実際に経験をしていく事で沢山の事が学べます
海外で商業公演をしたいバンドマンはメディア記事をまとめておくと良いかもしれませんね
熱烈歓迎に学ぶ
先日、初の台湾でのライブでした
台北空港を出た瞬間、我々の周りに人だかり。そのまま沢山の方々と写真を撮り色紙まで持参されていてサインをする状況でした。まるで芸能人だと勘違いするほど。メンバーもただただビックリしていましたがこの熱烈歓迎ぶりには非常に驚かされました。ライブ中も曲間のMCも熱烈歓迎でした
この時に思ったことは来日ツアーで来られたバンドに対してもっと歓迎の意を身体で大げさにでも表現することは重要だと思いました。せっかく遠方来日下さっていますし「また来日して欲しい」という気持ちを身体で表現できる1つ
国内音楽雑誌のインタビューでよく見る記事が来日バンドの日本のファンへの感想が「日本のファンは礼儀正しくて素晴らしく音楽をよく聴いてくださっている」の内容。
もしかしたらですが、言葉を選んでそういう表現(日本人は静か)になっている可能性も考えられます
もちろん国ごとの文化や習慣もありますのでそれぞれの迎え方があっていいと思います
我々が来日アーティストOA出演時は楽屋で共演挨拶等させて頂く際、地元の和菓子などをお土産にお渡ししていますが出迎える際は今後は身体全体でもっと熱烈歓迎していきたいと思います
そんな台湾での熱烈歓迎ぶりから学んだことでした

GENERAL RIDER(=technical rider+hospitality rider)
ライブ出演の際、我々の様な規模の小さいバンドの場合だと事前にステージ図、つまり①立ち位置、②持ち込み機材、③SEの有無、④曲順リスト等を書いたいわゆる「ステージプロット」(Stage-plot)を事前に1枚提出する範囲で終わることが多いですが世界を回るようなヘッドライナー規模のバンドの場合は「General Rider」があります
「General Rider」とは、アーティストやバンドがコンサートやイベントでの出演に際して要求する特定の条件や要件をまとめた文書のこと
「rider」は契約書に付随する補足条件や条項を意味し、通常は「技術的な要件」(Technical rider)と「ホスピタリティの要件」(Hospitality rider)に分かれます。
つまり「General Rider」=「Technical rider」+「Hospitality rider」と覚えてよいでしょう
※Technical Rider・・・ステージの設定、照明、音響機器、電源の配置など、パフォーマンスを行うために必要な技術的な要件etc
※Hospitality Rider・・・楽屋の設備、食事、飲み物、リラックスできるスペースなど、アーティストが快適に過ごすために必要な要件etc
主催者や会場側はアーティストのニーズを満たすためにこの各riderを参考に準備を行って行きます
「ジェネラルライダーの例」についてネット上で公開されているものがありましたのでリンクを↓
Inge van Calkar rider august 2024.pages
特にテクニカルライダーについてはバンドの規模を問わず参考になる内容が多いですし、イベントが円滑に開催進行される為にも我々出演者側としても理解を深めておき、会場、主催、演者が相互協力を図れる様にこちらの内容を熟読してみるのも良いかもしれませんね
参考までに
ライブ現場での対応能力と普段からの積み重ねは比例
これまでにも述べてきましたがライブ機材は「とにかく頑丈でシンプル」を重要視しています。
万一、ライブ中に壊れるような事があると中断も起き得ますし、機材接続が複雑だとトラブル時にそれだけ解決も複雑に
先日の台湾公演(2024年8月30日台北)においても機材トラブルは一切なかったです
飛行機等の移動も含めとにかく頑丈でシンプルが功を奏しています。
一つだけあったのが会場のステージモニター(内音)が壊れたことでした。こういった場合はもちろん会場側の設備ですので我々で防ぎようはありませんね
リハーサル時に発生したのが幸いでした。舞台上のスピーカ故障=ボーカルはどれだけ叫ぼうがマイクからの音がスピーカーから鳴らないので舞台上ではドラム音と爆音アンプで何も聞こえない訳です
ボーカルは自分の声がどれだけ歪んでるかも意識の中で確認しながらやっているので何も聞こえないとなると不安がよぎりがちです。良いパフォーマンスを出すためにも声の確認はしたいです
その後、スタッフさんによる懸命なチェックにより「舞台内のステージモニター8つ」の内、1つだけ壊れていない(音が鳴る)スピーカーがあることに気づきそれを今回はボーカル足元に置いて乗り切りました。安心感が全く違います
表現の仕方が難しいですが「故意にとは言わないまでも、普段からどこまでも劣悪環境な想定をしておき、それでいてどのバンドよりも素晴らしいパフォーマンスを出す事が出来るかも突き詰める」は常に意識を高めていきたいです
台湾公演会場の杰克音樂は非常に素晴らしい音でした。「音が良かった」という表現は普段からの音作りの賜物でもありますが会場の設備や会場の構造とのマッチングも含めてバンド側がその日のベストを尽くせるかどうか
我々はようやくライブでの音作りが固まってきた(手法確立が出来てきた)のでオールラウンドにどこでもイメージ通りの音が出せる確率が上がってきました
ライブの音作りはライブ活動をやり続ける限り永遠に研究しつづけることになりますが、確立できてくればくる程、比例してメンタル的にも強靭(不安想定要素がが益々無くなるので演奏に集中できる)になってきます

国内のリスペクトバンド2
国内のリスペクトバンドその2は長年に渡り世界を股に活動し続けている国内デスメタルバンド代表のDefiledです
Defiledのバンマス氏とはかれこれ30年以上のお付き合いがあります
前回のKRUELTYと同じくバンマス能力値が異常に高いです
どこまで彼の背中を追ってもその背中すら見ることが出来ないくらいの存在
キーワードは「頭脳とメンタル」という印象です
我々の様な超アンダーグラウンドシーンでここまで長年アクティヴであることは不可能に近い希少種であるにも関わらず近年もバリバリとワールドツアーをされていますし地球上のデスメタルバンドは「日本のデスメタルバンド代表格=Defiled」と認知していると思います
創作のみならず全方向において長けている稀なバンドでリスペクトしかありません
我々もバンド活動をしている身なのでこのシーンでバンド活動を長く続ける難しさは重々承知しているつもりです
多くのバンドは休止したり、いつの間にかフェードアウトしたりで続かなくなるケースが多い中、長年ずっとActiveであることが日本のデスメタルシーンのボスであることを証明しています
さらなる活躍を願うリスペクトバンドの1つですね

レーベル側とバンド側の温度差
バンドをやっていて「レーベルから音源リリースしたい!」
だけど「どこからも反応が無い」というパターン
もちろん第一には「良質な楽曲を作れているか」どうかが筆頭であり何よりも重要です。
ただ、それ以前の問題ということも多々あるようですので気になったことを述べてみます
貴バンドが「既に集客力のある国内外で有名なバンド」でもない限りはオールインワンでレーベルにプロモキットを送る必要があります
例えばデモ音源を送ってもほぼダメでしょう
完璧にミックスマスタリングを終えオリジナルのアートワークや歌詞カードも揃え、もちろんEPKも完璧に出来ていてようやく土俵にあがれると言うのが必要最低条件
つまりレーベル側としては「工場プレスするだけで即リリースできる」位のものを送る必要があります
そりゃそうなんですよね
バンド側が「良い曲を創ったからこのデモを聞いてください、気に入ったらリリースしてください」と言ってもレーベル側は「では音源が出来たら聞いてみましょうか?」位にしかなりませんし酷ですが最悪は直行ゴミ箱行きもありえると思います
厳しいニュアンスになりますが「どこぞの馬の骨」(我々も含む)が送ってきた音源を規模の大きいレコード会社が聴いて下さるまでたどり着くのは道のりが遠いと思った方が良いでしょう
中堅以上のレーベルともなると日々「俺たちの音源をリリースしてくれ!」内容の大量の音源が送られてきています
自分自身がレーベルの社長側に立ってみると分かるかもしれません
日々送られてくる音源だとうんざりするまであるかもしれませんし、会社経営ですから年度予算だってあります
ましてやミックスマスタリングすら終わってないラフデモ等はまず難しいでしょう
もしも私が中堅以上のレーベルの社長ならば「これは何?で?どうしたいの?」かもしれません
ですので全てを完璧に終わらせた内容物をプロモキットとして準備できた上でようやくレーベル交渉の土俵に立てると見た方が良いと思います
国内には素晴らしいバンドが沢山あるにもかかわらず、この辺りに関してはレーベル(特に海外)との勿体ない接触の仕方をしているような気がすることも
特に我々日本人の場合は英語のハードルがありますし仮に内容物を完璧にしたとしても、それでも不合格になるケースは多いと思われます
とはいえ、もちろんレーベル側もブランドイメージの保持があるのでプロモキットを送ったときの反応として「現在はリリーススケジュールが立て込んでいるので今回は申し訳ないですがまたチャレンジして下さい」(契約不成立)という回答パターンで柔らかくお断りされるケースもあるかと思います
色々と綴ってきましたが、やり方については各バンドの方針等があると思いますし上記はあくまでアングラ系バンドマン向けのレーベル交渉術として参考に留めておきます。
きっと別のやり方も多々あるかとは思います
バンマスの能力値の重要性
特に現代のバンマスに求められる能力値は非常に高いレベルだと思います
一言でいうと「なんでもこなせる」
いつでも活動に費やせる時間の確保と経済能力を備えているのが前提で創作センスと楽器スキルと外国語での交渉スキルと周りを見渡す能力等々
この辺りの能力はバンマスをやるならば前提として持っていて当然な範囲かもしれません
そこからようやく個性を出していけるのが現代におけるバンマスに課せられた使命というと厳しいように聞こえますがそもそも音楽が好き過ぎてやっている訳ですから上記を実行に移すのに努力とか苦労という感情ワードを感じないと思います
つまり好き過ぎてやっていることは環境作りも含めてやれて当たり前という感覚
そこに苦痛は無いと思いますし、むしろそういった流れを作る自分を楽しみながらやっているとも言えるでしょう
生涯を音楽から学んでいます
国内のリスペクトバンド1
我々は地の底の底を行くようなマニア向けアンダーグラウンドシーンでデスメタルという音楽ジャンルで活動しています
サブコンシャステラーは1994年の結成ですから長い休止期間はあれどもかれこれ30年になります
これまでの30年の国内デスメタルシーンを鑑みていて、これまでと全く違う活動パターンをしているバンドが存在します
そんな現代における国内エクストリームメタルシーンで我々が最も注目しているのがKrueltyです
彼らのインタビュー記事↓
Interview | KRUELTY | “俺らはこうだ”って表明したい | AVE | CORNER PRINTING (ave-cornerprinting.com)
つい数十年前、国内のアングラバンドの殆どがやり切れなかったことを全て行動に移し縦横無尽に世界的に活動しているKRUELTY
kruelty主宰のZuma氏と話しをする機会が幾度かあったのですが、その第一印象が「見ている視界が違う」です
あの若さであれだけの「実行力」と「スピード感」と「俯瞰力」はセンス以外の何物でもないでしょう
確かに当バンドも思い立った瞬間に即行動を基本としていますが、彼の場合は回転が速く本当に実行し結果まで出してしまうところまでをかなりの確度で想定(ものすごく考えているはず)出来ている印象があります。そういった観点からも彼らの行動から我々も吸収し学んでいます
といいますか、そもそもやっている音楽がカッコいい上にバンマス能力値が異常値レベルで高いというのは国内エクストリームメタルバンドにおけるかなりの希少種だと思います
このまま突っ走って欲しいですし縦横無尽に地球上を攻めながらワールドクラスエクストリームメタルバンドとして日本が誇るもっとも有名なアングラバンドの1つであることは間違いないと思います
もちろん我々も国内アンダーグラウンドシーンに少しでも寄与できるように益々邁進して行きたいですし亀足ではありますが少しづつでも海外シーンへも視野に出ていく準備もしながら背中を追っていきたいですね
特に若手バンドさんに向けてですが将来、活動視界を更に拡げて行きたいのならばkrueltyに相談をしてみると良いのではと思います。彼らのスピード感と行動力と視点はきっとご自身のバンドマンとしての考え方に化学反応が起きる可能性があると思います

無理をしない選択肢
タイトルは考え方次第なのですが活動において全方向で猪突猛進し過ぎて突然息切れを起こすバンドが多いような気がしています
原因はほぼ経済負担の行き詰まりか、思うようにバンドの駒が進んで行かない事による心理的なギブアップ
我々の様なマイナー(アンダーグラウンド)音楽&小規模なジャンルは市場規模も小さい訳ですから、逆にむしろ更に年々激しく元気に活動を行うバンドについてはただただ頭が下がりますしリスペクトしかないです
これは招聘会社も同じでしょう
例えば大きな会場を借りて集客を目論んだのに結果はスカスカで大赤字だと招聘会社でも大手以外は資金力が乏しいとそれ一発で飛んでしまうようなこともあります
これを読み切るのは本当に難しいですよね
海外でも同様
アジアを仕切るエージェント、ヨーロッパを仕切るエージェント、アメリカを仕切るエージェント
それぞれのエリアにエージェントのボスが居ます
個人招聘でもない限り、基本的にはそのエリアボスが各国の地元のエージェントにツアー日程の割り振りをしていきます
つまり地元ローカルエージェントの負担で会場費やバンドギャラや渡航費などの支払契約で招聘
地元ローカルエージェントのギャラ保証契約の成立により公演が開催される訳ですからバンド側とエージェントボス側はまだしも(=赤字は無い)ローカルエージェント側にはリスクが伴います
例えば世界的に有名なAというバンドがアジアツアーをするとなった場合
先ずはアジアエリアのエージェントボスに話が来てその後はそのアジアエージェントボスが日本だったりフィリピンだったりタイだったりインドネシアだったりの地元ローカルエージェントに日程を割り振りして行くという具合
有名バンドともなると「掛かる経費+演奏毎のギャラ」が発生します
バンド側もエリアボス側もそれが不成立(赤字)ならそもそも来ないですからね
つまりエージェントボスとバンドは利益が確定された状態で各国のエージェントに割り振りなので地元ローカルエージェントはギャラ保証しつつ招聘するというリスクが伴ってきます
万が一、箱選び(収容数)をミスって需要と供給が不成立なら赤字になりますし、盛況なら黒字ですのである意味でギャンブル性の高いビジネスに
我々は光栄にも来日バンドのOAを務めさせて頂く機会がありますがそういった背景を想定すると我々を使って下さったローカルエージェントに対し、万が一その公演(興行)の結果が赤字になってしまったらを想像すると嫌ですよね
もちろん主役は来日バンドとは言え、そんなことがあったら我々も心理的に辛くなるのでOAの立場とは言え必死でプロモします
それは出演の機会を与えられたバンドとして当然だと思います
どんなに世界的に有名なバンドであっても我々の様なマイナージャンルにおいては個人レベルの地元エージェントが箱を抑えて開催することもあります、むしろ多いかもしれません
なので資金力のない個人レベルのエージェントは心臓が苦しくなる程に一か八かの投資ギャンブルをしながら招聘するケースもあるので出演させて頂く限りはとにかく成功を願いながら出来る限りのプロモを行います
ただ、地元ローカルエージェント側の観点からするとエリアボスから指名(あなたに世界的に有名なAバンドのブッキングを〇〇〇万円のギャラでやってほしい、それをあなたの国で一任して開催を任せる)されたら今後の事も考えてやりたくなりますよね
結果として成功するに越したことは無いですが万が一、興行が散々だったところは最悪潰れることもありますし、その後弱体化していき淘汰される可能性も…
ですのでOAポジションであっても常に気が気では無いです
諸々の事情を踏まえてタイトルに戻りますが「無理をしない選択」ということも場合によってはありだと考えます
これはバンド活動も同様
デスメタルバンドでこういう考え方をする人は殆どいないかもしれませんが「売れたいとか有名になりたい」とかそういう部分が強いバンドは上記の様に息切れしてしまう可能性があると思います
我々は逆の考えかもしれませんが「創作を楽しみに年に3,4回ペースのライブ活動をしつつ、数年に一度の新譜リリース」という超マイペース型
でも、それは我々にとって長年続けていくのにちょうど良いペースであると自覚しているからです
無理をしたりペースを乱したりして万が一の異変を起こしてしまうよりも末永く活動して行きたい想いを選択しています
結局「焦らず、でも一歩一歩着実に進歩して行こうを目指す」なんだと思っています
楽器スキルも同じですよね、やはり日頃のコツコツやっていく基礎トレーニングが着実に実ってきます
次作
次作は既にプリプロダクションを作り終えています
あとはスケジュールを合わせてレコーディングやミックスマスタリングやアートワーク等の立案をしていく流れ
リリースまでの大まかな日程調整をしながら実際のリリース日まで細かい調整をしていきます
とは言え「言うは易し行うは難し」
いつもながら新作はリリース当日まであらゆる方面への調整を同時進行していくこととなります
例えばレコーディング日が決まったならばミックスマスタリングの目途が立つころまでにはアートワークも終わらせたいです
そうすることで多方面を待たずにリリースまで時間効率良く進行できます
とはいえ想定外なことがあった場合
例えば何か1つの予定が狂うと全体の見直しが入ったりもします
初っ端のレコーディングでつまづく(延長ややり直し)とエンジニアさんとの日程再調整もそうですし、CDやシャツなどのマーチに関しても工場プレス納期等の段取り見直しや、リリースライブにも間に合わなくなる等もあります
このように何か1つを動かすのにはあらゆる角度からのスケジュール立案と流動性を含んだ臨機応変な判断能力が必要
これを苦痛ではなく「面白い、やってやろうじゃないか」と思える人はバンマスのセンスが有るとも言えるかもしれません
ちなみに我々サブコンはひたすら壁にぶち当たりながら課題を1つづ体当たりしながら進んで行くのが大好物です
3rd Album “Chaotic Diffusion”歌詞日本語対訳
1.Cybernetics(人工頭脳生物)lyrics & music by Hammer
やがて時は来る。あらゆる動物遺伝子は100%解析され、やがて人間のコピーをも作り出す。100 年後ミイラ化された俺達はまた再生され生き返りその世界でまた意思を持ち続ける。そして更には機密下により研究部隊がキメラ分子成体の作成を成功させる。ヤギの身体を持った人間だって現れるさ。火を吹くライオンもな。そして最終的には人工頭脳がインプットされた動物の出現。その人工頭脳にコントロールされた動物たち。つまりはCybernetics。昆虫が見ている世界の把握。動物が見ている世界の把握。魚が見ている世界の把握。人間が見ている世界の把握。今は皆視界が違うし情報処理の仕方も違うがやがては俺達も昆虫がどのように世界を見ているのか分かるようになるだろう。その後に待つ宿命は人工頭脳を打ち込まれた動物達。離散的に判断する人間。そのCybernetics は概念を把握し始める。記号処理系RNN と認知運動系RNN の相互作用。人はいずれ死ねなくなる。死ねることが最大の幸福である時代がいずれ来るだろう。あらゆる病気は解決され、老いた臓器は新品へ交換されていく。だが、その時代が来た時が正に人類と地球上のあらゆるものが破滅へを迎える時でもある。楽しもうぜCybernetics 時代
The time will come.Every animal’s genes will be analyzed 100% and eventually a copy of us will be created.100 years later, we will be mummified, but we will be reborn, reanimated,and will have a mind of our own again in that world.And furthermore, under secrecy, a research unit succeeds in creating chimeric humans.There will even be humans in goats’ bodies.Or a fire-breathing lion.And finally, animals with artificial brains.Animals controlled by artificial brains.In other words, Cybernetics.Understanding the world as an insect sees itUnderstanding the world as animals see it(Understanding the world as a fish sees it)(Understanding the world as a human sees it)Now, we all see differently, and we process information differently.But eventually we will be able to understand how insects see the worldThe fate that awaits us after that will be animals with artificial brainsHumans making discrete decisionsThat Cybernetics will begin to grasp the conceptInteraction between symbolic processing RNNs and cognitive-motor RNNsPeople will eventually not be able to dieA time will come when being able to die is the greatest source of happinessEvery disease will be curable and old organs will be replaced with new ones.But when that time comes, that is exactly when mankind and everything on earth will meet its doom,Let’s enjoy the age of Cybernetics!
2.Nostalgic(郷愁) lyrics & music by Hammer
思い出す当時の記憶。懐かしい音楽は好きか?現代のAI は音階ヒットメーカー。録音した波形すら自由自在に切り貼りできて、ピッチもバッチリ修正可能。打ち込み音楽の全盛。それが悪いとは思わない、むしろ好きな音楽もある。ただ人間の脳内に焼き付く音は形骸化していき人間の耳がリズムマシン化する聴覚を発達させることでパーソナリティは失われていくだろう。組み合わせ符号による売れ線メロディー。俺たちはやりたい音階を貫ぬき、やりたい音楽を作り続けるだけさ。ストリーミング社会。幸か不幸か、俺たちの音楽は商業音楽とは剥離しているが、そもそも俺たちはアンダーグラウンドなブルータルミュージック好きだからね。何にも類似しない音楽を作り続けること。好きな様にやること。貫くこと。それが正真正銘、人間が創り出す自由音楽。触れた際に擦れる楽器の音やタッチ感はゾクゾクするね。老いても老いてもそこは変わらない。子供の様に俺たちのやりたいようにやるのさ。激烈にな
Recalling memories of those days.Do you like nostalgic music?Modern AI is a hit maker.Even recorded waveforms can be cut and pasted at will,and pitch can be perfectly adjusted.The heyday of digital music.I don’t think there’s anything wrong with that, in fact, I like music.But the sound that is burned into the human brain is becoming a skeleton.As the human ear develops a sense of hearing that becomes a rhythm machine,personality will be lost.Selling line melodies with combination codes.We will just continue to make the music we want to make,through the musical scale we want to make.Streaming society,Fortunately or unfortunately, our music is detached from commercial music.We like underground brutal music to begin with,To keep making music that doesn’t resemble anything else,To do what we want ,to stick to it.That’s the true free music created by human beings,The sound of the instruments when you touch them is thrilling!Old age and old age don’t change that We do what we want, just like kids.Fiercely.
3.Endurance Battle(耐久戦_狂気の沙汰)lyrics & music by Hammer
時報は止まらない,見えない終末世界からの更なる脳死進行,見渡す限りの人類の分断を面白がってほくそ笑むモンスター達,終わりの見えない耐久戦により人は全ての事に疑心暗鬼となり思考破滅,そして皆は精神狂気の沙汰へ,お前は知ってるか?本当はその疑心暗鬼社会すら思惑のあるやつらに操作されているのさ,その先の扉を開けオーバーワールド突入に賭ける者達とそれを妨ごうとする者達との終わりなき戦い,世直し大名は犬死,ぬくぬくしたい奴らの下界支配保持と引きこもり達の無関係な断絶社会,陰社会でひっそり生きるか、前に出ていって集中砲火を浴びて壊滅させられるのか,さもなくば操り人形のように踊らされることを了承するか,耐えきれなくなった陰社会人間も、最後は奴らの目の前に誘き出され、コントロールされ,拷問されるだけなのさ,窮す猫を噛む,全てを失い、全てを俯瞰し、全ての後ろ盾が無くなった時,一瞬だけ人は無敵になれるが消滅を選択することになるだろう,時報が聴こえるか?終わりなき時報との闘い,何度も何度も時報が鳴る,本当にこの時報が止まった時お前は土に返る,そう、既にこの世にはいないんだ,狂気の沙汰,耐久戦,時報は止まらない,その究極の耐久戦を潜り抜けたとしても,更なる上層部隊に打ち抜かれ、その未来の先にAI ロボットが待ち構え、永遠に打ち抜かれるのさ,狂気の沙汰と終わりなき戦い
The time signal never stops,Further brain-dead progression from an invisible apocalypse,Monsters gloating over the division of humanity as far as the eyes can see,Endless endurance battles make people doubt everything and ruin their thinking,And everyone goes into a state of mental insanity,You know what?The truth is, even the skeptical society is being manipulated by those with an agenda.The endless battle between those who want to open the door,and enter the overworld and those who want to prevent them from doing so.The lords of the world will die a dog’s death.A society where those who want to stay warm and cozy retain control of the masses,and the shut-ins are disconnected from the rest of the world.They can live quietly in the shadows,or they can come forward and be decimated by the concentrated bombardment.Or else, they will agree to be made to dance like puppets.The people in the shadows who can’t take it anymore will be lured out in front of them,controlled and tortured in the end.a doomed mouse will bite a cat,When everything is lost, when everything is overhead, when all the backs are gone,For a moment one can be invincible, but then one will choose to disappear.Can you hear the time signal?The endless struggle against the time signal,Again and again the time signal goes off,When the time signal truly stops, you will return to the earth.Yes, you are already gone,The madness of it all,Endurance warfare,The time signal never stops,Even if you make it through that ultimate endurance battle,And even if you make it through that ultimate endurance battle,you’ll still get knocked out by the higher ups,and the AI robots will be waiting for you at the end of that future,and you’ll be knocked out forever.Madness and endless battles
4.Irreversible damage(不可逆的損傷)lyrics & music by Hammer
アポトーシス,凝固壊死,融解壊死,後戻りはできない,動物は産まれた瞬間から死へ向かって消失までを生きる,覆水盆に返らず,人間社会,崩れた関係性を修復など無駄な努力,さっさと次へコマを進めろ,お人良しは淘汰,気の合う仲間との集合体,世界を旅した結果,一人の人間は確かに小さな存在,長年、どこまでも視野を広く見た結果,視野は狭くて良いことが分かる,何かに制御されるな,制御されることこそ不可逆的損傷,若者の敏感な感性,年寄りの俯瞰,長年の経験を持った奴らが浅い経験をもった若者達の芽が出ないようにねじ伏せる狡さを,最大利用,既得権益の保護,若い芽は潰せばいい,そんな腐敗社会へ不可逆的損傷を与えよ,老いる肉体との闘い
Apoptosis,Coagulation necrosis,Melting necrosis,There is no going back.Animals live from the moment of birth to the moment of death,there is no turning back,Human society,It is futile to try to repair broken relationships,Move on to the next stage,Weed out the good-natured,A group of like-minded people,As a result of traveling the world,One person is indeed a small entity,After years of seeing everything and everywhere,I see that it is good to have a narrow view,Don’t let anything control you,Being controlled is irreversible damage,Sensitivity of the young,The bird’s eye view of the old,Maximum use of cunning by those with years of experience to screw over,the young people with shallow experience to keep them from budging,Protection of vested interests,Crush the young buds,Do irreversible damage to such a corrupt society,Fight against the aging body
5.Demolition(滅亡) lyrics & music by Hammer
死とは消滅,意識も肉体も消滅,無かったことになることが死,お前は毎日精一杯生きているか?自意識はあるか?潜在意識の中で,消えゆく記憶,不満は意味の無い事象,相互の無害関係は繕うことから形成される,不味い店で飯を食べないだろ?上手い店なら通うだろ?同じことさ,そんなネガティブなことを考えてる暇があったらお前自身が消滅するまでの間にやることがあるさ,そこに至る瞬間までを無駄にするな,全力で走れ,自由を求めれば求めるほどに抑制者も出現,面白くないのさ、お前のその楽しそうな表情を見るのが,嫉妬は戦争をも起こす,嫉妬が世界滅亡をも起こす,その前に行き切れ!
Death is annihilation,Consciousness and body disappear.Death is to become what never was.Are you living every day to the fullest?Do you have self-consciousness?In the subconscious,Fading memories,Dissatisfaction is a meaningless event,Mutual harmless relationships are formed by mending.You wouldn’t eat at a bad restaurant, would you?You would go to a good restaurant if it was good.It’s the same thing.If you have time to think about such negative things,you have things to do before you disappear.Don’t waste time until the moment you get there.Run as fast as you can.The more freedom you seek, the more inhibitors will appear.It’s not fun to see your happy face,Jealousy can start wars,Jealousy will bring about the end of the world,But get out of here before it happens!
6.Devastation(惨状そして荒廃)lyrics & music by Hammer
この世に安全な場所など無い,24 時間監視社会,権力者によって不都合はもみ消される,目立った奴はメディアに抹殺される,作り上げられたストーリーによって,防弾チョッキ並みの無敵な身体を作り上げろ,不死の精神を作り上げろ,頭を打ち抜かれてもすぐに再生される身体を作り上げろ,まるでゾンビの様に生き返るしぶとさ,打ちひしがれる奴は弱者,自死も弱者,巻き添えも弱者,ただ、助ける者などそこには居ない,死なばもろともなヤツが蔓延る,勝てば官軍,そこに正や不正は不要,全ては作りあげられたストーリー,それを操る側がこの世の惨状と荒廃を楽しんでるのさ,皮肉にもそれが人類の寿命と篩にかけられた生存確率
There is no safe place in this world,A society under 24-hour surveillance.Inconveniences are covered up by those in power.Anyone who stands up will be obliterated by the media.With a made up story.Build a body as invincible as a bulletproof vest.Create an immortal spirit.A body that regenerates itself as soon as it is decapitated.Stubbornness to come back to life like a zombie,A man who is beaten down is weak.Suicide is weak.Collateral damage is weak.But there is no one there to help,The dead are the ones who die and the dead are the ones who pervade,When you win, you win,There is no righteousness or injustice,It’s all a made-up story,And those who control it enjoy the misery and devastation of this world.Ironically, that’s the human lifespan and the probability of survival through the sieve.
7.Phantom(幻影みせかけ)lyrics & music by Hammer
全てはみせかけ,ブランドイメージ,そう、イメージは良くも悪くも人を洗脳する,どんなに良質な商品を作っても見たくれが悪けりゃ誰も買わない,どんなに素晴らしい絵も倉庫に眠っていれば誰も気づかない,独特な創造をする者は商売が下手,だが、今度は商売が上手くなると創造が汚れる矛盾,かといって、その中間を宿ると中途半端,経営コンサルタントの無残なノーアイデア,生え抜きたちの逆襲,自力で培った強力なメソッド,知ったか野郎は切り捨て御免,幻影,真実,みせかけ,現社会においての猛者イコール”みせかけ”の強さ,虚構の洪水地獄,痛快だろう?虚構と真実,我々はその判断を求められる,だまされたまま楽しい生活を送るが吉,その真実を知った時,果たして人類の痛快はあるのだろうか?
Everything is a sham,Brand image,Yes, image brainwashes people, for better or worse.No matter how good the product is, no one will buy it if it looks bad.No matter how great a painting is, if it sits in a warehouse, no one will notice it.Those who produce unique creations are not good at business.But now, when business is good, creation becomes tainted.But if you stay in the middle of the two, you are halfway there,Management Consultants’ Cruel No-Ideas,The counterattack of the best and brightest,Powerful methods developed on their own,Know-it-alls will be cut off and spared,Illusion,Truth,Pretense,The fiercest in today’s society is the strength of pretense,Fiction floods hell,Isn’t it painful?Fiction and truth,We are called upon to judge,It’s good to be fooled and live the good life,When we know the truth,Will there really be a human pain?
8.The Shiftier,The Better(狡猾なやつが偉い社会)
Every day,we exposed to,Looking with suspicious eyes,Urging us to social master,Instilling the art of self-protection,Leadings ourselves to self-protection,Disturbing spiritual growth,Surrounded by unworthful scum,Knowledge-the only important help,Branded,and managed in turn,A tall tree catches much wind,We are taught to follow the majority,Needless to think!Tied down by the strict rules,A tall tree catches much wind,We must put the right man in the right place,Wide of the mark!The Shiftier,The Better,The vast meaningless knowledge’s crammed(Crammed),Practice takes it out oh us(Us),The social system leaves a void(Void),Be careful! Maddness will be burst,Extream strain causes,Torment and suicide,The pressure called education’s,Trying to crush us!The Shiftier,The Better
スクールに通う
担当楽器のスクールに通うのはかなり意味があると思います
当方はハタチ頃の大学生時に通っていました
その学生時代、自宅から徒歩で行ける音楽スクールの先生に師事。
メタル系でなくジャズやフュージョン系の先生でしたが、それまでが完全独学でしたし音楽理論を始めそもそも他人(先生)のプレイを間近で拝見することができた希少な経験になります
その後ですが、サブコンシャステラーを四半世紀ぶり(2019秋)に再活動する際にまず始めたのが「ギターの先生探し」と「DTMなる文明機器の習得」でした
すぐに地元で2名のギター講師さんを見つけ、2000年代以降の現代ギタープレイがどのような状況なのかを目の前で確認したくて習いに行きました、テク面もありますが何しろ四半世紀も楽器を触っていなかったので現代技術を含めて浦島太郎でしたし、果たして今の音楽技術についていけるのかという不安もあったからです
楽器技術に関してはまだまだ全くおこがましいレベルではありますが生涯を通じて突き詰めていきたいです
(余談)スクールに通う時に重視している事ですが、例えばギターならば一般的なスケールの速弾きでもよいので(メタル系ならディミニッシュスケールでも良いし7thスケールの様なジャズ系でも何でも)間近で先生が弾くところを拝見させて頂くだけで吸収できることが沢山あります。フォーム、指圧感、音の鳴り方、両手の動かし方、音作りのセッティングまで全てを凝視して自分に無いものを感じ取りつつ、それらを吸収して行くことで音楽の幅も更に広がると思います。なのでデスメタルを習いに行くというのは無いのですが知見を拡げられますね
活動規模を拡げるとは
我々の様にそもそもの知名度や規模が小さいバンドの状況下で「活動規模を拡げる」というのは本当に難しいです
例えばメタル系音楽であれば大手Century Media(ソニー系レーベル)と契約し音源をリリースできたなら、それは地元ローカルで100回ライブするよりも一瞬で地球上で名が知られて行きますよね
厳しい現実ではありますが例えそのバンドのライブを見たことが無くとも、例えその音源を聴いたことが無くともメディア上にどんどん名前が流布されて行きます
我々の様な小規模のバンドにとっては厳しい現実を突きつけられますが、もし仮に地球上で一番すごい音楽を創ったとしても知られなければ人知れず埋もれていきます
この部分はマイナー系音楽のバンドマンが葛藤しやすいケースの1つではないでしょうか?
結局は「知られなければ始まらない」→「知られないから音源販売なども売れないので活動資金が枯渇していく」→「徐々にバンド自体が活動をフェードアウトしていく」のループ
これを逆手に取るならばバンドをブランディングできればできるほど更にライブや創作活動がやり続けられるという皮肉めいた表現にはなりますがこれらをどこまで求めていくのかかもしれません
そういう意味では出世レースと一緒で、成長過程として「力を持ったレコード会社」、「力を持ったメディア」、「力を持ったエージェント」、「力を持ったプロモーション会社」等と繋がりその方達のサポート受けながら創作音楽を皆さんに知っていただくという活動
実際に招聘会社のコンサートに行けばその招聘会社の関係者もいらっしゃるわけですからそこで直接の面談約束を取るくらいの熱意は必要でしょう
とはいえ、もちろん最終的にはリスナーの皆さんに音源判断を頂くことにはなりますが「まずはそもそも音を届けることが出来るのか」という事も活動規模を拡げたい意思があるならば必要になってくると思います
例えばですがこれからゼロ状態でバンドを始めると仮定する話をしてみましょう
先ずはセルフででも音源をリリースし、それらを持参して「1年目」は国内東名阪等の主要都市、「2年目」に少し足を延ばしてアジアであれば人口の多い中国やインドネシアなどの主要都市、更には「3年目」に遠方としてアメリカやヨーロッパなどの主要都市ツアーを「敢行」しながら力を蓄え、その後徐々に地方都市まで広げていく様なイメージ
かなり大雑把で極端な内容例を挙げた道のりではありますがそういうマクロ視点で考えることも良いかもしれません
ただし前提としてそれらは自己資金が必要。特にゼロ状態のバンドからスタートするならばなおさらです
ですのでこれまでBlog1から伝え続けていますがバンドマンはセンスや技巧だけでなく「動ける環境」(生活も経済基盤も)かどうかが最重要な1つ(加えて「気力体力」)と言えるかもしれません
その他として挙げられるのはやはり「コラボ」です
例えば来日公演があったときにオープニングアクトとして呼ばれるケース
これもゼロ状態からバンドをスタートするのであれば「そもそも知られていないので呼ばれない」という、元も子もない話ですから、なかなか難しいところもありますがエージェント(招聘会社)に熱意をもってコンタクトしてみても良いかもですね
レコード会社だったりイベント会社だったりメディア会社だったりとのコンタクトは普段の日常生活の中でできる活動ですからどなたでもやれることだと思いますし、自主性をもって活動することは活動規模を拡げたいバンドならば必須項目かもしれません
個人的な話になりますが当方は人生上で就職活動というのを殆どしたことが無いのでもしかしたら違うのかもしれませんが「就職活動の際に何十社も会社のセミナーや面接を受けて就職活動をする」というようなニュースを見ていてこれらと類似している部分はあるかもしれません
つまり「縁があればあるし、縁が無ければ無い」という具合で一喜一憂せず淡々とそして諦めずに少しづつステップを踏んでいくような
とはいえ我々はそのあたり(自主性をもって活動する力)がまだまだ弱いので自己指摘する意味も含めて述べていますが、結論としては活動規模を拡げたいならば、いずれはブランディングも必要不可欠な壁に当たる可能性があるという内容でした
便利グッズ
弦楽器のハードケースの持ち運びについての便利グッズの紹介です
ハードケースの場合、取っ手を持ち手に運ぶのでどうしても手が塞がり気味になります
それを解消してくれるのがこちらです↓

これを取り付けることでハードケースを背負うことが出来るようになります↓

ROKKOMANのCP-4という型番で4000円弱
ROKKOMANN ( ロッコーマン ) CP-4 送料無料 | サウンドハウス (soundhouse.co.jp)
変形ギターのハードケースに取り付けられるという優れものです
運搬が楽になる便利グッズの1つですね
レコーディング準備が佳境
我々のレコーディング手法や機材等に関してはこれまでに沢山書いてきましたので省略いたしますがレコーディングもやはり様々な事前準備や手配があります
これをしっかりやっているかどうかでその後の行動や効率も含めかなり変わってきます
ミクロとマクロで全体スケジュールを「立て続ける」こと。途中で軌道修正があってもです
レコーディングしてリリースをするということは、のちにレーベルリリースなのかセルフリリースなのかであったり、新規でレーベルを探すのであればEPKやアー写の準備もそうですし、プロモMVの事前準備もありますし、ミックスマスタリングエンジニアとの日程調整もありますし、更にはアートワークを納期も想定手配する必要がありますし、リリース後にはリリースツアーをするならばその準備も
「レコーディング」と一口に言っても、結果的には全方向への準備を同時に進める必要があります
それをやりながら同時に既に決まっているライブ準備もあります。まして海外公演なら更に多くの準備も必要になります
ですので、アクティブなバンドであれば創作やライブだけでなく「一年中、何かを準備手配」をしているような感じになります
そしてめでたくもレコーディングからリリースまでの目途が立ったならば、今度はその瞬間から次の創作アイデアを温めストックして行くという流れです
なので我々の様な小規模なバンドですら年中が音楽漬けになります
これらを「生きがい」として感じられる人はバンマスに向いているかもしれませんね
音楽活動もやはり気力体力
ライブ活動を行うには気力体力がかなり必要になってきます
先日DEFEATED SANITY大阪公演に出演させて頂きました
彼らはワールドツアー中
毎日のように国を跨ぐ移動しては公演ツアーを行っています

「ワールドツアー」についてよくよく考えてみると
先ずは「家から空港に行き、飛行機に乗ってはイミグレーショーンを通過し、そこから車や列車で現地まで行き、日中には会場でのリハーサルを行い、そして夜に本番、その後すぐにホテルに戻って就寝できたとしても次の日の朝から移動」
これを繰り返しながらツアー活動を行って行く訳です
これがメジャー音楽シーンであれば2日に1回休みとかありますが我々は極端なアンダーグラウンドシーン。経費面も含め日々を回り続けます
そんな「好き過ぎて、だからやってる」が99%な世界です
そしてツアーが終わると新作レコーディング等を行いまたツアーに出るという
そもそもの音楽ジャンル自体が超人スポーツ的なテクニックと激烈なテンポスピード。それに加え過酷ともいえるかもしれない過密日程のツアーを敢行遂行していくという
「好き過ぎる人たちが辿り着く道」、リスペクトしかないです
これまでの過去ログは「Blog」、今後はこちらの「Blog2」よりブログ更新
当ホームページの「Blog」について。これまで通り見ることは出来るのですが開くことが出来なくなり編集ができないため、新たに「Blog2」を作りました。こちらから更新していきます